父の先見


本の雑誌社 2013
編集:浜本茂
装幀:金子哲郎
タイポスはスパイスの文字である。そこには窓際のトットちゃんがいる。料理の素材も仕上がりもスパイスでおいしくなるように、タイポスで文章がおいしくなっていく。それにくらべると、精興社の書体はプロの料理人がつくる氷の彫刻のようだ。研ぎすまされた刃先の跡がある。
正木香子(まさき・きょうこ)が綴った文字についてのエッセイは、とても新鮮だった。文字文化論ではない。エッセイの関心はひたすらタイプフェイスやフォントに向かっているだけなのだが、文字にこんがりした焼き目が見えてきたり、香ばしい匂いがしてくる。
どのようにか。こんな調子だ。
ドリトル先生も長靴下のピッピもナルニアの魔女も、岩田明朝体に攫われて読んだ。あの書体はドロップの缶から出てくる文字だ。けれどもデジタル化された「イワタ明朝体オールド」はもどかしい。チョコ味のドロップを食べたくても、たいていハッカ味が出てくる。
小川洋子の『密やかな結晶』を講談社文庫で読んだ。モトヤ明朝だった。記録や保存のように余地を残さない文字だ。そこからは、鏡のように正しく写し取ろうとするような「こわさ」が出入りする。
また、こんな調子だ。
写研の創業者の石井茂吉が写真植字の第1号としてつくりだした石井明朝は、いまは石井中明朝オールドスタイルと言われている。あらためて見るとゼリーのようだ。たっぷり濡れて透明なのに、かたまりきっているのかいないのか、わからない。山田詠美の『風味絶佳』に組まれていた石井明朝は石井中明朝オールドスタイルだった。甘くないゼリーなのである。
凸版明朝体は文春文庫がつかっている。林真理子も司馬遼太郎も石田衣良も、みんな凸版明朝になっている。読み手をとらえて離さないこのタイプフェイスは、密室の心細さをもって私を夢中にさせる。あれは、そう、「機内食の文字」なのである。
こういう書体感覚のことを綴った人がいることも、こういう本を紹介できることも、なんとも悦ばしい。うきうきするし、ほたほたする。日本文字の印刷書体と印字書体を案内しているのだが、その手立てがどんな文字に関する本よりも、おいしくて、なつかしいのだ。
著者がどういう人なのか、ぼくはまったく知らない。デザイナーでも造本家でも、文化の評論屋さんでもないようだ。それなのに、このような書体案内をするのにふさわしく、かつ慎ましく、かつ当分なのである。なかなかこういうことはできない。
たとえば自動車を紹介する、ラーメンを紹介する、蘭を紹介する、楽器を紹介するというとき、正木香子のように自動車やラーメン屋蘭や楽器を食卓に少しずつ並べるようにアレンジメントできるだろうかと思ってみるといい。おそらくこうはできないはずだ。たいてい自慢をするか、正確に分類しようとするか、それとも巧拙にとらわれる。さもなくば、なんでもイラストタッチにするか、歴史説明に徹するか。そんなふうになる。
この本はそうではない。石井細明ニュースタイルは「チューインガムの文字」、光村の教科書体は「給食の文字」、スーボは「アイスクリームの文字」なのだ。ゴナが「肉の文字」だとしたら、ナールは「卵の文字」なのだ。こんなメニュー仕立ては、この人にしかできない芸当だった。
文字のこと、活字のこと、タイプフェイスのこと、タイポグラフィのこと、レタリングのことは、これまでさまざまな本になってきた。矢島文夫やスティーヴン・フィッシャーの『文字の歴史』めいた本は、かなりある。
日本でも欧文活字の研究を筆頭に、大正時代からずいぶん書体研鑽が積まれてきた。斯界を牽引した佐藤敬之輔の『英字デザイン』(丸善)をはじめ、矢作勝美の『明朝活字』(平凡社)、高岡重蔵の『活版習作集』(烏有書林)、府川充男の『組版原論』(太田出版)など、いろいろだ。いずれも名鑑だった。
しかし、これらはプロフェッショナルのためのプロによる著作であって、文字設計やデザインのための著作ばかりなのである。本好きなアマチュアの読者が文字との出会いを綴った本はめったになかった。
市電に乗って街のあれこれの風情を見るように、何かを買いたいけれどどれにするか迷っている和菓子屋の店先での気分のように、自分がこれまで出会った文字についての感想を書ける者なんて、まったくいなかったのだ。
けれども、誰だって商店街の肉屋や総菜屋のコロッケがどんなふうにおいしそうかを感じているのだから、毎日出会う新聞の見出し文字や歯磨きチューブについているロゴ文字たちにも、あれこれの感想をもってきたはずなのである。文字にもおいしそうな文字、まずそうな文字、センセーショナルな文字、寡黙な文字があることに気がついてもよかったのだ。
なぜ、こういう見方をすることができなかったのか。あらためて、表意文字の国に生まれ育った者としてあまりに無頓着だったと言うしかない。
日本人なら、活字書体やフォントにはまずもってゴシックと明朝があることくらいは知っているはずである。それなのに、太明と細明に出会ったときの印象のちがいをちゃんとおぼえているかというと、かなりあやしい。
お母さんが読み聞かせてくれた絵本にだって、選びこまれた文字がいろいろ躍っていたはずだ。何十回も追っかけた絵本の言葉もあったろう。ひょっとしたら声に出していただろう。
それらはすべて、文字がもたらしてくれたものだったのだ。絵本のことはもう思い出せないというのなら、いまも書店に並ぶどんな本の表紙にも背にも、タイトルと著者の名がおおっぴらに出ているのだから、それが明朝かゴシックか、どんな色がついていたのか、思い出せてもいいはずである。ところが、いざリコールしようとするとさっぱりなのだ。
みすず書房の本のすべてが明朝であることも、初期の岩波新書と改版後の岩波新書の表紙文字が替わったことも、どうやらメッセージにはなってこなかったのだ。まして日本のマンガの吹き出しの中が、漢字はゴシックで仮名は明朝になっているなんてことは、ほとんど気が付かれてこなかった。
文字感覚というものはわれわれの日々をくまなく覆っている。テレビのテロップもスマホにひしめく大量の情報も、ファミレスや牛丼屋のメニューにも、文字はいっぱいだ。文字たちは、われわれがいつも服をまとうように、いつだって文字の意匠を着脱してきたわけである。
そして、そのいちいちの意匠は、誰かがこれがいいだろうというふうに選んできたものたちなのである。われわれはその文字によって吉本ばなな(350夜)や町田康(725夜)を読んできた。それなのに、そこにいた文字たちのことは、忘れていく。
ぼくもかなりの文字好きである。そうなったについては、きっかけがあった。中学生雑誌の投稿俳句欄で特選になって万年筆を貰ったときに、その万年筆で日記を書きたくなったのだ。
けれどもキシキシしてあまりうまく書けなかった。きっと安物の万年筆だったと思う。昭和30年代に学習雑誌から贈られる万年筆が上等であるはずがない。それでもその万年筆で書きたかったので、ペン先の角度をいろいろ変えて綴るようになった。その日の出来事にあわせて変えるのだ。
レタリングというほどのものじゃない。タイプフェイスのスタイルというほどでもない。それでもそれ以来、他人の文字にも、世の中の見出し文字にも注目するようになっていた。
長じて、杉浦康平(981夜)さんに出会って衝撃をうけた。写植文字を1文字ずつハサミで切って、2ミリほどに細かくカットした両面テープを裏につけ、猛烈なスピードで「文字並べ」をしている。腰を抜かすほどに驚いた。タテ組なら上の文字の形に応じて次の文字の位置を案配していた。
活字の清刷りをとって、それを切り貼りもしていた。これはタイトル文字や見出し文字につかっていた。この人は文字を裁縫しているんだと思った。そのうち写研の「文字の生態圏」というカレンダー・シリーズを手伝ってほしいと言われ、毎年、「様々な文字意匠」についての解説を書かされた。戸田ツトム君や羽良多平吉君とずいぶんタイプフェイスについての話を交わしたのが、この時期の思い出だ。
しかし、こうしたことはぼくをディープな文字文化に近づけはしたが、おいしいコロッケや着やすいカーディガンのように文字と接するということを、ちょっと遅らせたかもしれない。田中一光(786夜)さんや浅葉克己さんに頼まれて『日本のタイポグラフィックデザイン』(トランスアート)という大きな本を編集構成したときは、ぼくはすっかり構えるようになっていた。
正木香子が綴った文字感覚はまことに自由だ。屈託がなく、面倒くさくない。目で遊び、手で摘めるようになっている。
それでいて、文字が作家の感情や表現された意味のために仕えているということを、忘れない。最近はJポップやラッパーたちが歌詞の中で変わった漢字や言い回しを使うようになったけれど、それはだんだん乱暴になっている。語呂あわせがやたらにふえてきた。ところが正木は、あくまで意味の意表にそこはかとない敬意を払っている。
正木は、文字の意表をメタフォリカルにする才能も長けている。タイポスが『マザー・グース』の詩集につかわれていて、なんだか「レシピを感じた」とか、日々の新聞の見出しの特太ゴシックに、「どこも角張ってまっすぐを強調しているようで、でもよく見るとちょっと不器用なミシンの縫い目みたいだ」という感想をもつとか、そんな比喩感想をもてるのである。そのうえで新聞の特太ゴシックには「おべんとうの文字」というニックネームをつけていた。
ところでこの本は、正木の独特でライトな文字感覚を綴っただけのものではない。ふつうなら文字見本を掲載するところを、すべて自分が出会った本のページ組版をそのままサンプリングして、その本についての感想を重ねて述べている。
たとえば、石井中明朝ニュースタイルは「夜食の文字」となっているのだが、それは茨木のり子の『見えない配達夫』(童話屋)とさくらももこの『もものかんづめ』(集英社)のそれぞれ1ページとの絡みになっていて、その中身と書体が一緒になって声をたてているというふうなのだ。
また、岩田明朝の「缶ドロップスの文字」には「ちくま日本文学全集」の芥川の『杜子春』(筑摩書房)の1ページとアンドリュー・ラングの『みどりいろの童話集』(偕成社文庫)の1ページが対応して、サクマドロップスがそうであったように、甘いカラカラという音をたてるのである。
なんとも愉快で、ぴったりの引用が寄り添っている。ぼくのようなウルサ型の文字好きでもハッとさせられることが少なくない。たとえば、「発酵する文字」に配されたモトヤ明朝には村上春樹の『アンダーグラウンド』(講談社文庫)の1ページがあてがわれているのだが、いったい「活字になる」とはどういうことかを問うというふうにもなっているし、小野恵美子の『らくだ』(石文館)と手塚治虫の『ブラック・ジャック』(秋田書店)の一節はアンチック大見出し文字だったようなのだが、これらは「煙草の文字」と名付けられ、アンチック体にひそむ「不思議な暗さ」が引き出されてくるのである。
よくぞ、こんな一冊ができたものだ。うまいもんだと思う。
もともとはウェブサイトで「文字の食卓:世界にひとつだけの書体見本帳」として連載していたものを再構成したようなのだが、それがよかったのかもしれない。そのせいで、文字と書体を扱った既存の本とはおよそ異なる構成になれたからだ。きっと、もともとのウェブ連載がすでにしてブックウェア感覚に富んでいたのだろう。
文字や書体に色や声があるのは、風や気運さえあるのは、これまでも語られてきたことだ。空海(750夜)の『声字実相義』にもランボー(690夜)の「母音」にも述べられていた。けれども正木のように、どんな一節にも文字と形と言葉と意味が近寄って、五感が語感とともに動きだすなどというのは、めったに語られたことがない。
だからこそ、このブックウェア・プレゼンテーションの仕方そのものが、新鮮な文字文化クリティックにもなれたのである。これは正木が書体を所有したいのではないことがもたらした自在力というものだった。
ちなみに正木は本書のあとに『本を読む人のための書体入門』(星海社新書)という本も書いているのだが、こちらは“解説”を意識したせいか「うきうき」や「ほたほた」が乏しくなった。ちょっと残念なことである。
さて、さて、いったい文字って何なのか。
記号であって、記号ではない。記号だから形をもっているが、数学記号などとちがって、民族や国民ごとに記号群になっている。しかも綴ってナンボと、一字でナンボになっている。表音文字と表意文字があるわけだ。日本文字にはこれが混じっている。漢字と平仮名とカタカナとアルファベットだ。
こういう文字を並べると単語やフレーズや文章になる。文章になるにしたがって、句読点やカギ括弧や驚きマークが入ってくる。約物(やくもの)という。この文字と約物を並べれば「意味」と「意表」になるわけだ。しかし、これだけが文字がもっている力ではない。
文字はもともと「声」をもっていた。大半の文字は「口の文字」であって「耳の文字」 なのである。空海はそれを「内声(ないしょう)の文字」と言っていた。
かつて、本は音読されていた。みんなが声を出して本を読んでいた。文字は有声文字なのだ。それが活版印刷が普及するにつれて「黙読の文字」になっていった。そうなることでわれわれが喪ったものも少なくないが、それを機会にふえていったものもある。それがタイプフェイスというものなのである。タイプフェイスは近代黙読社会の「目文字」時代がつくった意匠となった。
文字は綴られるものでもあった。文字の歴史はペンや毛筆や鉛筆と紙との出会いでもあった。カリグラフィとかオトグラフという。ここには書き手たちの個性があらわれた。筆記用具のクセもあらわれた。これらの表情を、新たなタイプフェイスが反映していった。活字化もされた。そこにローマン体やイタリック体や、明朝体や宋朝体が屹立していった。ヘルベチカや岩田母型や石井明朝が産声を上げていった。
文字を見ることは、文字を読むことであって、意味を掬いとることだったのである。
正木は、こうした文字がつくるさまざまな「意味の光景」を、その書体の表情とともに文章の進行の渦中に感じられる人なのだろう。
この芸当は何に似ているのだろうか。誰もが友達や先生や映画の中の人物を、その口調やファッションや身振りで感得しているようなことに似ているし、陶芸やアクセサリーをおもしろがるときの感じ方にも似ている。ただこれまでは、文字や書体を人の口調やその人の洋服の着方や、陶芸の味や日本酒のコクとキレのように語れるとは、ついぞ思っていなかったのだ。
まことにもったいないことをしたものだ。グラフィックデザイナーやエディトリアルデザイナーにも、責任がある。
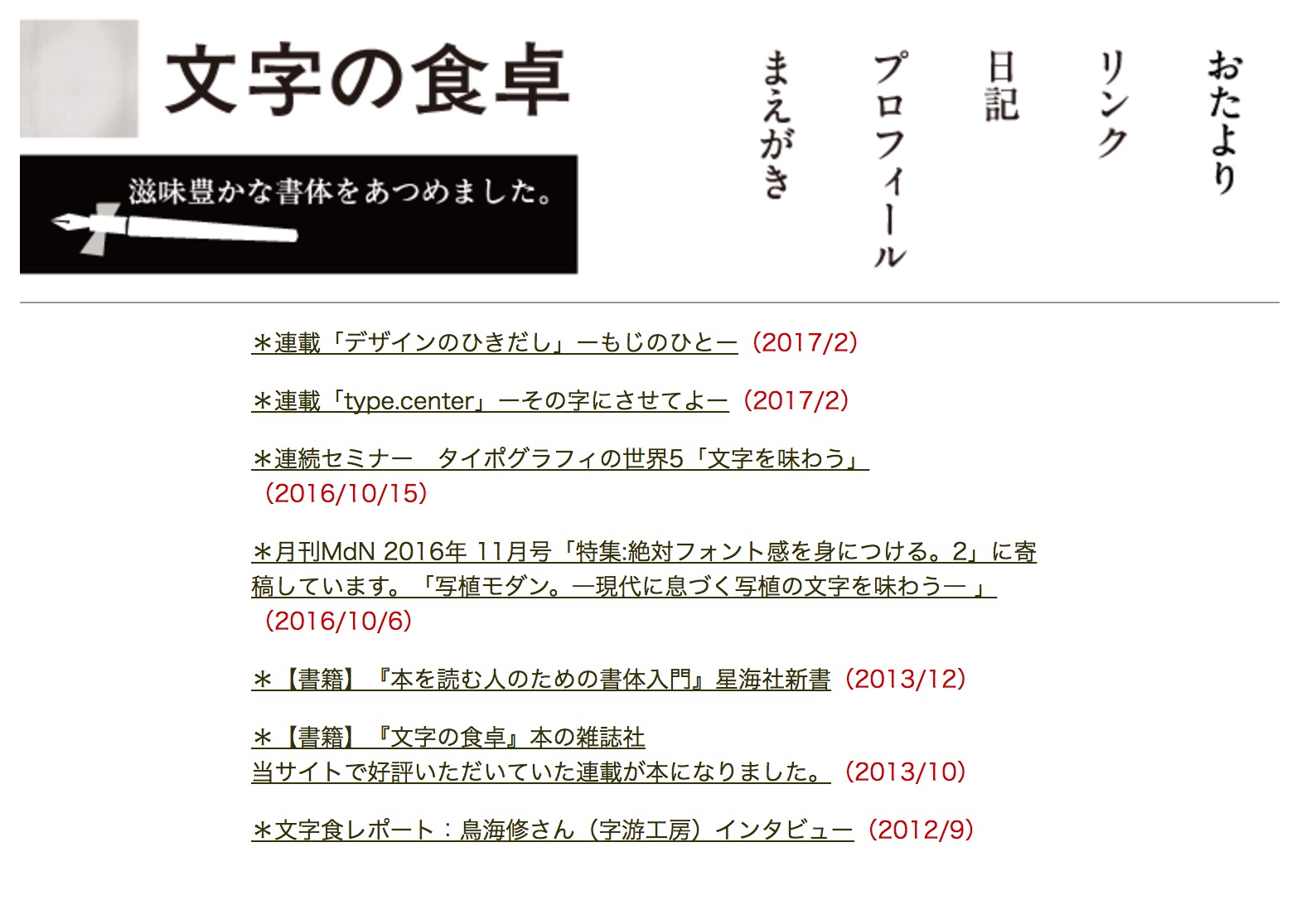
そもそも本には活字や書体が欠かせない。出版社が誰かの何かの原稿を本にすると決めると、まずは判型と文字組が決まり、ページ数が算出され、使用書体が決められる。それを決めないかぎりは本はつくれない。
だから出版社が本をつくるときは、かつてはその書体の活字をもっている印刷所の選定をしたものだ。秀英明朝を使いたいなら大日本印刷である。秀英体は大日本印刷の前身である秀英舎がつくりあげた書体だ。岩田母型を使いたいなら、イワタの活字をもっている印刷所を選ぶ。
ぼくの千夜千冊が求龍堂から全集になったときは、精興社の書体にしてもらった。この書体は白井赫太郎が大正2年に設立した東京活版所で生まれた。活字彫刻家であった君塚樹石がつくりあげた文字で、精興社はこの活版所が発展した印刷所なのである。ちなみにカバーと表紙の「松岡正剛・千夜千冊」の文字は資生堂書体に少し工夫を加えたものになっている。
どの本が、どんな本文活字で組まれているかを感じることは、お気にいりの洋服がどんな生地を使っているのかということくらいに、ものを言っていることなのである。
活版印刷の時代をホットタイプの時代と言う。銅や鉛などの金属を鋳造して作る「熱い文字」だったからだが、それが60年代後半から70年代にかけて、写真植字のコールドタイプ時代に移っていった。
ここに脚光を浴びたのが東の写研と西のモリサワだった。なかで写研の創作タイプフェイスコンテスト「石井賞」のトップに輝いた書体が、次々に一世を風靡した。中村征宏のゴナやナール、鈴木勉のスーボ、今田欣一の艶かな、橋本和夫の石井細明朝横組み用かな文字などは、こうして登場してきた。
文字づくりのグループもできてきた。桑山弥三郎・伊藤勝一・長田克巳・林隆男らのタイポスが登場してきたのは、かれらの精進による。
ところが、このあとに強烈な旋風がやってきた。デジタルフォント時代の到来だ。コンピュータによる文字出入力と電子デザインは、またたくまに「誰もがいじれるフォント」を撒きちらし、これで長きにわたって活躍してきた活版文字も写植文字も、すべてがビット数が伴う電子文字に組みこまれていったのだ。
かくしていまでは、往時の傑作フォントのあれこれもPCの中に棲息することになっている。本書に登場する組版ページも、その大半は電子組版による出力になっているはずである。
では、それでいいのかといえば、いいわけがない。どんな文字たちもコンピュータの中にいたのではしょうがない。かれらはやっぱり本の中への移住をくりかえし、「文字の森」や「文字のオーケストレーション」や「文字の食卓」をもっともっと感じさせるべきなのだ。

⊕『文字の食卓』⊕
∈ 著者:正木香子
∈ 発行人:浜本 茂
∈ ブックデザイン:金子哲郎
∈ 発行所:株式会社 本の雑誌社
∈ 印刷:中央精版印刷株式会社
∈ DTP:有限会社共同工芸社
⊂ 2013年10月25日 初版発行
⊕ 目次情報 ⊕
∈ ビスケットの文字◉石井中ゴシック
∈ チューインガムの文字◉石井細明朝ニュースタイル
∈ 炊きたてごはんの文字◉石井太明朝ニュースタイル
∈ 氷彫刻の文字◉精興社書体
∈ 肉の文字◉ゴナ
∈ 卵の文字◉ナール
∈ 夜食の文字◉石井中明朝ニュースタイル
∈ スパイスの文字◉タイポス
∈ 缶ドロップスの文字◉岩田明朝体
∈ 湯気の文字◉淡古印
∈ 果実の文字◉本蘭明朝
∈ 発酵する文字◉モトヤ明朝
∈ ゼリーの文字◉石井中明朝オールドスタイル
∈ 機内食の文字◉凸版明朝体
∈ 豆の文字◉石井中ゴシック小がな
∈ アイスクリームの文字◉スーボ
∈ 骨の文字◉ゴーシャ
∈ スープの文字◉日活明朝体
∈ バターの文字◉アンチック中見出し
∈ おべんとうの文字◉新聞特太ゴシック
∈ 微炭酸の文字◉石井太明朝オールドスタイル
∈ 花の文字◉リュウミン
∈ 給食の文字◉光村教科書体
∈ ビタミンの文字◉ゴシックMB101
∈ 蜜の文字◉艶かな
∈ 塩の文字◉秀英細明朝体
∈ キャラメルの文字◉石井細明朝体横組み用かな
∈ 貝の文字◉ファニー
∈ カレーライスの文字◉イナブラシュ
∈ 煙草の文字◉アンチック大見出し
∈ きのこの文字◉ツデイ
∈ ヨーグルトの文字◉ナカフリー
∈ 蠟燭の文字◉良寛
∈ 魚の文字◉秀英初号明朝
∈ こんぺいとうの文字◉石井太丸ゴシック
∈ 滴る文字◉A1明朝
∈ ミントの文字◉ボカッシイ
∈ 満腹の文字◉大蘭明朝
∈ 珈琲の文字◉石井太ゴシック
∈∈ あとがき
⊗ 執筆者略歴 ⊕
正木香子(まさき・きょうこ)
文筆家。1981年生まれ、福岡県出身。東京都在住。 早稲田大学第一文学部卒業。 幼いころから活字や写植の文字に魅せられ、絶対音感ならぬ「絶対文字感」を養う。 2011年にウェブサイト『文字の食卓|世界にひとつだけの書体見本帳』を開設。「書体の滋味豊かな味わい」をテーマに連載した文字と言葉をめぐる読書エッセイが 今までにない読者目線の書体批評として話題となり、「文字の食卓展」を開催する。 文字を食して言葉を味わう「文字食」日々実践をモットーに、 エッセイ・コラム・ルポルタージュなどの執筆を行う。 著書に『文字の食卓』(本の雑誌社)、『本を読む人のための書体入門』(星海社新書)、雑誌『デザインのひきだし』にて「もじのひと」連載中。