父の先見


岩波文庫 1956
Alexandre Dumas
Comte de Monte-Cristo 1841~1845
[訳]山内義雄
ぼくの少年時代の小さな胸を熱く濡らしたり、薄氷のように張り裂いたり、蜂のように襲撃してきた本はいくつもあるのだが、その途方もない興奮の度合い、ときに凍りつくような恐怖に富んだスリル、主人公の胸のすくリベンジの次々の展開、何度も読みたくなる麻薬のような吸引力といった点で、『巌窟王』にまさるものはなかった。
ずいぶん前のことになるが、どこかのデパート(渋谷東横だったか)の古本市でやっと当時の『巌窟王』を見つけた。講談社世界名作全集の第3巻にあたるもので、野村愛正が翻案していた。昭和25年(1950)の初版だから、まちがいがない。「そう、そう、これだ」と感慨が深かった。
それからしばらくして、ある昼下がりにざっと目を通したら、いまでも鮮やかに憶えている挿絵やセリフが目にとびこんできた。挿絵は少年ものの名人絵師の一人、梁川剛一だった(装丁も表紙も口絵も)。半分以上の挿絵が懐かしい。
よく見ると漢字はまだ旧活字で、各國、檢事、來た、顏、氣持というふうになっていたが、すべて漢字にはルビがついている。意外だったのは、促音が小さくなっていなかったことだ。

講談社 定価180円(当時)
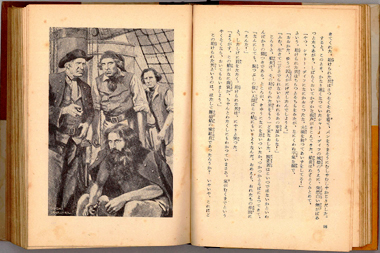

おそるおそる冒頭の場面を読んだ。うっすらとではあるが、当時のぼくが雲母を剥がすごとく蘇ってきた。
「けずりとつたような見上ぐる斷崖! とげとげと刃(やいば)を植えたようにとがった岩角! すこしでも海が荒れようものなら、だだん、だだんと打ちよせる怒濤に數十メートルのしぶきがあがり、一気に島ぜんたいをのんでしまうかと思われる、フランスの、地中海に面して、マルセイユという繁華な港がある。その入口近くの海上に、岩ばかりでできたシャトー・ディフという小嶋があつた」。
そして、「當時、フランスの人たちは、シャトー・ディフのやみ牢に入れられたら、生きて二度とこの世の光は見られないといつて、怖じけをふるって恐れていたものだ。じつさい、生きてこの世にでてきたものは、まえにもあとにもたった一人しかいなかつた」。
これでは、少年は息をつめて身構えるのはあたりまえだ。この「たった一人」って誰なんだ? こんなところからお話が始まるのか? 続いて、こう書いてある。
話は、いまから130年ほどまえにさかのぼる。西暦1816年、この年はどんな年かといえば、有名な皇帝ナポレオン・ボナパルトが、最初に流されていた地中海のエルバ島をやみ夜にまぎれてぬけだし、フランス本國に上陸してきて、たちまち國王ルイ18世をおいはらつて、フランス全土を自分の手に取りかえした。そのあとで歐州連合とワーテルローで戰つて大敗北をして、こんどはセント・ヘレナという島に流された。これが1815年のできごとだから、1816年は歴史に名高いその年の翌年なのである。
ある日、このシャトー・ディフの牢獄に政府の上役人のが巡視にやつてきた。はじめに軽い罪人にあつていろいろなことをはいたうえ、あきあきしたようすで典獄にむかって、
「囚人と言うものは、百人あっても、一人にあうも同じことだ、みんないうことがきまつている。自分は無實だ、食べ物が惡い、とな。まだほかにだれかいるか?」
「はい、地下のやみ牢に二人います。一人はきちがいで、一人はひじように危險な、おそろしい男です」
そうだった! これで、ぼくはこの異様な世界に巻きこまれるように引きこまれていったのだ。あとは、ずいずいずっころばし、手に汗握るばかり。布団にもぐりこみ、もう、おとさんが呼んでも、おかさんが呼んでも、聞きっこなあし、だ。嗚呼、そうだった。
黒岩涙香(431夜)の『巌窟王』は、30年ほど前に読んだ。エドモン・ダンテスが団友太郎に、モンテ・クリストが巌窟島(いわやじま)伯爵に、ファリア神父が法師梁谷になっていたのには驚いたが、波瀾万丈と奇想天外とをとりこんだ手腕はさすがなもので、なるほど、この手の物語編集力が最近はずいぶん落ちぶれたものだと思った記憶がある。
しかし、本物のデュマの『モンテ・クリスト伯』を読むことになったのは、それから数年後に始まって、なんと5年もかかってしまったのである。たしかどこかで中野翠さんが、『モンテ・クリスト伯』を愛読書の一番にあげていたはずだが、それからするとぼくは失格だ。
読書術にかけても速読にかけても、ふだんはほとんど不便を感じないほうなのに、なぜこんなことになってしまったかと考えてみると、これはあまりに少年期の『巌窟王』が効きすぎていたのである。いまだに母親のタマゴ焼の味や水菜(みずな)のおすましの味が抜けなくて、立派な京懐石のタマゴ焼に、いまひとつ乗れないのに似ている。
むろんデュマは大好きなのである。ただし『三銃士』も『ダルタニャン物語』も、そのあらかたを少年少女名作全集のたぐいで読んでしまったので、どうもちゃんとデュマにとりくんだというふうにはならない。
たしか新宿富久町の横田アパートにいたころに、『マルゴの王妃』と『王妃の首飾り』をおもしろがって読み、それが耽読できたので、その勢いを借りてなんとか『モンテ・クリスト伯』を読み切ったのだったと憶う。ピンクフロイドをかけながら江戸川乱歩全集(599夜)と夢野久作全集(400夜)をかたっぱしから読んでいた時期だった。
その程度なのだ。こんなわけだから、今夜は『モンテ・クリスト伯』を“文学読み”することはあきらめている。とてもその任じゃない。そのかわり、アレクサンドル・デュマを“モンテ・クリスト伯読み”したい。波瀾万丈と奇想天外をデュマに返したい。
もうひとつ、今夜デュマをとりあげたことについては、ささやかな伏線がある。年末に刊行した『世界と日本のまちがい』(春秋社)で、ぼくは思いきってナポレオン戦争を扱って、それをもって「ネーション・ステート」(国民国家)の本質を論じるための舞台素材にしたのだが、デュマを語ることは、このナポレオン時代のもうひとつの異様な動向を語ることになるという脈絡があるのだ。まあ、あまり詳しい話にはしないことにするけれど。
では、さっそく始めるが、デュマという作家、ともかく破天荒な男なのである。だいたいこの時代の作家たちは、みんな変だった。とくに自分の活動と歴史とをつなげたがった。
デュマが、ナポレオンが皇帝になる2年前の1802年に生まれて、普仏戦争が勃発した1870年に死んだことだけは、とりあえずおぼえておいてほしいのだが、この時代を生きた大作家たちは、みんな「歴史と自分の生涯を一緒くたにする癖」があったのだ。
自伝を歴史化し、歴史を自伝化したがったのだ。たとえばシャトーブリアンは『墓の彼方の回想』という奇妙な題名が象徴しているように、死後出版を想定した自伝を書いたのだし(1849)、962夜の『レ・ミゼラブル』のところでは触れなかったのだが、ユゴーは『言行録』とか『見聞録』といったリアルタイムなノートを“歴史現在的”に書きつづけてもいた。
あとでも書くけれど、これが「フランスのロマン主義」というものなのだ。「ナポレオンの時代」というものなのだ。実在と歴史とは自分において密接につながっていると思いたい時代だったのだ。
デュマの時代、こういう連中がもともと多かったのだが、しかしデュマはこの点においても並み居る連中より一段と破天荒だった。1851年から『回想録』を公表しつつ書き始めると、1854年までに全22巻を刊行し、その後も『思い出』を加えて、なんと30巻にのぼる「デュマの歴史は世界の歴史」ともいうべき自伝全集を刊行してしまった。これはいささか異常だ。出口王仁三郎級というのか、一人で中里介山(688夜)を10人ぶん演じたというのか。
このようなのっぴきならない自己歴史癖があることをアタマに入れたうえで、以下のデュマの生き方・書き方の波瀾万丈・奇想天外を、“モンテ・クリスト伯読み”してほしい。
まず、ちょっとした「数字」を紹介しておこう。デュマが生涯で出版した本は600冊である。改版を入れると1000冊をこえる。べらぼうだ。
本ばかり書いていたのではない。メディアにも手を出した。雑誌王・宮武外骨(712夜)には及ばないが、自分が発行発売元になって8種類もの新聞・雑誌を創刊した。バルザックほどではないが、すべて短期で休刊・廃刊に追いこまれている。投資額も破格だった。印税で建てた豪邸には、今日の価格に換算してざっと10億円の建設費をかけている。それをぬけぬけと「モンテ・クリスト城」と名付けた! その印税というのが、『三銃士』で3億円くらい、『モンテ・クリスト伯』で5億円くらい。半端じゃない。
愛人の数もざっと30人の名前がわかっている。不倫もしまくった。恋をしていないと書けない男だったのだ。
これでデュマがどの程度の「規模」で生きていたかが予想がつくだろう。が、しかし、だ。デュマがおもしろいのは、その「規模」で“物語王”を現実にも演じたということなのである。
それでは、いよいよ“モンテ・クリスト伯読み”を披露するけれど、のっけから怪しい。デュマの出生と肩書に「血の問題」と「父親の宿命」が隠されている。
血の問題というのは、デュマには黒人の血が4分の1入っていたということである。なぜ、そうなのかというと、ルイ15世時代に砲兵隊長をしていた祖父が、大西洋の彼方のハイチのサンドマング島(イスパニョーラ島)で、黒人奴隷でいちばん美しいとされていたセセット(のちにマリを名のる)を娶り、その長男として生まれたのがデュマの父親のトマだったからだ。
実はデュマという名が、「農家のマリ」の「農家の」(du mas)が一語になってDumasになったものだった。それをデュマは『回想録』で、自分の父の戸籍名は「トマ・アレクサンドル・デュマ・ダヴィ・ド・ラ・パイユトリー」というもので、だから貴族の出身なんだと偽った。「ド」が入ればフランスでは貴族をあらわすのだけれど、これはあきらかに経歴詐称である。デュマの血はようするにハイチの「クレオール」(1085夜)だったのだ。
このデュマの詐称は、あまりに豪勢だったデュマのふるまいにやっかんだ連中からのちに痛罵のような非難をうけるのだが、デュマ自身はそんなことは気にかけていない。経歴詐称は最近の世の中でこそ週刊誌ネタどころか、代議士失格の切り札にさえなってしまうけれど、この時代はそんなことは問題にすらならない。
それどころかナポレオン自身が皇帝を自称し、甥っ子がナポレオン3世界を詐称した時代だったのである。それよりなにより、エドモン・ダンテスが復讐のためにモンテ・クリスト伯を名のっていなければ、あの物語自体が成立しないのだ。
デュマにとって、父親が自分の存在証明そのものだったということは、その後のデュマの生き方と書き方を決定づけている。
父親トマが生きたのは、フランスでアンシャンレジューム(旧体制)が解体して、フランス革命に突入していった時代にあたる。父親はこのとき、国王の軍隊に所属していた。「王妃竜騎兵隊」という。なにやら“ベルばら”めいているが、王妃マリー・アントワネットを守る連隊である。
1789年にフランス革命の火蓋が切って落とされた。国王軍はこれを迎え撃つ。父親トマはパリから北東85キロのヴィレール・ル・コトレという町に駐留していて、革命の狼煙が上がったことを知った。ここは王家のオルレアン公ルイ・フィリップのご当地から近く、住民たちは公爵に保護してもらうことを期待した。そこで23人の竜騎兵が選抜されて、防備にあたった。トマはその一人となった。
このとき町にいたマリという娘にトマが惚れ、この二人が10年後にデュマを産むというふうになっていく。
事態は革命派の優勢に傾いていった。知ってのとおり、フランス革命はブルジョワの気勢によって成就した。しかしトマはそのどさくさのあいだに、義勇軍に参加した。そこに小柄な男がいた。この小柄な男はまことにはしっこくて、たちまち連隊長にのしあがってきた。トマはこの連隊に所属した。連隊長は恐ろしいほどの指導力だった。名前はナポレオン・ボナパルトといった。
こうしてトマは、このあとナポレオンとともに終始、トップ軍事にかかわることになっていった。ナポレオン軍麾下の将軍の一人にすらなった。ところがナポレオンが1799年に「ブリュメール18日のクーデター」をおこした前後のことらしいのだが、トマはナポレオン軍のイタリア遠征(エジプト遠征のあとのこと)の途中で、敵軍につかまって監禁されてしまう。のみならず毒をもられて聴力を失った。救助をナポレオンに頼む手紙を書いたものの、もはやナポレオンはこんな男を重用するはずはない。トマは失意のままに44年の生涯を閉じた。
これでだいたいの見当がつくだろうが、この父親の生涯の武勇伝と失意とが、のちにデュマの物語の最大のテーマとなったのだ。
フランス革命とナポレオン戦争との裏腹なダイナミズム、戦火の渦中で恋をすること、裏切りがおこること、助命や嘆願がむなしいこと、こうした出来事がデュマをして“物語王”にさせる下地となったのである。
デュマがどんな少年期と青年期をすごしたかということは、省いておこう。『回想録』によると、5歳でビュフォンの『博物誌』、6歳でデフォーの『ロビンソン・クルーソー』、7歳で『聖書』『千夜一夜物語』を読んで暗記し、ギリシア・ローマ神話にとくに夢中になったということになっている。よくある話だが、まあ、それに近いことがあったのかもしれない。
15歳のとき公証人のもとで見習いになり、ダンスをおぼえ、恋をおぼえ、芝居に熱中するようになった。なかでも芝居がデュマをめざめさせた。これは事実だ。デュシス作の悲劇『ハムレット』というすこぶる怪しい舞台を見たらしく、これがいたく気にいった。
この時代、まだ本格的なシェイクスピアのフランス語訳はなかったのだから、眉唾ものの翻案なのだろうけれど、しかし翻案というもの、黒岩涙香がそうであるように、ある種の達人の手にかかると原作よりずっとおもしろい。いまだって、よくできた映画がそうであろう。
こうして、ナポレオンがセントヘレナ島で死んだ翌年の1823年の春、デュマはパリに出る。いろいろの紹介状を手にして勤め先をさがしているうちに、オルレアン公の秘書室の事務にありつくことになった。あのオルレアン公だ。「父親の因縁」が動きはじめたのである。デュマは、ここでたっぷり力をつけて劇作家になろうと決める。秘書室には歴史に詳しい者もいた。
人脈も少しずつ広がった。書物フェチともいうべきシャルル・ノディエと知りあい、同い歳のヴィクトル・ユゴーと知りあった。二人とも当時先行していた物語作家ピゴー・ブランの愛読者で、デュマは「演劇とは物語である」という確信を深めていった。その物語も“歴史的現在”にもとづくべきだった。
さっそく17世紀スウェーデンのクリスティーナ女王をモデルとした『クリスチーナ』を5幕に仕立て、コメディ・フランセーズに応募した。上演許可は出たが、陽の目を見るのはまだあとになる。つづいて『アンリ3世とその宮廷』を書いた。そのころパリでは、芝居の題材になりそうな物語はほとんど音読されていた。音読に耐えられないものは当たらない。そこでデュマは一計を案じて、自分の作品の朗読会を開き、人士を招くことにした。これが功を奏して、『アンリ3世とその宮廷』は1829年2月に上演されることになった。オルレアン公ルイ・フィリップも謁見してくれた。大成功である。「大デュマ」がついにデビューした。
デビューしてからのデュマは多くの面で、まるで計算しつくしたかのように精力的になっていく。まず、このことこそ得意なのだが、次々に恋をする。メラニー・ヴァルドールとの恋が有名だ。これもお得意なようだが、不倫もした。これはもっと得意だが、女優や歌手にものべつ手を出した。恋愛はすべてデュマの活性剤になっていったようだ。
その一方で、不倫をテーマの『アントニー』を書いて当て(初演1831)、そのあとつづけさまに『ナポレオン・ボナパルト』『ネールの塔』『アンジェール』を劇作すると、喜劇にまで手を出した。7、8本を書いたはずだ。
猛然たる執筆能力を発揮しはじめた。途中、のちに『椿姫』を書いた息子のデュマ・フィス(小デュマ)が育っていった。
このあたりで、デュマは転換をはかる。小説を書きはじめたのだ。これにはオーギュスト・マケという若い相棒の協力と、ネルヴァルの助言が見逃せない(ネルヴァルはそのうち「千夜千冊」にとりあげる)。とくにマケは原稿の下書きや筋書きの多くを受け持って、何本かを“共作”するのだが、発表はすべてデュマ名になった。それでもマケはその仕事に甘んじていたようだ。
なかで長編の『騎士アルマンタン』が好評を博すと、デュマとマケはいよいよ新聞連載小説を主戦場にしていった。こうしてついに記録的大ヒットが生まれたのである。それが「シエークル」紙に連載した『三銃士』だった。
新聞連載小説というものは、のちに新聞王の異名をとるエミール・ド・ジラルダンのアイディアである。フランスのジャーナリズムはだいたい1830年代に未曾有の発達をはたしたと見るといい。これは産業革命の波及がもたらしたもので、最初のフランス情報メディア革命がおこったわけだった。とくにジラルダンの「プレス」紙の戦略が際立った。
ジラルダンは、それまでの新聞が年間購読80フランだったところを、半額の40フランにした。そのため広告を大量に取り込み(そこでフランス式の広告代理店が登場してきた。これはのちのアメリカ式とはちょっと異なっている)、そのうえで連載小説という無類の方式をつくりだした。バルザックの『老嬢』が連載され、それだけで1万部以上の定期購読者が上乗せされた。
これをライバルの「デパ」が真似た。ウジェーヌ・シューの『パリの夜』がバカ当たりした。ゴーチェは当時のことを「病人たちは『パリの夜』の結末がわかるまで、なんとか死なないようにしていたほどだ」と書いている。つづいて「シエークル」がデュマに頼み、『三銃士』が始まったのだ。連載小説の腕はデュマが一番うまかった。冴えまくっていた。これぞというところで、「つづく」という方式を最大限にいかしたのだ。デュマは“場面王”でもあったのだ。
ここまでのことで、ちょっと注釈を加えておく。
デュマの青少年期から壮年期というのは、時代がフランス革命からジャコバン党による恐怖政治へ、そしてナポレオン時代へと激しく動き、1814年にナポレオンが失脚すると(デュマ12歳)、今度はメッテルニヒによるウィーン体制が敷かれたのも束の間、いったんブルボン朝が戻った直後の1830年(デュマ28歳)には七月革命がおこって、国王は亡命してしまい、ついではルイ・フィリップ(例のオルレアン公)が「フランス国民の王」を名のったというような、無節操というほどに次から次への変転があった時代なのである。
このようなめまぐるしい変転で、多くのフランス人は「歴史の主権の移動」と「価値観の浮浪性」ということに、見切りがついた。市民の側に立とうが(市民といっても自己保守的なブルジョアのことをいうのだが)、王権に立とうが(といってももはやルイ王朝ではないが)、ノンポリでいようが(といっても貧富の差は激しいが)、どちらにいても歴史の波濤のほうがはるかに大きいということがわかったのだ。
実際にも、あれほど「自由・平等・博愛」を謳ったフランス革命はたった数年でロベスピエールの恐怖政治に突き落とされたのだし、そのあとはたった一人のナポレオン・ボナパルトによってヨーロッパ中が戦争に巻きこまれたのだし、ヨーロッパの平和を謳うはずだったウィーン体制は、その逆に、ナポレオンの戦争によって刺激をうけた各国のナショナリズムの嵐に沸き返ったのである。
日本では、敗戦と戦後によって価値観が一日でひっくりかえったというので、これをもってなげやりに社会不信や日本不信の第一の理由にあげるルサンチマンな風潮がいまなおあるのだが、フランスではこんなこと当たり前なのである(ドイツでもイタリアでも同じだ)。

また、もうひとつ、この時代を挟んで「知」が大きく変化しつつあったということがある。
ミシェル・フーコー(545夜)が『言葉と物』や『知の考古学』でうまく分析してみせたことだったが、18世紀は博物学に代表されるように、「森羅万象は分類されるべきだ」と考えられた。それが19世紀に向かうと、世界はそんな分類表にはあてはまらないことが見えてきた。分類に載ってないこと、そこにこそ新たな好奇心が移っていったのだ。
これらのことがあれこれ絡まって何が登場してきたかというと、ひとつにはイギリスに半世紀遅れて産業革命が広まり、ひとつには962夜に書いたように、フランス・ロマン主義が台頭した。これがごくジョーシキ的な見方だ。それをちょっと突っ込んで見るとどうなるかいうと、「メロドラマ」がフランスを覆っていくというふうになる。
メロドラマという用語を今日の感覚で見ないほうがいい。当時のメロドラマの意味はまったく異なっていて、ジャコバン政府やロベスピエールによって、はからずも政治も革命も実のところは「倒錯と混沌のカーニバルにすぎない」ということが暴露されたのだが、この情念のようなものを民衆は忘れられなくなったのだ。そして、その混乱をもたらすような情念の吐け口を舞台や小説に求めたとき、それがメロドラマとよばれたのだった。
もともとメロドラマは17世紀イタリアに端を発していて、台詞(せりふ)をすべてメロディにのせる演劇をさしていた。それがフランス革命期に既存のジャンルにはまらないものをメロドラマと呼ぶようになり、さらに恐怖演劇や暗黒小説やグロテスクな物語の呼び名になっていった。シャルル・ノディエが導入した「ヴァンピリスム」(吸血鬼趣味)も、そのひとつだった。デュマが最初に演劇に狙いをつけたのは、このようなメロドラマ目当てだったのだ。
このメロドラマとともに広がっていったのが、ロマン主義なのである。ただし、これは「フランスのロマン主義」というもので、ドイツ・ロマン主義やイギリスのゴシック・ロマンとはちがっている。1830年代にピークに達した。
このことの意味についてはすでに962夜にも少し書いたので、ユゴーの『エルナニ』上演がおこした歴史的な文芸的事件の意義とともに、今夜は詳しいことは言わないが、そもそもロマン主義は古典主義に反旗を翻したものだった。
古典主義はギリシア・ローマに規範をとるのだが、ロマン主義は先駆者のシャトーブリアンやスタール夫人がそうであったように、「新しいスタイル」を求める。
新しいスタイルを描くのに一番適しているのは、当然のことに「現在」だ。そこで最初は、当時の世相や日常の出来事が現在的に描かれたのだが、それをちょっと深めようとすると、現在の出来事を生み出したはずの「近過去」が必要になる。そのため、ついでは、近過去の歴史を現在とのつながりで取りこむ演劇や小説が次々に誕生していった。
デュマを育てたのは、このメロドラマ的ロマン主義だった。
ついでに言っておくが、フランスのロマン主義は、また「セナークル」によっても育まれた。これは文芸サロンのことだ。ユゴーの「セナークル」が先駆した。ヴィニー、サント・ブーブ、デシャン、ラマルチーヌ、バルザック、ミュッセ、メリメ、ネルヴァル、そしてデュマたちは、すべてユゴーの「セナークル」のメンバーだった。これだけ若い綺羅星の作家が集っていれば、歴史的現在を叙述する物語が、この渦中からどのように生まれていってもおかしくはない。
「セナークル」については、これ以前のコーヒーハウス(491夜)やロココのサロン(474夜)と、また、のちにパリやベルリンやチューリッヒに登場した文学キャバレー(97夜)と比較するとおもしろい。

というようなわけで、デュマは新聞連載とロマン主義的なメロドラマ風な物語と、そして「父親の宿命」とを組み合わせて、『三銃士』を書いたのだった。1844年のこと、42歳のときだ。
独創したのではない。ネタ本に「母型」があった。クルチルス・ド・サンドラなる者が書いた『国王銃士隊・第一隊長ダルタニャン氏の回想録』というもので、1700年にケルンで、その後もアムステルダムで出版されている。ただしダルタニャンは、ルイ14世時代のマザラン宰相に信頼され、フロンドの内乱にも活躍して1667年には銃士隊長になっている実在の人物だ。のちに伯爵になったが、オランダの戦闘で戦死した。
デュマはこの素材に目をつけた。物語として英雄戦士の母型をもっている。主人公の時間が直線的に流れ、周辺の時間が循環的に組み上げられている。それに、なんといってもダルタニャンにアトス、ポルトス、アラミスという三銃士がくっついているのがいい。アトスは沈着冷静な武人、ポルトスは人のよい豪傑、アラミスは詩人っぽくて聖職者に憧れている。この三位一体がよかった。これまた、のちに立川文庫の『真田十勇士』からモンキー・パンチの『ルパン3世』までが、ごっそり真似したくなる物語母型なのである。つまりは“三人の銃士”とは、「孫悟空」マザーや「桃太郎」マザーの変型なのだ。
こういうことをデュマとマケは見抜いた。まさに目のつけどころがバツグンだったのだが、もうひとつ、『ダルタニャン回想録』の記述スタイルに目をつけたのもデュマの炯眼だった。というのも、『ダルタニャン回想録』は、文学史用語ではいわゆる「偽回想録」というスタイルになっているもので、作家が、物語の主人公から聞かされた話を一人称で語るというふうになっていたからだ。
このスタイルをつかうと、他の登場人物のことまで語りおろし型の実録風に語れたのである。これがデュマの魔術に翼をつけたのだ。

「シエクール」連載の『三銃士』はめちゃくちゃに当たった。新聞の実売も、そのあとの単行本のほうも、あっというまに2万、3万部になった。その後はいったい何部売れたのか、はかりしれない。
「パリ中に三銃士がうようよしていた」と言われたほどだった。当時の総理大臣のフランソワ・ギゾーは、「シエクール」が自分を攻撃している新聞であったにもかかわらず、こっそり『三銃士』を読むために秘書官にこの新聞を届けさせ、「シエクールが何を言うかは気にならないが、ダルタニャンが何を言っているかが気になるんだ」という名セリフを吐いた。いまどきの日本の政治家もこのくらいは言ってみろよというところだが、実はいまどきの新聞にはそういう「つづき」を期待させる連載小説が一つもない惨憺たる現状だ。
むろん、こういう新聞小説をこっぴどく批判する連中もいた。皮肉屋のサント・ブーブがその一人で、「あんなものは量産文学だ」と難癖をつけた。
ちなみに『三銃士』は、さらに『二〇年後』『ブラジュロンヌ伯爵』の続編にまでつながって、例の『ダルタニャン物語』を構成する。のみならず、66歳のときのことになるけれど、デュマはこれらを懐かしんで週刊「ダルタニャン」を発行さえしたものだ。
こうしてデュマは、一躍、新聞連載の物語王になっていった。ここに全力を傾注することになったのが『モンテ・クリスト伯』なのである。
しかし、この波瀾万丈・奇想天外にも、タネ本も伏線もあった。1842年、デュマはイタリア旅行をするのだが、このときデュマはナポレオンの甥にあたるジョセフ・ボナパルトの知遇をえて、ナポレオンが流されたエルバ島に渡った。そのあとジョセフ王子らと付近をクルージングしているとき、一つの島が目にとまった。聞けばモンテ・クリスト島であるという。
帰って、あれこれの史料や資料をマケとともに当たっているうちに、『パリ警察古文書調査覚書』というものに出会った。かの警視総監ジャック・プーシェの監修だ。そこに「ダイヤモンドと復讐」という記録が入っていた。
ナポレオンの第一帝政期、パリに住む若い靴屋の事件の犯罪記録だった。その若者は大金持ちの娘と結婚することになっていたのだが、それを妬んだ4人の友人が、その若者を「王のスパイ」として密告した。若者は夜中に詮議もうけずに逮捕され、そのまま7年間を牢獄に送った。牢獄にはイタリア人の聖職者がいて、若者はその牧師に献身的に尽くし、臨終を看取った。このとき若者は莫大な遺産を譲り受けた。釈放後、若者は遺産を手にしてパリに戻ると、変装を駆使して自分を陥れた4人の友人に復讐していったというのだ。
この記録に、デュマは「謎のモンテ・クリスト島」を組みこんだのである。まさに『巌窟王』は、この下敷きの話だけであらかた出来上がったようなものだった。ちなみに、この靴屋の若者は4人目の復讐にとりかかったところで正体を見破られて、殺されてしまったらしい。

デュマとマケが、この話をどのくらい輻湊させ、波瀾万丈にしていったかということは、もはや説明するまでもないだろう。さまざまな物語編集術が、ほぼ完璧に駆使されたといってよい。
なかでも一番の工夫は、次のようなところにあった。
(1)時代をややずらして王政復古期の1815年から七月王政の1839年までの25年間にしぼったこと(そのためすべてのフランス人を歴史的現在に巻き込むことになった)、(2)主人公のエドモン・ダンテスを一等航海士にしたこと(そのためパイレーツ風の冒険をいくらでも組み込めるようになった)、(3)恋人を大金持ちではなく、メルセデスという可憐な美女に仕立てなおしたこと(しかし、のちに大金持ちに貰われてしまうようにしたこと)(→つまり、貫一お宮が真似したくなるようにしたこと)、(4)物語のトポスをマルセイユとローマとパリの3都市に分有させたこと(そのため、話変わってというふうに、オムニシエントな目とオムニプレゼントな目が交互作用をおこすようになった)、そして、(5)牢獄の日々からの脱獄を描く場面に、息づまるほどのファースト・クライマックスをもってきたこと(これで、この物語がいかに復讐に燃えた男の話になるかを決定づけられた)、などなどだ。
これらは、ぼくがイシス編集学校の「破」で提供している「物語編集術」を地でいっている。たいしたもんだ(ちなみに、この「物語編集術」の一端の秘法は、近々、ダイヤモンド社から『物語編集力』という単行本になる。木村久美子のもと、編集学校の師範の諸君が協力して構成執筆したものだ)。
まあ、『モンテ・クリスト伯』のことは、これ以上は突っ込むまい。それより見逃せないのは、このあとのデュマが“偽物だか本物だかわからないモンテ・クリスト伯”になっていったということである。
まず偽物っぽいことから言うが、デュマはさすがにダンテスのように金銀財宝を手にしたのではないが、そのかわり、連載小説とその単行本化によって莫大な印税を手にしたことは、すでにのべた。1840年代だけで10億円は下らないといわれる。ところがデュマは、これを豪邸「モンテ・クリスト城」をはじめ、湯水のように費いはじめたのだ。
復讐する相手などはいない。父親の血筋を貴族にするために、自身の快楽が頂点に達するために、歴代の文豪に自分が列せられるために、ただただ大枚をはたいていったのだ。豪遊パーティも何度も開かれたし、フランス一の料理による晩餐会も何度も開かれた。
それだけではなく、1847年にはパリ北部のタンブル通りに1700席をもつ「歴史劇場」なるものを建設したり、前に紹介しておいたように、合計8種類の新聞や雑誌の創刊を引き受けた。
しかしそれもこれも、「モンテ・クリスト城」のバルコニーに、ホメロス、ソポクレス、シェイクスピア、ゲーテ、バイロンから友人のユゴーにおよぶ彫像をずらり飾ったことほどには、異常な“偽物”ぶりではなかったといっていい。これには年長のバルザックさえ、「この狂気の沙汰はデュマにしか成就できないものだ」と呆然自失したほどだった。
これではさしもの貯金も、すぐに底をつく。実際にもこのあと、デュマは借金地獄と印税獲得のための小説量産との、いたちごっこに追いこまれていった。それでも『王妃マルゴ』『モンソローの奥方』『四十五人隊』の3部作も、『王妃の首飾り』『アシジェ・ピトゥー』『シャルニー伯爵夫人』『ある医師の回想録』の4部作も、すべてがヒットし、すべてにデュマは手を抜かなかったのだ。
いったいアレクサンドル・デュマとは何者だったのだろうか。物語王であり、近傍の歴史に活劇の息を吹きこんだ魔術師であり、そして歴史的現在を体現する作中人物になってしまった男だったのである。ようするに、偽物のモンテ・クリスト伯になった男なのだ。ただ、デュマの壮年期はもはや「ナポレオンの時代」ではなくなっていたのに、それがこの物語王には見えていなかった。
それを象徴する、さらに見逃せない出来事がある。二つのエピソードを伝えたい。
ひとつは1848年2月24日に、二月革命がおこった。これはパリが燃えて、ルイ・フィリップが退位せざるをえなくなった暴動のようなもので、歴史的にはウィーン体制の壊滅を意味していた。が、デュマはこの革命の意味を見誤った。すでにパリが最高の歴史的現在に達していたのに、デュマは「歴史劇場」そのほかで、『マルゴの王妃』や『三銃士』の上演の連打をするほうに走ってしまったのだ。劇場よりも市街のほうに刺激と興奮があったことを、見抜けなかったのだ。
これは失敗だった。いずれ「千夜千冊」でジャン・カスーが二月革命の精神史をみごとに活写した『1848年』や加藤節子の『1848年の女性像』(いずれも法政大学出版局)などを紹介したいと思っているが、それらを読めばわかるように、この時期のフランスは、とうていデュマのメロドラマでは乗り越えられないものになっていたのだ。
しかし、もうひとつの出来事は、デュマの革命的ロマン主義ともいうべき「強引」を象徴する。こちらにはちょっとだけ本物のモンテ・クリスト伯がいる。
1860年6月のこと、58歳になっていたデュマは、シチリア島のパレルモに一人の革命的な男を訪ねていた。男というのはジュゼッペ・ガリバルディだ。
『世界と日本のまちがい』にもふれておいたように、そのころイタリアは「リソルジメント」(再生・復活)を叫んだカルボナリ党や青年イタリア党が出てきていて、1859年にはカヴールを先頭にイタリア統一のための戦争に取り組んでいた。『まちがい』にも書いたように、これは日本の幕末維新の運動とぴったり重なる時期のナショナリスティックな革命運動で、なかなかめざましい。
この運動を継承したのがガリバルディで、1860年に1000人の赤シャツ隊を引き連れ、シチリア島に上陸するとパレルモに臨時政府を樹立していた。デュマはそこへ行ったのだ。おそらく血が騒いだのであろう。なにしろデュマのテーマは革命的ロマンに満ちた戦争というものなのだ。
ガリバルディはデュマを迎えて、厚遇する。デュマはデュマで、せめてもガリバルディの回想録(またしても!)を書いて応援をしたいと思っていた。ところが、事態はそんな生易しくはない。ガリバルディが次の作戦としてナポリ王国に進軍しようとすると、たちまち苦戦を強いられた。武器と弾薬が決定的に欠けている。
そこでデュマが、自分がフランスに戻って武器弾薬の調達を引き受けようと申し出た。ガリバルディはその熱情にほだされて、これを依頼する。デュマは借金などものかは、まるで天野屋利兵衛のごとくに、いやそれ以上に、大量の武器弾薬を2カ月後にみごとに運びこんだのである。このあと、ガリバルディが南イタリアに進攻してナポリを解放すると、ここにイタリア統一の第一歩が確立された。
つまりはデュマはイタリアの革命戦争を支えたのだ。デュマは勇んで、「インディペンデンテ」というイタリア統一をスローガンとする新聞の発行を買って出たほどである。自分の国のフランスでは見誤ってしまった現在を、なんとイタリアでは取り戻したのだ。こういうところ、その後の歴史を見ていると、案外、看過できない行動である。たとえば、ゲバラ(202夜)は、故国アルゼンチンよりもキューバで、そしてキューバよりも別国の南米諸国でこそ革命性を発揮したのだから。

デュマには、どうもこういうところがあったのだ。実は1848年の二月革命を読み誤ったデュマが、その革命の余波がベルリンに波及したとき、自身の失敗を取り戻すべく(実際にそういう自覚があったのかどうかはわからないが)、ブリュッセルに赴いたことがある。
これは、友人のユゴーが二月革命でブリュッセルに亡命したのを追ったものなのだが、このときデュマの耳に「ユゴー暗殺」の噂が届いてきた。こういうときはデュマの血が騒ぐ。さっそく各方面に手を打って、ユゴーを助けた。こういうあたり、デュマはやっぱりモンテ・クリスト伯をしたかったわけなのである。
ぼくは、こういう人物を“愛すべき人物”だとは言わないけれど、こんなふうに「物語を実践したい」と思っている男が、実はなんとも大好きだ。つまりはぼくは、どんな人物であれ、それがエドモン・ダンテスの類縁だというのなら、絶対の味方をしたいのだ。
いや、これはエドモン・ダンテスやデュマにのみ感じていることではない。すでに書いてきたことだが、アルセーヌ・ルパン(117夜)にもエイハブ船長(300夜)にも、ジョン・ラスキン(1045夜)にもゾシモ神父(950夜)にも、感じていることなのだ。ロバート・ラドラム(274夜)のジェイソン・ボーンが好きなのも、そこなのだ(マット・デイモンの映画はイマイチだったけれど)。
この、奇妙な友情を、さて、何と説明していいかはわからないが、モンテ・クリスト伯爵自身は、こう言っていた。最終巻の最後の最後に出てくる次のセリフだ。伯爵がマクシミリアンに言う。
「待て、しかして希望せよ!」