父の先見


青土社 2005
Donald Richie
The Image Factory 2003
[訳]松田和也
クール・ジャパンとかジャパン・クールという。ちょっとした「和」のブームをかっこよく言い直した用語のようだが、どうにも擽ったい。浮いている。
クール・ジャパンとは、日本の伝統と「かわいさ」とがまぜこぜになって、ファド(流行)をおこしつつあるものをいう。いわゆるヒップ(先端)なのではなく、そこに「日本というスタイル」がかわいい刷り色になっているものをいう。そもそもスタイルとは、チェスターフィールドらがとっくに定義してきたように「思考の意匠」であるはずなのだから、クール・ジャパンは現在の日本を象徴する日本という国柄(ステート)のスタイルなのだ、ということになる。が、そういうことで、よろしいのか。
欧米ではクールを「かわいい」などとは見ていない。ノーマン・メイラーが「クールはヒップのことだ」と言ったように、ディック・パウンテンやデイヴィッド・ロビンズが「クールは権威に対する不服従を表明する」と言ったように、クールは反抗の持続的スタイルのことなのだ。
日本に日本らしさを求めてやってきた観光客をはじめとするガイジンたちの多くが決まって不満に思うことがある。とくに知識人には不満は決定的で、バーナード・ルドフスキーからスーザン・ソンタグまで、ほぼ一致する。それは、日本に来るとつねに「新奇なもの」ばかりに取り巻かれてしまうということだ。おかげで石庭と五重塔を見た帰りにダッコちゃんやポケモンに出会い、歌舞伎座と浅草に寄った帰りに竹下通りやアキハバラに迷いこみ、どこにもかしこにも名状しがたい“変な日本”があることを見いだすことになる。
ガイジンが不満なだけならまだしも、いまやこの現象に日本の知識人がお手上げなのだ。それどころか大方がクール・ジャパンでいいんじゃないかとさえ思い始めている。が、それでほんとうに、よろしいのか。
先だっての一月二七日の土曜日(二〇〇七)、「連塾Ⅱ・絆走祭」として〈風来ストリート〉と銘打った半日を、自由学園明日館で催した。ぼくはナビゲーターのような役で、六人のゲスト(ゲストとはいえ、これまで連塾の聞き役として参加した連衆から選ぶ。これを「客主」と称んでいる)を、次々に舞台に呼んだ。
舞台というのは、フランク・ロイド・ライトと遠藤新が大正十年あたりから昭和二年にかけて仕上げた、いかにもライトらしい木造の講堂のことをいう。構造と細部のすべてがいまでは悉くセピアな懐古のなかにある。
その講堂での当日の光景は、冒頭ぼくが「風」と「ストリート」の日本芸能文化の話をし、そこへ大倉正之助の大鼓に送られてオートバイ・デザイナーの石山篤が人機一体のエロスとタナトスを語った。ついで、明日館の講堂に「黒い花道」を造作したハイパーダンサーの田中泯が拍子木に送られ、誉田屋源兵衛の鯉をあしらった衣裳で構造を解体する舞に耽り、五輪真弓の《恋人よ》で飄然と去った。
次は写真家のエバレット・ブラウンである。「日本」を撮った写真一四〇枚を連打して、それぞれにコメントを加え、静かな語りで「こういう日本でいいのですか」と問うた。ここで休憩を挟んで、東京新聞の一二〇回にわたる連載最終回を「日本という方法が必要だと私もやっと気がついた」と結んだ福原義春が、資本主義過飽和の日本に含蓄のある警鐘を鳴らし、入れ替わって高橋睦郎が自身の幼なごころの原郷に何が盤踞していたかを、独特の語り口で髣髴とさせた。失われた日本を告知するに、絶妙の語り部となってくれた。
最後は小堀宗実の「遠州好み」の御披露で、存分に茶の湯の趣向とは何かということを堪能させるものだったのだが、一番の場面はぼくが「現在のお茶ブーム、これでいいんですか」と聞き、家元が間髪を容れずに「全然ダメですよ」と言うところだったろう。ぼくは最後に西田幾多郎と井伏鱒二と徳川夢声のフィルムを映し出し、かつての日本人の語りを取り出した。

ざっとこんなふうだったのだが、鈴木清順・井上鑑・植田いつ子・コシノジュンコ・緒方慎一郎・山口智子ほか、参加者の多くが堪能してくれた。「日本という方法」の提示になっていると思ってもらえたからだろう。
そこで、今夜の一冊なのだが、以前からとりあげたいと思っていたドナルド・リチーの『イメージ・ファクトリー』にした。〈風来ストリート〉のあとにふさわしいと、ふいに思ったからだ。
リチーはGHQが統括した占領軍のタイピストとして来日して以来、長く日本に滞在した。日本のあれこれを熟知する「ニューヨークタイムズ」や「ワシントンポスト」のジャーナリストであって、映像作家であって美術評論家である。すでに『小津安二郎の美学』(フィルムアート社)、『黒澤明の映画』(キネマ旬報社)、『日本の大衆文化』(秀文インターナショナル)、『素顔を見せたニッポン人』(フィルムアート社)などを書いてきた。
そのリチーが本書では「日本×流行×文化」のサブタイトルのもと、日本という国柄のなかでは、スタイルは「思考の意匠」というより「イメージ」だけを、とりわけ「イメチェン」(イメージ・チェンジ)を追求しているようだけれど、これはいったい何なのか、それでいいのかということを突いた。現代文化では思考よりもイメージが雄弁であることはどんな国にもあてはまることではあるものの、それが日本においては極端なほどに「思考なきイメージ」の氾濫が大手を振っているという指摘だ。『イメージ・ファクトリー』というタイトルは、そういうイメージ偏重主義の日本のことを揶揄している。
本文では、さまざまな観察と着目と疑問がキャッチーに綴られる。なぜプリクラでは五人一緒にポーズをするのか。なぜラブホテルではショートタイム利用のことを「休憩」というのか。そのくせなぜ、必ず男が主導権をもつような「連れ込み」という名がまかり通るのか。それって、昔の「陰間茶屋」の名残りなのか。
カラオケは「空のオーケストラ」の略称らしいけれど、あんな程度の伴奏が入るだけで、どうしてオケ(オーケストラ)なのか。三十年以上も営業しているパチンコ店はなぜにまた毎日「開店」を自慢したがるのか。「コスチューム・プレイ」の略であるコスプレがマリス・ミゼルやXジャパンに変装し擬装するのはよくわかるが、それで何をプレイしようとしているのか。
ひょっとすると日本人は、その場かぎりの「共解」だけが大事で、ひたすら現在主義に甘んじていたいだけなのではないか。何がイメチェンしたかということだけが、文化だと思いこんでいるのではあるまいか……。まあ、こんな調子だ。
リチーは推理する。アメリカではコカコーラのTシャツを着ることは、「私はコカコーラなんて制度的にも習慣的にも受け入れていない」という意味であり、ミュージシャンがアメリカ陸軍の放出品を着ることは、ベトナム戦争やイラク戦争に反対か無関心であることを表明するのだが、日本ではどうもそのようなアイロニーがないままなのではないか。
だとすると、日本は海外文化は受け売りのままで、もっというなら無批判な現代文化屋になっているのではないか。日本人は海外のファド(流行)を、その思考のコンテキストから切り離して受け入れて平気なのか。どうも理解しがたい。
たとえば日本の青少年がアメリカン・ヒップホップのだぶだぶファッションが大好きなのは、アメリカの黒人の子供や若者たちがスポーツウェアを着て、パンツを下げ、野球帽を逆に被ってあらわすメッセージとなんら関係がない。だいたいアメリカでは黒人以外はこんな恰好を絶対にしない。なぜならあれは部族的アイデンティティであるからだ。あえてそれをする者がいたとしたら、そのことによってメッセージにアイロニーをもたせるミュージシャンやアーティストたちで(それがヒップだが)、それも、その恰好でメッセージが伝わらなければ、すぐやめる。それを日本ではまるで群衆の旗印のようにその真似が大流行してしまう。
リチーはそこで、日本は少なくとも輸入ファッションについては、あきらかに「文盲である」と断定した。その無頓着はおばさんが猫も杓子も着たがるシャネル・エルメス・グッチ現象まで肥大する。輸入ファッションだけではない。スターバックスにもガーデニングにもM&Aにも無頓着になってきた。
海外の文化に無頓着であることは、べつだん羞かしいことではない。それを自分のコンテキストにすれば、それでいい。どこの国だって“海外もの”はおもしろく、それを自分のものにするために文化をつくりだしてきた。ドイツがクレヨンをつくったのはフランスのプチ・ロココやプチ・ロマネスクが入ってからのことだった。
かつての日本もそういうことをした。ただし、どこも試みなかった「日本という方法」で。たとえば江戸の「粋」や「通」や「侠」と言われたスタイルの多くは海外からの「渡りもの」に触発されてのことだった。一例をいえば、「縞」が粋だとみなされたのは、最初はジャワや東南アジアの異質な染め物に目を見張ったからで、それゆえそういうものを「島渡り」と言った。けれども、江戸の流行はそれをただ受け入れたのではなかった。それらを徹底して工夫した。浮世絵という海外にない情報印刷文化スタイルのなかで練磨させ、浄瑠璃や常磐津や新内を好む芸者たちが、婀娜な着物に仕立てて徹底して着こなした。それが「縞」である。その「縞」は財布や煙草入れや野良着にまでなった。
これは文字をもっていなかった日本人が中国の漢字を受け入れ、それを仮名にし、カタカナにし、さらには散らし書きや分かち書きにしていった歴史このかた、日本人がむしろ得意にしていたことだった。そのはずだった。
ところが最近の日本人が好きなシャネル・エルメス・グッチは、買えば、そのままなのである。まったく応用がない。着なくなればクローゼットに吊るしっぱなしか古着屋に売る。だからいつまでたってもエルメスのスカーフは煙草入れにならないし、シャネル・スーツはシャネル・スーツのままで、決して野良着にはならない。日本のヒップホップ・ファッションも黒人そのままなのだ。

いったい、どうしてこんなふうになってしまったのか。きっと理由はいくつもあるだろうが、リチーは、この奇怪な現象の背後に一つのおぞましい言葉が君臨していることを突き止める。それは「かわいい」という言葉だ。
この二〜三十年間というもの(いつから流行したのかは知らないが)、どんな物品の出来栄えやどんなアイドルの印象についても、「それって、かわいい」「かわいいから、いいわよ」「かわいくなーい」で万事が片付けられてきた。「かわいい」は、そう言いさえすれば便利なのか、無責任でありたいせいなのか、実は何もあらわしていないのか、それともすぐには思いつけない何かのテイストを代弁しているのか、よくわからないにもかかわらず、どんな場面でも切り抜けられる言葉になったのである。
たしかに「かわいい」は、エルメスからフィギュアまで、家庭用ロボットからメイドカフェまで、帯留から安室奈美恵まで、現代アートから小料理屋の小鉢まで、片っ端からなぎ倒していった。「かわいい」と言っておきさえすれば、どんなスタイルにもテイストにもあてはまってきた。おそらくちゃんとした意味は、ない。ヴァージョンもない。すべて「かわいい」だけですます。きっといつかの時点で女性たちが言い出した言葉なのだろうけれど、それなら、それに代わる「思考の意匠」をあらわす言葉がつくられたかといえば、マスメディアも男性陣も何ひとつもたらせなかったのだ。そして、その「かわいい」がクール・ジャパンになったのだ。
「かわいい」は何を隠蔽してきたのだろうか。クール・ジャパンは何を「かわいい」から引き取ったのか。何も引き取ってはいない。

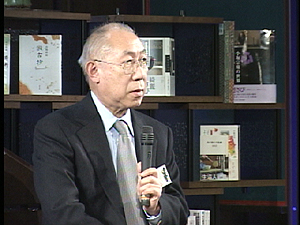
連塾の〈風来ストリート〉には、「かわいい」ものは何もなかった。むしろ「こわいもの」だけがあった。ラディカルだけが去来した。
石山篤はオートバイのデザインの根底に曼陀羅や観音があることを強調し、田中泯は自分の踊りが村祭りのお囃しに始まると言った。高橋睦郎は子供時代に聞いた北九州の婆さまたちの怖しげな語りのなかにこそ詩歌の発生があったことを証した。
日本の風来とは、そういうものなのだ。エバレット・ブラウンはそういう日本を求めて、一方で首相専用機のなかの小泉純一郎や稽古場の琴欧洲を撮り、他方で奥の細道や熊野古道を歩き、その二つの光景の「あいだ」にひそむ日本を伝えようとした。そのプレゼンテーションはみごとだった。小堀宗実は、「なぜブラウンさんのようなメッセージを日本人が発してこなかったのか」と言った。
リチーも、龍安寺の帰りにポケモンを買うという両極にあえなく股裂きになった日本の「あいだ」を探る。そして、日本中のテーマパークがスペイン村やオランダ村といった“外国”になってしまうこと、パチンコ屋とカラオケ屋がいっこうに廃れないこと、フィギュアやコスプレが現実の少女よりずっと現実感をもつという倒錯があいかわらずおこっていること、週刊誌が深刻なニュースとポルノまがいの“グラビア”をいまなお同時に飾り立てていることなどの特異な現象をあげつらい、そういうことを流行にしてきた理由をなんとか探そうとする。
そのうえでやっと仮説してみたことは、日本はいつしか「神」を喪失し、その喪失したものをまったく取り戻せていないだろうということ、そのぶん何もかもを「かわいい」で埋め尽くしているのだろうということだった。


リチーの仮説は半分くらいは当たっている。パチンコやカラオケが廃れないのは、戦後の日本人が「過去の忘却」を遊戯の本質としたせいだったと言うのだが、そういうこともあるだろう。昭和二七年から二年間にわたってラジオ放送された菊田一夫の『君の名は』は、冒頭、必ず「忘却とは忘れ去ることなり」というナレーションが入った。週刊誌が社会告発とタレントの噂とポルノまがいの“グラビア”で埋まるのは、戦後の日本人が自分の国の中のあれこれの「あいだ」を可視化できなくなっているからだった。これも当たっているところがある。
リチーは、きっと日本人はあえて何かを喪失したかったのだろう、忘れたかったのだろうと心配をしているのだ。
いつからか(むろん敗戦後あるいは日中戦争以降だろうが)、日本は「神」や「仏」だけではなく、「あいだ」も失った。日本人って曖昧だね、中間的だね、イエス・ノーがはっきりしないよと言われるうちに、日本にひそむ「あいだ」を見る力を失ったのだ。
それでどうなったかといえば、これはリチーが名付けた用語だが、一億総現在主義になった。どんな残虐な犯罪も、どんなに不幸な災害も、せいぜい三ヵ月か七ヵ月くらいしか話題の座にいられなくなったのだ。記憶のない日本人になったのだ。そのかわり、何が継続しているかというと、入れ替わり立ち代わり「よかったね」「がんばった」「かわいい」の連発で、ものごとが通りすぎていくだけなのである。

かつてロラン・バルトは、二十世紀後半に語られるイメージは、「見かけとそれ自体を同一視すること」になりさがったと指摘した。
当初、この「イメージの堕落」を最もスキャンダラスに体現したのはテレビであった。ロバート・マクニールは早くから、テレビの本質が「咀嚼しやすさ」「複雑さの排除」「洗練からの逸脱」「視覚的刺激の連打」「言葉の厳密さをアナクロニズムとして扱うこと」などにあると見抜いていた。まさに、その通り。しかし、事態はテレビにはとどまらなかったのだ。とくに日本においては。
ほぼ同じことが、いや、それ以上の刺激性をもって、マンガに、テレビゲームに、合コンに、吉本芸人に、フィギュアに、一挙に流れていった(同じことがおっつけ、ブログやミクシィを埋め尽くすだろう)。これはいったい何がおこっているのか、なかなかその傾向にひそむものを掴めなかったリチーは、あるとき「イメクラ」という言葉が「イメージ・クラブ」の略であったことを知って、呆れながらも膝を打つ。なんだ、日本人が言う「イメージ」って、そういうことなのか。
そうなのだ。コナミが売り出した「藤崎詩織」(TVゲーム「ときめきメモリアル」のキャラクター)が、ホリプロがモーションキャプチャーででっちあげた「伊達杏子」(三菱電機「ジェニー」のポップアイコン)が、日本人の言う「イメージ」なのだ。だから日本人は、オランダではなくてオランダ村へ、ペテルスブルクではなく新潟のロシア村へ、コペンハーゲンではなく登別のアンデルセンゆかりのニクス城へ、漱石のロンドンではなく修善寺のブリテン・ランドへ「イメージ」を求めて出掛け、仲間みんなで「わあっ、かわいい」を連発したら、もう二度と行かなくなってしまったのだ。
中学生のころか高校生のころ、ぼくは「女性自身」や「週刊女性」が金髪の外国人モデルばかりを表紙にしているのにうんざりしていた。それが原因かどうか、最初に海外に出たパリで、あまりに金髪が多いので落ち着かなくなったほどだった(パリで最初に惚れたのは友人の妹の黒髪のパリジェンヌだった)。
けれどもそんな話すらもはや遠い昔日のこと、日本中のどこもかしこも茶髪や金髪が流行し、いつしか、教師が茶髪を申請すれば、校長はこれを許可するしかないと東京都教育委員会が“認定”するようになっていた。茶髪・金髪・赤髪が流行しただけではない。日焼けも流行し、白顔メークもガングロも流行し、韓流も流行した。その流行はいまだ止まらない。
以上のことと、ヒップホッパーまがいのファッションが巷に溢れたこと、小顔が「かわいい」になったこと、安倍晋三が「美しい国」を標榜することとは、同じイメージ現象なのである。リチーの言いぶんなら、日本という国柄がそういうイメージ・ファクトリーになったということなのだ。
まあ、今夜の話はこれくらいにしておこう。リチーがあと半分で何が言えていなかったかということも、付け加える必要はないだろう。推して知るべし。
少々、補充しておけば、クール・ジャパンという言葉は、アメリカのエコノミストのダグラス・マックグレイが二〇〇二年の「フォーリン・ポリシー」誌上で、日本はGNPではもはや大国でも何でもないが、GNCから見れば世界一の大国だと書いてから、広まった。GNCとは「グロス・ナショナル・クール」の略で、マックグレイはふざけて国別のクール度(かっこいい度)を持ち出したのである。つまりはマックグレイは「日本はクール生産高に賭けているんですね」と揶ったのだ。
もっともトニー・ブレアのようなおっちょこちょいは、それとはべつに「クール・ブリタニア」を言い出した。「クール・ジャパン」や「ジャパン・クール」はそのおこぼれだった。いつまでも取りすがらないほうがいいだろう。どうしても追いかけたいなら、このあたりについては奥野卓司が『日本発イット革命』(岩波書店)で、クール・ジャパンがいかにアジアに広まっているかを報告しているので、参考にするといい。
ぼくが知らないだけかもしれないが、「かわいい」問題のほうは、実はその後もたいして研究されていない。たとえば「をかし」や「あはれ」や「粋」や「伊達」の流行と、「かわいい」の流行とは何が根本的に異なるのか、そこまで踏みこんだものもまったくない。それどころか、いま流行しているのは「かわいい」の増産の乱舞であって、それが「萌え」や「うざったい」の支流にまで至ったのだった。
気になるのは、世間から差別語が退治されるようになってから、とくに「かわいい」が氾濫したということだ。その結果かどうかは知らないが、日本は物差しの目盛が粗くなり、棒読みがまかり通る世の中になっていったのである。
