父の先見


角川書店 1970
ぼくの年代では白秋は童謡作家だった。子供のころの数年でどのくらい唄ったか、どのくらい聴かされたか。昭和23年くらいから昭和30年くらいまでのことだ。
「待ちぼうけ、待ちぼうけ、ある日せっせと野良かせぎ」「からたちの花が咲いたよ、白い白い花が咲いたよ」「土手のすかんぽ、ジャワ更紗」は、新町松原の修徳小学校で唄った。「大寒、小寒、山から小僧が飛んできた」「雪のふる夜はたのしいペチカ。ペチカ燃えろよ、お話しましょ」「赤い鳥、小鳥、なぜなぜ赤い。赤い実をたべた」は、ガキどもとがらがら唄った。「この道はいつか来た道、ああそうだよ、あかしやの花が咲いてる」「海は荒海、向こうは佐渡よ」「揺籃のうたをカナリヤが歌うよ。ねんねこ、ねんねこ、ねんねこ、よ」は、綺麗な声の母に教わった。
ぼくは、これらをすべてナマで聴き、その大半を歌って育った。その歌を母が唄ってくれると必ずや胸が詰まって、ううっと涙が溢れてくる定番があった。『ちんちん千鳥』『里ごころ』『雨』である。
「ちんちん千鳥の啼く夜さは」で始まるのは、千鳥が啼くと硝子戸をしめても寒いんだよ、千鳥の親はいないんだよ、ちんちん千鳥はだから眠れないんだよ、という歌詞だ。母がこれを唄い出すと、寝付きの悪い子であったぼくは泣きべそになっていた。近衛秀麿のメロディである。いまはあまり知られていないかもしれない『里ごころ』のほうは、こういう歌詞だ。中山晋平の曲がものがなしい。
笛や太鼓にさそわれて、山の祭に来てみたが
日暮はいやいや、里恋し、風吹きゃ木の葉の音ばかり
母さま恋しと泣いたれば、どうでもねんねよ、お泊まりよ
しくしくお背戸に出てみれば 空には寒い茜雲
雁、雁、棹になれ。前になれ
お迎えたのむと言うておくれ
この歌は「どうでもねんねよ、お泊まりよ」から「しくしくお背戸に」にさしかかるところで、もうがまんができず、「雁、雁、棹になれ」の先まで、母の美しい声を聴けたためしはなかった。
そして、「雨が降ります、雨がふる」だ。作曲は弘田龍太郎。『雨』がタイトルだ。一番の「遊びにゆきたし、傘はなし。紅緒の木履も緒が切れた」や、二番の「雨がふります雨がふる。いやでもお家で遊びましょう。千代紙折りましょう、たたみましょう」までは、まだいい。だいたいこの歌は女の子の歌である。だから男の子は泣かない。泣いちゃいけない。
けれどもあるとき、この歌をいとこの眞智子と一緒に唄っているとき、四番の「雨がふります、雨がふる。お人形寝かせどまだ止まぬ。お線香花火も、みな焚いた」で、眞智子がぐすぐすしはじめたのだ。そして最後の「雨がふります、雨がふる。昼もふるふる、夜もふる。雨がふります、雨がふる」というふうに、ただ雨ばかりが降りつづけるという空漠に眞智子が泣き崩れてしまったのだった。トラウマになった。

白秋とは、わが少年期の童謡において、すでにフラジリティを極め、ヴァルネラビリティに差し迫っていた詩人である。子供にも哀傷を辞さない詩人なのである。どんなふうに哀傷を辞さなかったのか、ちょっと啄みながら、逍遥してみる。
さきほどあげた『里ごころ』でいうのなら、「笛や太鼓にさそわれて、山の祭に来てみたが」の、「が」がめっぽう早い。最初から逆接の提示なのである。ついで「日暮はいやいや、里恋し」に「風吹きゃ木の葉の音ばかり」の「ばかり」が追い打ちをかけてくる。子供に向かって「音ばかり」とは何事か。音以外に何もないなんて。そのうえで「恋しい母」と「お泊まり」が突きつけられる。これでもはや行き場がない。それでもやっと一転、「しくしくお背戸に出てみれば」で全景がさあっと広がるのだけれど、そこはもう取り戻し不可能な、あの「雁、雁、棹になれ。前になれ」なのだ。
童謡についてなら雨情にも八十にも露風にもこういう芸当はあった。しかし白秋にはその芸当が、のちに「白秋百門」といわれたごとくに徹底して広く、また深い。この芸当は童謡だけでなく、近代詩にも短歌にも、そして長歌にも歌謡曲にも民謡にも彫琢されていた。雨にまつわる詩歌だけをとりあげても、白秋は多彩の表意と多様の意表なのである。
実際、白秋の表意と意表は綺語歌語縁語の宗匠というほどに、幅がある。だいたいこの時期、近代詩人で長歌に凝った者などいなかったはずだ。
白秋は折口信夫と「親類つきあひ」をした人であったのだが、その折口が唯一、長歌をものしたくらいだった。のちに朔太郎は「日本に幾多の詩人はあるが、概ね詩歌俳句等の一局部に偏するのみで、白秋氏の如く日本韻文学の殆どあらゆる広な全野に渡つた、英雄的非凡の大事業を為した人はいない」と評した。
ぼくが白秋を最初に活字として読んだのは、第二詩集『思ひ出』だ。高校3年くらいのころだったろうか。たちまち打擲された。おおげさにいえば、この詩集でぼくのフラジャイル感覚が劇的に発端した。とりわけ『蛍』で比喩の美に凌辱されて、『青いとんぼ』で極微の表現に幽閉された。青年は、少年のころの寂しい日々の印象に戻っていいんだ、そこからしか寂しい本質の何物かに触れうるはずはないんだ。そういう負の確信をもてたのが『思ひ出』だったのだ。
なかでも『蛍』は、昼の蛍を夏の日なかのヂキタリス(ゴマノハグサ科の花)に譬え、その小さな形象を五感に刻んでいくようになっていて、どぎまぎさせられた。とくに「そなたの首は骨牌の赤いヂャックの帽子かな」の二行に、まいった。昼の蛍の首筋の赤に目をとめ、幼児の記憶に戻って「赤いヂャックの帽子かな」のメタファーに遊んでいるのが、ああ、ひたすらに羨ましかった。
もっと驚いたのが『青いとんぼ』だ。「青いとんぼの眼を見れば 緑の、銀の、エメロウド、青いとんぼの薄き、燈心草の穂に光る」の出だしはともかく、「青いとんぼの奇麗さは 手に触るすら恐ろしく、青いとんぼの落つきは 眼にねたきまで憎々し」とあって、こういうふうにトンボにでも赤裸々な感情移入ができるものかと思った瞬間、次の二行の結末に、わが17歳の精神幾何学の全身がビリビリッと電気でふるえた。こういう二行だ、「青いとんぼをきりきりと夏の雪駄で踏みつぶす」。
それからは読み耽ったというより、その電撃を眼で拾うために、白秋の詩集や歌集のページをうろつきまわったというに近い。白秋が「幼年期の記憶の再生」をもって、新たな感覚表現を獲得したことを追走したかったのだろうとおもう。この「幼年に戻る」ということ、「幼な心にこそ言葉の発見がある」ということが、ぼくが白秋から最初に学んだことだったのである。
『思ひ出』冒頭の『わが生ひたち』の、そのまた冒頭に白秋自身が書いている。「時は過ぎた。さうして温かい苅麦のほめきに、赤い首の蛍に、或は青いとんぼの眼に、黒猫の美くしい毛色に、謂れなき不可思議の愛着を寄せた私の幼年時代も何時の間にか慕はしい思ひ出の哀歓となつてゆく……」。
また、こうもはっきり書いている。「…玉蟲もよく捕へては針で殺した、蟻の穴を独楽の心棒でほぢくり回し、石油をかけ、時には憎いもののやうに毛蟲を踏みにじつた。女の子の唇に毒々しい蝶の粉をなすりつけた。然しながら私は矢張りひとりぼつちだつた。ひとりぼつちで、静かに蝅室の桑の葉のあひだに坐つて、幽かな音をたてては食み盡くす蝅の眼のふちの無智な薄褐色の慄きを凝と眺めながら子供ごころにも寂しい人生の何ものかに触れえたやうな氣がした」。
おそらく詩集なら、いまでも『思ひ出』がいちばん好きだろうと思う。山本健吉も三島由紀夫も、そんなことを言っていたかとおもう。


早稲田に入ってしばらくして、第一詩集『邪宗門』をやっと読んだけれど、これは、言葉の耽美主義の錬磨が果実であったことに目を奪われたくらいで、それほどのダメージはなかった。
ぼく自身が白秋と同じ早稲田の学生になったこと、しかし白秋は青春に甘んずることなく早稲田を放り捨て、『天地玄黄』で世を震撼させた与謝野鉄幹主宰の新詩社の門をくぐり、さらに晶子の放埒がめざましい「明星」に入って、かつそこから離脱するにいたったことなど、ぼくのほうも白秋に関する知識も近代詩についての知識もふえていて、そういう経緯に詳しくなったことが邪魔なフィルターになり、まともな耽読に向かわなかったのだろうと憶う。
学生時代、そこまで白秋が気になったことについては、ちょっとした理由があった。白秋もぼくも同じく1月25日に生まれていたということだ。
白秋が早稲田に入ったのは明治37年の数えで20歳のときである。それまでは北九州屈指の水都柳川にいた。海産問屋と酒造りを営んでいた素封家のトンカ・ジョン(大きいほうの坊ちゃん)で、病弱で寂しがり屋の、何の苦労もない子供時代と見える。
むろんそんなことは見かけ上のこと、実際には妹がチフスで亡くなり、明治23年のコレラの流行に脅えたりして、不安きわまりない少年期をすごしている。柳川のことすら、白秋自身は「廃市」と呼んでいた。
そういう白秋が傾きつつある家業から逃れて、親や周囲の反対をおしきって早稲田英文予科に入った。同級に若山牧水、土岐善麿、佐藤緑葉、安成貞雄がいた。白秋は授業を捨ててこの破格の友人たちと語らい、図書館にこもって鷗外の『即興詩人』を、上田敏の『海潮音』を、さらに『大言海』の単語を片っ端から繰っていく。牧水とは同じ部屋に下宿もした。すでに相馬御風・人見東明・野口雨情・三木露風・加藤介春らは早稲田詩社を結成していた。
時はまさに鉄幹の「明星」全盛期である。鉄幹は明治25年には正岡子規・大町桂月・落合直文らと浅香社で新派和歌運動をおこし、30年代には佐佐木信綱・土井晩翠・外山正一・矢田部良吉が加わって新体詩会をかまえ、第一歌集『東西南北』では虎剣調とよばれた男性的謳歌を、第二歌集『天地玄黄』では万葉調の浪漫主義を標榜していた。その牽引力は絶顚ぎりぎりだ。そこへ晶子が飛びこんで、「明星」は新たな星菫調をもって女だてらのソフィスティケーションをおこしつつあった。
白秋も短歌や詩を寄稿しているうち、この歌壇新選組組長ともいうべき大丈夫に目をつけられて、詩歌壇の麒麟児ともくされた。それが弱冠22歳のときである。白秋は夜な夜な鉄幹・晶子・木下杢太郎・吉井勇、まもなく死ぬことになる石川啄木らの、才能ほとばしる詩才たちと語らった。
ついで明治40年7月下旬から1ヵ月をかけて、鉄幹、平野萬里、杢太郎、吉井勇と連れ立って、故郷柳川を振り出しに、佐賀・唐津・佐世保・平戸・長崎・天草・島原・熊本・阿蘇を遊歴した。例の「五足の靴」の旅だ。このときの「天草雅歌」こそ第一詩集『邪宗門』の頂点を飾っていく。こうして白秋は『邪宗門』を問う。露風は『廃園』である。二人によって、鉄幹の時代は遠のいた。
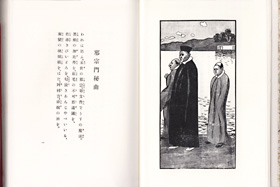
このあと白秋は大御所鷗外の観潮楼の歌会に招待され、そこで佐佐木信綱・伊藤左千夫・斎藤茂吉と知りあった直後、杢太郎・吉井・長田秀雄らと「明星」を脱退した。そこに石井柏亭・森田恒友・山本鼎らの青年画家が加わって浪漫異風の「パンの会」を結成した。翌年の明治42年の「スバル」創刊に「邪宗門新派体」の総題で『天鵝絨のにほひ』ほか七編を発表したところ、そこからは白秋こそが「スバル」を代表する詩人になっていった。
ある日、白黒テレビで美空ひばりが『城ヶ島の雨』を唄っていた。司会の誰かが「えー、これは北原白秋の作詞ですよね」と言ったとたん、白秋が「声」で言葉をつくっていたことが、ふいに理解できた。
雨はふるふる、城ヶ島の磯に、利休鼠の雨がふる。
雨は真珠か、夜明けの霧か、それともわたしの忍び泣き。
舟はゆくゆく通り矢のはなを、濡れて帆あげた主の舟。
ええ、舟は櫓でやる、櫓は唄でやる、唄は船頭さんの心意気。
雨はふるふる、日はうす曇る。
舟はゆくゆく、帆がかすむ。
曲は梁田貞。一聯ずつのトランジットが抜群にいい。最初は城ヶ島に「利休鼠の雨がふる」と、独特の水墨イメージを切り取っておいて、「真珠・霧・忍び泣き」のメタファー三発を並べて見せつつ、ついでは「わたしの忍び泣き」という自他の橋掛かり。その光景に舟を走らせ、そこからは「舟は櫓でやる、櫓は唄でやる」の返しがえし。そのくせ「唄は船頭さんの心意気」という親しみのこもった呼びかけが入って、あとはふたたび遠水幽帆の水墨画なのである。それが「絵」であって「声」なのだ。
ぼくは白秋がどうしてここまでモノクロームな烟語をつかいきれるかと思った。本屋に走った。このとき、近所の本屋には白秋の詩集はたしか新潮文庫の『からたちの花』しかなく、よく探しはしなかったのだろうけれど、そのほかは講談社「日本現代文学全集」の『北原白秋集・三木露風集・日夏耿之介集』があっただけだったので、これを買った。そこに『邪宗門』『思ひ出』全詩のほか、『真珠抄』『白金ノ独楽』『水墨集』の抄録とともに、『桐の花』全歌が収められていたのである。
このときまでぼくは白秋が短歌の名人でもあることを知らなかったのだ(岩波文庫の『北原白秋歌集』はまだ出ていなかった)。が、この歌集で「白秋の絲」とでもいうものにきりきり、切りまわされた。
歌集『桐の花』は、「わが世は凡て汚されたり、わが夢は凡て滅びむとす。わがわかき日も哀楽も遂には皐月の薄紫の桐の花の如くに也消えはつべき……云々」にもとづいている。白秋は桐の花の薄い咲き方、はかない散り方を31文字の歌に託していた。
いやはてに鬱金ざくらのかなしみのちりそめぬれば五月はきたる
廃れたる園に踏み入りたんぽぽの白きを踏めば春たけにける
桐の花ことにかはゆき半玉の泣かまほしさにあゆむ雨かな
君と見て一期の別れする時もダリヤは紅しダリヤは紅し
男泣きに泣かむとすれば龍膽がわが足もとに光りて居たり
どれどれ春の支度にかかりませう紅い椿が咲いたぞなもし
このなかで「ダリヤは紅しダリヤは紅し」だけは、高校時代に誰かが放課後の黒板に書き残していて、白秋の歌と知らずに心の隅にひっかかっていた歌だった。ぼくは「桐の花」と「かはゆき半玉」が根本対同した歌に感服した。
が、こういう花の歌もよいのだが、この歌集でぼくをふたたび白秋に向かわせるきっかけになったのは、「秋思五章」に歌われた“絲”の音である。きりきり、きりり、こんな音がする短歌だ。
清元の新しき撥 君が撥 あまりに冴えて痛き夜は来ぬ
手の指をそろへてつよくそりかへす薄らあかりのもののつれづれ
微かにも光る蟲あり三味線の弾きすてられしこまのほとりに
円喬のするりと羽織すべらするかろき手つきにこほろぎの鳴く
太棹のびんと鳴りたる手元より よるのかなしみは眼をあけにけれ
常磐津連弾の撥いちやうに白く光りて夜のふけにけり
第二首をのぞいて、とくに仕上がりがよい歌ではない。白秋にしてまだ未成熟のままであるけれど、それをこえて常磐津や清元の絲の音がチントンチンとする。のみならず、歌集全首がその三絃に切り結んで、魂に撥をあてている。いったいどうしてこんな歌を詠めたのか。
それは明治末年のことである。28歳の白秋は前年に原宿に転居したときに隣家の人妻松下俊子と知りあい、熱烈な恋愛に落ちた。ここまでならよくあることだが、運悪くというのか、白秋は俊子の夫に姦通罪で告訴され、市ケ谷の未決監に放りこまれてしまった。つい先だってまでは『思ひ出』が上田敏によって激賞されて栄光に包まれ、高踏文芸誌「朱欒」を創刊して気勢をあげたばかりの直後の事件だ。
さいわい1ヵ月後に無罪免訴となったのだが、白秋はそうとうに苦しんだ。一時は憂悶のあまりふらふらと木更津あたりをさまよいもしている。ここで詠んだのが『桐の花』の哀傷短歌群なのである。それを詠んで白秋は三浦海岸に渡り、死を決意する。そんなことがあったのだ。

結局、白秋は死を選べない。そのかわり敗残者の烙印を秘めて、心の巡礼者になることを誓う。そこへ夫に離別され、胸も病んでいた俊子から助けを求められ、白秋は新生を求めて結婚、三浦の三崎町の異人館に転居する。
ああそうだったのか、そういうめぐりあわせかと思ったのは、このとき三浦三崎の臨済宗見桃寺に仮寓していた白秋が一気に仕上げた歌こそ『城ヶ島の雨』だったということだ。だからこその、♪舟はゆくゆく通り矢のはなを、濡れて帆あげた主の舟……。
詩壇の寵児白秋は、あっというまの無一物なのである。しかも白秋はまだ「心の巡礼」を始めたばかりの日々である。そこであえて船上の人となり、小笠原の父島にまで渡って俊子の療養にあたる。自分で自分を「寂寥コワレモノ」の極限にまで追いこんだ。けれども、俊子は耐えられずに東京に帰ってしまう。一人白秋はそのまま貧窮を厭わず父島に留まった。大正3年のことである。白秋にして、そんな絶海の孤島にいたことがあったのだ。
しばらくして『城ヶ島の雨』は島村抱月によって芸術座の舞台で唄われ、つづいて中山晋平が曲をつけた『さすらひの唄』が大ヒットした。「行こか戻ろか、北極光の下を、露西亜は北国、はてしらず。西は夕焼、東は夜明、鐘が鳴ります、中空に」。一度口ずさんだら、胸をかきむしって離れぬ歌だ。
このあと経済的にも復活し、白秋は平塚雷鳥のもとに身をよせていた大分の江口章子と結婚する。なんとか安定を得ると家を建てるのだが、なんということか、その地鎮祭の夜に章子に逃げられ、ふたたび「心の巡礼」の杜撰であったことを思い知る。が、それも大正10年にはまたまた新たな大分の女性佐藤菊子と、今度こそはと結んで、子供を生むにいたった。
このあとの白秋がいよいよ童謡に磨きをかけたのである。三好達治だったか、白秋の作品では童謡が最もすぐれていると言っていたのは当然のこと、こうした激越な天罰の果てでの童謡ポイエーシスだった。
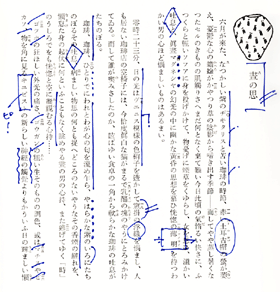
さて、ここまでがぼくの拙い白秋遍歴であって、その後はときおり白秋に対座する夜がつれづれあって、そのつど、白秋百門に唸る、ちょんちょん読む、考えこむ、飽きてくる、また唸る、黙って読みたい、なんだか胸騒ぎがしてくるという、そんな断続にすぎない。
そうしたなか、いま書いておきたいとおもうのは、ひとつには白秋はついに雅俗を分離しなかったということ、その言葉の旋律はつねにノスタルジアとフラジリティに接しようとして生まれていたこと、それが歳を食むごとに「無常の観相」や「もののあはれ」にまで結びついたことである。「鳴かぬ小鳥のさびしさ、それは私の歌を作るときの唯一無二の気分である」と白秋自身は書いた。白秋は「欠如からの表意」に向かったのだ。が、これらのことはいまさら説明するまい。
もうひとつは、そのことを書いて今宵の白秋と別れたいとおもうのだが、白秋には特別のオブジェの感覚に寄せる眼があったということだ。オブヂェと綴ったほうがいいだろうか。むろんいっぱしの詩人や歌人や俳人なら、なにかしら事物や物体に注意のカーソルが細かく動くのであるけれど、それが白秋ではやや風変わりだった。けれども、ぼくが白秋を贔屓にしたいのは、この風変わりなのである。
たとえば、カステラのことだ。そもそも『桐の花』には序文があって「桐の花とカステラ」が綴られている。そこで白秋は、夏の帽子をかぶるころ、眼で見るカステラの感触がわずかに変化するのが好きなんだと言い、触れぬのに感じるタッチというものの渋みこそ、自分が表現したかったものだと告白する。カステラの端の茶色が筋となって切れるところにも、眼を寄せる。
こういう感覚は、舌出し人形の赤い舌、テレビン油のしめり、病いのときに一口ばかり飲むシャンペンの味、銀箔の裏の黒、恍惚に達する寸前の発電機、堅い椅子に射す光、いままさに汽車が駅に入ってくるときの匂い、日曜の朝の蕎麦、背後の花火の音……そして、白金浄土のキリギリスというふうに、白秋においてはどんどん滑っていくものである。
シュルレアリスムのオブジェ感覚なんかではない。おお、ほろろん白秋、ほろろんの白秋オブジェのおぶぢぇぢぇ、なのだ。たとえては、「一匙のココアのにほひなつかしく訪ふ身とは知らしたまはじ」という、そのココアと一瞬だけ交わった眼の言葉、タッチの渋みなのである。
この感覚は風の変わりというものだ。風変わりとはそのことだ。その場を魂が立ち去る直前の風趣の変わりというものだ。それが白秋の郷愁という風趣、さもなくば風趣というオブヂェたちなのである。晩年、白秋は水墨山水の画境や老荘思想や黄表紙の戯れにも、さらにはついに「ほそみ」の趣向にさえ入っていくのだが、その趣向はすでにハッカの味がするオブヂェ感触の、風の去来に発端していたはずなのだ。しかしそれはまた、次の文章に秘められた白秋の風趣の極北を暗示していたともいうべきだった。「つくづく慕はしいのは芭蕉である。光悦である。北斎である。利休である。遠州である。また武芸神宮本玄信である。私もどうかしてあそこまで行きたい」。
そうなのだ。白秋は昭和の戦争の渦中、ひたすら日本回帰の人となり、日本語だけがもつ風来ばかりに耳を澄ませていたようにも想われる。
では、千夜千冊目からちょうど1年目の今宵の七夕は、こんなふうに良寛と響きあう2つの白秋を贈って、黒の夜を締めたい。ひとつはごく僅かな星の歌から一首、もうひとつは『他ト我』という、こんな詩が白秋にあったとはほとんどが気がついてない、こういう詩だ。
寂しくも永久に消ゆなと離るなと仰ぎ乞ひのむ母父の星
二人デ居タレド マダ淋シ。
一人ニナツタラ ナホ淋シ。
シンジツ二人ハ 遣瀬ナシ。
シンジツ一人ハ 堪ヘガタシ。