父の先見


新潮文庫 1996
David Herbert Lawrence
Lady Chatterley's Lover 1928
[訳]伊藤整
藤原猛先生がいた。京都初音中学校の国語の先生だ。難聴者で、いつも補聴器をつけていた。だから声が大きかった。のちに『音から隔てられて――難聴者の声』(岩波新書)を共著した。藤原先生によって、ぼくの奥にもぞもぞしていたらしい文章術的なるものが薫風を浴びてめざめた。
先生は日記を書くことを生徒にすすめ、各自の日記を読んではその感想をときどき授業中に話した。ぼくの日記はなぜかそのつど大声の感想の対象になり、そのうち教室のうしろの低い棚に“公開”された。先生は「松岡の日記はハイブンだ」と言った。さっぱり意味がわからなかったが、卒業後、あるとき先生の等持院の家に伺ったときに、聞いた。いや、聞いたのではない。そのころ先生はそうとうに失聴状態になっていたので、筆談で紙切れに「ハイブンって何ですか?」と書いた。先生は前よりも大きな声で、「ハイカイの文章だよ」と言った。またまたわからなくなったのだが、これは俳文や俳諧ということだった。
その先生の家に中学二年のときの同級生のYTと高校生になってから伺ったとき、帰り際、「これ、松岡へのプレゼントだ」と言って二冊の本をくれた。伊藤整が初訳したときの小山書店版『チャタレイ夫人の恋人』上下本である。包装紙のようなカバーが丁寧にしてあって、裏表紙の裏(表3)に色褪せた新聞記事の切り抜きが貼ってある。チャタレイ裁判の発行人有罪を告げる記事だった。藤原先生は大声で「なあ、松岡はこれを読んで、もっともっと自由になれ」と言った。
二日前からこの二冊の“初版発禁本”をさがしているのだが、見つからない。次の大掃除までには見つけたい。きっと古本屋では高値をよぶだろうあの二冊は、ぼくにとっては説明のつかない青春の突風のようなものだったのだ。薫風から突風へ。でもその本が見つからないので、今夜は新潮文庫になった伊藤整本をもってきた。伊藤礼が初版の削除部分を補訳している完訳版である。
いったいなぜ藤原先生が『チャタレイ夫人の恋人』を高校生のぼくに贈ってくれたかは、いまもってわからない。磊落だけれどそそっかしい先生は、ぼくがYTといつか結婚するとでも予想していたのだろうか。先生の乾坤一擲のプレゼントの甲斐もなく、ぼくは彼女と交わることもなく(振られたといったほうがいいが)、それどころか大学三年までをレディ・チャタレイはむろん、どんな女性とも雨に打たれることなく、童貞のままの日々をすごしたのだ。
こんな話のあとに、医者の前で自分の肝臓の話をするかのようにD・H・ロレンスの作品に入っていくのも照れくさいが、なんとなく遠いところから話すことにする(そのうち近くに寄っていく)。
猥褻文学などというものはない。猥褻罪を適用された出版物があるだけだ。「いたずらに性欲を興奮させ、正常な性的羞恥心を害し、公序良俗に反するもの」というのが定義のようだが、それなら大半のブンガクが猥褻なのである。
ふつうに読めば、『チャタレイ夫人の恋人』はどこにも興奮するような描写のない作品である。コニー(レディ・チャタレイ)と森番のメラーズが狂おしく交情する場面は何回も出てくるが、なかでも、降りしきる雨の場面はさすがに印象的だったけれど、春情を催すような気分にはなれない。ロレンスも読者を欲情させたいなどとはまったく思っていない。そんな意図はさらさらない。
この作品はポルノグラフィでないし、よく言われるような「性の文学」でもなく、むしろ「甚愛文学」であって、「自由文学」なのである。もっとはっきりいえば意外な反応をもつ者が多いだろうけれど、これは徹して「反ピューリタニズムの文学」だったのである。
ロレンスが、レディ・チャタレイとメラーズが交じりあうことに波状的なクライマックスをおいたのは、ロレンスの社会観や人間観や世界観があってのことだった。それならなぜ「性愛」を全面に出したかったのかといえば、いまからその話を書くけれど、その理由の背景はロレンスの人生にすべてあらわれている。ロレンスは短い人生のそこそこ異常な日々を通して、男と女の関係だけに社会と世界と宇宙の消息の燃焼をつきとめつつあったのだ。
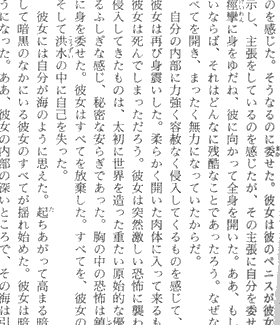
ロレンスが生まれ育ったのはイングランド中東の炭鉱の町イーストウッドだった。父親は炭鉱夫の親方の一人で大酒呑みだったので、とうていフツーの生活はできない。高校を出てすぐに医療器具屋の事務員になった。母親は優しく知的で、息子を偏愛したようだ。マザコンにかかった。
青春期に肺炎になった。それで仕事を退いた。肺炎の青年が考えることはそんなに多くない。農場の娘ジェシーに惚れた。ジェシーはロレンスと母親が睦まじいのを嫉妬して、できれば精神的な交遊を求めたのだが、ロレンスはジェシーの体がほしい。それがかなわず他の女と遊ぶ。それでセックスの快感はわかったが、その高揚をぜひともジェシーにこそ求めたい。ジェシーはジェシーで、そういうロレンスに体と脚が開けない。ロレンスの母親への気持ちが抵抗感になっていた。
このロレンスと母親とジェシーに渦巻く葛藤は、のちのロレンス出世作『白孔雀』(中央公論社「世界の文学」34)と『息子と恋人』(三笠書房→角川文庫・岩波文庫・新潮文庫)に再現されている。
ロレンスは教えることは好きなようだった。だいたいセックスが好きな男は教えたがりだ。そこで(そこでというのも変だが)、ここからは学業に転じてノッティンガム大学に入って教員資格をとると、教鞭生活を始めた。
ところが、ただひとつのきっかけが、ロレンスを文学者にしてしまった。すでに女性を心身ともに理想化する傾向があったので、詩を女友達にこっそり贈るようなところがあったのだが、そういう詩を何度ももらっていたジェシーがそれらの詩を「イングリッシュ・レヴュー」に送付してしまったのだ。これを編集者のフォード・マドックス・ヘッファーが目にとめてその才能に驚き、ロレンスははからずも文壇デビューした。ロレンスの才能を知っていたのはジェシーだったのである。
ここまでは、とくにロレンスに幸運があったわけでも不幸があったわけでも、才気があったわけでもない。けれども次にその話をするが、またまたただひとつの出来事がロレンスを放浪に追いこんだ。
文筆生活が始まりかけたロレンスは、ノッティンガム大学の言語学教授の夫人フリーダに恋をした。ドイツ・バイエルンのリヒトホーフェン家出身のフリーダはロレンスの六歳年上で、三三歳。三人の子の母である。フリーダは夫には倦いていた。ゾラもモーパッサンもトルストイもそうなったように、男はこういう人妻にすぐ夢中になる。二人は熱愛し、人目を盗むようにして溺れあった。
これでは古い町には何かがおこる。世間の目を忍べなくなった二人は別々にドイツに旅立つと、そこで落ち合ってチロルからアルプスを越えてイタリアに入るという恋の逃避行をした。一九一二年のことである。
この人妻との大胆な逃亡はロレンスの抵抗と逃避と燃焼を決定的に過熱させた(当然だろう)。それでも過熱のなかで夢中に綴った自伝的な『息子と恋人』が大評判になると、二人はやっとイギリスに戻り、正式に結婚をする。
離婚と結婚でようやく落ち着いたかに見えた二人だが、一九一五年に発表した『虹』(新潮文庫)が風俗紊乱の廉で発禁となり(『虹』はかなりの傑作だ)、加えて第一次大戦下のためもあって、フリーダがドイツ人だということでスパイの嫌疑をかけられた。二人は家宅捜査をうけたのち、退去を命ぜられる。こうしてロレンスの浪漫的世界放浪者とでもいうべき生涯と思想が決定づけられたのである。ロレンスはどこにも、だれにも“定住”できなかったノーマッドな男になっていく。
ロレンスには夢想癖があった。女が好きな男で夢想癖がない男なんているはずはないけれど、そしてその夢想の大小によって男の甲斐性も男の値段も決まっているのだが、ロレンスの夢想癖は本気で地上の理想境を求めた。
自身で「ラーナーニム」という小ぶりの楽園をつくりたかった。実際にも最初はそれを、コーンウォール地方の某所にしようとさえ考えた。いわばロレンスの『大菩薩峠』が始まったのだ。しかしそんな計画にはだれも乗ってはこない。それにロレンスが考えた「ラーナーニム」はフーリエの「ファランジュ」や有島武郎の牧場や武者小路実篤の「新しき村」や高田博厚の「共産村」とは異なって、社会的共同体構想ではなく、好きな男と女がひたすら愛しあって睦まじく住みあうという「愛滴の村」だった(タントラ的コミューンに近い)。
そこでは男たちは同志の関係であるべきで、女たちは好きな男と愛しあい、その男が同志をもてない男なら、これを捨てればよい。この男たちの同志的関係がどういうものかは、のちの『カンガルー』(彩流社)という作品で叙述されている。
なぜロレンスがこんなことを夢想するようになったかということは、とくに詮索するには当たらない。イギリスとヨーロッパがつくりあげたピューリタニズムの生活倫理とピューリタニズムの文学に背を向けたかったのである。禁欲的に精神の真実のアリバイを求めようとするピューリタニズムに対し、ロレンスは「性」をもってこれを打倒したかった。「性」の容認をアリバイとする理想の場所をつくりたかった。
ロレンスによれば、人間にとっての最も貴重な能力は想像力にある。その想像力の最も奥底にあって、かつ最も傷つきやすいかたちで表層で風波のごとく躊躇っているものがエロスとリビドーだ。ロレンスはこの想像力の振動子をこそ、理想の男女が交わしあうべきだと考えた。
そんな浮かれたことがいつもうまくおこるのだろうかと心配したくなるけれども、ロレンスは本気だった。『恋する女たち』(角川文庫)に書いているように(小学校教師のアーシュラと絵の修業をしているグドルーンという姉妹の物語)、そのためには、女は“見かけだおしの男の空虚”とさっさと訣別し、男は“固定した趣味に迷いつづける女”をあっさり放擲することを、大真面目で勧めたのだ。
こういう説教くさいロレンスの男と女のための人生相談を、かつてフェミニストたちは男のエゴイズムだとも勝手な空想だとも非難した(まさに男の妄想だ)。しかし、女の想像力の本質にもエロスとリビドーがあるはずだ。ロレンスはこの一点だけは生涯を通して譲らなかった。
理想(妄想)とはうらはらに、ロレンス夫婦のロンドンでの日々は鬱屈したままにある。ロレンスはついに決意して、「ラーナーニム」を“外”に求めて転々とする。
このあと二人が転々とした逃避行は、転地先を追っただけでも、その甘美でノーマッドな「普通社会での定住拒絶」の本気度が見えてくる。フィレンツェ、カプリ島、バーデン・バーデン、シシリー島、サルジニア、セイロン、オーストラリア、アメリカ、ニューメキシコ、そしてメキシコだ。まるで世界中に理想的な自由恋愛リゾートを求めたようなもの、「地球の歩き方」や「じゃらん」の先駆者だったのかと思われてくる。
ここでいったんイギリスに戻り、一年もたたずにまたアメリカからメキシコのオアハカに入って、『翼ある蛇』(新潮文庫・角川文庫)を書いた。この有翼龍蛇とはロレンスとフリーダそのものである。ロレンスの方法文学はしだいに男であって女であるような、それゆえ女であって男でもあるような、そういう両性具有の「あわい」に入っていった。こうして何度かの放浪遍歴のあと、フィレンツェ近くの村で書きあげたのが『チャタレイ夫人の恋人』なのである。
冒頭、ロレンスは「現代は本質的に悲劇の時代である」と書き、コニー(コンスタンス)が結婚したクリフォード・チャタレイが炭鉱主であることを示している。
この設定は、ロレンスが少年期から見つづけていた自由とはおよそ反対の社会というものだった。クリフォードは二十世紀資本主義の象徴なのである。そのクリフォードをロレンスは不能者に仕立て、コニーを理解する夫に仕立てた。それだけにレディ・チャタレイはこの日常環境からの脱出には蛮勇を必要とした。
しかしレディ・チャタレイにすべてを託したロレンスは、その二年後に南フランスの懐かしい村で死んだ。意外だろうが、まだ四四歳だった。
ざっとこんなところが、『チャタレイ夫人の恋人』が書かれた背景であって、そこに反ピューリタニズムがあったことと人を春情に走らせるポルノグラフィがなかったことの理由だが、さあ、それはそれとして、ここまであれこれ書きながら思い出していたのだが、あいかわらず藤原先生がどうしてぼくにレディ・チャタレイを勧めたのかは、まだわからない。
大声の「松岡、もっと自由になれ」はいまも耳に響いているけれど、そしてまさにいつもそうだ、そうだと思ってきたが、ぼくがレディ・チャタレイに出会えてきたのかどうかはまだわからないし、ぼくがD・H・ロレンスの日々を必要とする人生を追っているのかどうかも、よくわからない。
藤原先生は伊藤整の文学自由のための闘争をぼくに知らせたかったのかもしれない。あるいは『鳴海仙吉』(岩波文庫・新潮文庫)などにかまけるなよと言ってくれたのかもしれない。『鳴海仙吉』は伊藤整の長編小説で、郷里で知りあった姉妹がそれぞれ夫と別れて仙吉と再会するのだが、二人に関係をもつうちに妹が自殺してしまうという話である。それともやはりぼくがいつか知ることになるだろうD・H・ロレンスのピューリタニズムとの格闘を匂わせたのか。
そういえば先生は、ぼくが日記に書いた詩を褒めてくれたことがある。それは「鳥」というぼくが飼っていたメジロについての短い詩なのだが、その最後に、「右、下、ななめ、あっ、仰向いた」と書いた一行を、「松岡、ここがええんやで」と言ったのだ。いったい、先生はなぜここを褒めたのか。この公案、いまもって謎である。