父の先見


有精堂 1973
30数年前のことになる。前田愛の登場はそのころのネタヨミ本として、ちょっとばかし鮮烈だった。そもそも世の中のネタ本にはネタメタ本、ネタネタ本、ネタヨミ本の3種があって、前田愛はそのうちのネタヨミ本の異能者だったのです。
ネタメタ本というのははネタ本の母型にあたるもので、たとえばフロイトの『モーセと一神教』やヘルマン・ワイルの『数学と自然科学の哲学』などをいう。ネタを通して母型をさぐるわけですね。「千夜千冊」ではけっこう多い。ネタネタ本はネタ本の類型に属する眷属のことで、桑原武夫から宮崎哲弥まで、これまた「千夜千冊」ではまあまあ扱ってきましたね。深みの度合いはどうであれ、ここには多くのブックガイドが入る。
これに対してネタヨミ本は、それらの方法を読み解くための眷属で、ネタ本(たとえば『徒然草』とか漱石とかカフカとか村上春樹)を素材にして、そこからできるだけ思いがけないことを引っ張り出す。「千夜千冊」の日本中世文芸ものでいえば、唐木順三をはじめ、田中貴子、山本ひろ子といった猛者たちの本にあたる。
が、ぼくはなぜか近世近代文芸のネタヨミ本をほとんどとりあげてこなかった。これは失敬。手落ちでありました。それでも樋口覚や柄谷行人などは少しく通過しておいたけれど、むろんこれでは足りない。とりわけどういうところが足りないかというと、広末保、松田修、前田愛なのである。この3人こそは、近世近代文芸のネタヨミ分野における異色のエキスパートたちでしたから。今夜はそのうちの前田のネタヨミぶりの一端をとりあげるけれど、いずれ広末保や松田修の異色ぶりも紹介していきます。
前田愛のことは、25年ほど前にちらちら雑誌で見ていてしだいに気になったので、最初に『都市空間のなかの文学』(1982)を読んでいた。これで、春水の『春色梅児誉美』が広げた墨東の伝承的空間の「曲」を知り、また漱石の『彼岸過迄』の神田小川町にまつわる仮象的な「襞」というものを知った。そこには、三馬の『浮世床』や英泉の《新吉原八景》の店を出入りする光景が纏わりつき、四迷の『浮雲』から川端の『浅草紅団』におよぶ喧噪が泡立っていた。
そういう街の生きざまを、文芸を自在に切り取って読み手を想定しながら議論してみせる方法があったとは、この一冊で教えられたことだった。江戸や東京の描写など、ふつうは文学論では軽視されていたんです。そこを前田は果敢にとりあげた。
が、しかし、不満が残ったのも忘れない。前田の言いっぷりがアウトサイダーにしては、なんだか説教臭いようにも感じられたのだ。なぜならそこには、ジョルジュ・プーレやケネス・バークやオットー・ボルノウの「文脈読み取り装置のモデル」が下敷きになっていたからで、これらはぼくもそれぞれ早々に千夜千冊したほどだから、むろんおもしろいモデルや考え方を提供してはいるのだけれど、それを明治文芸のテキスト文脈にあてはめるのは、せっかく日本の近世近代都市の記述に分け入ったのに、そこに海外モデルを編入させるのでは、いささか「日本という方法」が殺がれるのではないか。そんな印象をもったのだと憶います。
それよりも『都市空間のなかの文学』で盲点を衝かれたのは、現代の都市民たちが「ぴあ」などの情報ガイド誌によって都市の空間イベントのジャンルと日付を通してしか、都市の祝祭にかかわれなくなったことをとりあげたことだった。
前田はそこで、「ぴあ」のようなメディアは情報ガイドとしてはいかに便利でも、カット(場面)とヴィスタ(通景)とシークエンス(局面)が決定的に欠けているのではないかと指摘した。それにくらべて、近世近代の文芸には、そのカットとヴィスタとシークエンスこそがある。それが今日の情報誌からは喪失しつつあると指摘した。うーん、なるほど、ちょっと唸ります。
これは今日のウェブ状況やグーグル状況にもぴったりあてはまる。ウェブにも、いまだカットとヴィスタとシークエンスの連結がないじゃないですか。ウェブに貼り付けられたコメントや画像はその数だけは猛烈なものであるけれど、どうにも相互の文脈と物語の深みを欠いたものたちなのだ。
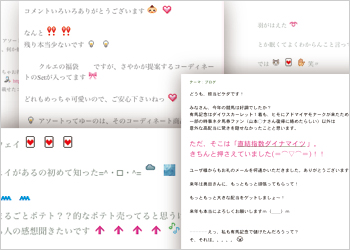
ウェブにおいてはサイトの“そこ”を覗き見ているのはユーザーである。しかし文学作品ではユーザー以前に、“そこ”に春水や漱石が投じたキャラクター(登場人物)がいる。この、読者と登場人物とが二重に見ている江戸や東京を、現在のわれわれがまた三重目に見ることになる。そこが漱石から荷風におよぶ近代文芸を読む多重のおもしろさなのである。こういう指摘は、いま思い出しても悪くない。十分に、今日のメディア情報の状況にもあてはまる。前田愛のネタヨミの真骨頂は、つまりはこういうふうにあらわれてくるわけなのですね。
もう少し前田愛ヨミの話をつづける。それからしばらくたって『幻景の明治』(1978)を読んだ。『都市空間のなかの文学』よりも前に書かれた著作だが、今度は前田愛の素材の扱いっぷりや料理の仕方にちょっぴり感応できた。
ふむ、ふむ、このように文芸テキストや思想テキストにあたかも頰杖をつくかのように密着して、その内容にふれながら時代のツボをあらわすキーワードを自在に取り出してみせる方法があったのかと思ったっけ。しかもどこか艶っぽい。のちに樋口覚にも感じたことだ。
素材というのは、たとえば『吾輩は猫である』で、漱石があえて「御維新」と書いてあることに着目するわけですね。そしてそこから、明治の連中が「御一新」「維新」「百事御一新」「王政維新」といった言葉の使い分けをしていたのは、いったい何をあらわしているのかということをめぐっていく。また福澤諭吉の『旧藩情』の中津藩についての説明のくだりから、当時の「言葉の階層化」がどのようにおこっていったかをめぐっていく。こういうネタヨミは、近世の「儒学の言葉」がどのように「近代の言葉」に変わっていったかを追ったものとしても、なかなか味がありました。
これらはまた、あの太平洋戦争の結末を、昭和の連中が「敗戦」と言うか「終戦」と言うかで、ご当人の思想の出自がわかるという手の話でもあって、いまどきの流行語大賞というくだらない言葉の押し上げにしか反応できなくなった「言葉のポピュリズム」からすると、こういう前田のものを読んでいると、やはりときどきギョッとさせられたのです。
ついで読んだのは『文学テクスト入門』(1988)だったろうか。いまはちくま学芸文庫に入って増補され、小森陽一の解説がついているのだが、当時は多木浩二が編集後記を書いていた。前田が亡くなってからこの本が構成され、没後刊行されたからだ。
この本では物語論と読書論が重なって進行していて、そのことに新たな編集的刺激を受けたことをよく憶えています。素材の最初に漱石の『草枕』を扱っている。有名な場面です。
画工の“余”が西洋の小説を読んでいると、それをハタで見ていた那美さんが「何かおもしろいんですか」と聞く。余が「適当に開けたところを読んでいるとおもしろいんだ」と言うと、那美さんは「初めから読まないと筋がわからないでしょう」と訝るので、「筋を読むのならそうするが、ぼくはそれを楽しんでいるのではない」というようなことを言う。けれども那美さんは「筋を読まなきゃ何を読むんです?」と引きさがらない。そこで漱石はこう書くわけである、「余は、矢張り女だなと思った」。
前田はこの箇所をつかまえて、世の中の読み手にはそもそも「精読者」(リズール)と「消費的読者」(レクトゥール)という2種類の読者がいるだろうことをあげ、しかし漱石は「小説の中に小説を嵌め込む入れ子型の物語」を『虞美人草』以来試みてきたのだから、そもそも筋だけでは伝わらない文学をめざしたのだと指摘する。
書き手というもの、自分が書いた物語が「精読」されるか「消費的読書」されるかなんてことは、カンケーないのです。いや、それどころじゃないのだ。書き手は、自分が書いたものの最初の読み手になるために、そうとうに七転八倒をする。だからそれが精読されるか粗読されるかの如何にかかわらず、多くの作家は自分が分け入った物語の構造にのみ向かっている。これが実情だ。
だとしたら、どうせ読書をするなら、できるかぎり「地」と「図」が二重化されているような物語を読んでいくことこそが、物語の本来と読書の本来とをつなげることになっていくのではないか。それこそが近世の戯作や近代小説がめざしたことであったのではないか。前田はそう説明していたのだった。
もっとも、ここまではとくにめずらしい意見ではない。書き手と読み手が同質のエディティング・モデルを相互に交換しているだなんてこと、当然の大前提であるからだ。それにぼくは精読と粗読はどちらも重要だと見ているし、ついでにいえば広読も狭読も、集読も乱読も重要なのですよ。読み方はいろいろあるものなのだ(このあたりのことは、ちくまプリマー新書『多読術』を見てほしい)。
それよりぼくが『文学テクスト入門』で気がつかされたのは、ジュリア・クリステヴァが提唱した「インターテクスチュアリティ」(間テクスト性)をどういうふうに、日本の近代小説にあてはめるかというネタヨミだった。
クリステヴァが「インターテクスチュアリティ」を提唱したのは『セメイオチケ』という本の中でのことだったのだが、これはテクスト間の相互作用に注目することだった。そこには、すべてのテクストは先行するテクスト、つまりプレテクストからの引用とそのモザイク(=編集)から成り立っていて、そのプレテクストは文学テクストだけではなくて、絵画や写真屋ファッションなどの非言語テクストを含めた“文化テクスト”によって成立しているという、いまではやたらに知られることになった重大な指摘がされていた。
そこで前田はさっそくこの方法によって、鷗外の『舞姫』や漱石の『草枕』や芥川の『杜子春』や鏡花の『照葉狂言』をネタヨミしてみせた。『舞姫』ではベルリンという都市のテクストを使い、『草枕』ではジョン・エバレット・ミレーが描いた《オフィーリア》の絵画テクストを使い、『杜子春』では大正の文化住宅のイメージ・テクストを使って、『照葉狂言』では金沢の民謡のテクストを使って、だった。なかには乱暴なネタヨミもあったと憶うけれど、『杜子春』の読み方には驚いた。
『杜子春』は唐代の伝奇小説『杜子春伝』を芥川が翻案編集した作品です。だいたいは原作を踏襲しているが、肝心なところを読み替え、芥川流の物語に仕立てている。ちょっと紹介しておく。
原作はどういうものかというと、長安の都の城壁の外に佇んでいた杜子春が、鉄冠老人という仙人に導かれて莫大な富を手に入れるというところから始まっている。ところがその富を数年で蕩尽してしまう。それが2度にわたる。
そこで杜子春は世の中の酷薄を思い知らされ、世俗的価値を得ようとすることを断念する。そのかわり鉄冠老人に頼んで仙術を身につけたいと申し出る。老人はさまざまな試練を課し、どんな恐ろしいことがおこってもけっして声を出してはいけないという誓いをたてさせる。杜子春はこれらを守り、試練も切り抜けるのだが、物語の終わり近くなって地獄に落ちてしまう。
地獄では父と母が馬に姿を変えられて獄卒たちに鞭で打たれていた。そのあまりの悲惨に杜子春は思わず呼びかけたくなる。ぐっとこらえているのだが、そうすると母は、私たちのことはいいから、おまえは立派な人生をおくりなさいと言う。これを聞いた杜子春はたまらず「お母さん」と声をかける。この場面で悪夢がさめて、杜子春は鉄冠老人のそばに立っていた。
やむなく杜子春は老人と別れ、いったん死んだ。そうしたら女の子に生まれ変わっていた。けれども老人との誓いはまだ生きているので、言葉が強く喋れない。周囲からは啞だと思われたまま、長じて結婚をする。ところが夫は杜子春が一言も言葉を発しないので腹を立て、生まれたばかりの子供の両足を握って逆さに吊り、床に叩きつけてしまった。そこで杜子春はアッと声をあげた……。
みごとな原作です。しかし芥川は、この最後の場面にかなり大きな変更を加えたのである。老人が杜子春に泰山の麓に小さな家を与えたというふうにした。これは原作の凄まじいプロット展開からすると、まことにおとなしい。いや、つまらなくしてしまったとも思えよう。けれども芥川はあえてそのようにして、その家の庭に桃が咲き誇っているというふうにした。陶淵明の桃源郷のような設定に変えたのだ。
なぜ芥川はそんなふうにしたのか。ここで前田は、芥川の日々や芥川が暮らしている都会の生活のテクストがここに流入していると見た。大正中期の郊外の小市民がもつコンテキストを、ここにインターテクストしたのだとみなした。仙人になれなかった杜子春は、しょせんは庭の桃で仙人の日々をいっとき想う程度だというふうにした。
なんだそんなことかと思われるかもしれないが、このネタヨミはその後の昭和の私小説から戦後の現代小説にまでつながっていく底流になった。小島信夫から島田雅彦まで、まさに芥川的インターテクストが流行しつづけたのである。そういう見方からすると、前田がクリステヴァの仮説的方法をたくみに近代日本文学にあてはめてみせた手腕は、ハイハイ、けっこうたいしたものだったのだ。
さて、こんなふうに発表順とは異なる前田愛読みをしてきたぼくは、それでも前田のネタヨミにはそんなに感服していなかったのである。ポストモダンな思想をモダンにずらして使っているのが、どこか気にくわなかったのかもしれない。ところがしばらくたって『近代読者の成立』を手にとったとき、おっとっと、これが一番おもしろいじゃないかと感じたのです。それまで書き手にこだわっていた前田が、ここで「読み手の社会」というものに思い切った目を向けていたからだ。
だから本書は総じては近代読者論ではあるのだが一般論になっていず、けっこうな細部を埋め立てたいくつかのネタヨミ論文から成り立っている。それがよかった。堪能させられた。「天保改革における作者と書肆」では、株仲間解散令をうけた版元(書物問屋・地本問屋)とその周辺の為永春水や柳亭種彦や滝沢馬琴の動向を追いかけていた。人情本・洒落本・読本を生きたソーシャル・メディアとして捉えられたのは、これが初めてだった。水野の改革の愚かさと版元をめぐる人物たちの慌てぶりもみごとに描かれていた。
次の「明治初期戯作出版の動向」は、江戸の合巻が東京の合巻にどう変わっていったかという、それまであまり知られていなかった近代日本の最初の出版事情が克明に浮上させられていた。合巻というのは、いまならウェブのポータル化といったことにあたる。同様に「明治立身出世主義の系譜」と「明治初年の読者像」も、当時の読み手がどんなふうに「本」にかかわったのかを丹念に浮き彫りにして、ドーダ、読書が明治社会の原像をつくったのだという、前田独自の解析に導いていた。
まあ、こういうぐあいに大いに見直したのだが、しかし、最もおもしろかったのは本書のなかの「音読から黙読へ」なのである。これこそは、当時、ぼくの読書論に新しい起点のようなものを付け加えてくれた。
前田はこの論文で、黙読による読書習慣が一般化したのはごく近年のことで、それも2世代か3世代のことにすぎないと断言した。
その証拠にといって、石川三四郎のばあいは父親が福澤諭吉の『学問のすすめ』を読んで聞かせていたこと、山川均のばあいは父親が馬琴の『八犬伝』を読んで家中のものが手仕事をしながらそれを聞いていたこと、長谷川時雨の家では祖母が草紙類を絵解きをまじえながら読んでくれていたことなどをあげ、さらにその前の徳富蘇峰や正岡子規や田岡嶺雲は、徹底して句読をもって読書の基礎を叩きこまれていたことをあげている。樋口一葉の日記に、一葉が母親のために小説をいろいろ読み聞かせている場面が出てくることも有名だ。
これらからは、読み手と聞き手が一種の“共同的読書”を「家」の生活様式とともに維持されていたことが如実に見えてくる。むろん音読の習慣はリテラシーの水準と関係がある。坪内逍遥の『当世書生気質』には、芸妓の田の次が仲間が投げ出す「いろは新聞」を小声に読んでいる場面が出てくるが、当時はリテラシーが不如意な婦女子が一人で何かを読むときは、たいてい周囲を憚って小声で拾い読むのがあたりまえだったのである。
それは同時に、他人が読む内容を耳で聞いているという状況が一般的だったということを示す。近世、人情本が流行したのはこのような音読習慣の上に成り立っていた。とくに為永春水の人情本の流行は、春水が句読点を音読のリズムにぴったりあわせていたせいもあって、名人技の音読読書の流行を築いていったものだ。
すなわち明治期、日本人の多くはこのように「肉親の声」の記憶とともに共読的な読書社会に入っていったのである。それはどこかで必ず「家」をともなっていた。そういう習慣が「家」から消えていったのは、おそらくラジオを共同的に聞くようになってからではないかというのが、前田の推理である。いいかえれば、「音読の家」は「ラジオを聞く家」に継承されたのだ。本書の「昭和初期の読者意識」や「読書論小史」には、そのあたりのことが、しばしばハッとさせられるネタ本を使って記述されている。 ま、今夜はこの一点だけでも心に留めておいてほしかった。
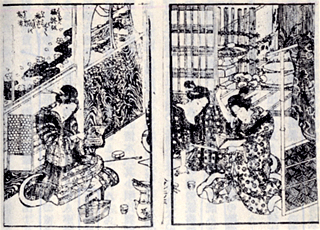
いま、音読社会の変質はどうなってしまったのか。この流れは「茶の間のテレビ」をへて、「一人ずつのウェブ」にまで行き着いた。それは読書や読者の変化ではない。たんなるメディア・テクノロジーの変化であった。それゆえここにはメディア・リテラシーの変化を読み取る装置さえ欠如したままだ。ウェブの中には前田愛にあたるネタヨミもない。だからウェブにまで行き着いたのだが、ここで読者像はぐちゃぐちゃになったのである。句読点はめちゃくちゃ、むろん音読はなく、前田が重視した共読もない。だから「家」なんてものは、とっくになくなっている。ウェブ社会というもの、これまでの「本」の社会とはまったく無縁なものになってしまったのである。
そこでぼくが惟うには、だったらいまウェブに不可欠なのはあえて「本」であるべきじゃないかということになる。そこに新たな書き手のモデルと読み手のモデルが投与されるべきじゃないかということになる。そうすればそこに、まずは人情本や滑稽本が、ついでは読本や合巻が、そしていずれは漱石の『草枕』や鏡花の『照葉狂言』が生まれてくるだろう。
しかしねえ、事態は悪化の一途をたどっている。ウェブ屋がウェブのことしか知らないようでは、まったく心もとないばかりなんですよ。