レンブラントと和紙
八坂書房 2005
1643年に出島から積み出された和紙だ。
アツガミ、アツヨウ、ウスヨウ、ウチグモリ、
ガンピ、コウシ、スギハラ、シュゼンジ、トリノコ、
ヒキアワセ、マニアイ、ミノガミ等々。
これらのうちの何をレンブラントは使ったのか。
17世紀のオランダと日本をつなぐ和紙をめぐって、
こんな一冊が上梓された。
本書の一冊の佇まいには仄かな気品があった。装幀者の名はしるしてないが、表紙カバーは生なりの地色と黒一色の明朝ゴシック併用文字が端然としていて、よろしい。定価は2800円だから高価な本ではないが、それでも端然と見えるのは、著者と編集者が丁寧につくろうとしたからだろう。それに『レンブラントと和紙』という表題がすでにして、これを読む者に丹念に読もうかなという気分をもたらす。
あとがきを見て知ったのだが、著者が早稲田の修士論文で「レンブラントと銅版画と和紙の関係の研究」を選んでいたことは、やや意外だった。なぜならこの著者は『小津安二郎と映画術』(平凡社)、『小津安二郎のまなざし』(晶文社)、『小津安二郎の食卓』(ちくま文庫)など、“小津安もの”で巷間に気を吐いていたので、てっきり映画評論に長けた人物かとおもっていたからだ。が、あらためてそれらの奥付著者紹介を見れば、パリ装飾美術書物中央校に留学しているのだから、実は書物美術史は専門だったのである。
というわけで、本書はその修士時代の調査や思索にもとづいたものを発展させた論文による構成となっているのだが、そのぶんいささか生硬で、繰り返しが多く、読んでいると退屈なところも多い。もっと紙漉きのごとく水洗いしたほうがよかった。ところがそれでも、仄かな気品は去らないのである。話題がレンブラントの銅版画とそれに和紙が使われていたという、まさにそこに去来しているからだった。つまり本書は“着眼”がすばらしいのだ。
慶長5年(1600)、豊後の臼杵湾に300トンほどの一艘の黒船が漂着した。オランダのリーフデ号である。リーフデは「慈愛」という意味だ。ウィリアム・アダムスやヤン・ヨーステンが乗っていた。一人はのちに三浦按針となり、もう一人は耶揚子となって八重洲の名を残した。
臼杵はキリシタン大名の大友宗麟の城下町で、当時は稲葉氏が治め、かなり繁栄もし、治安もゆきとどいていた。アダムスやヨーステンに対してもみごとな対応を示した。こうして日本とオランダによる長きにわたる日蘭交流の第一歩が踏み出された。やがて長崎や平戸や出島からは、さまざまな日本の産品がオランダに送られることになった。そこにレンブラントが手にした和紙が交じっていた。
レンブラントの銅版画については、ゲオルグ・ビオルクルンドの『レンブラントの銅版画・真作と贋作』、クリストファー・ホワイトの『銅版画家としてのレンブラント』、
ホワイトとカレル・ボーンの共著『レンブラントの銅版画・例証的で批評的なカタログ』などの浩瀚な研究がある。本書もそうした先行する研究書に依拠している。
それらによると、レンブラントはホワイトペーパー、オートミールペーパー、インディアンペーパー、中国紙とともに日本の和紙を使っていた。大半が雁皮を原料とした和紙である。多くは柔らかい黄色で、その色調も多様だった。薄い和紙には簀の目がついているものもあった。


上:インク詰め作業と刷り作業
下:銅版画(作画)職人と作品を見ている客
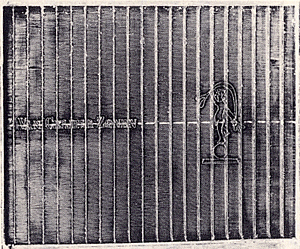
版画の主流は大きく分けると、木版画、銅版画、リトグラフ、シルクスクリーンの四種類になる。それぞれが印刷方式の凸版、凹版、平版、孔版に対応する。このうちの銅版画は硬い金属板に刻んだ原版にインクを詰め、湿った版画用紙に写しとるというもので、その技法のちがいでエングレーヴィング(ビュラン)、ドライポイント、エッチング、アクアチントなどに分かれる。
エングレーヴィングは力強い線が、ドライポイントは精細な線が特徴で、エッチングとアクアチントは硝酸などの薬品で版を腐食させる。デューラーはエングレーヴィングを、ジャック・カロはエッチングを、ゴヤはアクアチントを得意とした。レンブラントはドライポイントとエッチングを(ときにビュランも)くみあわせて駆使した。
使用したプリントペーパー(版画用紙)が多様であったことは、いまではたいそう貴重な版画美術史の伝説となっている。それとともに、レンブラントの実験性やコレクション趣味やリプレゼンテーション能力の謎を解く鍵にもなっている。今日鑑賞できるレンブラントの銅版画は280点ほどあるのだが、それらは黒白のコントラストを強調したものから、グレーのグラデーションを出そうとしたもの、柔らかい黒に徹しているもの、さまざまである。
一番多く使用したのはホワイトペーパーだった。これは日本でいう「簀の目紙」「漉き目紙」にあたる。レンブラントは最初期はドイツやスイスの、続く1650年以降はほとんどフランス製のホワイトペーパーを使った。ときに透かし文様(watermark)が入っている。オートミールペーパーはカートリッジペーパーともいって、表面がざらっとしていて小さな斑点がある。《イタリア風の景色の中で読書する聖ヒエロニムス》などがのこっている。
インディアンペーパーは淡い黄色の繊維結束が見えている紙で、よく知られた版画でいえば《ファウスト》に使われた。また、礬水を引いてから刷った作品もあって、これには《馬小屋での割礼》《エジプトへの逃避》《猫と蛇のいる聖母マリアと幼子》などがある。中国製の紙では《民衆に騙されるキリスト》《病者を癒すキリスト》の2点がわかっている。
結論からいうと、レンブラントはホワイトペーパーについで和紙を多く使用した。《灯のある羊飼いたちの礼拝》《寺院より両親と帰るキリスト》《エマオのキリスト》《埋葬》《金銀細工師ヤン・ルツマ》などはすべて日本で漉かれた雁皮系の紙だった。ヨーロッパにはめずらしい「流し漉」である。
抄紙法に「溜め漉」と「流し漉」があることは、『和紙千年』にもふれた(737夜)。中国は「溜め漉」で、後漢の蔡倫によって1世紀半ばには紙の製法が確立した。
それがシルクロードからサマルカンドをへて(タラスの会戦が751年)、さらにバグダッドに793年に製紙術が及び、1100年前後にはモロッコのフェズに、1276年にイタリアのファブリアーノに製紙場ができたのだから、古来のパピルスや羊皮紙の伝統を除くヨーロッパの紙も「溜め漉」だったといえる。パピルスはペーパーの語源となった言葉だが、漉いてはいない。
蔡倫の抄紙法は、朝鮮半島をへて日本にもやってきた。だから日本でも「溜め漉」の抄紙法が広まったのだが、早くも奈良末期から平安期にかけて、そこに独自のネリ剤を加える「流し漉」が考案された。トロロアオイやノリウツギやサネカズラなどをネリ剤にして、これを初水・調子・捨て水を微妙に調整しながら漉いたのだ。これが日本にしかない抄造法なのである。
あの独特の風合をもった柔らかな和紙の感触は、この「流し漉」による水の含ませ方とネリ剤の具合からできている。いま、われわれが手にする和紙の多くも「流し漉」による。それゆえ現在では、「溜め漉」による抄造和紙は泉貨紙・間似合紙・局紙など、ごく僅かになっている。
レンブラントは、こうした和紙の風合のみに惚れたというのではなかった。あくまで印刷の風味を見た。ではレンブラントはいったいいつごろ、このような和紙に出会ったのだろうか。本書はビオルクルンドらの調査やオランダ商館の記録などをもとに、和紙との出会いは1650年(慶安3)以前のこと、和紙が長崎から運び出された期間でいえば1609年(慶長14)から1650年までのことだったろうと推理している。
さらに特定を試みてみると、レンブラントが入手した和紙は1643年(寛永20)から1645年(正保2)に出島から積み荷されたものだったのではないかということになった。これはオランダ商館長から幕府に寄せた「オランダ風説書」が書かれはじめた時期、宮本武蔵や柳生宗矩や小堀遠州が没した時期になる。
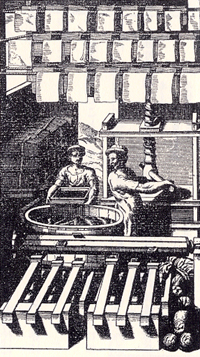
(17世紀の版画)

(『日本山海名物図会』1754年)
レンブラント・ハルメンス・ファン・レインは興味つきない生涯をおくり、興味つきない画業をのこした。あれだけ名声を博しながら破産宣告を受ける一方で、『聖書』にも人相学にも通じていたし、なんと100点をこえる自画像を描いた。
その興味つきない生涯と画業は、レンブラント個人に特有されるものというより、その時代(17世紀オランダ)の象徴であったろうという意味で、20世紀オランダを代表する知性ともいうべきヨハン・ホイジンガは、早々に(1933)『レンブラントの世紀』(創文社)を書いたものだった。
レンブラントが1606年(慶長11)にオランダのレイデンに製粉業者の六男として生まれたのは、グロティウスの『海洋自由論』が刊行された年である。1669年(寛文9)にアムステルダムに没したときは、オランダは東インド会社を先兵に世界を制しようとしていた。日本では徳川幕府の全国支配がほぼ完成していた。
こうした63年間をおくったレンブラント自身は、けれども世界の動向や祖国オランダの有為転変にはほとんど無関心だったようだ。ラテン語学校からレイデンの大学に進んだのだが、途中から画家を志し、そこでヤーコブ・スワーネンブルフやピーテル・ラストマンの徒弟となって研鑽した。やがて頭角をあらわしてレイデンで肖像画家として親方になってからは、もっぱら宗教画や肖像画に打ちこんだ。当時の肖像画はトローニーといって、上半身から上の顔貌を描く。どこかの特定個人の肖像というより、役割的肖像で、それもいわゆるバスト・ショットが多かった。
自身の仕事に打ちこんだがゆえに、それが17世紀オランダのアムステルダムをめぐっていたがゆえに、レンブラントは「レンブラントの世紀」の象徴ともなった。とくに1631年(寛永8)にアムステルダムに移ってのちは、その肖像画トローニーによって急速に人気をえた。モデリング・ランプを強く当てたようなコントラストの強い人物像は、鉛白によるグリザイユ技法や暗色によるグレーズ(曖昧さ回避)、さまざまなアンダーペインティング、独得のブラッシュ・ストロークが混然一体となって浮かび上らせたものだった。
けれどもレンブラントは、トローニーにばかりこだわらない。かの瞠目すべきキアロスクーロ(明暗法)を世に知らしめた傑作《トゥルプ博士の解剖学講義》はアムステルダムに移ってすぐの翌年の作品なのだが、集団肖像画とでもいうべき構想にもとづいていた。外科医組合会館に掲示された。その10年後の1642年(寛永19)には破格の大作《夜警》を手がけている。この10年はレンブラントがアムステルダムで一番有名だった時期にあたっている。
そういうレンブラントが油彩画制作の一方で、つねに版画の制作に勤しんでいたことは、レンブラント・ファンならだれでも知っているが、そのプリントペーパーに和紙が好んで使われていたことは、まだあまり知られてはいない。
というのも、レンブラントをめぐる論評はつねにその等身大を超えた論評がたいそう喧しく、また愉快にも、根掘り葉掘りにも展開されすぎてきたからだった。ホイジンガのものはべつとしても、ケネス・クラークは『レンブラントとイタリア・ルネサンス』で、エリック・ラルセンは『風景画家レンブラント』で(両書とも法政大学出版局の叢書・ウニベルシタス)、風景画家としてのレンブラントを重視しきってばかりいたし、尾崎彰宏のたいへんおもしろい『レンブラント工房』(講談社選書メチエ)では、国際商業都市アムステルダムが美術市場として圧倒的な力をもったことを中心に議論されていた。この本はレンブラントの真作と贋作もかなり突っ込んで話題にしているのだが、それはレンブラント個人の制作とレンブラント工房との制作に二重性があったためとされている。
とくにレンブラントの“思想”を拡張した議論として決定的なのは、レオ・バレットの『レムブラントとスピノザ』(法政大学出版局)だろう。この本ではこのオランダを代表する2人の巨人を「異質性の象徴」に仕立て上げている。いくら同時代とはいえ、スピノザとレンブラントをくっつけすぎるのはどうかとおもうけれど、バレットはこの2人の裡に自己中心主義と商業主義との両方が見え、それはこの時代のアムステルダム・オランダ主義そのものの真骨頂だったと言いたかったようだ。レンブラントの《若きユダヤ人の肖像》は30歳前後のスピノザをモデルにしたのだろう、という説もある。
まあ、こういう論評事情があり、ぼくもそのようなレンブラント論ばかり読んできたので、あえて「本書の一冊の佇まいには仄かな気品があった」とわざわざ冒頭に書いたのだった。
ちなみに、レンブラントの時代に徳川日本が抄造した和紙には、かなり多様な紙質があった。杉原紙、奉書紙、鳥の子紙、大高檀紙、美濃紙などで、正確にはわからないのだが、これらが輸出された可能性はある。
他方、これを『日匍辞書』で当たりなおすと、アツガミ、アツヨウ、ウスヨウ、ウチグモリ、ガンピ、コウジ、スギハラ、シュゼンジ、トリノコ、ヒキアワセ、マニアイ、ミノガミなどとなる。このすべての和紙が出島から船荷となって輸出されたとは確定できないのだが、このうちの厚様、薄様、打曇、雁皮、修善寺、鳥の子、間似合などが雁皮系の和紙になる。レンブラントは雁皮に印刷適性を見ていたようなのだ。
これらのこととレンブラントの版画用紙のこれまでの分析を総合すると、レンブラントが使用した和紙は、厚様の雁皮紙、薄様の雁皮、鳥の子紙あたりではないかということになる。
もう一度、1650年前後の日本とオランダを見直したほうがいいようだ。シーボルト時代ではなくて、1650年の前後だ。1650年に有田で焼かれた磁器のうち、最初は3000個か4000個が出島から運ばれていた程度だったのである。それも小さな壼や医薬用の瓶が多かった。それが7、8年後の1659年(万治2)の記録ではなんと6万個の磁器が西の海の波濤をわたったのである。
恐るべしオランダ東インド会社、恐るべしレンブラント。恐るべし東西のバロック・ムーブメント。ジャポニズムは17世紀にこそ始まったというべきである。



