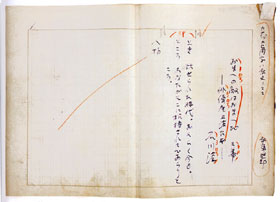父の先見


新潮文庫 1957
リグナイト葬儀社を経営するヒメと「裾野」で骨を探しているマゴが、あるとき出会う。ヒメは井伊直弼に仕えて悪名を流した長野主膳の末裔らしいのだが、やがてマゴもヒメもイチノベノオシハノミコの血統だということが判明する。
忍歯別(オシハワケ)の伝説である。それを下敷きに持ち出して何度か捻り上げ、1000年の時空をまたぐ乱脈の物語地図を書こうというのだが、さあ、そのへんまで読んできて、これはひょっとして半村良にも及ばない大失策かと見て取れた。
大作『狂風記』のことである。石川淳にして、ついに衰えたのかとか、御乱心めされたかとか、そう、見えた。さすがにギョッとした。鳴り物入りでこの大作が発表された昭和55年のこと、すぐ上下2巻を買って読み始めたときのことである。
ついついそう思えたのだが、しばらく読みすすむうちに、別の感慨が動き始めた。「此世というやつは顛倒させることなしには報土と化さない」という言葉がふと思い出されたのがきっかけだった。往年の傑作『普賢』のなかの一節だ。
そう思うとたちまちにして、なんだこれは『虹』や『荒魂』が膨大に換骨奪胎されていたのだということにピンときた。
いや、それだけではない。『狂風記』に入れ替わり立ち代わり登場してくる破天荒な人物たちは、『修羅』の足軽、『至福千年』の非人、『紫苑物語』の弓取り宗頼といったアウトローの主人公たちと、まったく同じ象形文字で書かれていたわけなのである。
そうだったのか、『狂風記』は石川淳の短編の集大成なのか(長編はこれが初めてに近かった)。これは石川ファンとしては、さすがにホッとした。
しかし、なぜこんな勘違いをしてしまったのか。ここに、石川淳を読む難しさがあったわけである。
われわれは石川淳が“江戸に留学した”ことを、あまりに重視しすぎてきた。江戸戯作のアルチザンとして、石川淳を貴重に畏怖しすぎたために、その自在な方法意識がいったい奈辺にあるかをつい見失っていた。
そもそも石川は骨法の達人だった。書の骨法ではなく、文の骨法である。その骨法は、次のような文章で見えるようになっている。「随筆の骨法は博く書をさがしてその抄をつくることにあった。美容術の秘訣、けだしここにきわまる。三日も本を読まなければ、なるほど士大夫失格だろう。人相もまた変わらざるをえない」。
洒脱で聞こえた『夷斎筆談』にある一節を引いてみたのだが、何を言っているかというと、日本の士大夫とはどういうものかを宣言している。いや、日本の士大夫なんているわけはなくて、ただ石川淳が子供のころから四書五経を叩きこまれてきた宿命的な自身をそう呼んでいるだけなのである。わかりにくければ、これを文士と見てもいい。ただし高見順ではなくて、石川淳。
その文士ふうの“幻の士大夫”は、無学を嫌い、無知を嗤うことを徹底した信条とする。まず、そこまでが前段である。
しかし後段、石川は無学に切りこんだ刀を自分に返して、ありうべきはずもない士大夫の自分自身の身上を、その返す刀の言葉と文脈の中で別所に向かわせていくべきだというのである。それが石川の言う美容術の秘訣なのだ。
別所に向かわせるとはどういうことかといえば、自分の身上をでっちあげるために固めた言葉を言葉によって逆襲し、自分の行く道を言葉の中で逸らしていくことをいう。あるいは自分で自分を攫(さら)うことをいう。
これは、自分の言葉による信条から他者に属する言葉のほうへ外れていくということだ。まあ、孔子の「正名」を荘子「狂言」で逆襲していると言ってもいいだろう。
もともと江戸の戯作とはそういうものだった。若くしてフランス文学に嵌まり、それが鼻についてからは江戸文芸にやたらに傾倒していった石川淳としては、このような「逸らし」など、いつだってお手のものである。とくに俳諧とはそういうものだ。
そこで、こんなふうになる。「俳諧化とは、一般に固定した形式を柔軟にほぐすことをいう。これをほぐすためには、精神は位置から運動のほうに乗り出さなければならない」(『夷斎清言』)。
石川は、精神を「位置」から「運動」のほうに乗り出すと言っている。これは石川がよく「精神の運動」と言ってきたもので、どうしてこんなつまらない言葉を使うのかと石川ファンをがっかりさせてきた言い回しでもあるのだが、いまはそれはさておき、石川があえて「位置」から「運動」へと言ったのは、もっとただならない覚悟なのだと思いたい。
石川自身の言葉でさらに説明することにする。すでに処女作『佳人』のなかに、その覚悟を綴った一文がある。
ところで、わたしの樽のなかには此世の醜悪に満ちた毒々しいはなしがだぶだぶしているのだが、もしへたな自然主義の小説まがいに人生の醜悪の上に薄い紙を敷いて、それを絵筆でなぞって、あとは涼しい顔の昼寝でもしていようというだけでならば、わたしはいっそペンなど叩き折って市井の無頼に伍(くみ)してどぶろくでも飲むほうがましであろう。
わたしの努力はこの醜悪を奇異までに高めることだ。
これで充分だろう。「醜悪を奇異にまで高めること」が精神の運動なのである。それを処女作であきらかに宣言していた。しかも醜悪を奇異に高めるにあたっては、「薄い紙」ではなくて「何重もの紙」によって、というふうに。
よろしいか。これなのである。石川淳はこれをしつづけてきたわけなのだ。
石川淳の「精神の運動」は、きっと明治32年に浅草で末っ子に生まれ育った当初のころから始まっていた。けれどもその「位置」を「運動」にし、「醜悪」を「奇異」に変えるためには、叙述してみることが必要だった。『普賢』や『焼跡のイエス』はその確認である。
では、時空をずらせば、どうなのか。それでも「精神の運動」は叙述の中に入ってきてくれるのか。こうして石川が取り組んだのが名作『紫苑物語』(昭和31年)である。
『紫苑物語』が名作であることは、石川ファンならばこれをたいていベスト5には入れるにちがいないから説明するまでもない。ただし、その『紫苑物語』をどのように評価するかというと、ぼくの見方と一致できる批評は、これまで知るかぎりは澁澤龍彦くらいのものだった。
主人公は宗頼という国の守である。和歌の才能をもっていたにもかかわらず、弓矢の道に耽って遠国に赴き、「知の矢」「殺の矢」にとどまれず、ついに「魔の矢」の習熟にまで及んでしまった。
石川はこの物語で初めて王朝を舞台にした。満を持したのであったろう。そして本来の歌道を捨てて、無頼の武芸に生きた男を主人公にもってきた。
宗頼は自身の行く手を塞ぐすべての邪魔者を抹殺し、背に悪霊を負うほどになっていく。殺した邪魔者の死骸のあとには紫苑を植えればいいと言い放つような、そんな男である。石川はこのデスペレートな男を形象して、ついで、その行く先で一人の宿敵と出会わせることにした。
その男は岩山の頂上近くに小屋を組み、岩肌に仏像を彫りつづける平太という男で、どんな武芸もできず、歌の才能も宗頼に劣っている。それなのに宗頼は平太の裡に宿敵を見る。
ところが出会った瞬間に、平太は「おぬし、あやかしに憑かれたな」と見抜いた。野にいる仏師としての慧眼である。けれども宗頼も怯まず、「おまえはどこの崖に仏を彫ったのか」と聞く。「告げたらば、何とする」という平太に対し、宗頼は傲然と一言、「それを射る」。
ここからが石川淳の「位置」から「運動」への努力になっていく。ここからが「醜悪」が「奇異」に切り替わる。
平太は磨崖仏の位置を教える。三段に切り立った崖の一番上の美しい岩に仏がいる。今宵は月が昇っているから、よく見えるだろうが、そんなもの射抜けるかと挑む。
宗頼はたやすいことと一言のこして、駆け上がる。足下は底知れぬ深い谷である。しばらく攀じ登ると、向こうに小さな鋼の半島の如く空中に浮き出す岩がある。その周囲は闇になっていて、崖だけが一際あかるくなっている。月はまさにその頭上にあった。
宗頼は弓を絞り、矢を放つ。一の矢は外れ、二の矢は闇に落ちていく。しかし三の矢はその崖の仏の頭部とおぼしきを射て、そのまま空中に飛んでいった。そのとたん宗頼は真っ逆さまに谷底に転落していった。
のちに人々が語るところによると、崖の仏の頭だけが欠けてなくなっていた。さすがに「宗頼の弓」とも、さすがに「平太の仏」とも言われたが、その谷からはときどき鬼の歌が聞こえてくるという噂が立った。
平太は宗頼のまったくの分身なのである。読んでいくとすぐにわかるが、宗頼自身が平太は自分の一対の片割れであることをはやくに察知する。
この片割れは、宗頼の悪魔性に対するに慈悲の象徴を秘めているが、この悪魔が慈悲に勝つというのではなく、慈悲が悪魔に克つというのでもない。仏の頭部は削られて落ちたのである。しかし宗頼もまた落ちていったのだ。
どっこいどっこいなのだろうか。そうではない。両者にマイナスがあったのである。そのマイナスがあらわれた。しかも宗頼は自身のマイナスを最初から知っていた。最初から知っているマイナスは「負」というものである。宗頼はそれを和歌を詠んでいるころからうすうす知っていた。一方、平太のほうは正直なぶん、「負」には気づいていなかった。
石川淳はそのような「負」の側からの宿命の配当を耿らかにするために、二人の対比を描き、それらを片割れにした。
これは鏡像関係なのではない。負荷と負荷の関係である。どちらもどちらかがいなければ、その先はないという関係なのだ。そのうえもっと重要なことは、さっさと常識を蹴破った宗頼のほうがずっと早くに「負」を抱え持っていた。
石川淳が日本の現代文学を代表する方法意識の持ち主であったことは、どんな凡庸な批評家も口にしてきたことである。だから、そのことを強調する必要はない。
ところが、その「方法」が何であるかということは、意外にもはっきり指摘されてはこなかった。江戸戯作精神の継承などという評価だけですまされてきた。しかし、そんなことは明白なのである。石川淳の「方法」とは、人間が背負う「負」によって事態を叙述をするということなのだ。
石川はそのために、「負」がもたらす精神と行動が事態を分断させることを好んで描いてきた。作品ごとに、その「分断の様式」を選択してくることが、石川の仕事だったのだし、分断されるべき事態をどこかから探してくることが、石川文学だったのだ。
これを「分断の負による文芸」とでもいえば文学史っぽいが、もっと端的には「言割りの文学」の貫徹と言ったらいいだろう。言割りとは言葉を割って、その中にコトワリを見ることをいう。
こうして、「分断の負」あるいは「言割り」がもたらす作用だけが作品を覆っていくという方針は、『普賢』『焼跡のイエス』から『紫苑物語』『狂風記』まで、徹底して貫かれてきたということになる。
ついでにもうひとつ、『八幡縁起』(昭和33年)という作品を老婆心ながら紹介しておきたい。
前半、山に棲む木地屋の石別(いしわけ)の一類と、その一類の名なしの神を奪って国づくりをしようとする里の荒玉(あらたま)の一族とのあいだの対立と抗争が描かれる。やがて数百年がすぎ、名なしの神は源氏の氏神としての八幡大菩薩になった。さらに時がすぎ、足利尊氏と後醍醐以降の南朝が争う時代のなかで、高師直の軍勢により木地屋の一党が斬殺される。このとき同時に火を付けられたのが八幡宮である。
武士の象徴の八幡宮も、なんらの身分保障もない木地屋も、結局は時代変化のなかで浮上し、厚遇され、あしらわれ、焼尽してしまう。いったい、何が「あらわれ」で、何が「はかなさ」というものか。
石川淳は、これらの浮沈を時をまたいで叙述して、そのどこを事態として切り取っても、結局は「負」の同時交換がおこっていることを告げたのだった。つねに何かがおこっているかといえば、「負の互酬性」なのである。
これは「日本」というものである。どういう「日本」を石川淳が見ていたかということは、面倒になったからここでは証かさないことにするが、それを石川淳の日頃の常套句でいうなら「躾」(しつけ)というものだろう。作品名でいうのなら、日本とは、『おまへの敵はおまへだ』ということになる。