父の先見


新潮文庫 1972
Emile Zola
L'Assommoir 1877
[訳]古賀照一
ミシェル・セールには『火、そして霧の中の信号―ゾラ』(法政大学出版局)というエッセイがあって、エミール・ゾラが同時代の知の構図を「ルーゴン゠マッカール叢書」に埋めこんだ驚異を語っている。
アンドレ・ジッドは毎年夏になると、その「ルーゴン゠マッカール叢書」を一作ずつ読み継いでいたという。毎年夏になるとというところが、いかにもゾラの叢書を読む気候にふさわしい。ジュリア・クリステヴァは、ゾラには悪と不幸を極限まで語る可能性が試されていると見た。ジル・ドゥルーズの『意味の論理学』(法政大学出版局・河出文庫)には「ゾラと亀裂」があるのだが、そこではゾラが作中人物の感情によらない文学的構築を試みた理由をさぐっていた。
みんな、それなりの読み方でゾラを読んできた。日本でゾラが爆発したことがないのが不思議なくらいである。むろん翻訳の質や量や版元の事情によるのであって、ここから日本の読書界の特質を云々するわけにはいかないのだろうが、ちょっと気になる。作家にとってのゾラの方法は見逃せないはずなのに、これについても小杉天外や永井荷風や島崎藤村らをのぞいて、日本の作家はどうにも淡泊だった。ということは、この三人もまたゾラ的には理解されていないということなのだろうが、ただし、これにはいささか事情がある。
小林秀雄や中村光夫が日本における自然主義文学の未成熟、ひいては「私小説の空虚」を徹底して批判したことがあった。「西洋的な自我」を借りてきてその歪みや停滞や崩壊を日本の作家が描いたところで仕方がないじゃないかというものだ。
この批判は当たっていた。それとともに、この鋭敏な二人に強烈な先手を食らって、作家たちが恐れをなした。だから、日本の私小説はその後、ゾラとは異なるところでタクアンの切り口などに人生の味を見いだして、ぬくぬくと羽を伸ばした。
ゾラの方法はぬくぬくとした風土や日常などというものとはまったく異なっている。峻厳だ。そこにはドレフュス事件で「作家は告発する」と言い放って行動をおこしたゾラの生真面目で徹底した社会派としての体質も関与していたが、さらにはジャーナリスティックな科学者風の分析癖も関与した。
そういうゾラを、ルイ゠フェルディナン・セリーヌは「ゾラの仕事はパストゥールの仕事に匹敵する」と書いていた。科学技術に関心をもっていたアプトン・シンクレアは「われわれはゾラみたいな作品を書きたいんだ」と本音を言った。アンチロマンの旗手となったミシェル・ビュトールさえも、「小説の実験はゾラが試みたように、小説そのものの中にある体液によらなければならない」と指摘した。
これらは、シンクレアを除いてみんな「フランスの知」によるゾラ賛歌ばかりだ。それならおフランスが大好きなはずの日本の作家や文芸者がゾラに傾倒してもよかったのだが、そうなっていない。結局、日本ではまだゾラは明らかにされてはいないと言うしかない。
エミール・ゾラは遺伝理論を文学のシンタックスにつかった。セマンティクスにさえつかった。いわば遺伝子配列を作品に流れる血の系譜につかったのだ。それがバルザックの『人間喜劇』に並称される「ルーゴン゠マッカール叢書」である。二十巻、実に二五年にわたる執筆に及んだ。
文芸的な構想の大半が計画倒れになるか、途中で挫折することが多いなかで(たとえば野間宏や小田実の全体小説構想)、「ルーゴン゠マッカール叢書」ばかりは一八七一年の第一巻『ルーゴン家の誕生』から一八九三年の第二十巻の『パスカル博士』まで、たった一つの家系が生み出した人間の宿命を次々に描いて、その相貌のすべてを刻んだのだ。そこには遺伝的宿命が時をまたいで演ずる苛酷な出来事が書き尽くされた。「第二帝政下における一家族の自然的社会的歴史」という副題がつくのは、そのせいだ。ナポレオン三世時代である。
なぜゾラが遺伝理論に夢中になり、その完璧な文芸化を計画したかという理由の謎は十全には解かれていない。
恵まれた気候のプロヴァンスに育ちながら六歳で父を失ったこと、急激に一家が貧窮し、同年輩のセザンヌと景色の見方を語りあったこと、十八歳で理科にめざめたにもかかわらず受験に失敗したこと、やむなく港湾局に書記として勤めるうちに、またそのあと出版社のアシェット書店で発送・宣伝・編集にかかわるうちに、人間の印象が強い類型を発していると感じたことなど、いくつものトリガーが想定されるのだが、それらが遺伝文芸大系になるトリガーなのかどうかはわからない。
ともかくもゾラは時代の宿命と社会環境の宿命と遺伝的宿命を三つ巴にして描きたかったのである。
ルーゴン゠マッカール家の出来事をめぐる作品は、連作とはいえ、それぞれ完全に独立した作品になっている。そのように自立した物語として読まれ、かつ、それらが見えない絆でつながっているようにすることがゾラの望んだ狙いであり、周到な決意だったのである。それらの作品はいくつもが話題になったが、とりわけ第七巻の『居酒屋』、第九巻の『ナナ』、第十三巻の『ジェルミナール』、第十七巻の『獣人』がセンセーショナルな賛否の嵐をおこした。
ルーゴン゠マッカールの家系は、十八歳で孤児となったアデライード・フークの血(遺伝子)が発端になる。父親が錯乱死し、アデライードも異常な気質を受け継いだまま比較的健康なルーゴンと結婚して一男をもうけ、ルーゴンの死後はアルコール中毒者マッカールと通じて一男一女を産む。こうしてルーゴンとマッカールにより三人の子が残されるのであるが、ここからおびただしい血脈の物語が派生する。
登場人物は合計一二〇〇人にのぼる。けれども二十巻のなかの主要な人物はすべて、アデライードが交わったルーゴンかマッカールかの血をひいている。たとえば『ナナ』の主人公の女優であって高級娼婦のナナは、『居酒屋』の主人公ジェルヴェーズの娘であった。
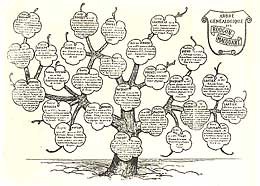
ぼくは最初、ゾラを文学作品として読んだのではなかった。ジェルヴェーズに対する憧れの印画紙を追いたくて読みはじめた。
鬼才ルネ・クレマンの映画《居酒屋》(一九五六)でジェルヴェールに扮したマリア・シェルが、当時のぼくの理想の女性の顔だったのだ。中学三年くらいのときだ。しかし映画のなかのマリア・シェルは理想的な優しい表情をもっていたが、ゾラの原作のなかのジェルヴェーズは、学生のぼくにはあまりにも不幸で痛ましかった。最初はどう読んでよいやらわからない。
ジェルヴェーズは遺伝的にはアントワーヌ・マッカールとジョセフィーヌ・カヴォーダンの血を引き、酒乱の父親は第四巻『プラッサンの征服』にも登場する。第三巻『パリの胃袋』の豚肉屋クヌーと、第十五巻『大地』および第十九巻『壊滅』に登場するジャンの妹にもあたる。
こういうことも最初はまったく見えてはいなかった。ゾラを読むとは「ルーゴン゠マッカール叢書」を読むことだとは、ずっとあとになって知ったことなのだ。
ジェルヴェーズは生まれながらに足が悪く、酒びたりで粗野な父親の暴力を浴びて育った。十四歳で町の革職人オーギュスト・ランティエに誘われ惑わされて、二人の子を産む。一人がクロードでのちにセザンヌ風の才能を発揮する画家になり、もう一人のエチエンヌがゾラの後半の名作『ジェルミナール』の主人公になっていく。
ジェルヴェーズは浮気な夫ランティエのことなどおかまいなく小さな洗濯屋を開き、かいがいしく働く。映画のマリア・シェルはここではドガの洗濯女さながらに美しく、そこには慎ましく生き生きと働いて町の片隅に生涯をおえることを理想とする庶民の姿が象徴されていた(意外に思われるかもしれないが、そのころのぼくは《二十四の瞳》の女先生や《蟻の町のマリア》などの、ようするに庶民の貧しさのなかで生き抜く女性にひどく憧れていた。その傾向は倍賞千恵子のさくらにまで続いている)。
やがてジェルヴェーズはトタン職人のクーポーと再婚した。束の間の幸福がおとずれた。ところがクーポーは不慮の転落事故がきっかけで仕事を失い酒びたりとなる。そこへ娼婦遊びからも排斥された前夫ランティエが舞い戻り、ここに奇妙な三人による生活が始まる。ジェルヴェーズはしだいに生きがいを失い、極貧に耐えられず身を売り、アルコールに浸る。娘のナナはこのような環境で育てられ、のちに娼婦となっていったのである。
一八七七年に『居酒屋』を書いたゾラは、三年後に『ナナ』を仕上げる。叢書では九巻目にあたる。
ジェルヴェーズの娘アンナは家出をしたのち、身をもちくずして娼婦となり、さらに淫らな姿態の女優ナナとして売り出し、さらには高級娼婦ともなって上流階級の男たちを翻弄する。男たちはナナを遊んだつもりだが、ナナは男を弄び、その身も心も砕いていく。そして普仏戦争の直前に天然痘に罹って、誰とも知られず死んでいった。日本語訳に最初にとりくんだのは永井荷風だった。
ジェルヴェーズの血は息子のランティエの物語として、『ジェルナミール』(一八八五)にも噴き出る。叢書の十三巻目で、ゾラの最高傑作として激賞されてきた。移住労働者のランティエが北フランスの炭坑街モンスーに入って、社会主義の熱情に駆られてストライキを決行するという話で、ゾラが亡くなったときの葬儀では、労働者たちから「ジェルミナール! ジェルミナール!」のシュプレヒコールがおこったというほど、生前から愛読された。
ゾラは何度か炭坑街の取材や炭坑労働者のインタヴューをしたようで、そのせいか読んでいると、社会の底辺の一隅の息詰まるほどの緊張が、マッカール家の内なる血とともに伝わってくる。野間宏の『真空地帯』(新潮文庫)にはこれがない。
ゾラは社会主義の中に「逆上」を見つめ、その正体をさらに描くために、ついでは一八九〇年にジェルヴェーズの次男ジャック・ランティエを主人公とした『獣人』を書いた。マッカール家で最も危険な男となった機関士の物語だ。十七巻目にあたる。
ゾラはクロード・ベルナールの『実験医学序説』などの熱烈な信奉者であって、当時の曖昧きわまりない遺伝学の傾倒者だった。この作家を貶めることにはならないだろうけれど、ゾラは「アルコール中毒は遺伝する」という俗説を信じていた。そのため作中人物の不幸はつねに過剰に血の系譜に重なっていく。
しかし、ゾラにはこの実験が必要だったのである。実験を通して時代・環境・遺伝の枠組を設定し、激震をつづける社会の中で浮沈をくりかえす「人間の鎖」を観察しきろうとした。鎖では言いすぎというなら、「人間の絆」といえばいい。登場人物はほぼ第二帝政期のフランスの人物だが、そこには古代神話よりも濃く、中世魔術よりリアルに、近世の悲劇を城から町や店にもちこんだ「強引」が生きていた。
よくぞこんなことを仕上げたものだ。「ルーゴン゠マッカール叢書」は二五年にわたって、ほぼ毎日のように書き続けられたのである。
これだけのことをなしとげるに、ゾラはそうとうに禁欲的な日々をおくり、執筆課題に向かうための意識をたえず鍛練し、資料と動向の調査に向かえる態勢をととのえ、そして筋書きと事態と人物の描写のための「単語の目録」「イメージの辞書」「ルールの群」をつねに研ぎ澄ましたはずなのだ。文芸の仲間もふやす必要があった。有名なメダンの別荘もそのために用意した。
第五五八夜にも書いたけれど、一八七〇年代、ゾラはパリ郊外メダンの地にお気にいりの別荘を入手し、そこにユイスマンスやモーパッサンを招いて文学指導をした。「メダンの夕べ」だ。セザンヌらも出入りした。ゾラにはそのように文学を「生‐社会」に向けての印画紙にするという猛然たる意志のようなものがあった。
ときに想うことがある。日本でゾラを本気で理解していたのは大佛次郎だったろうということを。いいかえれば大佛が『パリ燃ゆ』や『ドレフェス事件』(ともに朝日選書)にあれほどの情熱を注いだ理由を、われわれがいつしか理解できなくなっているのではないかということを。杞憂や危惧でなければいいのだが……。