父の先見


安全・安心生活はありうるか
NHKブックス 2006
どうしたことか。今日の社会はいつのまにか「安全と安心を求めるリスク社会」になっている。えっ、安全や安心を求めてそれでどこが悪いのですかと訝る諸君もいるだろうけれど、それはそうとうにおめでたい。
いまや安全と安心は、古代ギリシアのアタラクシアでも、古代仏教のニルヴァーナでもなくて、身のまわりに及ぶかもしれないリスクと、めったに身のまわりには及ばないであろうリスクを、同時に除去することからしか得られなくなったのだ。困ったもんだ。
それというのも、フランク・ナイトが「計算できない不確実性」と「計算できるリスク」とを分けて以来(1337夜など参照)、その計算可能のリスクをなんとか数値におきかえて、地球温暖化から新型インフルエンザまで、病気保険から投資行為まで、リスクとおぼしいものならなんでも防ぐようになったからだった。はいはい、防げればおおいに結構、せめてリスクとリターンがうまく見合っているならまだしもね。けれども、それがなかなかそうはいかなくなっている。
そうこうしているうちに、計算できそうなリスクをことごとく数え上げたいという度しがたい趨勢が大きくなって、あげくは安全とリスクを奇妙にも裏腹のサンドイッチにして、安危(あんき)抱き合わせのキマイラ社会をつくりあげてしまった。そこには口さがない“たれこみ”も“チクリ”も含まれていた。赤福も吉兆もその歯牙にかけられた。あの雪印や不二家すら‥‥。
そもそもリスキーな行動や出来事は、それこそが稀少価値の創出だったのである。新たなリスクの認定は新たな冒険であり、それが新しい価値の創出だったのだ。
それが証拠に神話も昔話の大半が、大きなリスクを受け入れた者たちの物語になっている。ジョセフ・キャンベルの『千の顔をもつ英雄』(704夜)の登場人物は、ことごとく”リスク”の英雄たちだった。
昔のことだけではない。新丹那トンネルも黒四ダムも、YS11の開発もコンビニエンスストアの日本導入も、つまりはNHK「プロジェクトX」の主人公たちの挑戦は、すべてリスクを取って価値の創出に賭けたという物語だったはずである。いま放映中のNHK「プロフェッショナル」の登場人物たちだって、リスクを価値にしなかった者なんて一人としているまい。
むろん日本ばかりではない。ジョージ・ソロス(1332夜)やスティーブ・ジョブスのようなリスク・テイカーは世界中に、いっぱいいる。
ところがいまでは、リスクを避けつづけ、賞味期限を守りつづけなければ、安全はけっして保証されず、心穏やかな日々の安心もやってこないことになった。しかもその基準がどこにあるかは、なかなか見えがたい。
たとえばタミフルである。インフルエンザ特効薬として知られているが、数年前、アメリカの食品医薬局(FDA)が「日本ではタミフル使用を認可した2000年以降、12人の子供が死亡した」というあけすけな報告書を公表した。ただちに日本のマスメディアは「タミフルに危険な副作用」といった見出しをおどらせた。
けれども一方、新型インフルエンザの流行の兆しが報じられると、今度は「日本のタミフル備蓄は足りるのか」というふうに、備蓄を基準とする報道になった。わずか0.4パーセントの備蓄しかないという記事だ。
続いて新型インフル上陸が報じられると、今度はマスク着用と手洗いと学校閉鎖がやたらに煽られ、マスクがゆきわたらないことがリスクになったのだ。そのうちこれら付和雷同はまたまた切り替えられて、ワクチン備蓄の準備問題の報道に移っていった。
これではいったい、タミフルが足りないことが危険なのか、タミフルを使うことが危険なのか、ワクチンがリスク管理の王者になっているのか、「どうでもいいからマスクは買いなさい」ということなのか、まるでどっちつかず、さっぱりわからない。ことほどさように、リスクの認定も評価も一筋縄ではいかないものなのだ。
ひるがえっていえば、人間社会にとって「危険」(danger)とは何かということが、もっともっと存分に問われるべきだった。じっくり哲学され、科学されるべきだった。
そのうえで、そのうちの何をもってリスクと見るのかを問うべきだった。この順序こそが重要なのだが、これがぐちゃぐちゃなままなのだ。
だいたい危険といってもいろいろなのである。災害もあるし、事故もあるし、病気もある。円高もあれば、不渡り手形もある。自分では法令遵守をしていも、部下がミソをつければそれで責任が問われるということもある。これでは小沢一郎よろしく、上は何くわぬ顔をしつづけるしかなくなっていく。
わが子が川に落ちたり、麻薬に走ることもある。手塩にかけた娘が肉食系男子に娶られるのだって、男親にとってはけっこうリスキーなことなのである。いやいや、「愛は世界を救う」だなんて言っているけれど、人を恋することすらいまではきわめてリスキーだ。不倫、ストーカー、セクハラ、ハニートラップ、いつなんどき恋愛が犯罪にひっくりかえされるか、わかったものじゃない。
ヒトというもの、生涯においてどれだけの危険に出会うか数知れない。ましてどのような条件が整えば安全だ安心だと感じられるかといえば、そんな数値があるわけじゃない。すべてはことごとく相対的である。「予想どおりに不合理」(1343夜)なのだ。
それでもなんとか安全・安心の基準を決めたとしても、では、それにもとづいて危険がもたらすであろうリスクを次々に消していこうとすれば、それでいいのかというと、これまたそんなわけがない。
むしろ適度にリスクと仲良くしておくことも、「柔らかい闇」があることも重要で、ときにはリスキーな仕事こそ生きがいなのだ。ぼくなど、ほとんどこっちのほうだ。ぼくには何もおこらない退屈こそが危険なのである。けれども世の中、「さわらぬ神に、たたりなし」。法律が安全度の基準を提示して、あなたがそんなことをしたら当局も会社も責任がとれませんといって、コンプライアンスな規制をかけるばかりになっている。あんたらねえ、はっきりいって、それがお節介なんだ。
ともかくもぼくの知るかぎりでは、危険の正体など、まだ誰も思想していないというべきだ。そのためには“偶然や必然の哲学”を総ざらえしなくてはならないから、そういう思想的努力をするのがめんどうなのだ。みんな、シェリングや九鬼周造(689夜)や木田元(1335夜)のような思索をするのは、しんどいだけなのだ。
むろん当局は、そんなことを待っていてはリスク管理(リスク・マネジメント)はできないから、現状、さまざまな規定やガイドラインをつくってきた。みんなもその上にちょんちょん乗ることにした。たとえば危険の分類も、アメリカの保険業界に発したリスク学に倣って次のようにした。
インフラが切断されて多数の死傷者が出るような災害による危険をクライシス(crisis)、山火事のような偶発事故のことをペリル(peril)、軍事的脅威のようなものをスレット(threat)、事故をおこす要因に満ちた危険のことをハザード(hazard)などと分けたのである。これで何が分類できたというのだろう。これは現代国家が欲したリスク分類にすぎまい。これらがどんな風土のどんな民族のどんな生活にもあてはまるかといえば、そんなことがあるはずもない。砂漠の危険と森林の危険では同日に語れないことなんて、かなりある。
それでもなんとか危険を分類できたとしてみても、それなら、それらの危険の何をもってリスク(risk)とみなせるかという視点や視野が確立しているのかというと、これこそが一番わかりにくい。
そもそもリスクの語源はラテン語の“risicare”で、岩礁の間を航行するというような意味だった。それがスペイン艦隊が海洋を制圧するころには常套用語化されて、その覇権をイギリスが握る17世紀ころに英語のリスクになったといういきさつをもっている。
ということは、英語のリスクは最初から、コンメンダ(交易会社)やカンパニア(株式会社の起源)のメンバーたちが、船が遠洋貿易に出港するにあたって出資をするときの保険観念としてしだいに流布していった概念なのである。つまりは「元手を失いたくない」「なんとかお互い保証していこう」という保険用語なのである。
もちろん投資者にとっては失敗回避も保証も必要であるのは当然だ。とはいえ、そういうようなリスク概念を、そのまま生活の安全や安心のすみずみににまでこじ入れたままでいいのかといえば、これはやっぱりあやしかったのだ。
前置きが長くなってしまったが、誤解なきように言っておくと、本書が以上のような乱暴なセイゴオ流議論をしているわけではない。
著者は奈良の帝塚山大学の福祉学部教授から現在は同志社大の心理学部に移ったばかりのセンセーで、おそらくは心優しい社会心理学のセンセーだ。それは本書を読むと、すぐ伝わってくる。「あとがき」で奥さんや子供や飼い犬に感謝しているところや、帽子をかぶった柔和な顔写真を見ても、そのことは伝わってくる。中谷内一也は「なかやち・かずや」と読む。
すでにナカニシヤ出版から『環境リスク心理学』や『ゼロリスク評価の心理学』といった著書を出していて、きっと既存のリスク学のあらかたをマスターしたうえで、新たなリスク管理の問題にとりくんでいる人なのだ。ただし、わかりやすくは書いてあるけれど、その問題提起は決して安易なものにはなってはいない。
本書の大きな見通しは、このままのリスク管理社会がこのままの基準で続いていくなら、われわれの生きている価値の質はしだいに低下していくだけだろうというものだ。
著者は現状のリスクをめぐる取り決めや議論の仕方に限界があると感じてきた人なのである。
どうしてそう感じるかといえば、理由はいろいろある。たとえば、リスク管理についての人々の「合意の過信」(フォールス・コンセンサス)がありすぎる。母乳哺育とダイオキシン汚染の関連が取り沙汰されると、ほかのお母さんがたは誰もがこれを危険だと考えるだろうと、勝手に思ってしまう。一般に、世間はサイエンス・リテラシーがひどく低いものなのだ。
そこへもってきて、専門家たちがもっともらしい汚染の危険や服用の危険を訴える。それが拡声されてマスメディアで報道される。問題は、このサイエンス・リテラシーが高い専門家たちの見解がめったに合致しないということで、しかも専門家たちは自分は一貫した意見を言っているというふうに、数値や理屈で「合理の城」をつくっていく。
こうなると、誰(どの専門グループ)の専門意見にもとづいてリスクを判断していいかは、ほとんどわからなくなっていく。それがメディアを席巻するのだから、世間は右往左往なのである。
リスクの認定はたいていエンドポイントで決められている。だが、これもいろいろあやしい。著者はそういうこともあれこれ検証している。
たとえば喫煙は肺ガンになるリスクがあるとされているけれど、このリスク評価は肺ガンがエンドポイントになったためで、そのため習慣的喫煙者のうちの何パーセントが肺ガンになったかというエンドポイントでの数値ばかりが発表される。ここには家族構成も職能も他の疾患率も加わらない。喫煙と肺ガンだけが結ばれるのだ。
これは何かに似ている。ラグビーが危険なスポーツで、したがって小中学生には向かないというような見方があるのは、骨折をエンドポイントとしたリスクがあるからだという話と似ている。骨折者の数を競技人口の中の割合から計算しているのだが、そこには、その当人がラグビーの練習や試合に出る前にどんな疲労状態にあったかとか、そもそもどういう体力や筋肉力のある者がラグビーを選んだかということは、考慮されてはいない。
著者はこうしたことをさまざまあげて、いまだリスク認知についてのモノサシが確立していないということを指摘した。そして、そのモノサシにはできれば、次のような目盛りが工夫されなければならないと暗示した。これって、どこか編集工学っぽい。
①そのリスクが発するメッセージは何か。
②情報源は何だったのか。
③リスクの証拠に何が上がっているのか。
④そのリスクと自分の関係は何か。
⑤リスク発生の頻度の基準はどこなのか。
⑥他のリスクと比較できるようになっているのか。
⑦何をするとリスクが減るのか。
⑧そのリスクを何とトレードオフしているのか。
⑨ほかに何を知りたいのか。
⑩どこへ行けば別の情報があるのか。
著者の提案にはいろいろ考えさせられるところが、いくつかある。たとえば、リスクを考えるには二分法(二値主義)にこだわらないということだ。黒か白か、危険か安全か、拒絶か容認か。これではリスクのいっさいから「ほど」(程度)というものがなくなっていく。
またたとえば、リスクを議論するばあいには、安全か危険かにやみくもに突き進むよりも、実は「信頼」とはどういうものかということを考えるべきではないかというのも、本書の提案のひとつになっている。そのための一案として、SVSモデル(主要価値類似性モデル)を紹介する。
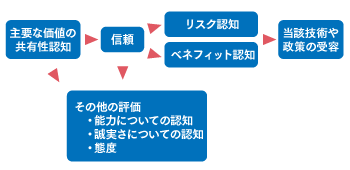
経済学では有名な「レモン市場」という話がある。レモンというのは欠陥を隠した中古車のことで、一般の消費者にはその車にどんな欠陥があるのかはわからない。
そのためレモンであることを見越して、消費者は安い買い値しか申し出ない。売り手は優良な中古車を仕入れても結局買い叩かれるので、そういう優良車だけでは儲からないから、むしろレモンを売って利益を得ようとする。その結果、一般市場に出まわる中古車はレモンがふえ、買い手はさらに安い値でしか中古車を買わなくなっていく。かくて市場はレモンで溢れかえります。こういう話だ。
これは「情報の非対称性」がもたらす「逆選択」と名付けられている現象なのだが、この話の奥には、そもそも社会的信頼性はどのようなソーシャル・キャピタルになっていくのかという問題がひそんでいる。どうすれば、こんなふうにならないですむようになるのか。
いっとき大ニュースになった耐震強度偽装事件は、地震強度というリスク基準を偽って、人々のソーシャル・キャピタル(ソーシャル・コスト)についての信頼を狂わせた事件だとみなされた。そこで取り組まれたのは「監視と制裁の強化」であった。
ところが、この監視と制裁のためのコストは建築のコストそのものには反映していない。設計者や建設者が仕組む偽装を見張るために費やすコストなのである。だから、このことをいくら強化しても、本来のリスクたる「耐震の安全性」には貢献しない。ソーシャル・キャピタルの信頼は、これではまったく進捗していかない。
信憑性と本来の信頼性は“べつもの”なのだ。いくら信憑性を監視したところで、それによって社会的な信頼性は確保できないのである。
そこで著者が「信頼」をもうすこしはっきりさせるために参照してみるといいと勧めているのが、SVS(Salient Value Similarity)、すなわち、「主要問題についての価値をめぐる類似性に関する思想」から導かれた考え方だった。
主要価値といっているのは、ある問題、たとえば河川修造計画や耐震問題やBSE問題や母乳哺育問題ということについて、人々が抱く表象のことをいう。その問題はどのような結果が望ましく、そのためにどんな方法がとられるといいだろうということに関する表象だ。
このとき、自分と相手や世間のあいだに、あるいはユーザーとシステムのあいだに、その問題についての価値観の類似性があるかどうか。SVSモデルでは、自分(ユーザー)が相手(システム)と似たような価値観を共有しているように感じられると、その相手に対する信頼も共有されるというふうにみなす。
ぼくは、ハッとした。これって何かに似ている。そうだ、漱石の「可哀想だた、惚れたってことよ」なのである。いや、わかりやすくは“信頼の相似律”というものだ。なるほど、なるほど、信頼のコストは類似性の連鎖にどれだけコストを払うかということだったんですね。
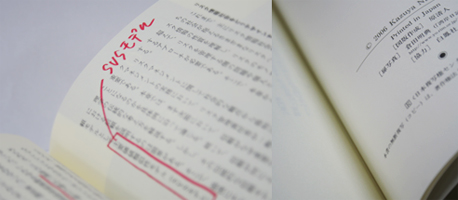
【参考情報】
(1)あまり著者の言い分を紹介できなかった。本書や『環境リスク心理学』や『ゼロリスク評価の心理学』(ナカニシヤ出版)にジカに当たられたい。リスクのモノサシに踏みこんだものが少ないので、類書はあるようで、ない。けれどもちょっと専門を変えた立場の類書ならいろいろある。
ごく一般的なものなら、岡本浩一の『リスク心理学入門』(サイエンス社)や吉川肇子の『リスク・コミュニケーション』(福村出版)や『リスクとつきあう』(有斐閣選書)。コミュニティ論の立場からは、山下祐介『リスク・コミュニティ論』(弘文堂)など。もっと広くリスク論を心理学から総覧したものでは広田すみれ・増田真也・坂上貴之の『心理学が描くリスクの世界』(慶応義塾大学出版会)だろうか。
環境論の立場からは、なんといっても中西準子の『環境リスク論』(岩波書店)や『環境リスク学』(日本評論社)が圧倒的である。『環境リスク学』は毎日出版文化賞を受賞した。
(2)千夜千冊しないかもしれないのでここに書いておくが、ダン・ガードナーの『リスクにあなたは騙される』(早川書房)は、原題が「リスク:恐怖の科学と政治学」というもので、かなりおもしろかった。恐怖とリスクとを関連づけて多様な話題をとりあげている。おおむねは行動経済学を応用しているのだが、ガードナーは「頭」と「腹」とが別々の推定や判断をしているということをみごとに暴いている。
(3)ソーシャル・キャピタル(社会関係資本)は、本書の背後がかかえている問題意識で、本書にはその説明はない。いずれぼくもとりあげたいと思うのだが、いまはたとえばマーク・グラノベッターの『リーディングス・ネットワーク論』(勁草書房)、ロバート・パットナム『ソーシャル・キャピタル』(東洋経済新報社)、ナン・リンの『ソーシャル・キャピタル』(ミネルヴァ書房)などを参考にしておいてもらいたい。