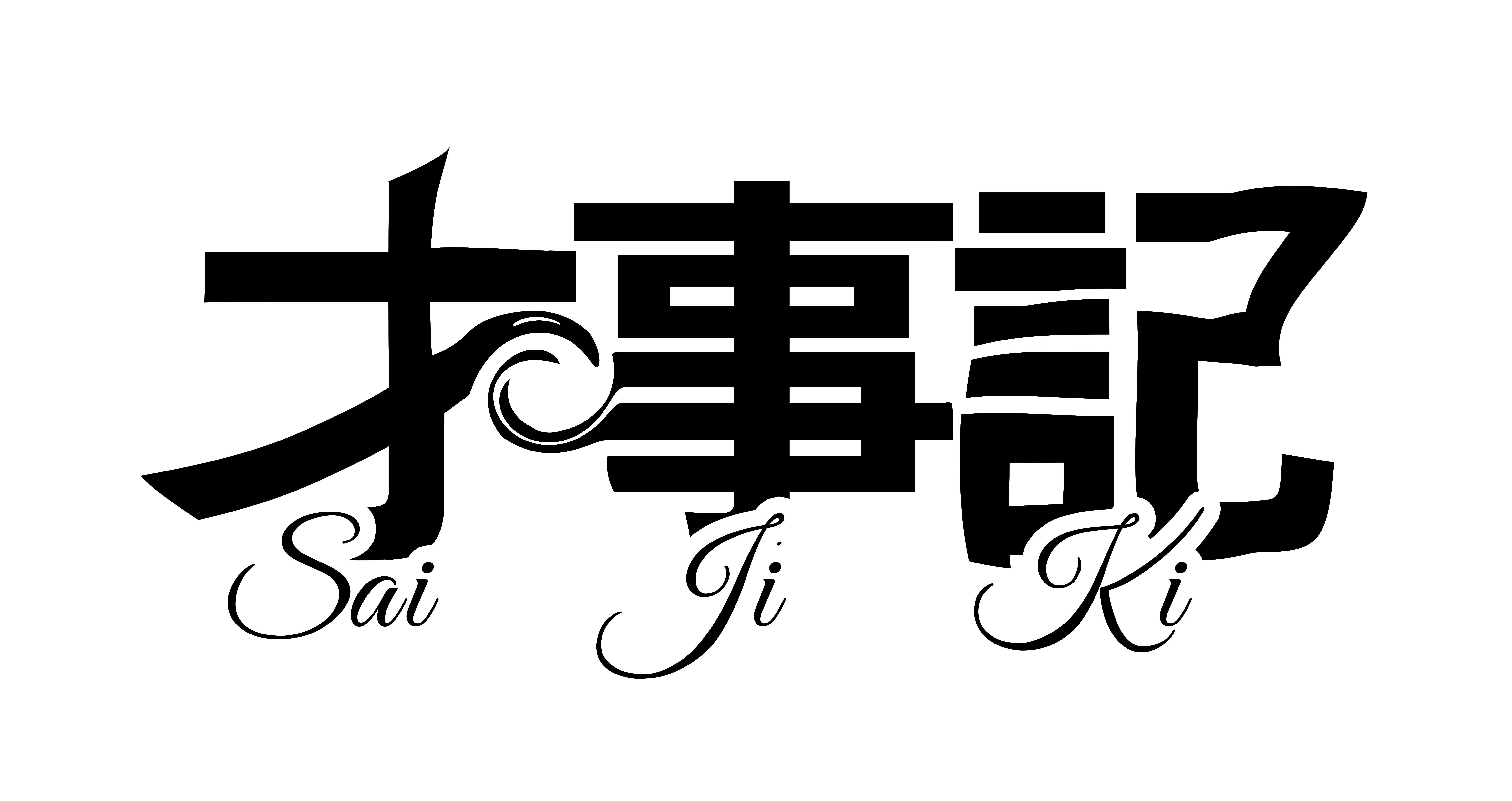旅先で通りがけに出会ったツンとした曼珠沙華、すれちがいに疾駆していった高速自転車のシュッとした軽み、映画館の白黒ニュースにあらわれた漁師の爺さんの笑み、近所の植え込みに咲く松葉ボタン、こういうものは、一度見ただけなのに忘れられない。
高校時代に見た瀬戸内海の船上から見た塩飽諸島の眩しい光景なども、ながらく忘れられなかった。
目を奪われたわけだ。ハッとしたのかといえばハッとしたのだろうが、「それ」の何によって心を動かされたのか、うまく説明できない。少年時代のその時その場での擦過体験だから、思い出してもわからない場合が多いのだ。
幼稚園のころ、敗戦の焼跡がまだ残っている人形町の雑踏を母に手を引っ張られて歩いていて、玩具屋の片隅に花火の束が置いてあった。安っぽくて鮮やかなパッケージの意匠だ。その後ずっとアタマの中で想像の花火が爆ぜていた。
ほんの数秒の知覚だったろう。それでも「それ」はピカピカと残照しつづける。なぜ「それ」は忘れられなくなるのか。「それ」が鍵として陥入してきて、鍵穴に気が付いたのかもしれない。その逆かもしれない。だとしたら「それ」は未知の鍵や鍵穴を創出したわけだ。
所作や作品が忘れられなくなることも少なくない。こちらは小さいころの出会いではない。そこそこ長じてからの話だ。
先代吉右衛門の『黒塚』の舞台、「ナショナルジオクラフィック」のバックナンバーに見たどこやらのエクストリーム・ネイチャーな地形、川喜多半泥子のそげているのにほっこりした茶碗、山口小夜子が着ていた或る日の衣裳とその着方、ロジェ・カイヨワの家の棚に無造作に置いてあった植物化石、銀座の書店イエナで次から次へと作品集をパラパラめくっていたときのダイアン・アーバスの写真、そういうものだ。
なかで、「作りもの」や「技もの」(業もの)として忘れられなくなる逸品がある。20代のおわり、ふと立ち寄った徳川美術館で見た「後藤藤四郎」など、とくに忘れられない。直刃(すぐは)の短刀である。
たちまちハッとしたが、ガラスケースの中の「作りもの」(拵えもの)だから、いろいろ目に焼き付けておこうと思っても、容易ではない。容易ではないけれど、あのとき目に焼き付けたそのままが、いまなおギラッと残像している。
作者は粟田口(あわたぐち)吉光である。通称を藤四郎といった。北条執権時代の京都粟田口にいた刀工だ。相州鎌倉の岡崎正宗と並んで名工と謳われた。
「それ」は藤四郎吉光の作刀としてはめずらしい乱刀で、刃先も焼き崩れ気味になっている。刀剣史ではおそらく失敗作だろうともくされていたのだが、のちに本阿弥光徳がその風味を激賞して、名付けて銘「後藤藤四郎」として名刀扱いされるようになった。金座の頭取だった後藤庄三郎光次が所持していた短刀なので、この不思議な銘が付いた。
造り込みは平造の三つ棟で、地鉄は小板目肌が約(つ)んでいて、地沸(じにえ)に大肌交じりだ。匂いは深く、刃文(はもん)は浅く湾(のた)れていて、丁子が交じる。
茎(なかご)もよく見たが、わずかな区(まち)を送って、目釘孔が四つあいていて、そこに「吉光」の二字が刻まれてこちらを睨む。この短刀はヤバい。怖いほどだ。
刀剣そのものは怖いものではない。凡庸な刀はいくらでもあるし、見掛け倒しも少なくない。正直なところ、刀は見た目では切れ味などわからない。そんなことは金物屋やスーパーで包丁をいくら見たっも、切れ味などわからないのと同断だ。よく「妖刀」とはいうけれど、伝承がないかぎりはその刀が妖刀かどうかなんてこと、ほぼ実感できない。
妖刀「村正」は家康の親父(松平広忠)、じいさん(松平清康)、嫡男(松平信康)が命を落としたことになっているので(そういう噂が尾鰭とともに広まったので)、やたらに有名になってはいるが、一胴七度(いちのどうしちど)の村正も、刃文が表裏で合致する千子刃(せんごば)の村正も、その場で見ていて怖くなるというものではなかった。
それなのに「後藤藤四郎」は怖かった。印象を容易にまとまらせない何かが光っていた。
短刀だからではない。吉光の作りものには短刀はすこぶる多い。ただ「後藤藤四郎」がやたらに怖く、忘れがたいのだ。鍛治のせいではない。何かが損なわれていながらも、逆境を一刀で乗り切ったのだ。
こんなことを言っておきたい。「作りそこね」は失敗とはかぎらない、むしろしばしば何かの「気味」を立ち上げている、と。
これはアートの歴史でも文章の歴史でもしょっちゅう見られることで、ときに「不完全性」とも言われることに近いだろうが、もう少し攻めて言うと「危険な偶然」が発意されているのだろうと思う。危険というのは、制作者当人にとってもこれを受ける者にとっても、何かの均衡や安心(あんじん)や既存の主張を破るものがあるということだ。
意図的にそうなったのではなく、作りそこねたのだ。だから野心作ではなく、前衛作品なのではない。ところが、そこがのちのちまでただならないものを誘い、不気味に及んだのである。
アーティストやクリエイターというもの、何作も何十作も何百作も作品をつくる。伊藤若沖もゴッホも、高浜虚子もピカソも魯山人も、ポール・オースターも藤沢周平も松本隆も、みんなそうだ。
そうなるのは作家や制作者の編集的宿命というものだけれど、そこまでたくさん試作していれば、当然ながら、なかに変格があらわれる。これがしばしば「危険な気味」を発意する。予想はできない。なぜそんなふうになるのかというと、隠れていた才能が意想外に向かって誤爆したからだ。あるいは「技」がついつい撚(よじ)ったからだ。そこが誤爆でありながら、危機迫る。そうすると、そこに「後藤藤四郎」という才能があらわれる。
才能とはどういうものかということは、軽々しくは説明できない。技能も芸能もあるし、模作力もある。「型」もあるし、「破格」もある。
スポーツのようなルール上の加点や減点が明確なものならまだしも、美術や文芸や音楽の才能は、そういうものではない。どこかニュッとしている。そんな才能になんらかの採点をしなければならない場合は、ふつうは、あれこれを比較しないと見えてはこない。時代や民族やその領分の技とスタイルがもたらしてきた表象の流れと較べ、作り手や表現者の過去とも比べて、見えてくる。
ぼくは役者や書人や写真家の才能を見誤るということはないような気がしているが、これは「目利き」の力によるわけではない。また真贋の見分けにはカンケーがない。
才能を感じるには、とくに時間はかからない。ほぼ瞬時にわかることが多い。では、何によって瞬時に才能を感じ取っているかといえば、つまりは「気味」による。
ただ、そうなるには、「作りそこね」に出会っておく必要がある。それゆえ、ときどきは「後藤藤四郎」のたぐいに出会って、その気味が当方の中に沈殿してもらっておく必要があるわけだ。
これからしばらく『才事記』というものを好き勝手に綴ってみようかと思っている。このタイトルはとりあえずの仮称だから、この言い方でどこまで話を通せるかはわからないが、できるだけさまざまな例示を紹介しながら、綴ってみたいと思っている。
才能とはどういうものなのか、ゆっくり披露する。ただし徒然なコラムなので、みっちりしてくるとはかぎらない。そこは御容赦いただきたい。それでもなんとか、何が光るのか、何がヤバイのか、どこがインチキなのか、その正体を少しずつお目にかけたいと思う。