父の先見


その2
新潮日本古典集成(1~8) 新潮社 1999
[訳]石田穣二・清水好子
どんな小説にも、どんな偉大な物語にも、調子が上がっていくところと、そうでもないところがあるものです。映画やテレビドラマがそうであるように、文学作品もそういうものです。
調子のよしあしは筋書きや内容のつながりというより、だいたい文章の興奮度や透明度や稠密度でわかります。ははん、このへん来てるなという感じがやってくるんですね。『源氏』の場合は、畳みかけるような暗示感と、肝心の出来事や浮沈する心情を一言やワンフレーズで伏せていくところです。
だいたい『源氏』は総数40万語で仕上がっている長尺な大河ドラマです。当然、緩んだり高まったりもする。それに40万語のうちの半分の20万語は助詞か助動詞です。だから、ちょっとしたことで調子が変わります。
それでも『源氏』全巻のなかで調子が最初に上がっていくのは、巻7「紅葉賀」(もみじのが)から「花宴」(はなのえん)、「葵」へと続くところでしょうね。暗示的文章がみごとに連鎖する。
少し筋立てを言っておきますと、光源氏19歳のとき、藤壺がようやく皇子を出産します。のちの冷泉帝ですね。気を揉んでいた桐壺の帝は胸をなでおろす。
「紅葉賀」はその皇子の父親が光源氏であるかもしれないことを仄かに暗示して、「花宴」では心地よく酔った源氏が弘徽殿の三の口の細殿に忍びこんで見知らぬ女と交わる夢うつつな夜を描きます。その夢のような官能をもたらしたのは東宮(のちの朱雀帝)と契りを結んでいた朧月夜の君だったのです。
はたして桐壺の帝は、わが子のこのような過ちをどう見ているのか。だいたい帝はどこまで知っているのか。そんなことを読者にやきもき感じさせるところなんですが、そこを紫式部は次のような文にして綴ります。
「師走も過ぎにしが、心もとなきに、この月はさりともと宮人も待ち聞え、内裏にもさる御心まうけどもあるに、つれなくてたちぬ」。師走を過ぎても藤壺が皇子をお産みにならないので、女官たちは正月にはと案じて待ちうけ、帝もそのご用意をなさっていたけれど、日はむなしく流れたというんですね。
「御物の怪にやと世人も聞え騒ぐを、宮いとわびしう、この事により身のいたづらになりぬべき事とおぼし嘆くに御心地もいとくるしくて悩み給ふ」。こんなに出産が遅れているのは「もののけ」のたたりのせいかなどと人はうるさく噂する。藤壺はたいそう辛いお気持ちで、この遅れのせいで事が露見し、身の破滅となるのではないかと怖れを嘆くので、身も心もひどくお疲れになった様子だったと描写します。
紫式部は「この事」あるいは「事」とだけ書いてますね。その書き方で、源氏と藤壺の不義がこのあと何をもたらすのか、何がどのように露見するのか読者は気になるところだろうけれど、そこを藤壺の宮の「御心地もいとくるしくて悩み給ふ」とするだけで、何も解説しない。
事態の本質的気配というか、その核心におよぶ人々の気分のアフォーダンスのかけらというか、それだけを示すんですね。
それで無事に皇子が産まれると、「程よりは大きにおよすけ給ひてやうやう起きかへりなどし給ふ」(発育がよくてよかったが)、「浅ましきまでまぎれどころなき御顔つきを思し寄らぬ事にしあれば、また並びなきどちは、げに通ひ給へるにこそはと思ほしけり」(驚くほど源氏の君に似通った顔立ちに、帝はすぐれている者は似通うというけれど、まったくそうだと思われたようだ)というふうに、今度はただその顔立ちの印象だけを残響させるだけなのですね。
ここに出入りするのは文章の上では一瞬の「面影」のイメージの擦過です。あとは連想するしかないことばかり。たいへんアレゴリカルでメタフォリカルです。
そして巻立てはそのまま「きさらぎの二十日(はつか)あまり、南殿の桜の宴させたまふ」に始まる「花宴」(はなのえん)に移り、そこでは今度は源氏が20歳の桜の宴を南殿(紫宸殿)で堂々と舞っている。映画の前シーンで謎を仄めかし、次のシーンではもう源氏の舞にカメラが寄っているんです。まるでその顔立ちに新しい皇子の貌(かんばせ)が宿っているかのように、ですね。そんな感じです。
ところが舞いおわり、上達部(かんだちめ)たちと酒を酌みかわし、ほろ酔い気分になった源氏はなにやら動き出す。ほんとうは藤壺のところに行きたかったのに、戸がしまっているので向かいの細殿に入りこんで、「朧月夜に似るものぞなき」とだけ声にした見知らぬ女と一夜をあかします。
一ケ月ほどたってこの「朧月夜の君」が右大臣の六の君であることを知るのですが、そんなことはここでは一言一句も綴りません。源氏が詠んだ歌「深き夜のあはれを知るも入る月のおぼろけならぬ契りとぞ思ふ」と、その女の歌「うき身世にやがて消えなば尋ねても草の原をば問はじとや思ふ」だけが示される。紫式部は一言、「艶になまめきたり」という一行だけを添える。これで充分なんですよ。
こういう、文章の明暗陰陽の効かしかた「ハイライトちょっと」と「シャドーのグラーデーション90パーセント網伏せ」といった表現術は、まったくもって巧妙です。ひたすら読者の想像力や連想力に訴えるだけの文体に徹している。
実は『源氏』には「心内語」(しんないご)と「草子地」(そうしじ)というものが駆使されているんですね。「心内語」は作中人物が心に思う言葉のことなんですが、秋山虔さんが指摘したように、『源氏』の心内語は人の心情心理と、そのような心をもたらした状況との、「双方のけじめをつけない表現」になっているのです。
「草子地」はいわゆる地の文にあたる文芸用語ですが、これも『源氏』では作者の詞、登場人物についての詞、状況描写の詞が巧みに交錯しているんです。
ということは、『源氏』の文章文体はすこぶる「共示性」に富んでいるということになりますね。そのうえで、紫式部はそうした心内語と草子地をまぜながら、われわれの想像力や連想力に生じるアフォーダンスに“限り”をつけていくんです。仄めかしの範囲を限定して測っている。そういうことはミステリー作家なら誰だってできることだけれど、それは筋書きやプロットによる仄めかしの限定です。紫式部はそれを文章の調子だけで測っているというのは、憎いというか、じれったいというか、たいしたもんです。これこそがきっと「雅びのサスペンス」というものなんでしょうね。
こうして「葵」に話が進んだときは、1年以上がたっています。この切り替わりもまことにうまい。そのあいだに桐壺帝は退位して、朱雀帝の治世となっている。「御代替り」(みよがわり)がおこっていたのです。
そういう「世」の変わりぐあいだけを語っておいて、ここに登場してくるのが六条御息所(ろくじょうのみやすどころ)です。このあと御息所の生霊が葵の上に取り憑くという前代未聞のホラーな出来事がおこるのですが、これまで御息所についてはちょっとしか記述がなかったので、読者はこの女性が何者かはわかっていない。どのように御息所を再登場させるか。
そこで紫式部は「まことや、かの六条の御息所の前坊の御腹の姫君、斎宮にゐたまひにしかば、大将(源氏のこと)の御心ばへもいとたのもしげなきを、幼き御ありさまのうしろめたさにことつけて下(くだ)りやましなましと、かねてよりおぼしけり」というふうに、いったい源氏と御息所はどんな因縁をもつのかということを、ごく少々摘まんでみせます。
どうも御息所は源氏に対する気持ちをがまんして、娘の斎宮と伊勢に下向しようかと迷っていたらしい。そのとき、葵の上がいよいよ懐妊するという、ここまでの物語の筋書きからすると最も正当な予兆があきらかになります。その直後、葵の上が御息所の生霊に苦しめられ、ついに男児(源氏の長男となった夕霧)を出産したにもかかわらず死んでいくというふうに、いまでは誰もが知っている恐るべくも意外な展開が波状的におこるわけですね。
要約すればそういうことなんですが、紫式部の文章はさらに複相暗示的で、読んでいる者には得体の知れない「もののけ」のような「もの」ばかりが静かに跳梁跋扈しているかのように感じさせています。
「大殿(おほいどの)には御もののけいたう起こりて、いみじうわづらひたまふ」「この御生霊(いきすだま)、故父大臣の御霊などいふものありと聞きたまふにつけて、おぼし続くれば、身一つの憂き嘆きよりほかに、人(葵の上)をあしかれなど思ふ心もなけれど、もの思ひにあくがるなる魂は、さもやあらむとおぼし知らるることもあり」といったふうに。
こういうふうに「もの」の気配で文章を書くんですが、それだけではありません。紫式部はここで御息所の滲み出るような教養に源氏がたじたじになっていることを巧みに浮上させるように、文章を綴っている。ぼくはこのへんにも参りました。
こういう場面があります。
「深き秋のあはれまさりゆく風の音」が「身にしみけるかな」と感じられる夜を独り寝ですごした源氏が、翌朝ふと見ると、たちこめる霧の中の咲きかけの菊の枝に、濃い青鈍(あおにび)の付け文が結ばれているんですね。それが御息所の手紙で、「ちょっとご無沙汰してしまったあいだのこと、お察しください」とあって、一首がしたためられていた。
「菊のけしきばめる枝に、濃き青鈍の紙なる文(ふみ)つけて、さし置きて去(い)にけり。今めかしうもとて、見たまへば、御息所の御手なり。聞こえぬほどはおぼし知るらむや。人の世をあはれときくも露けきに おくるる袖を思ひこそやれ」というふうです。そして「今朝の空模様にそそのかされて、つい筆をとりました」と添えてあるんですね。これでは源氏は手も足も出ない。
紫式部は、このように独特の暗示的文章によって随所で登場人物にまつわる気配を自在に操り、宮中文化のあれこれに思いのたけをぶつけているように思います。それがまた、当時の宮中に対するあてこすりになってはまずいことも手伝って、とんでもなくアンビバレントで優雅な文章と、そこに秘めた歌の雅びの表象力になっていくんですね。
まあ、こんなふうに『源氏』を読むにはなるべくその原文に浸るにしくはないのですが、今夜はそうそう原文をいちいち照覧していくわけにもいきません。みなさんはどこかで原文を愉しんでください。
ということで、ここから千夜千冊『源氏物語』第2夜の本筋に入りますが、今夜はあらためて全巻の巻名をちゃんと並べ、ざっとどういうふうに巻立てがされているのか、かんたんな説明を割りふりながら一瞥しておこうと思います。
これは物語の推移があらかたわかっていないと、『源氏』特有のディテールがなかなか立ち上がってこないだろうと思うからで、また、好きな場面や気になる場面だけをお話ししているだけでは、なんだか訳知りなことでおわりかねないなという気になっているからでもあります。そういう訳知りはぼくの意図ではありません。
ということは、このあとの話をするにも、やっぱりアウトラインが必要だろうということです。
ごくごく粗雑な簡易ペーパーをつくっておいたので、見てください。それを読みながらときどき話を補っていきます。
『源氏』は時の流れに沿って綴られているのですが、前にも言ったようにクロニクルとして成立しているわけではありません。そこで中世このかた、源氏注釈が試みられるたびに物語や登場人物を年代順に並べることが流行してきました。これを源氏ギョーカイでは「年立」(としだて)といいます。
このペーパーでも光源氏をはじめとする主な登場人物の「年立」が見えるようにするため、カッコ内に年齢と季節、主要登場人物の途中年齢と没したときの年齢を入れてあります。源氏をめぐる人物たちが、みんなとても若いことがわかると思います。
加えて、それぞれの筋立てが何を本歌取りや物語取りをしたか、その巻がどんな問題を扱ったのか、ちょっとしたオムニシエントなメモを入れてあります。
それから、ほんの少しですが、主要な和歌を詠み手とともに掲げておきました。なんといっても『源氏』は歌物語であって、歌の交わしあいが“心境会話”になっているんですから、これは欠かせません。
平安王朝期の和歌には一人で詠む独詠歌、二人で贈りあう贈答歌、三人以上の唱和歌という3つのスタイルがありますが、『源氏』は圧倒的に贈答歌です。ちょっと例をあげておきますね。
たとえば巻10の「賢木」(さかき)に、さっきの場面と関連してこんな場面があります。源氏が久々に嵯峨の野宮(ののみや)に六条御息所をたずねたとき、二人は互いになんとも名状しがたい気持ちをもっていたんですね。
御息所は源氏を振り切って娘の斎宮とともに伊勢に下向しようと思っている。源氏のほうは御息所の生霊が「もののけ」となって自分の正妻である葵の上に取り憑いた事件からというもの、自分たちがかかえこんでいる妄執の深さをかみしめています。
とはいえ、二人は互いの未練を捨てきれない。そこで源氏が簀子(すのこ)に上がりこみます。御簾(みす)を隔てた庇(ひさし)の間(ま)には御息所が対座しています。源氏はきまりわるそうに榊の枝を少し手にとって御簾の下から差し入れて「榊の色のように昔ながらの変わらぬ心でいたいのに、こんなにも情けないあしらいをするんですか」などと未練がましいことを言う。
そうすると、御息所が「神垣はしるしの杉もなきものをいかにまがへて折れるさかきぞ」と詠むんですね。この神垣には目印の杉もないのに、どこをどう間違われて榊を折って私のところに来られたのですかという歌です。そこで源氏が「少女子(おとめご)があたりと思へば榊葉(さかきば)の香(か)をなつかしみとめてこそ折れ」と返す。だって神にお仕えする乙女のいるあたりだと思って榊の葉の香りが懐かしいので折って来たのですという返歌です。
『源氏』にはこういうやりとりがしょっちゅう挟まっています。いや、挟まっているというより、こういう応答によってメインの“心境会話”が進んでいくと言ったほうがいいでしょう。『源氏』はそういうものなんです。
では、もうひとつ。巻14の「澪標」(みをつくし)の、都に戻った源氏が願解(がんほどき)のために住吉神社に詣でると、そこで明石の君も恒例の住吉詣でをしていて二人が鉢合わせをするという場面。
明石の君は気後れをしているんですね。そこで源氏が「みをつくし恋ふるしるしにここまでもめぐり逢ひけるえには深しな」と詠むと、やっと明石の君はこれに応じる余裕がちょっと出てくる。それで「数ならでなには(難波)のこともかひなきになどみをつくし思ひそめけむ」と答える。
源氏の一首は、身を尽くして恋い慕う甲斐があって、澪標のあるこの難波までやってきたら巡り会えましたね、あなたとの縁は深いんですよと詠んでいる。澪標と「身を尽くし」を掛けています。明石の君は「自分なんて人の数に入らないような身で、特別の甲斐なんて何もないのに、どうしてあなたのことを思うようになってしまったのでしょう」と返歌します。いろいろ掛詞(かけことば)や縁語が櫛されていてわかりにくいかもしれませんが、二人の心境や感情が十分に伝わってきます。
贈答歌というのはこういう感じなんです。独特のコミュニケーションですね。メールやツイッターでもこんなふうにするといいんじゃないかと思うほど、暗示的な言葉の技量のかぎりが尽くされて、相互編集状態をつくりあげています。『源氏』はこんなふうに歌による文脈的編集力を見ながら読めるようにもなっています。だから、やっぱり和歌は欠かせない。
ただし、以下に掲げたのは代表的な和歌と気になる和歌だけです。あしからず。
というところで、それでは以下に『源氏物語』五十四帖をざざっと案内してみます。
少し長くなりますが、どうもこれをしておかないと突っ込んだ話ができないんですね。突っ込んだ話は第3夜でやってみます。
【第1部】
1.「桐壺」きりつぼ
(源氏誕生~12歳元服。桐壺更衣没。藤壺入内16歳、
葵の上16歳)
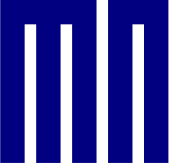
「いづれの御時にか」(おそらく醍醐天皇期)、桐壺の帝は弘徽殿の女御とのあいだに第一皇子として朱雀帝をもうけ、桐壺の更衣とのあいだに第二皇子としての光をもうける。更衣は女御たちからいじめられ、帝(みかど)が庇えばかばうほど憎まれる。その日々に耐えられず3歳の光の君をのこして病没する。その後、幼児の光の君に「源」姓が与えられ、帝には美しい藤壺が入内する。源氏は母に面影が似ている藤壺を慕い、宮中で源氏は「光る君」「かかやく日の宮」と呼ばれるほど人気を集める。12歳の元服のとき、左大臣家の葵の上と結ばれる。桐壺帝の悲嘆の描写は白楽天の『長恨歌』などを投影させている。
◉桐壺更衣「かぎりとて別るる道の悲しきに いか(生・行・逝)まほしきは命なりけり」
◉桐壺帝「雲のうへも涙にくるる秋の月 いかですむ(澄・住)らむ浅茅生(あさぢふ)の宿」
◉桐壺帝「いときなきはつもとゆひ(初めての元結)に長き世を契る心は結びこめつや」
◉左大臣「結びつる心も深きもとゆひに 濃きむらさきの色しあせずは」
あまりにも有名な冒頭なのでとくに説明することもないと思いますが、ここにこれからの物語のすべてがイニシャライズされているということから言うと、いくら説明しても足りないところです。ともかくも桐壺の帝も光源氏も藤壺に桐壺の更衣の面影を求めたのです。この面影が『源氏』全巻につながっていくアーキタイプの面影です。
桐壺の更衣の歌はイミシンですね。帝(みかど)に偏愛されるのですが、その日々はそうとう辛いものだったということが、この物語冒頭近くに掲げられている更衣の歌から察せられます。「いかまほしき」は「行く」「生く」「逝く」の掛詞。これが『源氏物語』の本文で最初に出てくる歌です。
更衣は物語が始まってすぐに病気になります。そこで更衣の母が病気を治すために「里下り」(実家に戻る)させようとするのですが、帝は重篤になるまで手放さない。母が泣く泣く訴えてやっと実家に戻ったら、更衣はその夜のうちに死んでしまいます。なんとも苛烈な物語のスタートです。
この更衣のモデルは、おそらく花山天皇に寵愛されながら早くに亡くなった姫子(藤原朝光の娘)や、やはり花山天皇に迎えられながら懐妊とともに周囲の憎しみをかって17歳そこそこで亡くなった忯子(きし)、あるいは一条天皇に迎えられながら出家した定子(藤原道隆の娘)などにあったのではないかと思います。
2.「帚木」ははきぎ
(源氏17歳夏)
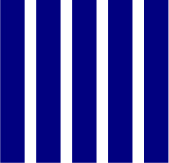
五月雨の夜、元服は頭中将(とうのちゅうじょう)・左馬頭(さまのかみ)らと世の女の品定めに興じる。結論として「中流の女」(中品の女)が評価されると、翌日、源氏はさっそく伊与介の後妻の空蝉と交わる。今後の源氏の行動パターンが予告される一帖。有名な「雨夜の品定め」は『法華経』、空海『三教指帰』などを踏襲している。
◉光源氏「帚木の心を知らで園原(そのはら)の 道にあやなくまどひぬるかな」
◉空蝉「数ならぬふせ屋(伏屋)に生ふる名のう(憂)さに あるにもあらず消ゆる帚木」
3.「空蝉」うつせみ
(源氏17歳夏)
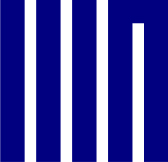
源氏は空蝉の弟の小君(こぎみ)をつてに執拗に空蝉との再度の交情を求めるが、空蝉は寝所に忍びこんできた源氏に薄衣(うすぎぬ)の小袿(こうちき)を残してたくみに逃れてしまう。源氏はその場に寝ていた軒端荻(のきばのおぎ)と交わる。こんな空蝉の「引かないやりかた」から、これはきっと紫式部自身をモデルにしているのではないかという説が出ている。
◉光源氏「うつせみの身をかへてける木(こ)のもとに なほ人がら(人殻・人柄)のなつかしきかな」
◉空蝉「うつせみの羽(は)におく露の木隠れて 忍び忍びに濡るる袖かな」
早くも源氏の「隠ろへごと」が綴られます。こっそり女性たちを口説くんですね。ただ空蝉(うつせみ)は目上の男との恋の戯れについて心得ている。誇りもある。源氏の甘い誘いに身も心もとろけそうになりながらも、辛うじて小袿一枚を残して生絹(すずし)の単(ひとえ)で逃げだしました。源氏は仕方なくというか、無謀にもというか、残っていた軒端荻(のきばのおぎ)と寝てしまうんですが、読んでいると、むしろ「はかない逢瀬」という情感が香りたってきます。
それにしても貴族の情事というもの、かなりあやしいものです。そこで、当時の王朝社会のルールについて一言。そもそも、当時の結婚は男が女の住んでいる所に通うという「通い婚」です。その仕方は、女の家にときどき行く、女の家に住みつく、女が男の家で暮らす、の3つがあります。
このことから女の身分や家格や親族の勢力が重要になってくるんですね。女の実家が権力をもっていれば、男はそこへ行って婿(むこ)になり、その家の力を後ろ盾にして出世していけます。それほどアテにならなければ、男は女を自分の屋敷に引き取るんです。
で、どうしたら結ばれるかというと、男のほうは人の噂や垣間見(かいまみ)でめらめら恋情を燃やし、なんらかの「やりとり」(手紙や部下のさぐりなど)で「脈」があるとなると、三日続けて通うんですね。これをしなければいけません。で、その三日間が成立したら二人で「三日夜(みっかよ)の餅」を食べ、女の邸で親族とともに「露顕」(ところあらわし)をすると、これで結婚なんです。でも、あとは夫が通ってくるのを待つだけ。来なければ「夜離」(よがれ)です。
4.「夕顔」ゆふがほ
(源氏17歳夏から冬へ。夕顔没19歳)
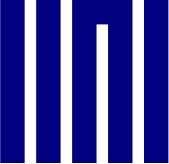
五条の一隅で夕顔の咲く家に好奇心をもった源氏は、その家の女君の夕顔に気持ちを寄せ、二人は互いに身元をあかさぬまま魔性のような激しい恋情にのめりこむ。しかし夕顔は「もののけ」に取り憑かれて急死。源氏も病いに臥せる。のちに夕顔が頭中将の愛人だったことを知る。三輪山伝承、唐代の伝奇小説『任氏伝』などが投影される。
◉夕顔「心あてにそれかとぞ見る白露の 光(光・光の君)そへたる夕顔の花」
◉光源氏「寄りてこそそれかとも見めたそかれに ほのぼの見つる花の夕顔」
◉夕顔「前の世の契り知らるる身の憂さに ゆくすゑかねて頼みがたさよ」
◉光源氏「夕露に紐とく花は玉鉾(たまぼこ)の たよりに見えしえにこそありけれ」
◉夕顔「光ありと見し夕顔の上露(うわつゆ)は たそかれどきのそら目なりけり」
この「帚木」「空蝉」「夕顔」の3帖はあきらかにつながっています。紫式部が執筆にあたって最初に仕上げたエピソディックなプロトタイプと言っていいでしょうね。これで語り部としての自信がついたんだと思います。それとともに、桐壺の更衣と藤壺という「面影」の系譜を前提にしたことによって源氏の浮気心に免罪符を与えたんですね。おかげで源氏はこれ以降、やたらに「色好み」を発揮する。
もうひとつ、とくに「夕顔」がそうなっているんですが、歌の贈答によって話を進行させるという方法が、この3帖でみごとに確立し、読者をめくるめく「歌の雅び」に導いていくというふうになっていきます。まさに宣長のいう「あやの詞(ことば)」の徹底です。
5.「若紫」わかむらさき
(源氏18歳、藤壺23歳、紫の上10歳、明石の君9歳)
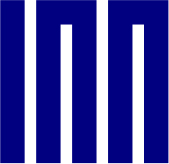
源氏が静養のために北山を訪れたとき、垣間見た美少女は藤壺によく似ていた。聞けば藤壺の姪である。源氏はこの少女を引き取って理想的女性に育て上げたいと思う。その一方、源氏はついに藤壺に迫り、夢のような逢瀬をとげてしまう。こうして藤壺は不義の子をもうけ、この子がやがて冷泉帝になるのだが、そこはこの段階では明かされない。二人はひそかに罪の深さにおののく。北山の少女のほうは源氏の自邸に引き取られる。彼女こそのちの紫の上だった。
◉光源氏「見てもまた逢ふ夜(合う世)まれなる夢のうちに やがてまぎるるわが身ともがな」
◉藤壺「世語りに人や伝へむたぐひなく 憂き身をさめぬ夢になしても」
◉光源氏「手に摘みていつしかも見む紫(藤壺のこと)の 根にかよひける野辺の若草(少女・のちの紫の上のこと)」
源氏がのちの紫の上、当時10歳の少女を発見するという話。これで桐壺の更衣、藤壺、紫の上という「面影の系譜」がいよいよ始動するのですが、しかし源氏の思いはこのレールの上にあるとはかぎらない。つねにつねに揺動するんですね。フラクチュエートする。それを「いろごのみ」と言うのですが、その意味にはなかなか深いものがあります。これについては、前夜にも少し触れましたが、次夜でもうちょっと踏み込みます。
6.「末摘花」すゑつむはな
(源氏18歳春~19歳春)
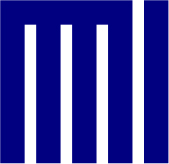
貧しく、鼻の先が赤い末摘花と一夜を共にしてしまった源氏は、なぜか実生活上の援助がしたくなる。末摘花は紅花(べにばな)のこと、鼻が長くて赤かったことにちなむ。大山津見(オオヤマツミ)神の娘のうち妹が美しいコノハナサクヤヒメであったのに、姉のイワナガヒメが醜女だったエピソードを思わせる。
◉光源氏「夕霧のはるるけしきもまだ見ぬに いぶせ(鬱悒)さそふる宵の雨かな」
◉末摘花「晴れぬ夜の月待つ里を思ひやれ 同じ心にながめ(長雨)せずとも」
◉光源氏「なつかしき色ともなしに何にこの すゑつむ花(鼻)を袖に触れけむ」
◉光源氏「紅(くれなゐ)の花ぞあやなくうとまるる 梅の立ち枝(え)はなつかしけれど」
末摘花のエピソードは「王朝のブス」の話としてかなり有名ですが、どうして顔も見ないで寝遊びができるのか、そこが不思議ですよね。むろん理由があります。
宮廷社会では、まず女性は外出することがめったにない。外出するときは牛車に乗って簾(すだれ)を下ろしてしまうから中を覗くことができませんし、家の中でも男と話すときは御簾(みす)か衝立(ついたて)を通します。つまり、ほとんど「手さぐり」なんです。なかなかアイデンティファイできない。だからこそ視覚よりも触知感覚や匂いや香りが「手がかり」になるんですが、それゆえ、ちらりと顔が「垣間見」できたりすると、それだけでたいへんな衝撃になるわけです。
7.「紅葉賀」もみぢのが
(源氏18歳初冬~19歳秋。藤壺24歳、葵の上23歳)

紅葉の美しい頃、桐壺帝の遊宴が開かれている。源氏は御前で頭中将とともに「青海波」(せいがいは)を舞って絶賛される。翌年2月、藤壺は帝の第十皇子を生む。源氏そっくりの皇子であったが、実は源氏との不義の子だった。藤壺はこのことを隠すために出産時期については嘘をつく。それでも源氏は懲りずに源典侍(げんのないしのすけ)という老女官と戯れの交渉に耽る。
◉光源氏「よそへつつ見るに心はなぐさまで 露けさまさるなでしこの花」
◉藤壺「袖濡るる露のゆかりと思ふにも なほ疎(うと)まれぬやまとなでしこ」
8.「花宴」はなのえん
(源氏20歳春、桐壺帝譲位・朱雀帝即位24歳。
藤壺25歳)
宮中の南殿(なんでん=紫宸殿)で桜の宴が催され、源氏はまたまたその舞を絶賛される。その深夜、右大臣家の姫君である朧月夜(おぼろづきよ 実は六の君)と出会って濡れる。彼女は東宮(のちの朱雀帝)への入内が予定されていたが、源氏に心を奪われる。藤原俊成は全巻を通じて最も優麗な巻だと評した。
◉光源氏「深き夜のあはれを知るも入(い)る月の おぼろけならぬ契りとぞ思ふ」
◉朧月夜「うき身世にやがて消えなば尋ねても 草の原をば問はじとや思ふ」
朧月夜との戯れは、のちに発覚して源氏の立場を危ぶませるものとなるのですが、その話は例によってまだ伏せられたままです。朧月夜の君は弘徽殿の女御の妹でもありましたからね。
それよりも、ここではこの巻をもって桐壺帝の治世下の源氏の青春期が閉幕したことを告げていることが重要です。そのため源氏研究の泰斗の一人である藤岡作太郎は「桐壺」から「花宴」までを第1期のストーリー群というふうに括りました。
9.「葵」あふひ
(源氏22~23歳。六条御息所29歳、葵の上没26歳。
紫の上14歳)
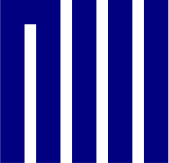
桐壺の帝が譲位して朱雀帝が即位した。六条御息所が葵祭の見学に出掛けようとしたところ、葵の上の一行に難癖をつけられ牛車まで蹴散らされた。有名な「車争い」の場面だが、このあと屈辱にがまんできない御息所は呪いの生霊(いきすだま)となって葵の上にとりつき、夕霧(源氏の長男)出産直後の葵の上を死に致らしめる。葵の上の喪があけると、源氏は紫の上と新枕を交わす。
◉六条御息所「袖濡るるこひぢ(泥・恋路)とかつは知りながらおりたつ田子(たご)のみづからぞ憂き」
◉葵の上「嘆きわび空に乱るるわが魂(たま)を 結びとどめよしたがひのつま(褄)」
◉六条御息所「人の世をあはれときくも露けきに おくるる袖を思ひこそやれ」
◉光源氏「とまる身も消えしもおなじ露の世に 心置くらむほどぞはかなき」
葵の上と六条御息所との「車争い」から、御息所の生霊が葵の上に取り憑いて、葵の上が亡くなってしまうというたいへん有名なところです。しかもここで源氏の長男の夕霧が生まれるわけなので、この巻は『源氏』全体の最初の折り返しになります。ここで物語の屏風がゆっくり折れていくんですね。でも、うっかり「もののけ」(物の怪)をたんなるオカルト扱いしていると、見当違いになります。
そもそも「もののけ」の「け」は病気や元気や習気(じっけ)などの「気」と同じ意味で、「もの」(霊)そのものの気配的属性です。ですからこの「け」が何かに取り憑くには生霊や怨霊がいったん「よりまし」(憑坐)を媒介にして憑くんですね。「もののけ」はそういうツールメディアを使うんです。そんな「よりまし」は童子の姿をしていることも多い。
葵の上の病気も験者がいろいろ祈祷したり調伏したりして、幾つかの「よりまし」を除去するのですが、一つだけぴたりと取り憑いたしつこいメディアがあって、この「もの」のせいで葵の上は亡くなってしまいます。このとき御息所も「もののけ」の動静に応じた夢を見る。そのあいだ葵の上は苦しみ、その途中で夕霧を出産する。なんとも凄い話です。
しかし、もっと重要なことは、王朝文学においては「もののけ」が物語をまるでハッカーのように外側から支配しているということです。そう、ぼくは思っています。
10.「賢木」さかき
(源氏23歳秋~25歳夏、桐壺院崩御)
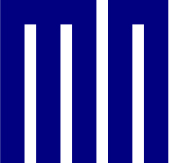
六条御息所母娘の伊勢下向が近づき、源氏は嵯峨野の秋に交流するも、御息所の決心は鈍らない。桐壺院が崩御。朧月夜は源氏との仲が知られて正式な入内ができず、尚侍(ないしのかみ)として朱雀帝に近侍する。この事態に弘徽殿の大后(おおきさき)ら右大臣の一派の専横が目立ってくる。それでも源氏は藤壺・朧月夜・朝顔らと危うい懸想(けそう)をくりかえす。藤壺はさすがにこのままでは東宮の位置を守ることは叶わぬとみて、自身は出家するのがいいだろうと落飾してしまう。ある雷雨の早朝、朧月夜のもとに忍んでいた源氏が見つけられた。激怒する右大臣と弘徽殿の大后はいよいよ源氏を失脚させようと、策謀をめぐらした。
◉六条御息所「神垣はしるしの杉もなきものを いかにまがへて折れる榊(さかき)ぞ」
◉光源氏「少女子(をとめこ)があたりと思へば榊葉の 香(か)をなつかしみとめてこそ折れ」
◉光源氏「八州(やしま)もる国つ御神(みかみ)も心あらば 飽かぬわかれの仲(源氏と御息所)をことわれ」
◉斎宮「国つ神そらにことわる仲ならば なほざりごとをまづやたださむ」
この「賢木」という一帖は、これだけで一篇の文芸作品になるくらい出来がいいですね。ここで朧月夜に惹かれる読者も多い。たしか丸谷才一さんがそうだった。
流れの推移としては桐壺の帝が亡くなり、朱雀(すざく)帝の代になります。ここから源氏はいったん追い込まれるんですね。追い込んだのは右大臣一派で、物語の冒頭で桐壺の帝が更衣を選んだときすでに源氏系と対立していました。物語の中では名前は示されずにただ「右大臣」とあるだけですが、その娘が弘徽殿の女御です。
弘徽殿の女御が一の宮を産み、その一の宮がいま朱雀帝として即位したので、右大臣の一族が外戚として権力を握ったわけです。だから源氏はこのあと須磨・明石に退却する。物語がゆっくり波乱含みになっていくところです。
一方、この巻は紫式部の天つ神・国つ神をめぐる神祇観が出ているところとしても注目されます。「賢木」は榊のことです。
11.「花散里」はなちるさと
(源氏25歳夏)

五月雨の晴れ間に、源氏は亡き桐壺帝の女御の一人だった麗景殿(れいけいでん)を訪れた。同じ庭内に住む妹の花散里は源氏の愛人でもあったが、この巻では源氏は姉妹とともに桐壺帝の懐かしい往時を偲んで語らう。
◉光源氏「をちかへり(昔に戻る)えぞ忍ばれぬ郭公(ほととぎす) ほのかたらひし宿の垣根に」
◉光源氏「橘の香をなつかしみ郭公 花散里をたづねてぞとふ」
きっとわかりにくいでしょうから、女御とか女房について、ちょっと説明しておきますと、女御というのは公卿(くぎょう)の娘で、それ以下の娘が更衣です。帝の第一のお后になるのが中宮ですが、これは女御の中から選ばれる。ですから桐壺の更衣が桐壺帝にいかに寵愛されようとも、決して中宮にはなれません。
で、これら女御と更衣たちすべてが帝の夫人として後宮(こうきゅう)に入ります。一夫超多妻です。この後宮の一人ひとりの女御や更衣に侍女として採用されているのが、女房なんですね。上流貴族に仕える女房もいます。夕顔の右近、藤壺の女御の王命婦(おうみょうぶ)、若紫の少納言、みんな女房です。『源氏』はこの女房たちが見聞したことを語りなおしているという“女房見聞記”の形式なんです。だから敬語がやたらに多く、現代人のわれわれを悩ませるんですね。
12.「須磨」すま
(源氏26歳春~27歳夏。紫の上18歳、明石の君17歳)

このまま都にいたのでは身が危ういと感じた源氏は、ついに須磨への退出を試みる。須磨では閑居するしかなく、源氏は都の女君たちや伊勢に赴いた御息所などと文通して心を癒す。都のほうでも源氏を偲ぶ。翌年3月3日、海辺で開運のための禊(みそぎ)をしていると、にわかに風雨が荒れて源氏は奇妙な夢を見る。この巻では源氏の風流韻事に耽る様子を通して、在原行平・在原業平・菅原道真・源高明、中国古代の周公旦らの事跡が明滅する。
◉光源氏「身はかくてさすらへぬとも君があたり 去らぬ鏡の影は離れじ」
◉紫の上「別れても影だにとまるものならば 鏡を見てもなぐさめてまし」
◉花散里「月かげのやどれる袖はせばくとも とめても見ばやあかぬ光(光・光の君)を」
◉朧月夜「涙河うかぶ水泡(みなわ)も消えぬべし 流れてのちの瀬をも待たずて」
◉藤壺「見しはなくあるは悲しき世の果てを そむきしかひもなくなく(無く・泣く)ぞ経(ふ)る」
◉光源氏「八百よろづ神もあはれと思ふらむ 犯せる罪のそれとなければ」
さあ、須磨ですね。須磨は在原行平に「津の国のすまといふ所にこもり侍ける」とあって、「わくらばにとふ人あらば須磨の浦に藻塩たれつつ侘ぶとこたへよ」と歌われているところです。紫式部は「心すごき場所」というふうに書いていますね。
源氏はその須磨に行くにあたって、紫の上を置いていきます。18歳になっていた紫の上は寂しがる。そこで源氏が「身はかくてさすらへぬとも君があたり去らぬ鏡のかけは離れじ」と歌に詠む。私の身はこうして遠くへさすらうことになったけれど、おまえのそばの鏡があれば私はここから離れてはいないんだよ、という歌ですね。
これに返して紫の上は「別れても影だにとまるものならば鏡を見てもなぐさめてまし」と詠む。その鏡にあなたの姿がずっと留まっているなら、それを見て心を慰めることもできるでしょうけれど、という文句です。ここに「〜ならば〜まし」という言い方がありますが、これは「反実仮想」の用法というもので、ありえないことを仮定するときのレトリックです。紫の上は源氏の歌はありえないことを言っていると詠んだわけです。このへん、紫式部はいつも女性の観察認知力をさまざまな歌語のなかに組み入れていますね。
13.「明石」あかし
(源氏27~28歳秋。紫の上20歳。明石の入道60歳
前後)
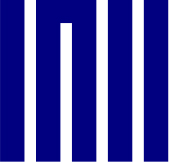
源氏が見た夢には亡き桐壺帝が現れ、早くこの地を去れと言っていた。それにあたかも呼応するかのように、長らく住吉神に願をかけてきた明石の入道の一行がやってきて、自分も「源氏を迎えよ」という住吉の夢告を受けたと言う。そこで明石に移った源氏はその地で入道の娘の明石の君と結ばれる。一方、都では凶事が続き、朱雀帝は眼病を患い、気弱になっている。そこで帝は弘徽殿の大后の反対を押し切って源氏の都への召還を決定した。源氏は懐妊した明石の君に琴(きん)をのこして帰洛する。身分不相応に心を痛める明石の君の「身のほど」の思想が語られる。
◉光源氏「海にます神の助けにかからずは 潮の八百会(やほあひ)にさすらへなまし」
◉光源氏「あはと見る淡路の島のあはれさへ 残るくまなく澄める夜(よ)の月」
◉明石の入道「ひとり寝は君も知りぬやつれづれと 思ひあかし(明石)の浦さびしさを」
◉光源氏「都出でし春の嘆きに劣らめや 年経る浦(明石の浦)を別れぬる秋」
◉光源氏「このたびは立ち別るとも藻塩(もしほ)焼く 煙は同じかたになびかむ」
◉明石の君「かきつめて海士(あま)のたく藻の思ひにも 今はかひ(貝)なきうらみ(浦見)だにせじ」
◉光源氏「うち捨てて立つも悲しき浦波の なごりいかにと思ひやるかな」
◉明石の君「年経つる苫屋(とまや)も荒れて憂き(浮き)波の帰るかたにや身をたぐへまし」
「須磨・明石」は全巻のなかでも最も壮大な景色が見えてくるところです。のちのち多くの芸能にも採り入れられました。ぼくも明石の住吉神社に行ってみて、そこが海に面して海境(うなさか)を越えて海神の力が寄りくるところだという実感をもったことがあります。光源氏が「住吉の神、近き境を鎮(しず)め護(まも)りたまふ。まことに迹(あと)を垂れたまふ神ならばたすけたまへ」と祈った感じがよく伝わってきた。この巻には神さまが出入りしているんですね。実際、源氏が救われたのは、夢にあらわれた桐壺の帝の「住吉の神の導きたまふままに、はや舟出してこの浦を去りぬ」という夢告によるものだったわけですからね。
だから「須磨・明石」は、都から離れた自然の風景を描きたくて紫式部の筆がすべったからではなくて、亡き桐壺の帝と住吉の神の威力がはたらいたからだというふうになっているということが、この続き2巻の眼目なんです。その威力の行く先で明石の入道が都落ちの源氏を迎える。そういう構図です。
では、なぜ源氏は流謫(るたく)の身になったのか。そこに藤原政権が糸を引く宮廷をめぐる権力争いが降ってきたからです。このへんのことはあとでも突っ込みます。一方において、「須磨・明石」には源氏が「侘び」に向かい、都の姫君たちとの歌のやりとりが一途に列挙されるという、かけがえのない歌物語になっています。気品と美貌をそなえた明石の君のとびぬけた詠歌の技法もたまりません。
14.「澪標」みをつくし
(源氏29歳。朱雀帝退位32歳、冷泉帝即位11歳。
六条御息所没36歳)
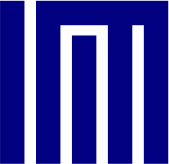
朱雀帝が「朧月夜に対する気持ちは源氏にはかなわない」という恋の恨み言を言う一方、源氏の召還を決めた。そのあと朱雀は退位して、東宮が冷泉帝として即位した。久々に都に帰った源氏も内大臣に昇進、わが子が帝になったので藤壺も異例の女院となった。一方、権中納言になっていた頭中将の娘は冷泉帝の後宮に入内して新たな弘徽殿の女御として、権力競争の一翼を担うことになる。明石の君は女児を出産。六条御息所はついに死去。
◉明石の君「ひとりして撫づるは袖のほどなきに おほふ(覆ふ)ばかりの蔭をしぞ待つ」
◉明石の君「数ならでなには(難波・何は)のこともかひなきになどみをつくし思ひそめけむ」
◉惟光「住吉の松(待つ)こそものは悲しけれ 神代(かみよ)のことをかけて思へば」
15.「蓬生」よもぎふ
(源氏28~29歳。藤壺34歳)
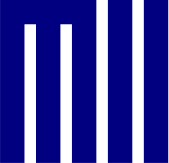
末摘花の後日譚。源氏が荒廃した邸を通りかかり、自分を一途に待ちつづけていた末摘花のこころざしを感じ、行く末長く庇護しようと思う。彼女は十分な暮らしができなかったのである。宮家の姫君としてある程度の暮らしを維持することの困難が綴られる。このへん紫式部の筆はけっこうリアルになっている。
◉末摘花「絶ゆまじき筋を頼みし玉かづら 思ひのほかにかけ離れぬる」
◉末摘花「亡き人を恋ふる袂(たもと)のひまなきに 荒れたる軒のしづくさへ添ふ」
16.「関屋」せきや
(源氏29歳秋)

空蝉の後日譚。かつて一夜を交えた空蝉は夫の赴任地にいたが、それが終わって上京する。その途次の逢坂の関で石山参詣の源氏の一行と行き合わせた。源氏の詠む歌に感慨にふける。空蝉はその後、夫に死なれ、出家して尼となるのだが、のちに源氏に庇護されて二条東院に住むようになる。
◉空蝉「行くと来(く)とせき(関)とめがたき涙をや 絶えぬ清水(しみづ)と人は見るらむ」
◉空蝉「逢坂の関やいかなる関なれば しげきなげきの中を分くらむ」
巻14「澪標」からは都に帰った源氏の動向になるのですが、「蓬生」と「関屋」は末摘花と空蝉のその後の動向の話に耽ります。なんだか源氏に余裕が出てきているような運びですが、宮廷社会での見かけは実際にもそうなっていくんですね。
さきほど、空蝉は紫式部自身がモデルになっているのではないかと言いましたが、「関屋」ではその空蝉のその後が語られます。東国に下り、その後、都に戻ってくる途中に石山詣で源氏の一行に出会うという「もののあはれ」を感じさせるシーンが描かれますね。「しげきなげきの中を分くらむ」がなんともいえない表現です。
17.「絵合」ゑあはせ
(源氏31歳春。斎宮女御=秋好中宮22歳)

六条御息所の遺児の前斎宮は冷泉院の後宮に入内、弘徽殿の女御と帝の寵愛を二分する。冷泉帝は絵を好んだので、二人の女御のもとに名品が集まり、二人は物語合せや絵合せで競う。絵合せは斎宮側の勝利となり、そんなことが宮廷では有効で、源氏方の権勢も優位になっていく。実は平安期の史料では絵合せは見当らない。紫式部の考案だろう(つまり光源氏のアイデアだったというふうにした)。
◉朱雀院「別れ路に添へし小櫛(おぐし)をかごとにて はるけき仲と神やいさめし」
◉斎宮女御「しめ(標)のうちは昔にあらぬここちして 神代のことも今ぞ恋しき」
18.「松風」まつかぜ
(源氏31歳秋冬。明石の君22歳、明石の姫君3歳)
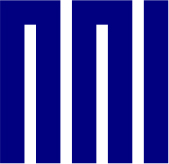
二条東院が落成、西の対(たい)に花散里が入る。東の対に入る予定だった明石の君の母娘は嵯峨の大堰川(おおいがわ)のほとりの別荘に移り住む。源氏は紫の上に気兼ねしつつも明石の君を月に二度訪れる。大堰の山荘には結局、明石家三代の女性たちが住んで源氏を通わせたことになる。「反藤原」の呼吸が聞こえてくる。
◉光源氏「契りしにかはらぬ琴の調べにて 絶えぬ心のほどは知りきや」
◉明石の君「かはらじと契りしこと(琴・言)を頼みにて 松の響きに音(ね)を添へしかな」
19.「薄雲」うすぐも
(源氏31歳冬~32歳秋。藤壺没37歳)

明石の姫君を将来の后にと願う源氏は紫の上の養女として引き取り、二条院に移させる。源氏32歳の年は天変地異が多く、そのなかで藤壺が37歳の生涯を終える。源氏が深い悲嘆にくれるとき、藤壺の加持僧が冷泉帝に「帝は実は源氏の子なのです」と告げ、帝ははげしく動揺する。このあと話は春秋優劣論になる。紫の上が春を好むのに対して斎宮が秋を好むことを知った源氏は、四季の花鳥風月を満喫できる豪壮な邸宅を造営したいと思う。これがのちの六条院となる。
◉明石の君「いさりせしかげ忘られぬ篝火(かがりび)は 身の浮舟(憂き舟)やしたひ来にけむ」
◉光源氏「浅からぬしたの思ひを知らねばや なほ篝火のかげは騒げる」
桐壺の更衣の面影を淡々と曳航してきた藤壺が亡くなります。源氏にとっては二人目の母の喪失です。死の床で藤壺は「高き宿世(すくせ)、世の栄えも並ぶ人なく、心の中(うち)に飽かず思ふことも人にまさりける身」というふうに、自身をふりかえる。「すぐれた果報に恵まれ、この世での栄華も並ぶ人のないものでしたけれど、それとともに胸ひとつに秘めた嘆きも際限のないものでした」というんですね。
藤壺の死は源氏が抱いてきた「永遠の母性」のようなものがぷつりと切れることでもあったわけですが、ところが源氏はその母なる藤壺と密通をしたことで冷泉帝という不義の子をつくってしまってもいたわけですから、また、その子が帝になっていくのですから、その切断感と苦悩は帝の悲しみや苦悩に転化するとともに、源氏自身をも苛(さいな)むものとなります。
さあ、それで源氏はどうするかというと、ひとつには紫の上に注がれるはずなんですが、ところが性懲りもなく過去の女性遍歴にしばし酔っているようなんですね。ま、どこかの芸能人のようなもんです。その女性遍歴の回顧が次の「朝顔」で語られます。
20.「朝顔」あさがほ
(源氏32歳秋から冬へ)

源氏は桃園式部卿宮(ももぞのしきぶきょうのみや)の娘の朝顔に繰り返し懸想する。紫の上はこれに嫉妬するが、朝顔は心を開こうとしていなかった。12月の雪映えが美しい庭先を見ながら、源氏は紫の上に過去の女君たちのことをやや自慢げに語り、紫の上こそ藤壺の面影を継いでいるとまことしやかに話す。しかしその夜、源氏が夢うつつの状態でいるとき、藤壺の幻影があらわれた。気配を察した紫の上が声をかけると源氏は泣きじゃくり、紫の上はじっと体をかたくする。冬の月下の雪景色の描写が絶妙。
◉光源氏「人知れず神のゆるしを待ちしまに ここらつれなき世を過ぐすかな」
◉光源氏「なき人を慕ふ心にまかせても かげ見ぬみつの瀬にやまどはむ」
◉朝顔「なべて世のあはればかりをとふからに 誓ひしことと神やいさめむ」
◉朝顔「秋果てて霧の籬(まがき)にむすぼほれ あるかなきかにうつる朝顔」
21.「少女」をとめ
(源氏33歳春~35歳冬。太政大臣に就任。夕霧元服。雲居雁
14歳。紫の上27歳)

源氏長男の夕霧が元服し、大学教育を受け、寮試に及第する。源氏はついに太政大臣となり、斎宮の女御も中宮(秋好中宮)となる。絶頂である。巻名の「少女」(おとめ)とは、権中納言(もとの頭中将)の次女の雲居雁(くもいのかり)の東宮入内の期待がなかなか叶わず、しかも雲居雁が夕霧と相思相愛らしいことを知って、内大臣がむりやり自邸につれ去ってしまったため、少年夕霧と少女が引き裂かれたことに由来する。源氏の方は最高の栄誉を得て、いよいよ完成した六条院に、春の町には紫の上が、秋の町には秋好中宮(あきこのむちゅうぐう)が、夏の町には花散里が、冬の町には明石の君が住まうという、このうえない四季を牛耳る権勢を誇る。
◉夕霧「あめ(天)にますとよをかびめ(豊受姫)の宮人も わが心ざすしめ(標)を忘るな」
◉夕霧「ひかげにもしるかりけめやをとめ子が 天の羽袖(はそで)にかけし心は」
◉光源氏「をとめ子も神さびぬらし天(あま)つ袖 ふる(古・振)き世の友よはひ経ぬれば」
元服した夕霧の周辺と、かねて造営中だった六条院が完成したことが主に語られる一巻です。源氏は太政大臣になり、なんだか自信をつけていった感じがします。とくに四季を配した区画をつくりあげた六条院の威容は鼻高々で、自慢したくてしょうがないんです。
そもそも源氏はどんなところに住んでいたんでしょうね。むろん公務は内裏(だいり)でするのですが、光源氏は賜姓源氏として臣下に下ったのですから、内裏での描写は物語の初めのほうに限られています。あとはどうなっているかというと、もっぱら二条院に居た。ここは桐壺の更衣の実家(里第)です。紫の上を強引に連れてきたのも、ここですね。その後、須磨・明石から戻ってからここを拡張して二条東院を造営すると、ここに住みます。ほかに「絵合」「松風」には嵯峨の御堂があり、「松風」「薄雲」には桂の院もあったとなっていますから、かなり贅沢です。で、そのうえに六条院を大造営したんです。
22.「玉鬘」たまかづら
(源氏35歳。秋好中宮26歳、明石の君26歳)
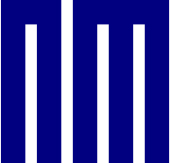
急死した夕顔の遺児に玉鬘がいた。彼女は4歳のときに乳母一家に伴われて筑紫に下っていたのだが、ようやく土地の豪族の求愛などから逃れて上京していた。けれども頼るものもなく、初瀬の長谷寺に参詣したおりに、亡き夕顔の女房で今は源氏に仕える右近とめぐり会った。右近がこの話を源氏にすると、源氏はよろこんで玉鬘を六条院に迎え、夏の町に住まわせる。歳末、源氏は晴れ着を女君たちに配った。この「玉鬘」から「真木柱」までを「玉鬘十帖」とグルーピングすることがある。
◉玉鬘「数ならぬ三稜(みくり)や何の筋なれば うき(浮・憂・泥)にしもかく根をとどめけむ」
◉光源氏「恋ひわたる身はそれなれど玉かづら いかなる筋を尋ね来つらむ」
23.「初音」はつね
(源氏36歳正月。紫の上28歳、玉鬘22歳)

源氏は紫の上と正月を祝い、六条院の庭内を満足げにめぐり、明石の君、花散里、玉鬘らの女君たちを次々に訪れ、さらに二条東院の空蝉や末摘花などもたずねる。四季の町を巡訪する源氏は、まるで古代の王さながらの「国見」(くにみ)をしているかのようである。
◉光源氏「うす氷とけぬる池の鏡には 世にたぐひなきかげぞならべる」
◉紫の上「くもりなき池の鏡によろづ代(よ)を すむ(澄・住)べきかげぞしるく見えける」
さあ、この巻23から巻29の「行幸」(みゆき)までは、四季の風物行事が次々に描かれる色彩鮮やかな王朝絵巻です。鶯の初鳴きの「初音」に始まって、3月の「胡蝶」、5月の「蛍」、6月の「常夏」(これは撫子の別名ですが)、そして7月の「篝火」(かがりび)、8月の台風の季節の「野分」というふうに、巻名が旧暦の移り変わりをあらわすんですね。
ちなみにこれを花鳥風月の「うつろひ」で追うと、若菜、霞、梅(梅が枝)、桜(花)、葵、橘、時鳥(ほととぎす)、蛍、野分、朝顔・夕顔、松虫・鈴虫、女郎花(おみなへし)、萩、雁、紅葉(紅葉賀)、桐、雪といったふうになりますかね。
24.「胡蝶」こてふ
(源氏36歳晩春~初夏。秋好中宮27歳)

晩春3月、源氏は六条院春の町で船楽(ふながく)を催し、翌日は秋好中宮の季の御詠経(みどきょう)の仏事。紫の上と中宮は春秋くらべの贈答歌を詠み交わす。『源氏』にはこうした王朝文化の独特の催事がくりかえし描写される。のちの源氏文化の飛沫になっていくところ。
◉紫の上「花園の胡蝶をさへや下草に 秋まつむし(松虫・待つ)はうとく見るらむ」
◉光源氏「橘のかをりし袖によそふれば かはれる身とも思ほえぬかな」
◉玉鬘「袖の香をよそふるからに橘の み(身・実)さへはかなくなりもこそすれ」
25.「螢」ほたる
(源氏36歳5月。玉鬘22歳)

しばらく前から玉鬘のところには多くの懸想文(けそうぶみ)が寄せられている。人気の的なのだ。けれどもあろうことか源氏も養女の玉鬘に懸想する。煩わしく思う玉鬘に、源氏は蛍兵部卿宮がやってきた夜、玉鬘の身のまわりに蛍を放つという趣向を演出して歓心を買おうとする。長雨の頃、玉鬘たちが世の物語に熱中している。ここで源氏は「物語の本質は虚構(フィクション)であることにある。そのほうがずっといい」(ひたぶるにそらごとと言ひはてむ)と説く。「日本紀などはただ片そばぞかし」(日本書記などはほんの片端にすぎない)とも言う。蛍火の薄明かりで女性の美貌が際立つ話は『伊勢』や『宇津保物語』にもある。物語虚構論は紫式部の思想の表明。
◉玉鬘「声はせで身をのみこがす螢こそ 言ふよりまさる思ひなるらめ」
◉玉鬘「あらはれていとど浅くも見ゆるかな あやめもわかず泣かれけるね(根・音)の」
26.「常夏」とこなつ
(源氏36歳6月)
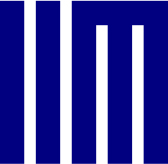
暑い夏の日、源氏が釣殿で涼をとりながら夕霧や親しい殿上人たちを相手に話しているところへ内大臣の公達たちが来る。源氏は内大臣には含むところがあるので、近江の君などを悪しざまに皮肉る。源氏一党と内大臣一党との対立が深まっていく一節。一方、源氏は玉鬘に和琴(わごん)を教えながら胸をときめかせる。巻名の「常夏」は撫子(なでしこ)の別名。
◉光源氏「撫子(なでしこ)のとこなつかしき色を見ば もとの垣根を人や尋ねむ」
◉玉鬘「山がつの垣ほに生(お)ひし撫子の もとの根ざしをたれか尋ねむ」
27.「篝火」かがりび
(源氏36歳7月)

夕月夜に琴を枕に玉鬘に添い臥す源氏。もやもやした気分だが、それ以上には手は出さない。その気分、庭の篝火の煙のようなのである。柏木は玉鬘と源氏のそうした関係をまだ知らない。夕月夜にこちらは笛を吹くばかり。
◉光源氏「篝火にたちそふ恋の煙こそ 世には絶えせぬ炎なりけれ」
◉玉鬘「行方なき空に消ちてよ篝火の たよりにたぐふ煙とならば」
28.「野分」のわき
(源氏36歳8月。夕霧15歳。柏木20〜21歳)
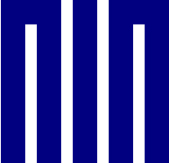
仲秋8月、激しい野分が襲来した。その見舞いに六条院春の町を訪れた夕霧は、はからずも紫の上を垣間(かいま)見て、霞の間に咲く樺桜のような美しさに魂を抜かれる。その一方、玉鬘に戯れかかる父の源氏を垣間見て驚く。夕霧は秋好中宮(あきこのむちゅうぐう)、明石の姫君、玉鬘、花散里を見舞う源氏のお供もしている。15歳の夕霧が男と女の姿態を通して宮廷文化の官能に少しずつ気づいていくわけだ。
◉玉鬘「吹き乱る風のけしきに女郎花(おみなえし) しをれしぬべきここちこそすれ」
◉光源氏「した露になびかましかば女郎花 荒きかぜにはしをれざらまし」
◉夕霧「風騒ぎむら雲まがふ夕(ゆふべ)にも 忘るる間なく忘られぬ君」
ここはなかなか読みごたえのある一巻ですね。われわれは夕霧の目によって源氏をとりかこむ女君たちの姿態や様態のバイアスにつきあわされるのですが、紫式部はこの手法で新たな人的景観と客観性を『源氏』に与えているんです。
夕霧はミドルティーンの15歳。もう十分に性に目覚めています。六条院を激しい野分が襲ったあと風雨見舞いに人が動く。そこで夕霧は廂(ひさし)の御座所にいる紫の上を見るんですね。心臓がとまるほどに美しい。いささか几帳面な性格の夕霧は、そのままどきどきしながら、それぞれに綺麗なお姉さんを見くらべていくと、父親の源氏の戯れている姿を見て違和感をおぼえるんですね。ここはぼくも父に連れられて祇園・先斗町に行った中学時代のことを思い出したところです。
29.「行幸」みゆき
(源氏36歳12月~37歳2月。玉鬘22〜23歳)

冷泉帝が大原野に行幸し、源氏のはからいで玉鬘も行列を見物した。玉鬘を帝の尚侍(ないしのかみ)として出仕(入内)させたい源氏は、玉鬘の父である内大臣(以前の頭中将)を腰結(こしゆい)として裳着(もぎ)の儀をしようと計画していた。裳着は女子が成人になったことを記念したしるしである。内大臣はいったんこの申し出を断ってきたが、二人は対面をはたして対立を切り抜け、玉鬘の儀式がとりおこなわれた。
◉冷泉帝「雪深き小塩(をしほ)の山にたつ雉(きじ)の 古きあとをも今日は尋ねよ」
◉光源氏「あかねさす光は空にくもらぬを などてみゆき(深雪・行幸)に目をきらしけむ」
◉内大臣「うらめしや沖つ玉藻をかづくまで 磯がくれける海士(あま)の心よ」
30.「藤袴」ふぢばかま
(源氏37歳春~秋。柏木21〜22歳)
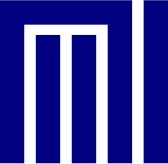
玉鬘の公開の裳着の儀によって、夕霧は自分と玉鬘が兄妹ではないことを知る。柏木(内大臣の長男)も玉鬘が実の妹だったことを知って戸惑う。玉鬘の出仕は10月と決まり、それまで求婚してきた男たちはそれぞれに苛立ち、思いおもいの歌を寄せてきた。
◉鬚黒「数ならばいとひもせまし長月に 命をかくるほどぞはかなき」
◉兵部卿宮「朝日さす光を見ても玉笹の 葉分けの霜を消たずもあらなむ」
◉左兵衛督「忘れなむと思ふもものの悲しきを いかさまにしていかさまにせむ」
31.「真木柱」まきばしら
(源氏37歳冬~38歳冬。真木柱12〜13歳。鬚黒32〜33歳)

意外なことに鬚黒(ひげぐろ)が玉鬘をわがものにした。耐えかねた北の方は実家に引き取られると「もののけ」に病み憑かれ、火取りの灰を鬚黒に浴びせる。鬚黒のそのときの歌「心さへ空にみだれし雪もよにひとり冴えつるかたしきの袖」。北の方の父の式部卿宮(もとの兵部卿宮)は娘を自邸に引き戻そうとする。髭黒の娘の真木柱は父親と別れがたく、その心情を歌に詠み柱の割れ目に差しこんでおいた。ホラー少女マンガとして十分な傑作に変相できそうな一巻。以上、「玉鬘」からここまでが「玉鬘十帖」。
◉冷泉帝「などてかくはひあひ(灰合)がたき紫を 心に深く思ひそめ(初・染)けむ」
◉玉鬘「いかならむ色とも知らぬ紫(三位の紫色)を 心してこそ人は染めけれ」
◉近江の君「おきつ舟よるべ波路にただよはば 棹さし寄らむ泊り教へよ」
◉夕霧「よるべなみ(波・並)風の騒がす舟人も 思はぬかたに磯づたひせず」
ここまでが玉鬘をめぐる十帖です。ちょっとまとめてふりかえると、玉鬘はそもそも夕顔の娘ですね。夕顔はかつては頭中将の隠し妻だったのですが、中将の北の方の脅しが気になって身をひいて、娘の玉鬘と所在をくらましていた。そのとき五条の夕顔花咲く宿で源氏に見いだされた。けれども「もののけ」で命を落としたというところまでが「夕顔」の巻の話です。
その後、玉鬘は行方がわからない母の死を知ることなく、4歳から筑紫の国に下っているんですね。やっと20歳をすぎて乳母に連れられて都に戻ります。その、鄙(ひな)に育ったとは思えないほどとんでもなく美しい姿が源氏のお付きの右近に見つかり、源氏に引き取られてあの壮麗な六条院に住むようになりますと、周囲の男君たちがものにしたくて色めきたつんですね。どんなふうに玉鬘をめぐった男たちが色めきたったかというのが「玉鬘十帖」なんです。
ただ、紫式部はここに少し仕掛けをしておいた。源氏が玉鬘の素性をあかさず自分の娘としたということ、今は内大臣になっている頭中将が父親であることを源氏のほかは誰も知らなかったこと、それが裳着の儀式のときにあきらかになっていったこと、こういう仕掛けをしておいたのです。ぼくはこういう仕掛けは紫式部の「当人主義」だと思います。当人だけが知っていることを暗示して、作家の記述がやたらにそこに踏みこまないようにしています。
32.「梅枝」むめがえ
(源氏39歳春。紫の上31歳、夕霧18歳)
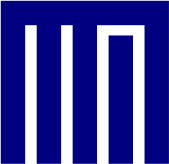
明石の姫君の入内が迫ってきた。源氏はその準備に余念がなく、「薫物(たきもの)合せ」などで遊ぶ。名筆の草子類なども数多く収集される。夕霧と雲居雁(くもいのかり)とが少し火花を散らす。
◉前斎院「花の香は散りにし枝にとまらねど うつらむ袖に浅くしまめや」
◉光源氏「花の枝(え)にいとど心をしむるかな 人のとがめむ香をばつつめど」
◉夕霧「つれなさは憂き世の常になりゆくを 忘れぬ人や人にことなる」
◉雲居雁「限りとて忘れがたきを忘るるも こや世になびく心なるらむ」
この薫物合せはかなりのものです。六条院のみんなに伝来の名香を配って調合を頼んでいるんです。源氏も紫の上とあえて居場所を離して腕をふるっている。蛍兵部卿宮が招かれて判定の段となるんですが、それぞれが好みを尽くしていて香の素材を判じかねるほどだと書いてあります。宴では内大臣の子の弁の少将が催馬楽(さいばら)を舞って興を添えます。そのタイトルが「梅が枝」なんですね。
まだあります。2月半ばがすぎると、今度は名筆の草子を集めて、いろいろその書きっぷりを競い論じたりしています。まさに王朝絵巻のおいしいところです。
33.「藤裏葉」ふぢのうらば
(源氏39歳。源氏、准太上天皇になる。明石の君30
歳)
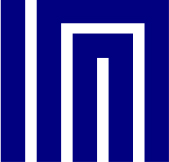
内大臣は夕霧と雲居雁との結婚を許可した。4月には明石の姫君が入内した。紫の上は心のうちを察して明石の君を姫君の後見役に推す。秋、源氏は異例の准太上天皇(じゅんだいじょうてんのう)の位についた。かくて源氏は摂関家にない権威と帝にはない権力を合わせもった絶対者として君臨することになる。
◉光源氏「色まさる籬(まがき)の菊もをりをりに 袖うちかけし秋を恋ふらし」
◉太政大臣「紫の雲にまがへる菊の花 濁りなき世の星かとぞ見る」
◉夕霧「なれこそは岩もる(守・漏)あるじ見し人の ゆくへは知るや宿の真清水(ましみず)」
◉雲居雁「なき人のかげだに見えずつれなくて 心をやれるいさらゐの水」
ここまでが第1部ですね。源氏はついに准太上天皇の位に昇りつめるのですが、それは天皇でもなく、またもはや誰の臣下でもない位です。准太上天皇というのは、譲位後の前天皇に準じる位なんです。けれども、その先はない。ふりかえれば、源氏は近衛中将→参議→右大将→大納言→内大臣→太政大臣というふうに公卿として次々に官位を昇ってきたのですが、ここで行きどまりなんですね。ここに「桐壺」で暗示されていた桐壺帝の「逸れ」が最高位にまで達したことが告げられているんです。
【第2部】
34.「若菜上」わかなのじょう
(源氏39歳~41歳。紫の上32歳、女三の宮14歳。
夕霧19歳)
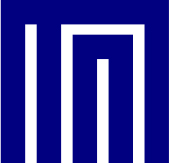
病いがちの朱雀院はすぐにでも出家したいのだが、女三の宮の将来が心配なので、源氏に降嫁させようとする。源氏は彼女が藤壺の姪でもあるので承諾するが、このことで紫の上は心を痛める。源氏は紫の上と女三の宮との板挟みを感じて朧月夜と忍び逢う。明くる3月、明石の女御が東宮の皇子を出産、明石の入道もこの慶事をよろこぶ。
◉秋好中宮「さしながら(すっかり・挿しながら)昔を今に伝ふれば 玉の小櫛(をぐし)ぞ神さびにける」
◉朱雀院「さしつぎに見るものにもが万世(よろづよ)を 黄楊(つげ・告)の小櫛の神さぶるまで」
◉紫の上「目に近くうつればかはる世の中を 行く末遠く頼みけるかな」
◉光源氏「命こそ絶ゆとも絶えめ定めなき 世の常ならぬなかの契りを」
◉女三の宮「はかなくてうはの空にぞ消えぬべき 風にただよふ春のあは雪」
◉紫の上「背(そむ)く世のうしろめたくはさりがたき ほだしをしひてかけな離れそ」
第1部では源氏につながる女君たちが、源氏とそれぞれに、いわば放射状にトップダウン型で広がっていたのですが、第2部では女君たちの間のつながりが浮上してきます。横にネットワーク連鎖していくんですね。それは当初こそ六条院に同居する男女の内部栄華をあらわすわけですが、やがては源氏の主語性が少しずつ薄れていくということでもあるわけです。
秋好中宮の「さしながら昔を今に伝ふれば玉の小櫛ぞ神さびにける」はいいですねえ。宣長につながります。
35.「若菜下」わかなのげ
(源氏41歳~47歳。冷泉帝退位28歳。今上帝即位20
歳)

冷泉帝が退位して、今上帝の御代になった。柏木の女三の宮に対する恋情がますます募っているなか、4年の歳月が流れた。源氏は紫の上・女三の宮・明石の君らをともない盛大な住吉詣をする。源氏47歳の早春、六条院で女楽(おんながく)を催す。紫の上は和琴(わごん)、女三の宮は琴(きん)、明石の君は琵琶、明石の女御は箏(そう)。その後、紫の上が病いに臥せる。「もののけ」に憑かれたらしい。病状は悪化するばかりなので加持調伏したところ、そこにあらわれたのは六条御息所の憑坐(よりまし)だった。一方で、柏木がついに女三の宮と思いをとげる。源氏は柏木の恋文を発見して、真相を知る。
◉柏木「恋ひわぶる人(女三の宮のこと)のかたみ(片身・形見)と手ならせば なれよ何とて鳴く音(ね)なるらむ」
◉光源氏「たれかまた心を知りて住吉の 神代を経たる松にこと問ふ」
◉紫の上「住の江の松に夜ぶかく置く霜は 神のかけたる木綿鬘(ゆふかづら)かも」
◉女三の宮「明けぐれの空に憂き身は消えななむ 夢なりけりと見てもやむべく」
◉柏木「くやしくぞつみ(摘・罪)をかしける葵草 神のゆるせるかざしならぬに」
この巻は大きな流れの推移をまとめていますね。でも、その推移は源氏・女君・柏木がそれぞれに「宿世」を深く実感していくステージだったのです。前にも言っておいたように『源氏』のワールドモデルは「宿世」です。紫の上に御息所の霊が取り憑いたことはその象徴ですね。「宿世」イコール「もののけ」なんですよ。
一方、源氏は自分の人生が栄耀栄華においても抜きん出ていたけれど、苦悩憂愁においても人に抜きん出ていたことを思い知ります。なんとも身に滲みることですね。そういう源氏はもう47歳になっていました。
ところで、上にあげた柏木の「恋ひわぶる人」の歌には、「何とて鳴く音」とありますが、これは猫のことです。東宮がたいへんな猫好きで、たくさん猫を飼っているんです。そこで柏木はこの東宮のために、女三の宮の猫をなんとか手に入れようとするというエピソードです。猫が「ねうねう」と「いとらうたげ」に鳴くのが、とてもかわいい。
36.「柏木」かしはぎ
(源氏48歳春秋。薫誕生。朱雀院51歳。柏木没32〜33歳 、
女三の宮22〜23歳)
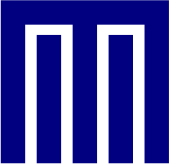
女三の宮が男児を出産。柏木との不義の子で、のちの薫である。源氏は暗然とし、女三の宮は出家してしまう。柏木も親友の夕霧に妻の落葉の宮の後事を頼んで、かき消えるように死ぬ。源氏は薫の五十日(いか)の祝いでわが子ならざるわが子を抱き、「あやにくな定め」を思う。夕霧は落葉の宮を見舞ううちに恋心をもつ。
◉柏木「今はとて燃えむ煙もむすぼほれ 絶えぬ思ひ(思う火)のなほや残らむ」
◉落葉の宮「柏木に葉守(はもり)の神はまさずとも 人ならすべき宿の梢か」
このへんから何もかもが少しずつ複雑になっていきます。もはや主人公ではない源氏は48歳。あれほど女三の宮を愛していた柏木が亡くなり、女三の宮は薫を出産します。のちの新しい主人公です。しかしここには「逸れ」とともに「歪み」が生じていました。女三の宮の出家と柏木の死は、それぞれその「歪み」を覚悟していたことだったんだと思います。
37.「横笛」よこぶえ
(源氏49歳春秋。薫2歳、夕霧28歳)

柏木の一周忌。秋、夕霧は落葉の宮母娘と語らい名曲「想夫恋」(そうぶれん)を琵琶で弾く。その折、夕霧は柏木遺愛の横笛を譲られるのだが、後日、夢に柏木があらわれ「横笛を伝えたい人は他にある」と言う。横笛は源氏に預けられた。
◉夕霧「こと(琴・言)に出でて言はぬも言ふにまさるとは 人に恥ぢたるけしきをぞ見る」
◉落葉の宮「深き夜のあはればかりは聞きわけど こと(琴・言)よりほかにえやは言ひける」
38.「鈴虫」すずむし
(源氏50歳夏秋。紫の上42歳、秋好中宮41歳。
夕霧29歳)

尼君となった女三の宮の持仏開眼供養。源氏は女三の宮の前庭を秋の風情に造作し、鈴虫・松虫などを放つ。源氏は冷泉院を訪れ詩歌管絃に興じるも、秋好中宮から亡き母(御息所)がいまなお成仏できずにいると聞かされ、愛憐執着のおそろしさを思う。
◉光源氏「心もて草のやどりをいとへども なほ鈴虫の声ぞふりせぬ」
◉冷泉院「雲の上をかれ離れたるすみかにも もの忘れせぬ秋の夜の月」
◉光源氏「はちす葉をおなじ台(うてな)と契りおきて 露のわかるるけふぞ悲しき」
人のあさましさやこの世の宿命が徘徊していくなか、物語はだんだん「救済とは何か」というほうに舵を切っていきます。それを象徴しているのが、登場人物たちの出家がふえていっているということでしょうね。
「賢木」で藤壺が出家し、仏道にいる明石の入道が登場し、「澪標」で六条御息所が出家するあたりまではともかく、第2部になると、まず朱雀院が出家する。実は空蝉も出家して尼になっていました。紫の上も出家したいと訴えますが、これは源氏が承知しない。でも朧月夜の君は出家して源氏を悲しませ、そこへ女三の宮が薫を残して出家するわけです。このあと落葉の宮も剃髪したいと言いだしますからね。
そして最後に源氏その人が巻40「御法」(みのり)で出家を決意するわけです。「無常の風」が吹きまくるばかりです。
39.「夕霧」ゆふぎり
(源氏50歳秋冬。夕霧29歳。雲居雁31歳)

落葉の宮にのめりこむ夕霧。その行動に懸念する落葉の宮の母(一条御息所)は消息(手紙)を送るのだが、嫉妬する北の方の雲居雁に奪われる。夕霧からの返事がこないことに悲嘆した一条御息所は死去。それでも夕霧は強引に婚儀をはこび、雲居雁はたまりかねて実家に戻る。
◉落葉の宮「われのみや憂き世を知れるためしにて 濡れそふ袖の名をくたすべき」
◉夕霧「おほかたはわれ濡衣を着せずとも 朽ちにし袖の名やは隠るる」
◉夕霧「たましひをつれなき袖にとどめおきて わが心からまどはるるかな」
◉夕霧「せくからに浅さぞ見えむ山川の 流れての名をつつみ(包・堤)はてずは」
◉雲居雁「あはれをもいかに知りてかなぐさめむ あるや恋しき亡きや悲しき」
40.「御法」みのり
(源氏51歳春秋。紫の上没43歳。匂宮5歳)

紫の上発願の法華経千部の供養が二条院でおこなわれる。死期の近いことを感じる紫の上は明石の君や花散里らと歌を詠みかわし、それとなく別れを告げ、まもなく死去。荼毘にふされる前の紫の上が美しい。茫然自失の源氏は、この悲しみに耐えた後に出家しようとひそかに決める。
◉紫の上「惜しからぬこの身(実・菓)ながらもかぎりとて 薪(たきぎ)尽きなむことの悲しさ」
◉明石の君「薪こる思ひはけふをはじめにて この世に願ふ法(のり)ぞはるけき」
◉紫の上「絶えぬべき御法(みのり・身のり)ながらぞ頼まるる 世々にと結ぶ中の契りを」
◉光源氏「ややもせば消えをあらそふ露の世に 後(おく)れ先だつほど経ずもがな」
◉光源氏「のぼりにし雲居ながらもかへり見よ われあき(倦・秋)はてぬ常ならぬ世に」
41.「幻」まぼろし
(源氏52歳で死去。薫5歳、匂宮6歳)
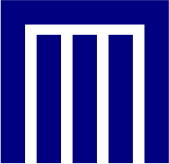
新年を迎えても源氏の悲傷はいっこうに癒されない。深まる春に紫の上への追慕が募るばかり。自身を回顧してみれば栄え映えしくもあったが、憂いにも満ちていた。季節が夏・秋・冬と移ろい、風物は少しずつ変わっていくものの、源氏の心は変われず、歳末に紫の上と交わした消息などを焼いた。
◉光源氏「なくなくも帰りにしかな仮(雁)の世は いづこもつひの常世(とこよ・床の世)ならぬに」
◉光源氏「おほかたは思ひ捨ててし世なれども 葵はなほやつみ(罪・摘)をかすべき」
◉光源氏「大空をかよふ幻(まぼろし)夢にだに 見えこぬ魂(たま)の行方たづねよ」
◉光源氏「もの思ふと過ぐる月日も知らぬまに 年もわが世もけふや尽きぬる」
いよいよ源氏の最期です。「幻」にはその死の場面は描かれないのですが、のちの巻で源氏が嵯峨の地に出家して、仏道に入ってそのまま崩じたということが回想されるので、この第2部の終わりが光源氏の生涯の最期であったことがわかります。けっこうあっけない源氏のクロージングです。なぜこんな終わり方にしたのか。ぼくは紫式部が光源氏に倦きていたんじゃないかと思いますね。だって終盤、ほとんどターミナルケアしてませんからね。
なお「幻」と次の「匂宮」とのあいだに、かつて「雲隠」(くもがくれ)という巻があったのではないかという議論があり、後世の写本や目録にそのタイトルが見えているのですが、いまではのちの付会だろうとして、否定されています。
【第3部】
「幻」の巻から9年がたって、匂宮(にほうのみや)と薫を新たな主人公にして第3部がスタートします。二人はまことに対照的なので、世間は「匂ふ兵部卿宮、薫る中将」ともてはやします。この二人はこれまでの物語とはまったく異なる強烈な個性を発揮するんですね。『源氏』はがらりと舞台を変えるのです。
42.「匂宮」におふのみや
(薫14歳~20歳。匂宮15歳)

源氏の死後、その跡を継ぐべき人物がいなかった王朝社会だが、なかで匂宮と薫が世間の声望を受けていた。薫からは生まれながらに仏のような体香が放たれていた。冷泉院の寵愛を受け14歳で中将に19歳で三位宰相に昇ったのに、自身の出生への疑念から出家に憧れている。そうした薫に匂宮は何かにつけて対抗心を抱き、麝香・伽羅などの名香を集めて薫物(たきもの)に熱中したりする。世間では誰もが二人を婿に望んだ。けれども薫には結婚の意思がない。
◉薫「おぼつかな誰に問はましいかにして はじめも果ても知らぬわが身ぞ」
43.「紅梅」こうばい
(薫24歳。玉鬘48歳。紅梅大納言54歳)

亡き太政大臣家の後日譚。柏木の死後、弟の按察(あぜち)大納言がその家系を保ち、真木柱(まきばしら)と再婚して大夫の君をもうけた。真木柱には蛍宮とのあいだにもうけた姫君(宮の御方)もいた。大納言は繊細な中の君を匂宮と添わせたいと願うのだが、匂宮は宮の御方に執心する。
◉按察大納言「心ありて風の匂はす園の梅に まづうぐひすの訪はず(問はず)やあるべき」
◉匂宮「花の香にさそはれぬべき身なりせば 風のたよりを過ぐさましやは」
◉匂宮「花の香をにほはす宿にとめゆかば 色にめづとや人の咎めむ」
44.「竹河」たけかは
(玉鬘56歳、薫14歳~23歳)

鬚黒亡きあとの後日譚。玉鬘(尚侍の君)は3男2女を育ててきたが、いまは姫君たちが帝からも冷泉院からも蔵人少将からも所望されている。しかし玉鬘は源氏の形見というべき薫にこそ嫁がせたいと思ううち、正月下旬に薫の弾く和琴が柏木に似ていることに気が付いた。何かを察知したのである。そのほか、姫君たちの行く末は決まるようで決まらない。巻名は催馬楽「竹河」にもとづく。
◉薫「竹河のはし(橋・端)うちいでしひと節(ふし)に 深き心の底は知りきや」
◉尚侍の君「竹河に夜をふかさじといそぎしも いかなる節を思ひおかまし」
◉大君「あはれてふ常ならぬ世のひと言も いかなる人にかくるものぞは」
◉薫「流れてのたのめむなしき竹河に よは憂きものと思ひ知りにき」
ここまでは「匂宮三帖」とも言われるところなんですが、どうも文章・文体・運びそのほかちょっと出来が悪いので、古来、ここは偽書ではないかという説にもなっています。紫式部がこんな書き方をしないだろうというんですね。あるいは後世の補筆が入っているのかもしれません。でも、匂宮と薫の対比はいかにも紫式部がやりそうなことで、ぼくとしてはやはり五十四帖全部がひとつながりだと見ています。
(宇治十帖)
45.「橋姫」はしひめ
(薫20~22歳。八の宮50代後半。大君24歳、
中の君22歳)

話は変わって、そのころ世間から忘れられていた古宮がいた。若い日々に政争に巻きこまれて失意の日々をおくっていた八の宮である。宇治の山里で大君(おおいきみ)と中の君を男手で養うかたわら、仏道に励んでいた。薫は宇治の阿闍梨から八の宮の俗聖(ぞくひじり)ぶりの噂を聞いて親交を結ぶ。それから3年目の秋、八の宮の留守を訪ねた薫は月下に合掌する姫君たちの美しさを垣間見て、大君に惹かれる。思慮深い大君は薫をたしなめる。
◉八の宮「うち捨ててつがひ(番)さりにし水鳥(みずどり)の かり(仮・雁)のこの世にたちおくれけむ」
◉大君「いかでかく巣立ちけるとぞ思ふにも 憂き(浮き)水鳥の契りをぞ知る」
◉八の宮「見し人も宿も煙になりにしを なにとてわが身消え残りけむ」
◉八の宮「あと絶えて心すむ(澄・住)とはなけれども 世をうぢ山に宿をこそかれ」
◉薫「橋姫のこころをくみて高瀬さす 棹のしづくに袖ぞ濡れぬる」
ここからがぼくが若い頃好きだった「宇治十帖」です。八の宮の存在が告げられるところから物語が始まります。不運をかこってきた八の宮なんですが、そのぶん道心が深まっているんですね。その八の宮を薫が知って「法(のり)の友」となるのだけれど、薫の前には思慮深く魅力的な大君(おおいきみ)があらわれます。八の宮の「あと絶えて世をうぢ山」の歌はいかにも八の宮らしい歌ですね。こういうところ、紫式部はさすがに手を抜きません。
巻名の「橋姫」は薫が大君に贈った「橋姫のこころをくみて高瀬さす棹のしづくに袖ぞ濡れぬる」から採ったのですが、本歌は古今和歌集の「さむしろに衣かたしき今宵もや我を待つらむ宇治の橋姫」です。橋にいながら夫が通ってくるのを待つ橋姫のイメージです。
もっとも橋姫伝説にはいろいろあって、橋のたもとで通りかかる旅人を襲ったり、開かずの箱を渡したり、目を抉ったり、けっこう恐ろしい橋姫もいる。いずれにしても「境界神」なんですね。「宇治十帖」はその橋姫をもって始まるんです。
46.「椎本」しひがもと
(薫23~24歳。八の宮没60歳前後)
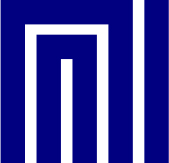
◉八の宮「山風に霞吹きとく声はあれど へだてて見ゆるをちの白波」
◉匂宮「をちこちの汀(みぎは)に波はへだつとも なほ吹きかよへ宇治の川風」
◉中の君「かざし折る花のたよりに山がつの 垣根を過ぎぬ春の旅人」
◉八の宮「われなくて草の庵(いほり)は荒れぬとも このひとことはかれじとぞ思ふ」
薫から八の宮の姫君のことを聞いていた匂宮と薫とのあいだに、消息の代理行為が介在し、ここで八の宮を通して、薫と匂宮と姫君たちがクロスする。八の宮が遺戒をのこして死去すると、姫たちは薫を頼る。いったい八の宮が何を遺戒したのか、物語はあきらかにしない。
47.「総角」あげまき
(薫24歳秋冬、大君没26歳)

薫は大君に夜通し意中を伝えるが、何事もない。大君は父の意志を守って独身を通し、むしろ薫が中の君と結ばれることを思い、薫は薫で中の君と匂宮が結ばれれば、大君が自分を選ぶと考えていた。八の宮の遺戒のせいなのか、各自の関係はあやふやになっていき、そうしたなか大君は比類のない美しさをその相貌に漂わせて死んでいく。
◉大君「ぬきもあへずもろき涙の玉の緒に 長き契りをいかが結ばむ」
◉薫「おなじ枝(え)をわきて染めける山姫に いづれか深き色と問はばや」
◉大君「山姫の染むる心はわかねども うつろふかたや深きなるらむ」
◉薫「しるべせしわれやかへりてまどふべき 心もゆかぬ明けぐれの道」
◉大君「かたがたにくらす心を思ひやれ 人やりならぬ道にまどはば」
◉匂宮「中絶えむものならなくに橋姫の かたしく袖や夜半(よは)に濡らさむ」
◉中の君「絶えせじのわがたのみにや宇治橋の はるけきなかを待ちわたるべき」
宇治の大君はいいですねえ。八の宮の姫君です。妹が中の君。八の宮は処世力がなく、二人の娘の養育のために再婚もしていない。そこへ薫が訪ねてくるようになるのですが、3年目のある夜、八の宮の留守に大君が薫を応接するんですね。ここから薫の思慕がふくらんでいきます。
大君は父が「この世は仮の世、来世の浄土に生まれるために功徳を積みなさい」という教えに生きている女性なので、薫が求道者の気持ちをもっているうちは迎え入れているんですが、八の宮が亡くなったのちついに薫が愛を告白すると、大君は頑なに交情を拒みます。
この設定は紫式部の熟慮のうえのものでしょうね。薫は源氏の子として世に通っているけれど、実際には柏木と女三の宮とのあいだの罪の子です。凋落した日々だった八の宮家を栄えさせるには源氏一族の薫を受け入れればそれで栄達は保証されるのだけれど、それはできない。そこで妹の中の君を添わせようとします。けれどもこれでは今度は薫が承知できない。そこで薫は中の君が結婚してしまえば大君は自分の気持ちに靡くだろうと思い、匂宮を中の君の寝所に忍ばせるのですが、これがかえって大君を動揺させてしまうんですね。
なにしろ匂宮は有名な「色好み」ですから、こんな結婚は中の君をダメにすると大君は思う。そんな心労がたたって大君は重篤になり、最期は薫に看取られて死んでいきます。紫式部の『源氏』全巻の仕上がりが冴えていくところです。
48.「早蕨」さわらび
(薫25歳)
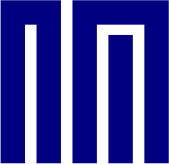
大君が亡くなり、薫が悲嘆にくれていた宇治の山里に早蕨の陽光がさしこんで、山寺の阿闍梨(あじゃり)からの山菜も届く。匂宮が中の君を迎えることになった。薫は中の君を譲ったことを香ばしく後悔する。
◉阿闍梨「君にとてあまたの春を摘み(積み)しかば 常を忘れぬ初蕨(はつわらび)なり」
◉中の君「この春はたれにか見せむ亡き人の かたみ(形見・筒)に摘める峰の早蕨(さわらび)」
◉匂宮「祈る人の心にかよふ花なれや 色には出ずしたににほへる」
◉薫「見る人にかこと寄せける花の枝(え)を 心してこそ折るべかりけれ」
◉大輔「ありふればうれしき瀬にも逢ひけるを 身を宇治川に投げてましかば」
49.「宿木」やどりぎ
(薫24~26歳。浮舟20歳前後。女二の宮14〜16歳)

中の君は匂宮の子を宿すが、薫は納得していない。中の君が薫の懸想をそらそうと大君に似る異母妹に浮舟という乙女がいることを告げる。中の君が男児を産み、薫は今上帝が勧める女二の宮と結婚する。結婚よりも宇治の御堂の造営に熱心な薫だったが、あるとき偶然に浮舟を垣間見て、亡き大君に貌(かんばせ)が酷似していることに感動する。
◉匂宮「また人に馴れける袖の移り香を わが身にしめてうらみつるかな」
◉中の君「み(見・身)なれぬる中の衣とたのみしを かばかりにてやかけ離れなむ」
◉薫「やどりきと思ひいでずは木のもとの 旅寝もいかにさびしからまし」
◉弁尼「荒れ果つる朽木のもとをやどりきと 思ひおきけるほどの悲しさ」
ついに浮舟がその姿をあらわすところです。『源氏物語』最後のヒロインですね。浮舟は八の宮とその女房の中将の君とのあいだに生まれているんですが、大君や中の君とはお母さんが違う。大君らは北の方から生まれ、浮舟は八の宮に仕えていた中将の君の娘です。しかも途中から宮家を出て、常陸介の後妻になっている。だから浮舟も関東で育っているんです。それでどうなったか、「東屋」がそこを綴ります。
50.「東屋」あづまや
(薫26歳。中の君26歳)

浮舟の母である中将の君は薫の気持ちを知るのだが、身分違いを感じて左近少将を婿に選ぼうとしている。ところがこれはうまく話が進まず、中の君に浮舟を預けることにした。そこへ匂宮などが接近し、浮舟の動静を知った薫は彼女を宇治に移り住まわせ、彼女の成長を願う。
◉薫「見し人の形代(かたしろ)ならば身に添へて 恋しき瀬々のなでもの(撫物)にせむ」
◉中の君「みそぎ河瀬々にいださむなでものを 身に添ふ影とたれかたのまむ」
51.「浮舟」うきふね
(薫27歳。匂宮28歳。浮舟22歳前後。)

浮舟を忘れられない匂宮が従者をともない、薫と偽って宇治に乗りこんだ。浮舟は人違いと気づくのだが、匂宮の情熱に絆(ほだ)された。匂宮はさらに浮舟に執着して宇治の対岸の隠れ家で二夜を過ごす。匂宮との関係を知った薫は浮舟の不誠実を咎める手紙を送る。これで気が動転した浮舟は宇治川に入水してしまいたいと思い、書き置きをのこす。
◉匂宮「年経(ふ)ともかはらぬものか橘の 小島の崎に契る心は」
◉浮舟「橘の小島の色はかはらじを この浮舟ぞゆくへ知られぬ」
◉匂宮「峰の雪みぎはの氷踏みわけて 君にぞまどふ道はまどはず」
◉浮舟「降りみだれみぎはに氷る雪よりも 中空(なかぞら)にてぞわれは消ぬべき」
◉薫「水まさるをちの里人いかならむ 晴れぬながめ(眺め・長雨)にかきくらすころ」
◉浮舟「かきくらし晴れせぬ峰のあま雲に 浮きて世をふる身をもなさばや」
◉浮舟「のちにまたあひ見むことを思はなむ この世の夢に心まどはで」
◉浮舟「鐘の音の絶ゆるひびきに音(ね)をそへて わが世尽きぬと君に伝へよ」
五十四帖全体のなかで、「若菜」上下と並んで最も構成と文章がすばらしく組み上がっているのが「浮舟」です。ここだけ取り出して映画にしたり宝塚の舞台にしたくなるのが、よくわかります。誰もが参考にしたくなる物語モデルですね。
人物の心の動きとして注目しておくべきは、薫の浮舟に対する気持ちなんですが、薫にとっての浮舟はあくまで大君の面影の形代(かたしろ)だったということです。これは浮舟からするとせつないことで、心厚い薫を敬いながらも匂宮の情熱に体を合わせてしまう。けれどもそんなことをしていれば、当然、この二人の貴公子の板挟みになるわけで、そこで入水を決意するんですね。
ただし、この決意は仏道の教えからするととんでもないことで、仏教では自死は仏罰に当たります。とすると、紫式部はここで別の思想を持ち出したということになります。それは古来の「処女塚」(おとめづか)の考え方でした。二人以上の男に求愛された女が自身の死によって男たちの争いを回避させるという話です。万葉にもよく歌われている。『源氏』はこのラストストリームにおいて、こうした「古代の母型」を持ち出すんです。
52.「蜻蛉」かげろふ
(薫27歳)

浮舟の失踪の噂が駆けめぐる。母の中将の君は愕然とし、亡骸(なきがら)のないまま葬儀を営む。石山参籠中の薫は浮舟を放置したことを反省し、匂宮は自分の行為に臥してしまう。一方、明石の中宮の法華八講で女一の宮を垣間見た薫は、その美貌に目が眩んで妻(女二の宮)に一の宮と同じ恰好をさせる。しかしそんな戯れをしているものの、自分が八の宮の姫君たちを次々に失わせているような気がして、おのが宿世のつたなさを嘆く。
◉薫「忍び音や君もなく(鳴く・泣く・亡く)らむかひもなき 死出(しで)の田長(たおさ)に心かよはば」
◉匂宮「橘のかをるあたりはほととぎす 心してこそなくべなりけれ」
◉薫「ありと見て手にはとられず見ればまた ゆくへもしらず消えし蜻蛉(かげろふ)」
53.「手習」てならひ
(薫27歳。浮舟22歳前後。横川の僧都60歳あまり。小野母尼80歳あまり)
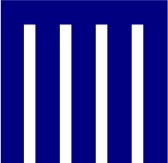
浮舟は死んでいなかった。水辺で正気を失い、「もののけ」に憑かれていたとおぼしい。が、横川の僧都(よかわのそうず)の母尼・妹尼らの一行に助けられていたのである。さっそく小野の山里の屋敷で看病世話されるのだが、容易に回復しない。やっと意識が戻っても浮舟は素性や過去を語らず、いちずに出家を願うばかり。そこへ立ち寄った横川の僧都に浮舟は懇願して出家する。やっと浮舟に念仏と手習いの日々がおとずれた。薫は出家した浮舟の噂を聞き、訪ねたいと思う。
◉浮舟「身を投げし涙の川のはやき瀬を しがらみかけてたれかとどめし」
◉浮舟「はかなくて世にふる川(経る・古川)の憂き瀬には たづねもゆかじ二本(ふたもと)の杉」
◉浮舟「なきものに身をも人をも思ひつつ 捨ててし世をぞさらに捨てつる」
◉浮舟「限りぞと思ひなりにし世の中を かへすがへすもそむきぬるかな」
54.「夢浮橋」ゆめのうきはし
(薫28歳。匂宮29歳。浮舟23歳前後)

横川の僧都のもとを訪れた薫は、僧都から浮舟の入水と出家のあらましを聞き、浮舟に取り次いでほしいと頼む。僧都は浮舟の弟の小君(こぎみ)に手紙を託すことにしたが、彼女を出家させたことを後悔し、このままでは女人を破戒者にさせかねないという危惧をもつ。僧都の文使いとして小君が浮舟のもとに派遣され、浮舟はここに薫の愛欲の罪が消えるようにしてほしいと書いてあることを読む。けれども浮舟は薫との対面を激しく拒んで「これは人違いの手紙だ」と言い張る。小君はやむなくこれを薫に伝えるが、薫は何かが釈然としない。長きにわたった物語はそのことを告げて、悄然と幕を閉じる。
◉薫「法の師とたづぬる道をしるべにて おもはぬ山に踏みまどふかな」

このラストはけっこう難解です。浮舟が自分のしたことを「けしからぬ」と思ってひたすら頑なになっていますし、薫も浮舟に何を求めているのかわからない。ただ紫式部だけがこの男女の未来を知っている、そんな終わり方です。
浮舟は助けられてからぐんと深くなっているんですね。横川の僧都でさえその心境を左右できない。まして薫は浮舟の胸中に一歩も踏み込めない。すごい終わり方です。では、なぜ『源氏』はこんなふうに終わっているのか、そこを考えるには、もう一度、全容の隙間にひそむ王朝社会哲学のようなものを読み解く必要があります。
以上、駆け足で五十四帖をたどってみました。
詳しい筋立てやエピソードは現代語訳や解説本などで補っていただくとして、こういうアウトラインや物語構造を前提として、さあ、『源氏』から感じるべき問題や示唆は何かということ、あるいはこれを「日本という方法」から見るとどういうふうになるかということです。
それでは千夜源氏第3夜につないでいきたいと思います。宮崎慎也、小西静恵、久保田文也、橋本英人、中村碧らの編集工学研究所のスタッフの諸君が『源氏』のヴィジュアルのあれこれを配してくれたので、とくと参考にしてください。

⊕ 『源氏物語 新潮日本古典集成(1~8)』 ⊕
∃ 著者:紫式部
∃ 校注:石田穣二・清水好子
∃ 発行者:佐藤隆信
∃ 発行所:株式会社 新潮社
∃ 印刷所:大日本印刷株式会社
∃ 製本所:加藤製本株式会社
⊂ 2014年10月30日発行
⊗ 目次情報 ⊗
∈ 一巻
∈∈∈ 凡例
∈∈ 桐壺
∈∈ 帚木
∈∈ 空蝉
∈∈ 夕顔
∈∈ 若紫
∈∈ 末摘花
∈∈ 解説
∈∈ 付録
∈∈∈∈ 長恨歌
∈∈∈∈ 系図
∈∈∈∈ 図録
∈ 二巻
∈∈∈ 凡例
∈∈ 紅葉賀
∈∈ 花宴
∈∈ 葵
∈∈ 賢木
∈∈ 花散里
∈∈ 須磨
∈∈ 明石
∈∈∈ 付録
∈∈∈∈ 催馬楽
∈∈∈∈ 琵琶引
∈∈∈∈ 系図
∈∈∈∈ 図録
∈ 三巻
∈∈∈ 凡例
∈∈ 澪標
∈∈ 蓬生
∈∈ 関屋
∈∈ 絵合
∈∈ 松風
∈∈ 薄雲
∈∈ 朝顔
∈∈ 少女
∈∈ 玉鬘
∈∈∈ 付録
∈∈∈∈ 天徳四年内裏歌合
∈∈∈∈ 系図
∈∈∈∈ 図録
∈ 四巻
∈∈∈ 凡例
∈∈ 初音
∈∈ 胡蝶
∈∈ 螢
∈∈ 常夏
∈∈ 篝火
∈∈ 野分
∈∈ 行幸
∈∈ 藤袴
∈∈ 真木柱
∈∈ 梅枝
∈∈ 藤裏葉
∈∈∈ 付録
∈∈∈∈ 春秋優劣の論
∈∈∈∈ 薫集類抄
∈∈∈∈ 海漫々
∈∈∈∈ 系図
∈∈∈∈ 図録
∈∈∈∈ 官位相当表
∈ 五巻
∈∈∈ 凡例
∈∈ 若菜上
∈∈ 若菜下
∈∈ 柏木
∈∈ 横笛
∈∈ 鈴虫
∈∈∈ 付録
∈∈∈∈ 系図
∈∈∈∈ 図録
∈ 六巻
∈∈∈ 凡例
∈∈ 幻
∈∈ 雲隠
∈∈ 匂兵部卿
∈∈ 紅梅
∈∈ 竹河
∈∈ 橋姫
∈∈ 椎本
∈∈∈ 付録
∈∈∈∈ 系図
∈∈∈∈ 図録
∈ 七巻
∈∈∈ 凡例
∈∈ 総角
∈∈ 早蕨
∈∈ 宿木
∈∈ 東屋
∈∈∈ 付録
∈∈∈∈ 飛香舎藤花の宴
∈∈∈∈ 三日夜の儀
∈∈∈∈ 李夫人
∈∈∈∈ 系図
∈∈∈∈ 図録
∈ 八巻
∈∈∈ 凡例
∈∈ 浮舟
∈∈ 蜻蛉
∈∈ 手習
∈∈ 夢浮橋
∈∈∈ 付録
∈∈∈∈ 陵園妾
∈∈∈∈ 系図
∈∈∈∈ 図録
∈∈∈ 年立
⊗ 著者略歴 ⊗
紫式部
生没年不詳。平安時代中期の女性作家、歌人。『源氏物語』の作者と考えられている。中古三十六歌仙、女房三十六歌仙の一人。『小倉百人一首』にも「めぐりあひて 見しやそれとも わかぬまに 雲がくれにし 夜半の月かな」で入選。屈指の学者、詩人である藤原為時の娘。藤原宣孝に嫁ぎ、一女(大弐三位)を産んだ。夫の死後、召し出されて一条天皇の中宮・藤原彰子に仕えている間に、『源氏物語』を記した。
==