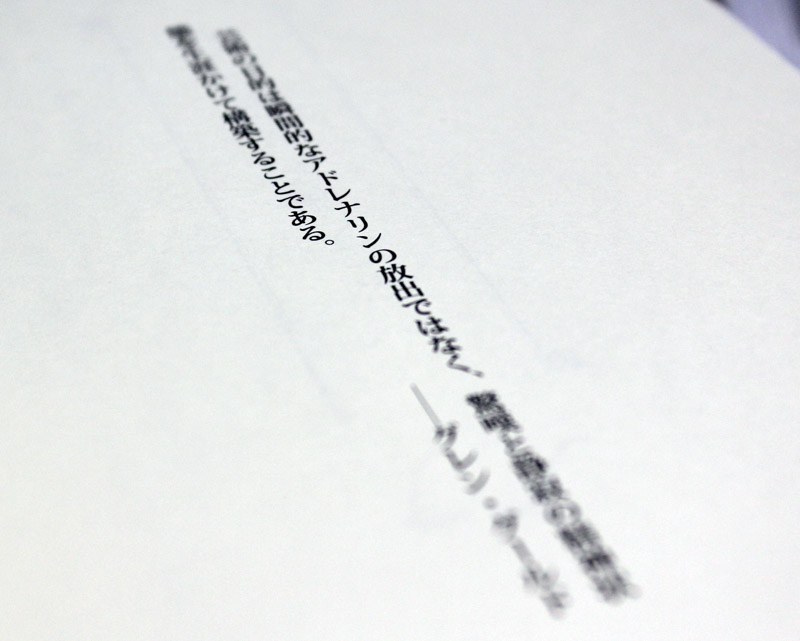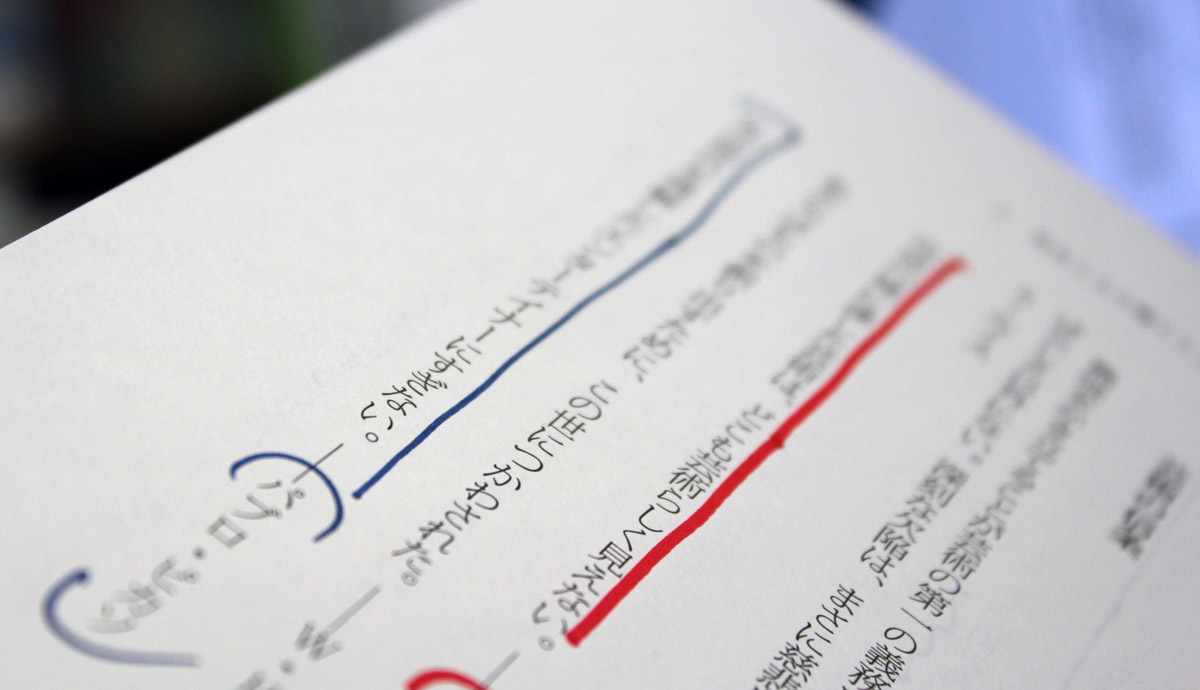本は世界の引用でできている。
本たちはその連鎖でつながりあっている。
読書の愉楽とは、その引用の連鎖を
次々に渡り歩いていくことで成立してきた。
だから読書とは、本というスタイルやモードの特色を
取っ変え引っ替えして好きに遊ぶことなのだ。
BOOK by BOOK、BOOK from BOOK。
書評家ディルダの案内にかこつけて、
そんな引き出し読書術を伝えたい。
本書は文字(フォント)と組(フォーマット)がよかった。精興社の活字が生きている。精興社の活字を実感することは、日本人が日本語の本の極上な気質に触れることなのだ。これ、知っておいたほうがいい。
日本文字の活字化は本木昌造以降さまざまな文字職人によってタイプフェイスが漢字・仮名・約物ともに工夫されてきたが、やっぱり岩田母型と精興社活字が美しい。精興社のものは求龍堂版『千夜千冊』に使ってもらった。

精興社は日本一美しい活字を目指し、今年で創業百年を迎える。
邦訳タイトルもいい。“BOOK BY BOOK”という原題もいいけれど、これをよくぞ『本から引き出された本』にした。
そうなのだ、本は一冊ずつがネステッド(入れ子状態)になっているインターテクストたちの束の集まりで、本によって引き出され、その引き出された本によって次の新たな本に入っていくことが、読書の醍醐味なのだ。
読書するとはこのインターテクストに分け入って、自身を不定形なアンドロイドふうの怪盗紳士にしたり、きゃりーぱみゅぱみゅのように自在な“重ね着”をするハイパーテクスト嬢に仕立てていくことなのである。
本書の著者はアメリカ東海岸のフリーインテレクチュアルズを代表するオヤジだ。本の読み方ではぼくの趣味とは異なるところもあるが、恥ずかしげもない正々堂々の選本は、まずまず信用できる。
ワシントンポスト紙の書評欄「ブックワールド」をこつこつと30年以上担当して、1993年にはアメリカのブック・ジャーナリストとしてこれ以上の誉れのない批評部門のピュリッツァー賞を受けたから、信用するのではない。このオヤジが13歳のときにデュマの『モンテ・クリスト伯』(1220夜)に夢中になって、来る日も来る日もあのダンディきわまりない復讐の鬼エドモン・ダンテスになりたかったというところが、けっこう信用できるのだ。
ぼくもそうだったけれど、こういう体験はただちに次のルパンやホームズに走れることを約束し、ついではエドガー・アラン・ポオ(972夜)の幾多の短篇で、言いようのない読書のよろこびを学ぶことになる。これ、確実な路線なのだ。
大人が自分の前に並んだ皿本をむしゃむしゃ食べられるようになるには、このように、10歳前後に何かの本に夢中になり、その次は、その次はと“続き”を求めてたてつづけに読んだ数冊を、その後の生涯の伴侶とできることが、大きな出発点になる。デュマ、ルパン、ホームズ、ポオというふうに。
とはいえ、不幸にしてそんな少年少女期のスリリングなときめき経験がなかったからといって、がっかりすることはない。似たようなことを「今でしょ」から始めればいい。これからいくらでも、ときめける。

デュマからポオまで本棚に並ぶといつでも本の世界に誘われる。
ミシェル・フーコー(545夜)は人生にとって一番の根幹になるのは、「当初の自分とは違う人間になろうとすることである」と言った。そのうえで、そのためのエンジンに最もぴったりしているのは「次々に本に没入することだ」と断定した。こうしてフーコーは知の考古学者になった。
手近なオリジナリティに堕するのが大嫌いなジャン・コクトー(912夜)は、「人生にとって最も重要なことは周囲から批判されるところをこつこつ磨くことだ」と書いている。実際にもコクトーは、ココ・シャネル(440夜)をはじめ、いつも親身になってくれる友人たちの忠告や批判を受け入れるために闘った。そして「もし、諸君がそういう友人や周囲に恵まれていないのなら、すぐさま本と首っぴきになることだ」と提案した。

「機知の才を磨くには、相手かまわず恋をするにかぎる」
―ジョージ・ムーア
(本書p.90より)
コクトーが言うように、われわれは自分の現状をどのように訂正するか、変えられるかということによって想像力と創造力を鍛えていく。
訂正するということは、修繕(ブリコラージュ)するということで、つまりは自己編集するということなのだが、ただし、それには相手がいる。周辺がいる。相手がいないとき、その相手になってくれるのが本なのだ。
その本に没入したり、首っぴきになったりするには、どうするといいか。ぜひとも肝に銘じておいてほしいのは、「読書は内容で読むものだ」などと決めつけないことだ。むしろ本との多様でスタイリッシュな付き合い方を豊富にしていくのがいい。以前からぼくも言ってきたように、読書は交際なのだ。
交際には相手のチャームポイントを存分に感じる必要がある。これは恋でも友人関係でもビジネスでもコミュニティでも、本でも同じだ。
たとえば、タイトルの魅力、中身の使い勝手、著者のプロフィール、装幀のよしあし、文字組や見出しの調子、紙のめくりやすさ、その本に出会った時期、出版社の勇気、一冊の屹立性、その日の当方のコンディション、編集のうまさ、図版に対する驚き、評判、どこで読むかということ、文体、知の空腹感、書架に並ぶさま、超難解度、類書の多さ‥‥。
こういったチャームポイントをいろいろ感じられるようにしたい。ただし読書の交際はたった一人の夫や妻を選ぶのではなく、何人何冊もの相手との複合交際なのである。たいへんラッキーなことに、本に対してはいくら浮気をしたって不倫をしたってかまわない。これを聞いて急に意欲が湧くかもしれないが、実際にも本とは多く付き合えば付き合うほど、相手の魅力が見えてくる。
さいわいなことに、ぼくは本にまみれる日々を送ってきた。最近の仕事場のゴートクジISIS館には6万冊の本が3フロアにまたがって並んでいる。編集工学研究所や松岡正剛事務所を訪れる諸姉諸兄は、スタッフにその旨を言ってくれれば、どんな“本組”なのか、ご覧になっていただいてよい。
自宅には2万冊くらいの本がある。職住一体をやめてからほとんど客を招かないので、こちらはお見せするわけにはいかないが、ここには文学作品、マンガ、美術もの、洋書、ファンタジー、SF、ミステリー、和本、全集もの、絵本、ネコ本、辞典・事典、囲碁将棋本、英語ペーパーバックなどがある。
これら8万冊ほどのすべてが必要な本だったということは、ありえない。ずるずる入手した本、送られてきた本、失望した本も数多い。買ったままほったらかしも、たくさんある。しかしおそらく、このうちの3分の1か4分の1は、あきらかに自分を変えたくて求めた。

編集工学研究所1階・ブックサロンスペース「本楼(ほんろう)」
日本に関する本が2万冊配架されている。

1階・本棚茶室「井寸房(せいすんぼう)」

編集工学研究所の各フロアは6万冊の本で囲まれている。
変えるきっかけや変える方法はいろいろだが、それをまとめれば「変化のための12茶」になる。“CHAnge”という茶(CHA)をおこすための、十六茶ならぬ十二茶だ。
CHAnce、CHAnnel、CHAllenge、CHAracter、CHArge、CHAse、CHApter、CHArity、CHAin、CHAt、CHArt、CHArm‥‥。
これらの“CHA”を動かすために「これかな」という目ぼしい本を選び、その本に自身のCHAを「あれかな」と次々にあててみる。これが交際だが、その次にはAの本をもってチャージをおこし、Bの本によってチャネルを変え、Cの本の中のチャプターを自身にチャートする‥‥。そういうふうに読んでいく。
ちなみに編集工学では、このうち7つを抜き出して「7茶の法則」と呼んでいる。何が7茶かはイシス編集学校で知られたい。
こうして本は、生活や知識や仕事や環境にひそむ価値観を自分にむけてCHAngeするためにあるわけだ。本たちは、もし自分の何かが停滞しているなら果敢にアクティベートを喚起し、ぐちゃぐちゃに混乱しているなら揺動的なバランスをもたらし、のっぺりした状態になっているならそこに強引なアクセントをつけてくれる。
本はそういう武器であって、絵筆であって、自分を変えるための髪形であってコスプレなのだ。かつまた、本は体をまるごとそこに入り込ませておきたくなる炬燵であって、何万本もの注射器であって、心の筋肉をぶるぶる震わせてくれるオーダーメイドのエクササイズマシンなのである。
このことは、本がどういう目的で刊行されてきたかを考えてみれば、すぐわかる。一度でも本を書いた者や本を編集した者なら知っているように、どんな本であれ、そもそも何かを変えたいために生まれてきたものたちなのだ。人を変えたくないなどと思って刊行される本など、ほとんどない。
そこをジョン・ラスキン(1045夜)は「本は誰かを変えるか、誰かを助けるためにある」と言い、漱石が好きだったジョーゼフ・コンラッド(1070夜)は「本(小説)を書くのは読者に目をひらかせるためだ」と言った。
さあ、こうして本の中に入ったとしよう。活字がごちゃごちゃ並んでいる、難しそうなことが書いてある、これを何日くらいで読めるのか、電車の中で読み切れるかな、言葉は苦手で、などとはくれぐれも思ってはいけない。
諸君はいつだって言葉を使っている。本を前にして逃げ腰になってはいけない。
ごくごく初歩的だが大事なことを言っておくけれど、いったい本に没入したり首っぴきになると何がいいのかというと、5つほどのトクがある。
第1には「そこには世界がある」ということ、第2には親や親戚や友人よりもずっと変化に富んだキャラクターと出会えること、第3に本には人類の英知と努力と逸脱がふんだんに待ってくれているということ、第4にそれらのことが手際よい構成的パッケージになっていること、第5にそれらすべてが自在に選択可能で、かつ類書とつながっている、ということだ。
一言でいえば、どんなレパートリーにもどんなシーンにも、どんな人物にも出会えるというトクだ。
ラルフ・エマーソンは「本を選べるようになれば、両親や恋人さえ取り替えられる」と確信していたし、岩野抱鳴は「本に向かっていればいつでも獣にさえなれる」と言った。ぼくもほとんどそう感じてきた。本はいまだ出会っていない未知の恋人たちであり、いつか師事したいと希っていたマイスターたちで、どんな妄想をも許容するフロイトの館なのだ。
本を読みだしさえすれば、うっとうしい日々、退屈な夫、くだらない上司、自慢たらたらの友人、貧しい部屋、似合わない洋服といった、あまりうまくいかない自分の不遇など、まったく嘆く必要がない。
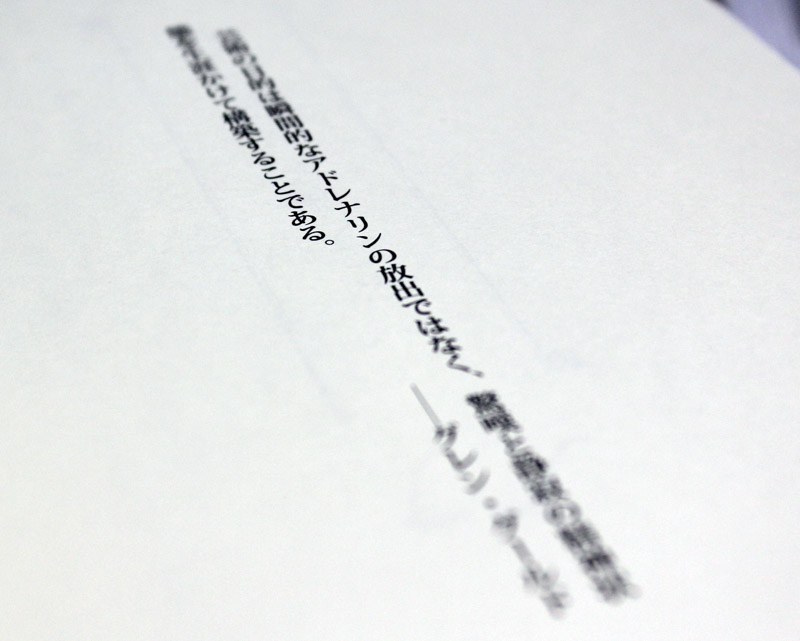
「芸術の目的は瞬間的なアドレナリンの放出ではなく、
驚嘆と静寂の精神状態を生涯かけて構築することである」
―グレン・グールド
(本書 p.154 より)
ところで、本好きにはたいていとびきりの特技がある。その特技のひとつは、すぐに登場人物に思い入れができるということだ。それはたいへん浮気っぽい。ぼくのダンテスやルパンはその後は、ハックルベリー・フィン(611夜)にも三四郎にも、アンナ・カレーニナ(580夜)にも露伴(983夜)の「のっそり十兵衛」にも飛び火した。
これが村上春樹なら『ライ麦』のホールデン・コールフィールドで、山田洋次なら「寅さん」や藤沢周平(811夜))の「たそがれ清兵衛」で、いとうせいこう(198夜)なら杜子春で、田口ランディならヘッセのデミアン(479夜)だ。本書のオヤジはなんと女三宮やボヴァリー夫人(287夜)に横恋慕したようだ。
文学的な登場人物に惚れるばかりではない。スイミー、クマのプーさん、長靴下のピッピ、バットマン、火の鳥、数々の歴史上の人物、2・26の青年将校、ヘイエルダールのような冒険家、珍獣の飼育係にも、惚れる。
このように本の中のキャラクターとフィギュアに惚れること、これが初心者がすぐさま読書プロになれるコツなのだ。諸君がマンガや映画やトレンディドラマが好きなのは、このせいだ。

左上から、三四郎・ハックルベリー・ボヴァリー夫人・デミアン・
ピッピ・スイミー・クマのプーさん・火の鳥。
しかしもうちょっと本格的に本が好きになるには、「本を読んで理解できるようになりたい」のではなく、「理解するから本が楽しくなる」という逆転感覚をもつことだ。理解できそうもない本を次々に避けているうちに、あの町この町日が暮れて、読書はどんどん遠のいていく。
そういう理解の愉楽を感じるにはどうすればいいかといえば、答えはかんたんだ。二つの種類の言葉につきあえるようになることだ。ひとつはジョン・キーツの「暖かい南の国の味をたたえた赤いヒポクレネの味を知りなさい」、もうひとつはシェイクスピア(600夜)の「おい、このボタンをはずせ」。
どちらにもピンとくるべきだが、前者の愉楽に馴染むにはどうみたって詩歌と親しくなるのがいい。本書のオヤジはボードレール(773夜)、ワーズワース、T・S・エリオット、アレクサンダー・ポープ、リルケ(46夜)、ラングストン・ヒューズらと、オーデンとピアソンが編んだ英米詩篇集などを熱く勧めているが、ぼくのばあいは中高時代に高浜虚子や川端茅舎や山口誓子の句から入って、学生期に中原中也(351夜)の詩や寺山修司(413夜・1197夜)の短歌、あるいはジュール・ラフォルグやアンリ・ミショー(977夜)の詩に遊んでいるうちに、何の苦もなくなった。
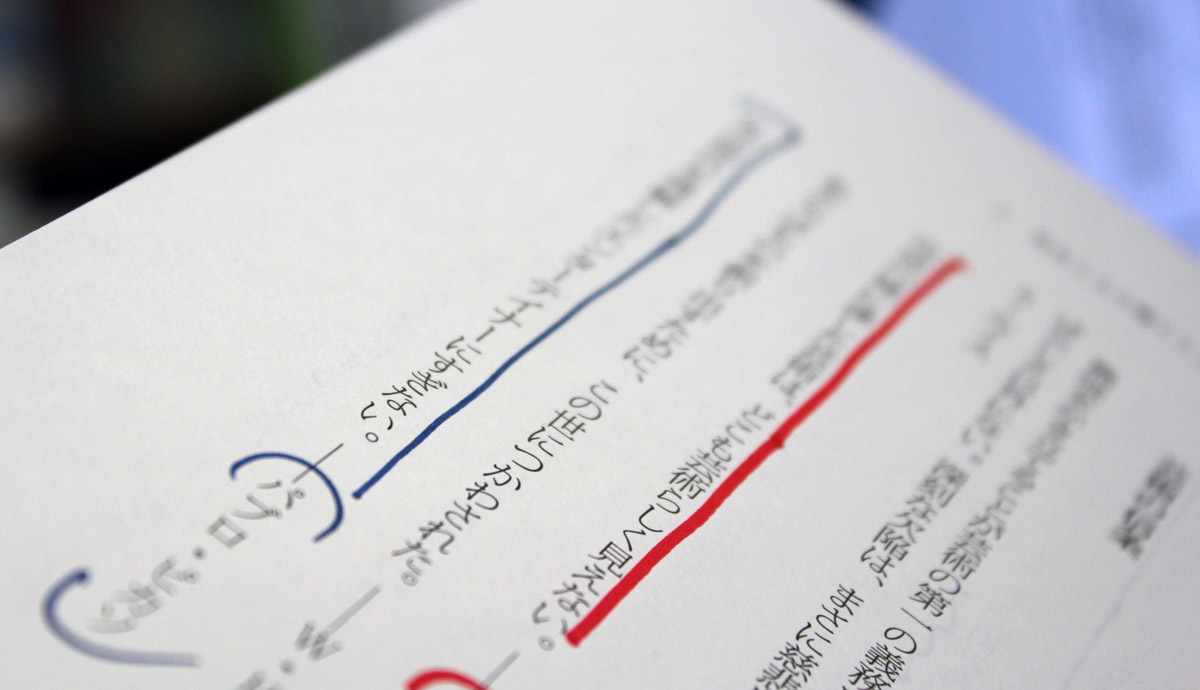
「私は時代を理解したエンターテイナーにすぎない。」
―パブロ・ピカソ
(本書p.155より)
後者に親しむには、出来のいいノンフィクションやハードボイルドをできるだけ早めに読むといい。文体に煩わされることがないので、きわめて効果が高く、抵抗感が少ない。
ノンフィクションは簡潔な文章と事実の積み重ねがぞくぞくさせる。そこが文芸作品とはそうとう違う。関心のあるものを選んで、5W1Hの連打がいかに快感になるかを知ってほしい。
むろんいろんなノンフィクションがある。最近話題になった映画の原作の、ハンナ・アーレントの『イェルサレムのアイヒマン』(みすず書房)など格別な出来だけれど、下町ものでも歴史ものでも、事件ものでもバクロものでもいい。さっさか読んで自分に合口のいいもの、読みたくなるライターに早く出会うべきだ。
千夜千冊でいえば、たとえばコリン・ウィルソン(372夜)らのアウトサイダーもの、アーサー・ケストラー(946夜)らの現代社会批判もの、ノーム・チョムスキー(738夜)らのアメリカ告発もの、松本健一(1092夜)らの近代日本もの、猪野健治(152夜)のヤクザものなど、どれもこれも堪能させられる。
ノンフィクションを面倒に思っているのは食わず嫌いにすぎない。諸君が推理小説やサスペンス映画に夢中になれるなら、だいたいが大丈夫だ。
ついで、ここから先は日記や伝記を読むのがいいだろう。オヤジのお勧めはサミュエル・ピープスの日記、ヴァージニア・ウルフの日記などだが、ぼくのばあいは国木田独歩(655夜)とアナイス・ニンの日記で目がさめた。

以上のようなヒントでも「やっぱりうまく本好きになれない」というのなら、いったん童話や絵本や怪談に立ち寄ってみるといいだろう。子供用のものを読むのは、自分の子供時代の想像力に翼をつけてくれるときがあって、けっこう納得感がある。
クリスマスに因んでいえば、レイモンド・ブリッグズの『スノーマン』、ピーター・スピアの『クリスマスだいすき』、クレメント・ムーアの『クリスマスのまえのばん』、極め付けならドクター・スースの『グリンチ』だ。これらの直後にスティーブンソン(155夜)の『クリスマス・キャロル』やアンデルセン童話集(58夜)を読めば申し分がない。
そういう童話で興がのってきたら、ついでに怪談に進むのがおもしろい。そもそも童話というのはその本質に怪談が含まれているのだから、この併列進行はたいそう理に適っている。
初心者への一番のお勧めは小泉八雲(7夜)か小川未明(73夜)、あるいは中島敦(361夜)か諸星大二郎の中国ものマンガだが、少し泰西ふうの妖しい恐怖を味わいたいなら、これもオヤジも勧めるレ・ファニュ、ヴァーノン・リー、アーサー・マッケン、ブラックウッド、ウォルター・デ・ラ・メア、ラヴクラフトという深入りだ。諸君がすでに『ウィスパーズ』『インテンシティ』のディーン・クーンツや『キャリー』『シャイニング』のスティーヴン・キング(827夜)のモダンホラーを読んでいたとしても、いったんここらへんに戻りたい。
ちなみにぼくがこれらに深入りしたのは、わが傍らでホラーファンタジーが躍如していたからだった。
荒俣宏(982夜)が何かというとブラックウッドやラヴクラフトを持ち出し、山野浩一がサンリオSF文庫の構成編集を始め、小尾芙佐や山田和子がル・グィンのあれこれを翻訳し、月刊ペン社の「妖精文庫」シリーズの装幀・飾画をまりの・るうにいが毎月描いていた。こういうことが重なっていたので、いろいろ読むことになったのだ。
いまでもレ・ファニュやル・グィンの奇妙な味は忘れないままにある。いずれ千夜千冊したい。

「人に襲ってくるもののなかでも、
最も思いがけないものは老いだ。」
―レフ・トロツキー
(本書p.227より)
さて、何といっても読書を通して「何かを学びたい」というのが、やっぱり大きな読書動機になっている諸君も多いだろう。その気持ち、よくわかる。
ただしそれには、いったい学習や教育が信ずるに足りているのかということを問うておかなければいけない。
だいたい学校とウェブは幼稚な愚行に満ちている。バーナード・ショーは「学校で生徒が教わるのは、嘘をつくこと、権威への不名誉な服従、下品な冗談、愚弄と怯懦、臆病者が臆病者をいじめることばかりだ」と、とっくの昔に言っていた。
そのなかで学習とか教育がめざすべきことは、生徒たちがどんな「お題」にも自由に向かっていけることを保証し、そのことがなによりも愉快で知的であることを体感させることである。『批評の解剖』で大向こうを唸らせたノースロップ・フライが、ずばりと書いている。「教育の主たる目的は、平凡な社会に適応しない人間をつくることである」と。
そうなのだ。何かを学ぶために本を読むなら、自分が平均点から大幅にずれていくことを快感とすべきなのである。
きっとピーター・ウィアーの映画『いまを生きる』のラストシーンに泣かされた者ならわかるだろうが、机にしがみつくのではなく、机の上で立ち上がることが、読者の屹立なのである。
あの映画のモデルとなったのはサミュエル・ピカリングという語学教師だが、ピカリングは「何かに急速に関心を向けること、そこに仲間を誘うこと」がすべての学習のすべての入口になることを教えようとして、生徒たちに「読書クラブ」を推奨したものだった。「共読クラブ」だ。ぼくにとっては修徳小学校の吉見昭一センセイがピカリングに、母と真智子と茂ちゃんとが共読クラブにあたる。

帝京大学メディアライブラリーセンターでは、「共読ライブラリー」を展開中。先日の「図書館総合展」では、職員と学生と一緒に本棚をつくり、ワークショップを実施した。右上は本のおみくじ。
というわけで、およその見当がついただろうが、読書がおもしろくなるには、本だけ選ぼうとしてもダメなのだ。「本を読もう」「本を読まなくちゃ」と焦っているときは、たいていは本は読めないものなのだ。
むしろ冷蔵庫の中や動物園の生き物を観察するクセをもつとか、気になるニュース、たとえば猪瀬都知事に5000万円を貸した徳洲会について報道を鵜呑みにせずにもっと詳しく知ってみようとするとか、アイソン彗星が太陽近くで消えたのはどうしてだったのかとか、そういうふだん気になるイシューに対する好奇心を旺盛にさせておくのが、実は読書のトリガーが起動する恰好の準備状態を育んでくれるのだ。
現代詩人のフィリップ・レヴィンがデトロイトの仕立て屋のアイロン職人を何度も見つめていたように、ココ・シャネルのお友達だった天才コレット(1153夜)が本を書いたり読んだりするために衣服を着ることに修練を課したように、井上ひさし(975夜)が行き先の地図をいつもドローイングして、戯曲や小説の舞台の地図づくりに役立てていたように、諸君も本と昵懇になるには、自分の好奇心を何かに向けて掻き立てておいて、そのモダリティをいかしたまま、さあ、一気に読書に突入することである。
ぼくは、いまでは3年に1着か2着しか洋服を買わないが、それでもそういう新しいファッションに身を包んだときは、意気軒昂になる。必ずその服装で本屋を訪れ、その服装にふさわしい本を求め、その姿のまま近くの店で珈琲をのみながら、一気にその本を“服用”する。
読書は自分で好きなスタイルが選べるモード探検なのである。読書はみかけの値段よりもずっとおトクな、最も手近かな世界感覚入手装置なのである。

「体にビタミン、仕事にPC、読書力には、ブックサプリを!」
(松丸本舗より)

⊕本から引き出された本―引用で綴る、読書と人生の交錯―⊕
∃ 著者:マイケル・ディルダ
∃ 訳者:高橋知子
∃ 発行者:早川浩
∃ 印刷所:株式会社精興社
∃ 製本:大口製本印刷株式会社
∃ 発行所:早川書房
⊂ 2010年2月20日 初版印刷
⊗ 目次情報 ⊗
∈ はじめに―世に通じる
∈ 1 命綱になる言葉
∈ 2 学ぶ喜び
∈ 3 仕事と余暇
∈ 4 恋愛の書
∈ 5 すべてを家に持ち帰る
∈ 6 世界に生きる
∈ 7 見ることと聴くこと
∈ 8 室内の書架
∈ 9 精神の諸問題
∈ 10 おわりに
∈ 一部のみの風変わりな人名録
∈ 謝辞
∈ 訳者あとがき
⊗ 著者略歴 ⊗
マイケル・ディルダ(Michael Dirda)
1948年生まれ。コーネル大学より比較文学の博士号を取得。1978年にワシントンポスト紙の書評セクションブックワールドの書評家兼コラムニストの任に就き、ライターを長年勤める。1993年には批評活動に対してピュリッツァー賞受賞。著書として本書のほかに、Readings: Essays and Literary Entertainments, An Open Book, Bound to Pleaseなど多数。