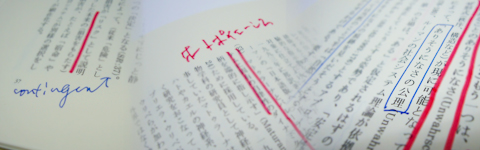リスクがリスクを生み、
そのリスクの連鎖の大半を
社会や組織が次々に呑みこんでいる。
こんなリスク社会をいったいどう見ればいいのか。
ルーマンは、そのようなリスク社会の特徴検出にこそ
新たな社会システム理論のきっかけがあると見た。
オートポイエティックで、自己準拠的な、
しかもダブル・コンティンジェントな社会モデル。
その入口を、今夜はちょっとだけお目にかける。
本書では、ニクラス・ルーマンがその独特の自己準拠的システム論あるいはオートポイエティック・システム論にもとづいて、どのようにリスクおよびリスク社会を見つめたのかが集中して論じられる。
論者の小松丈晃は東北大学出身の1968年生まれの若手研究者で、ルーマンの大冊『社会システム理論』(恒星社厚生閣)の翻訳なども手掛けてきた。ただし本書は自立した単著ではなくて、勁草書房が刊行してきた“ルーマン論シリーズ”ともいうべきものの一冊で、福井康夫の『法理論のルーマン』、馬場靖雄の『ルーマンの社会理論』、春日淳一の『貨幣論のルーマン』などとも対応して、このシリーズ全体で、ルーマンがどういう社会学者であるかが総じて展望できるようになっている。
今夜は、そのなかのリスク論にかかわったルーマンの問題提起の仕方だけをとりあげる。ルーマンの社会論や経済論やルーマン自身の著作は次夜で紹介したい。まずは外側の解読者の目から案内しておきたいからだ。
その前に一言。
ルーマンはこれまでの社会学者とちょっとちがっている。ドイツのフライブルク大学で法律学を修めたのち、いったん行政の実務にかかわり(ハノーヴァーで文部行政)、その後にハーバード大学では行政学と社会学を、さらにシュバイヤー行政大学で行政研究に携わったり、ドルトムントの社会調査局の主任研究員をやったりしていた。このとき早くも「複雑さ」「信頼」「システム」「意味」といった問題意識を前面に持ち出そうと試みていた。
そのあとの1968年から25年以上は、ビーレフェルト大学の社会学教授として「社会システムの科学」を理論的に探求しつづけた。とくに1971年にユルゲン・ハーバーマスとの公開討論をしたのをきっかけに、その独自の探究心にもっと火が付いて、70年代後半には「オートポイエーシス」の社会学化に猛然と向かっていった。
まるで”社会のシステム化”を一身に引き受けたかのようなのだ。こういう傾注ぶりは、アカデミックな社会学者の姿とはちょっとちがっている。
ルーマンは1927年のリューネブルクの生まれである。父親はビール業。ナチス抬頭の折りから、15歳のときに高射砲部隊に入営し、17歳のときはフランスの収容所で強制労働に就かされもした。敗戦後もアメリカ軍の捕虜収容所に入れられた。ルーマンとドイツ社会の関係はいささか特異なのである。
こういう経歴もあって、その問題意識はかなり広範にわたるのだが、またその著作は研究者のあいだでさえ難解きわまりないともくされてきたのだが(たしかにロジック・プレゼンテーションの仕方はヘタッピーである)、ぼくがルーマンの思想で最も注目するところははっきりしている。世界や社会をつねに複雑系として捉えつづけてきたこと、その世界や社会を形成する根源的な単位を「意味」に求めようとしつづけたこと、その意味を加工編集するものはすべからく「システム」であるとみなしたこと、このことにある。
ルーマンは社会は複雑なシステムであり、そのシステムは意味によって構成されるとみなしたのである。ということは市場も価値も意思決定も、とことん「意味」で構成されるということになる。当然といえば当然のことではあるけれど、社会学者がこのように「システムと意味の関係」を長期にわたってぶらさないでいることは、実はめずらしい。
では、そのような見方をしたルーマンにとって、リスクというものはどのように解釈できるのか。本書はそこに焦点をあてた論評になっている。
すでに時代社会は1980年代後半あたりから、生態系の毀損や原発事故やエイズなどの人間社会が生み出したリスクに人間社会自身が曝されるにいたっていることが、あきらかになってきた。そのリスクは国民国家の枠をこえてグローバル化しつつあった。
そこでウルリヒ・ベックが『危険(リスク)社会』(1986)をもっていちはやく社会学的警鐘を鳴らしたというところまでは、前夜の『現代社会のゆらぎとリスク』(1347夜)で紹介した。だから話はそこからだが、このように急速に浮上したリスクには前例のない特徴があった。また多様性があった。
第1には、リスクの作為者とリスクの犠牲者を分かつことが困難なリスクであった。第2に、環境汚染や薬害やコンピュータ・ウィルスなどがそうであるように、多くのリスクが直接に知覚できないものに向かっていた。ベックはこれを「非知」のリスクというふうに捉えた。「知りえない知」としてのリスクということだ。第3に、原発事故や鳥インフルエンザなどがまさにそういう例にあたるのだが、時代が進むにしたがって保険制度などによってとうていカバーできないほどの大規模なリスクが次々にふえ、のみならずそれらが連鎖してきた。
こうした異様なリスクの波及は、社会はもはや「富の分配」ではなくて「リスクの分配」で成り立っている、と言ったほうがいいような度しがたい様相をふりまくことになった。
これではリスクの研究も多様にならざるをえない。オートゥイン・レンによると、いまやリスク学の研究分野は、①保険数理によるリスク論、②確率論によるリスク分析、③リスクを組み合わせる経済学、④リスク社会論、⑤リスクをめぐる認知心理学、⑥リスク文化論、⑦毒物学や疫学などに分かれざるをえなくなっているという。
この分類でいえば、ルーマンは④リスク社会論を先駆けたということになるのだが、けれどもその思索の半径は、むろん④にはとどまらない。
ルーマンは1980年代半ばから環境リスクについての発言を始めていて、スイスのザンクトガレン大学で講演をしたり、紙誌に寄稿したりして、政治的なエコロジー運動がさかんなドイツの実情をある程度意識したスタンスをとっていた。ドイツはナチスの体験もさることながら、「緑の党」などが早くから運動をおこしていた国柄なのだ。
このスタンスのなか、マトゥラナとヴァレラが提唱した「オートポイエーシス」概念(1063夜)を社会システムに適用するようになった。ふいにというか、思い切ってというか。
オートポイエーシスは生命システムの謎、とくに免疫的なシステムの謎を解くための概念として考えだされた。生命が「非自己」を活用しつつ自己組織化をとげながら、それでもシステムとしての「自己」を環境の内外で保持しているのはなぜか。そこには「自己を再生産するための自己準拠」や「自己による自己再帰」のしくみがあるのではないか。生命は自分自身についての「自己言及」をしながらもそこに生じる自己矛盾(コンフリクト)をたくみに超越するしくみをもっているのではないか。それはオートポイエーシスとでもいいうるものではないか。マトゥラナとヴァレラはそういう仮説をたてた。
ルーマンは、そのようなオートポイエーシスが社会システムにも動いているだろうとみなした。法や価値観や市場の動向にも、オートポイエーシスのなんらかの作用が関与したり滞留したり、また逸脱したり過剰になったりして、システムの内外を出入りしているのではないかとみなしたのだ。
しかし生命システムと社会システムとは似ているところもあるが、似ていないところも少なくない。社会生物学者たちはこのことにつねに悩んできたし、ローレンツ(172夜)やアイベスフェルトらの勇気をもってしても、動物行動学(エソロジー)の成果は容易には人間社会にあてはまらない。
ましてオートポイエーシスのようなメタシステム仮説と現実社会の関係はいちがいに決めがたい。けれども、生命にも社会にも共通して動いているものがある。それは広くいえば「情報」であり、また、記号やメタファーをともなう「意味」である。
ルーマンはそこで、社会システムにおいては「コミュニケーション」(あるいはコミュニケーション行為)が動いて、それがなんらかのかたちでオートポイエーシスに向かっている、ないしはオートポイエティクなしくみと関与している可能性があるとみなしたのである。
これはけっこう大胆な展開だった。もしくは安直な比較かもしれなかった。しかしルーマンは躊躇なくここに深入りしていくことになる。ことに研究の途中から、大きな変更を加えもした。それは、社会システムのどこかににオートポイエティックなはたらきが部分的にあるのではなく、オートポイエティックな動きのなかに社会が機能しているのではないかというような、大きな見方の逆転だった。
社会そのものの様態が、もっと大きな自己言及的なオートポイエーシス活動のひとつのケースであり、プロセスのあらわれであろうと見てとったのだ。そこから法や市場や組織が、また価値観やリスクが生み出されている(分出している)のではないかと見てとったのである。
一般にリスクは「損害が生じる確率」だとみなされてきた。そのため、リスクは危険がともなうものであり、したがって安全の反対概念であると考えられてきた。
しかし、はたしてそうなのか。危険や安全が確定されてからリスクが計算されたのか。そうではなかった。ことは「たまたま」から派生し、そこから統計学や確率論が生まれ、保険や数理経済学が生まれ、事故の記録や損害の算定が先行するにつれ、そのリスク回避が検討されるようになったのである。リスクは「危険」や「安全」の確定から生じたのではなく、事態の進展そのもののなかから鬼っ子のごとく生じたものなのだ。
そこでルーマンは、リスクを「危険」や「安全」に対比させるのではなく、社会システムにおける「決定」のプロセスに関するものと見たほうがいいと考えた。
近代以降の社会は、おおむね「真/偽」「法/不法」「統治/反対」「就業/失業」「支払い/未払い」「貸付/返却」「成功/失敗」「健康/病気」といった二値コードによって成り立ってきた。
最近の普天間基地移転をめぐっても、トヨタのリコール問題をめぐっても、景気失業対策をめぐっても、国母クンの冬季オリンピック服装問題をめぐっても(笑)、この二値コードは政府によってもマスメディアによっても間断なく発動されている。
ルーマンは青年期以来、このことにずっと疑問を抱いてきた。のみならず、このように二値コードをもって社会を裁断し、判定することそのことがリスクを生じさせていると見た。二値的な決定プロセスがあやしいのである。多くのリスクは“システミック・リスク”なのである。
ひるがえって、社会というもの、つねに「規範」や「稀少性」や「競争点」を決めようとしてきた。それが市場に競争原理を生み、都市を賑やかにさせ、生活をさまざまな方向に導き、会社を成長戦略に向かわせ、景気や物価を上下させてきた。
けれども、そこではいくつもの矛盾も派生した。たとえば、企業活動や消費者活動が仮に“環境にやさしい”ような方向に進んでいったとしても、そこにはエコポイントなどのような“数値”が課せられる。また、どんな会社や組織にも、社会の複雑な要素を反映したぶんのコンプライアンスの縛りが、網の目のように課せられる。つまりは社会はエンドポイント(1346夜参照)の数値の網目によって決定されてきたわけなのである。
これは何をあらわしているかといえば、社会システムの各所に「決定者」とその決定を受ける「被影響者」の範囲があって、それが社会システムをついつい自己決定しているだろうということである。それも、ありうべき社会システムのグランドモデルを想定することなく、ずるずると結果的にそんなふうにさせてきてしまったのだ。
ここには何がおこっていたのだろうか。これが自由主義市場の原則と体たらくというものなのか。それともすべてがまちがいで、だからネオリベラリズム過剰に向かってしまったのか。ルーマンはこの二つの見方ともに当たっていないと見た。
では、なぜこんなふうになってきたのか。このような事態になった社会システムについての理論が欠乏していたせいだったのである。そこにリスクの介在を認めておかなかったせいなのである。
社会システムはコミュニケーション行為で構成されているのではない。社会システム自体がオートポイエティックな動きをすることが、さまざまなコミュニケーションの行為的属性になっている。
こういうコミュニケーションは再帰的コミュニケーションであり、自己言及性をともなっている。そして、ここが肝要なところになるのだが、リスクの本体はこの構造の隙間やきしみから生まれるのである。どのように生まれるかとといえば、コンティンジェントに生まれる。
コンティンジェンシー(contingency)という言葉は、そのもっている意味がきわめて重要なわりには、とてもわかりにくい。よく「別様の可能性」とか「機能的な等価性」とかと訳されたり、説明されるけれど、これではとうてい掴めまい。
辞書的な定義では、事件や事故が偶発的におこるときに、「まさかこんなことがコンティンジェントにおこるとは思わなかった」というふうに使う。また、その偶発的な出来事によって付随しておこる一連の出来事が、ことごとくコンティンジェントなのである。それゆえここは不確実なこと、不確定なこともコンティンジェントなものとしてすべて含意されている。いいかえれば生起するかもしれない可能性もコンティンジェントなのである。
つまりここには「偶然の本質」がかかわっているとともに、「生起の本質」もかかわっている。それがコンティンジェンシーである。
ルーマンは、オートポイエティックな社会システムには、リスクがコンティンジェントにかかわっていくと見た。システムがシステムの次のふるまいを、自分がかかえもった多様性のなかから選択することそのことがコンティンジェントであって、かつリスキーなのである。
これはシステムが外部環境や内部環境に適応したからではない。そうではなくて、システムが次の様態を求めてシステムの“分出”をはかったのだ。システムの次の制限に自己準拠したのだ。つまりは、システムは複合的構成に向かうために自身をコンティンジェントにし、オートポイエティックなふるまいを保持しているということなのだ。
システムに出入りするものはすべて「情報」とみなしていい。システムの状態はどんなときであれ、つねに情報がかかわっている。
しかし、ひとたびシステムがシステムたらんとするためには、この情報の多様な様相と動向のなかから、なんらかの「意味」たちを見いだしているはずである。
システムは情報システムであるとともに、意味を構成するシステムに向かって自己生産あるいは自己更新をしているはずなのである。ルーマンはこのようなシステムにおける有意的な情報処理のプロセスに注目し、そこに高度な複合性や相互依存性を生ずるしくみがあると見た。
ここまではしかし、とくにめずらしい発想ではない。ホワイトヘッド(995夜)からフォン・ベルタランフィ(521夜)まで、ハーバート・サイモン(854夜)から清水博(1060夜)まで、動的なシステムを考えたことのある者なら、誰もが考える。ぼくならば、有意的な情報処理とは「編集」そのものであり、編集することがリスクを意味に転換しつづけることになるとも考える。
だが、ルーマンはここを「意味を構成するシステム」がダブル・コンティンジェントにシステムを自己形成して、リスクを組み上げていくというふうに見た。ここがおもしろい。「ダブル・コンティンジェンシー」という概念もたいへんに特異である。「二重偶発性」とでも訳せるだろうが、そのままダブル・コンティンジェンシーと言ったほうがいい。
もともとはタルコット・パーソンズが言い出したことで、これはコンティンジェントな事態には、そのことがあるものに依存するという意味と、そのこと以外のこともおこりうるという意味とが、二重に生起しうることにもとづいている。そういう二重のダブル・コンティンジェンシーがシステムが自己言及するたび、自己再帰するたびに選択され、そしてそのたびにリスクが内包されるということなのだ。
さて、では、このようなオートポイエティックな社会システム論をもって、ルーマンがどのようにシステム理論を組み上げていったのか。このことについては、次夜の一冊に任せたい。今夜はリスクがコンティンジェントにあらわれるというところにだけ着目しておいてもらいたい。
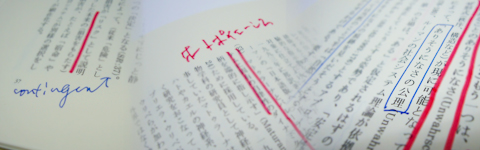
【参考情報】
(1)ニクラス・ルーマンについては前夜・今夜・次夜を通してそのプロフィールを把握してほしい。この人は真理も全体も主体も理性も必要としなかった社会学者なのだ。それだけではわかりにくかろうから、前夜は『自己言及性について』(国文社)と『ルーマン、学問と自身を語る』(新泉社)を紹介したので、そこからひとつ、ふたつ、リークしておくと、ルーマンは第1に、「知」というものの前駆的段階にずっと関心をもってきたということだ。第2には、「意味」にとって最も重要なのはその意味が情熱を迸(ほとばし)らせるときだと感じつづけていたということである。
そして第3に、これはずっとエピソディックなことであるのだが、ルーマンはいつもカードに自分の発想をメモしていて、それをカードボックスに入れてはシャッフルしていたようなのだ。それで何をしたかというと、そのカード群の離合集散のために「読書」をしつづけていたらしい。この読書術、なんともいえない魅力をもっている。
(2)ルーマンは「正しいもの」を設定しておいて、その論証のために思索や研究や調査や分析をするなどということをしなかった。こんなふうに自分の研究の方針を説明している。「現にあるものがそのようなかたちで現にあることにまず驚き、現にそのようにあることの”ありそうになさ”(Unwahrscheinlichkeit)を仮定することから初めて、そうであるにもかかわらず、なぜ形式や様式(秩序・構造など)が現に可能になっているのかを、探求する」(『社会システム理論』より)。ね、これって凄いよね。
(3)「ダブル・コンティンジェンシー」を最初に提唱したタルコット・パーソンズ(1902~1979)はアメリカの社会学者。ヨーロッパの社会理論をアメリカに移植するにあたって、そこに数理的・情報科学的な手法をまぜて社会システム理論の規範をつくった。主著に『行為の一般理論』『社会的行為の構造』『社会システム論』などがあり、その思想は「構造機能主義」などとも呼ばれる。システムをA(適応)を受け持つ経済、G(目標達成)を進める政治、I(統合)を反映する社会共同体、L(パターン維持)を継続する家族の4つで説明したAGIL図式が有名だ。
ちなみにパーソンズのコンティンジェンシーは「依存性」の意味あいが強い。これらのことの解説を含めて、本書は「注」が充実している。参考に。