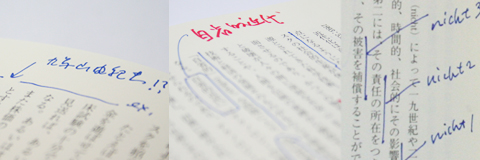石橋を叩けば橋が壊れるリスクが生じ、
叩きすぎれば手にリスク(傷)が生じ、
叩きもせず渡りもしなければ、
行く先のリターンは決して手に入らない。
リスクを免れることが新たなリスクを生み、
リスクを排除しようとすることそれ自体が、
社会をリスクに満ちたものにする。
リスクと社会の関係は、
いったんリスクとシステムの関係で
語られる必要がある。
ウルリヒ・ベックやニクラス・ルーマンは
そこを新たな社会学の踏み台にしてみせた。
そこで、今夜からしばらくは
リスクをめぐる理論篇を案内したい。
臨床試験の十分でない新薬を投与することはリスキーである。しかしそのリスクを避けるために投薬を見送れば、患者を見殺しにするリスクを負うことになる。ヘッジファンドに多額の資金の運用をまかせるのはリスキーである。しかしそれを惧(おそ)れて資金を遊ばせておけば、リターンがないというリスクを負う。
リスクを少なくしようとする試みは、それ自体がリスキーなのである。現代におけるリスクのパラドックスは、「安全が危険の函数になっている」ということにある。このような問題は、社会がそのようにシステム思考をすることが自己言及的構造をもったということに由来する。いまやリスクを考慮しない社会など、考えるべうもない。そうだとすると、ここに新たな「リスク社会学」のようなものが出てこなければならない。
すでに「リスク学」というジャンルも生まれている。日本でも2007年に「リスク学」と銘打った全5巻のシリーズが岩波書店から刊行された。橘木俊詔・長谷部恭男・今田高俊・益永茂樹の監修構成で、第1巻が総論の「リスク学入門」、第2巻が『経済から見たリスク』、第3巻『法律から見たリスク』、第4巻『社会生活から見たリスク』、第5巻『科学技術から見たリスク』。
リスク学の扱い範囲を告知する入門的な講座ではあったが、出版物としてはそれなりの役割を果たした。しかし、中身からすると災害や医療やリーガルなリスク対策が勝ちすぎて、広井良典「リスクと福祉社会」、椿広計「リスク解析とは何か」、中西準子「環境リスクの考え方」などは収穫が濃いものでありながら、社会学や経済学が本気でとりくむべきリスク論のメルクマールは明示しきれていなかった。
山口節郎の本書は2002年の執筆ではあるが、この20年ほどの社会学がリスク論にさしかかったあたりを理論的に俯瞰トレースしていた。比較的よくまとまっている。とくに第4章は「リスクの社会学」と銘打たれていて、その章題どおりの内容になっていて、今日でも参考になるマップを提供していた。そこで今夜はこの本の案内をしておく。
リスク論が社会科学のなかで急速な話題になったのは、1986年にウルリヒ・ベックが『危険社会』(原題は『リスク社会』)で「リスク社会の到来」を告示してからのことである。「豊かな社会」を求めすぎた歴史は必ずやリスク社会に向かっていくだろうというものだ。
むろん、自然災害がもたらす危害や生老病死にかかわる危難についてのリスクや、世の中の出来事の「たまたま」「偶然」「不確実性」に関する議論なら、ずっと昔からあった。リスクという概念が浮上したのも、フランク・ナイトが「計算できない不確実性」と「計算できるリスク」を区別してからのことだから、かれこれ半世紀はたっている。
しかし社会学的なリスク論はベックからで、以来、急速に議論の俎上にのぼるようになった。けれども如何せん、課題が大きすぎた。アンソニー・ギデンズの「自然的リスク」と「人為的リスク」の区別があったりしたものの、リスクの多様性や多義性はとうていその程度の分類ではおさまるはずはなく、とくに金融市場や企業社会におけるリスクヘッジやリスクマネジメント議論と、環境リスクをめぐる議論とが激しく発火して、いまではリスクに関する認識と評価、リスクをめぐる防止と削減、リスクをめぐる運用と応用は、それぞれ実に多岐にわたるものになっている。
今日の社会学では、リスク論は大きくは二つの目で眺められている。ひとつはベックのように、高度な資本主義社会が拍車をかけた富への加担とグローバリゼーションが拍車をかけた豊かさと情報がまじりあった豊かさとがあいまって、社会のさまざまな場面でのリスクとなって亀裂を生じているとみなす見方だ。いわば暴走する欲望社会のしっぺ返しとしてのリスクをどのように見るかという問題である。
もうひとつはニクラス・ルーマンらの見方で、社会が高度に発達して職業選択から生活スタイルの選択まで人間活動の自由度が高まって、人々がさまざまな場面でのコンティンジェントな選択を強いられるようになったため、その選択がかえって期待どおりの結果をもたらさなくなったという、「選択の自由にともなうリスク」に注目する見方だ。
いずれも、いったい社会におけるシステムや人間の生き方における自由とは何かということが問われていることには変わりないのだが、しかしながら問題は単純ではない。多様なリスクをどのように社会的に管理するのか、地域社会でのリスク・コミュニケーションはどのように進めるのか、さらにはリスクの共有とリスクの削減をめぐる不一致の問題をどう解決するのか、問題群はずらりと並んでいる。
経済学や市場の現場では、リスクは損失をともなうものであるとともに、利得を返すものとして早くから扱われていたので、リスクとリターンが一衣帯水の現象として議論され、組み立てられてきた。
とくに「オプション」の考え方から派生したデリバティブ、スワップなどの金融派生商品が人気を得るにいたって、「リスクの経済学」こそが経済社会の鍵を握るようになってきた。カール・ポパーの社会工学とジョージ・ソロスのリスクヘッジ(1332夜)が結びついたのは、その象徴的な例である。経済リスクと社会リスクは切り離せないはずなのだ。
しかし、ここまでリスクの多様性が広まっていくとは、社会学のほうも予想していなかった。たとえば前夜ではリアルオプションの可能性についても紹介しておいたけれど、このへんのことは社会学でもほとんど注目されていない。
本書の著者の問題意識の出所にも、20世紀の「豊かな社会」が新たな社会的不平等というリスクを生んだこと、市場システムがもたらしたリスクを解決するために登場した福祉国家が新たなリスクを生んだこと、この二つをめぐる大きな矛盾が露呈していた。
この矛盾が互いに交差すると、そこからおびただしい問題が吹き出してくるのだが、それが何を示しているかということを議論するには、社会学は用意がなかったのだ。そこでまるで判で捺したかのように、ベックの『危険社会』を起点におくことがジョーシキになっていた。スリーマイル島やチェルノブイリの原発事故の直後に執筆されたせいでもあった。だからたいへん話題を呼んだ。
話題になったのだが、その後、この一冊が投げかけた“啓蒙的リスク論”ではまにあわないこともいくつも見つかった。それでも現代社会学は、それまでリスクについては甚だ鈍感だったので、「リスクの社会学」を議論するとなるとこの一冊を起点にせざるをえなかったのである。
ベックが『危険社会』で何を書いたかということを整理しておこう。第1に、産業社会は「残余リスク社会」であるという判断を提出した。第2に、したがってその後の社会の近現代化のプロセスは、産業社会が生み出した「負の副産物」を新たなリスクとして認識できるかどうかという視点で捉えなおせると見た。しかし第3に、そのような捉え方をすることはその認識がかなり苦(にが)いものになるだろうため、そこに自省的な社会が登場するだろうと見た。ベックの問題提示はそういうものだった。
わかりやすくいえば、こうである。産業社会が掲げた目標は“I am hungry”という物質的アンバランスの改善だった。「欠乏」の克服だった。ところが産業技術が発展していくと、それに代わって公害や原発やテクノストレスや環境ホルモンや「うつ」などの「負の副産物」があらわれてきた。それは、他山の石ではなく、世界中の一人ひとりの自分自身がかかわるかもしれない環境や生命をゆるがすもののようだった。人々は“I am afraid”という「不安」を募らせた。
“I am hungry”はいつのまにか“I am afraid”に切り替わっていたのだ。それは「欠乏の共有」から「不安の共有」への切り替わりでもあった。そのとき、その切り替わりの断面に、あっというまに「リスク社会」が次々ごしごしとさしはさまれたのだ。そういうスコープなのである。
こういう判断をしたベックは、近現代化のプロセスは総じて自省的(あるいは再帰的=reflexive)になり、今後の社会学は「自省的近代」を問題にしなければならないと考えた。
いまから思うと、ベックが掲げたリスク社会は、3つの「ない」(nicht)で定義されていた。①リスクを空間的時間的に限定できない(限定不能)、②多様なリスクの責任を特定所在者に負わしきれない(帰責不能)、③大規模リスクの被害を補償しきれない(補償不能)。
いったいどうして3つもの「ない」が揃ったのかといえば、リスクが多様になり複雑になり大規模にもなったからであり、それにもかかわらずそうしたリスクの多様性から逃げようとする「組織化された無責任」がはびこったからだった。このことが責任と規範と習慣の関係に次々にミスマッチをおこさせた。多発するリスクと多様なリスクについての限定と帰責が立証できないことが、しだいに組織的無責任をつくったのだ。
このことをベックは比喩的に、「リスク社会における生活と行為は、言葉の厳密な意味においてカフカ的にものになっていく」と言っている。たしかに今日の社会はいっそうカフカ的であり、村上春樹的である。
現代社会学史の観点からいうと、このようなベックのリスク社会論はアドルノ(1257夜)やホルクハイマーの『啓蒙の弁証法』の意図をすぐれて引き継いでいた。不気味なものの浸透と断絶に対する警告でもあった。しかしながらそのような意図だけでは、文明のパラドックスに対する警世や啓蒙にはなったとしても、リスクを不可避に抱えた社会やシステムの分析にはなりえない。
ここはいったん、リスクをもっと大きな「不確実性」のなかで捉えなおし、その捉えなおした不確実性のもと、新たな社会構造やシステムやネットワークの特性を見いださなければならない。社会学者たちはそのことをひしひしと実感していた。ベックの『危険社会』の余波がほどほどに収まってくると、多くの社会学者はそのような感想をもつようになり、次のようなスコープを想定するようになった。
いまや世界は、「かくあらねばならない」という必然性と合理性をとっくに失っている。世界は「たまたまな偶然」と「予想どおりの不合理」と「バイアスとリフレクシビティ」に満ちてしまっている。
加えて、空間は民族空間や仮想空間を含めて一様ではないし、時間も将来の予測に向かって変質をとげている。生命から環境にいたるまで、すべての情報は非対称なのだ。こういう世界のなかで、社会とシステムとネットワークが不確実性を吸収しながら、急激なデジタル技術の波及のなかにふらふらと浮かんでいる。
そこへもってきて、「リスクの経済学」のほうも保険から証券へ、投資リスクや信用リスクから複合リスクへと大胆不敵に姿を変えて、その適用範囲を暴力的に加速させてきた。デリバティブに至っては複雑なポートフォリオにまでなった。ベックが巧妙にも名付けた「残余リスク社会」は、IT社会の進行のなかではまたたくまに別の様相の「リスク後遺社会」に代わってしまったのだ。
こんな時代社会では、意思決定のための「最適化ルール」なんて役に立たないし、「決定の合理」に行きつくことも無理である。せいぜい限定合理性や最小合理性を使って、できるだけ印象的な「行為の経済」を積み重ねていくしかなくなっている。
けれども、このように社会とシステムとネットワークが不確実性をあまりに吸収しようとしていくと、今度はそこには「結果としての不確実」というコストの支払いがのこされる。そのツケは誰が払えばいいかといえば、そんな答えは政府も社会学も用意はしていない。そもそも異種配合しつづけるようなリスク複合体を、いったいどう考えていけばいいものか、それすらもわからないままなのだ。
ベック以降、こんな議論が次々におこっていたのだが、さて、ここに登場してきたのが、それらのスコープを新たに組立て直すものとしてのニクラス・ルーマンの新たなリスク論だったわけである。これは、システムから見たリスク社会学の登場だった。
システムは成長しつづけることによってしか存続することができない。そのためシステムは、どんどん変わっていく外部環境に適応し、自己更新を続ける。こういう宿命をもつ。しかしシステムはそのはたらきの「自己言及性」ゆえに、たえずリスクにさらされる。逆に見れば、システムはその作動を通じてたえずリスクを生み出している。
ルーマンはリスク社会を、このような自己言及的なシステム特性に見舞われた現代社会として特徴づけたのである。そこでは、システムの部分性だけが相互依存性をもっている。
そういうシステムでは、部分システムを全体システムとして調整する中央機関はなく、審廷もない。各部分が自分で世界を観察し、さまざまな情報を編集し、コンティンジェントに自律的再生産に向かう。そうなっていくしかない。しかしリスクは、このプロセスのさまざまな場面にこそ出入りするものだったのである。
すでに20世紀の100年間のあいだに、システム理論の基本パラダイムが大きく変化した。最大の変化は量子力学と相対性理論と生命情報論によってもたらされた。システムは自分がシステムでありつづけるために、「歪み」と「ゆらぎ」を伴うようになったのだ。
そこへさらに脳と環境が加わった。「全体と部分」の問題はしだいに「システムと環境」の問題に変わり、「インプットとアウトプットの関係」は科学においても社会においてもフィードバックやバイアスをともなう「自己言及的な関係」に変わっていった。ベルタランフィ(521夜)やウォディントンやホワイトヘッド(995夜)のシステム論は、そういうものだった。
システムは「制御」から「自律」への変化を組みこむようになったのである。しかしながら、それはまた、リスクの頻繁な出入りと滞留でもあった。ということは、リスクとは、こうしたシテスムのふるまいからこそ観察できるものなのかもしれないということだった。
こうしてルーマンは、生命・脳・自己・社会・環境にわたるシテスムとリスクの関係に分け入り、そこに「オートポイエーシス」の視点を積極的にとりいれて、さまざまな理論的分析を加えていった。それは、ウンベルト・マトゥラーナとフランシスコ・ヴァレラが著した、あの『オートポイエーシス』(1063夜)からの援用によるオートポエティック・システム論でもあったが、そこにはマトゥーラナらのオートポイエーシス仮説を超えて、かなり独自な見方も加えられていた。
ルーマンは、リスクをシステム・カテゴリーとして語る方法を発見したのである。リスクのふるまいはその大半をシステム・リスクとして語りうるだろうとみなしたのだ。
システムは自分自身の自己言及性によってたえずリスクを生みだし、「ゆらぎ」にさらされるのだ。もはやリスクのないシステムはシステムたりえず、システムに関与しないリスクはリスクたりえなくなったのだ。
ということは、どんなシステムであれゼロ・リスクを求めようとすることが最大のリスクなのである。リスクを排除しようとするシステムは、必ずや自身のシステム維持コストの増大に悲鳴をあげるにちがいない。
ここから導き出されるのは、システムが選択強化的なコンティンジェンシーによって、どうしたら自己変更をとげられるかということである。どのようなオプショナル・システムの様相を、どのようにオートポエティックに組みこむことができるかということだ。「計画論」から「オートポイエーシス」へと言ってもいいだろう。ルーマンのシステム論はそこを考えた。
これを最近の大企業や銀行のように、合併や合体や資本提携によってひたすらリスク回避に走ろうとしても、リスクは決してなくならない。それどころか図体が大きくなったらそのぶんそれだけ、かえってリスクが生じたときの危険度はバカでかくなる。リスクはもっと大きくなって撒き散らされるだけなのだ。
このように、リスクをシステムとの関係を読んでいくというルーマン以降の方法は、新たなリスク社会学の登場としてさまざまな展開の可能性をもっていた。新たな問題もかかえた。ルーマンのリスク論を中心に、次夜で、もう少し詳しく説明したい。
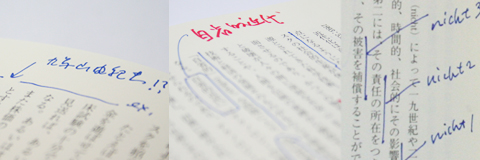
【参考情報】
(1)著者の山口節郎は1940年生まれ。名古屋大学文学部ののち東京大学大学院で社会学の博士課程を修了し、いくつかの教授をへて大阪大学の大学院教授を務めた。『社会と意味』(勁草書房)のほか、『現代アメリカの社会学理論』(恒星社厚生閣)、『二十世紀社会学理論の検証』(有信堂)などの共著、ハーバーマスの『コミュニケイション的行為の理論』(未来社)やルーマンの『批判理論と社会システム理論』(木鐸社)の共訳がある。
本書は、第1章で「現代社会と不平等」をハーバーマス、クレッケル、パーキン、オッフェ、ブルデュー(1115夜)らの理論をおりまぜて資本と属性の両面から分析し、第2章「福祉国家のトリレンマ」で、ルーマンのシステム理論やトイプナーの法理論をつかって問題を整理し、第3章「支配の正当性」ではオッフェの言う「手続きの自己正当化」の議論を敷延して、「合意」の意義に迫ろうとしている。
(2)ウルリヒ・ベックが提起したリスク社会には「再帰性」(リフレクシビティ)という特色が付与されていて、このことをめぐる社会学的な議論がルーマンを含めていまやかなり多弁なものになっている。その中身が比較的かんたんに見てとれるものとして、ここでは『再帰的近代化』(而立書房)をあげておく。ウルリヒ・ベック、アンソニー・ギデンズ、スコット・ラシュかそれぞれ論文を書いている。なかでギデンズは強靭な論客で、社会学が向かう先をつねに批判的に提起しつづけてきた。『社会学』『社会学の新しい方法規準』『近代とはいかなる時代か?』(而立書房)などがある。
(3)ニクラス・ルーマンについては次夜以降に解説したい。いまのところ社会システム理論の成果としては最も充実している。オートポエティック・システム論もさることながら、「ダブル・コンティンジェンシー」というとびきりの概念もある。今夜の中身に即してなら、『システム理論入門』(新泉社)、『社会システム理論』上下(恒星社厚生閣)、とりわけ『自己言及性について』(国文社)などを“予習”されるといい。ルーマンのわかりやすい全貌なら、連環篇1333夜の『リスク』の訳者の土方透さんが「昼にドライに読むか、夜に背後から読むか」でルーマンがいろいろに見えてくると言っている『ルーマン、学問と自身を語る』(新泉社)がいい。では、次夜以降を、おたのしみに。だんだん編集工学っぽくもなっていくぜよ。