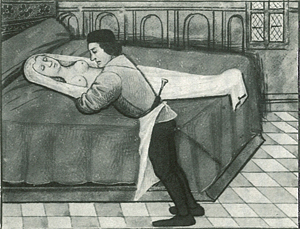「閾」と「間」の政治哲学。
政治意識と美意識の両方をかっさらう生-哲学。
アガンベンはいつも「鍵と鍵穴」のAIDAを見ている。
たとえば、言葉は言葉以前の場所から育つ。
ポルノグラフィは神聖で犯せないものを犯す。
カリカチュアは付与と剥奪の両義性をもつ。
そういう見方をするアガンベンが、
言葉の鍵とイメージの鍵穴の間隙に介入した。
スタンツェとは、多様なイメージが通過する部屋のことだ。
ベンヤミンのパッサージュが
意識と表象のあいだにまで及んだ場所のことである。
この時代、スタンツェが足りなすぎる。
一九七七、八年に観たのだと憶うのだが、マーティン・スコセッシの《タクシー・ドライバー》は臓腑のどこかに何かがぐにょりと移植されるような映画だった。ロバート・デ・ニーロの演技が卓抜なせいだろうと思ったが、あとあとポール・シュレイダーの脚本やスコセッシの編集演出力に何度も感服することになった。
ベトナム戦争帰りの元海兵隊員と称する主人公トラヴィス・ビックルは、戦争の後遺症とおぼしき不眠に悩まされて定職につくことができず、タクシー・ドライバーの日々を送っている。社交性がなく、同僚たちからは「守銭奴」と仇名され、自身も暇さえあればポルノ映画に通っているのだが、マンハッタンを流すたびに麻薬と性に溺れる若者たちに腹を立てるようになった。
そのうち上院議員の選挙事務所に勤めるベッツィ(シビル・シェパード)にホの字になるのだが、ポルノ映画館に連れていったところで激昂され、別れる。荒んだ気分になっている夜、暴行を受けた少女(ジョディ・フォスター)がタクシーに乗ってくる。ヒモらしき男が少女を連れ戻していったとき、トラヴィスの「弁」が外れた。拳銃を入手し、射撃訓練をし、来たるべき日の復讐に備えるのである。少女に再会したのに、少女は売春から逃げられない身だったのだ。
こうして暴発がおこる。モヒカンにサングラスの出立ちとなったトラヴィスは上院議員の射殺に向かい失敗し、その夜に少女のヒモたちの巣窟で拳銃をぶっぱなし、売春宿の客たちも射殺する。トラヴィスも銃弾を受けて重傷を負った。マスコミはトラヴィスを一人の少女を裏社会から救ったヒーローとして持ち上げるのだが、トラヴィスの薄気味悪い笑いはなくなっていない。
ジョルジョ・アガンベンを読んだとき、ぼくは《タクシー・ドライバー》をまるまる思い出していた。
アガンベンは「閾」と「間」の政治哲学を潜走しつづけていた。それは政治意識と美意識の両方をかっさらう生-哲学の漂泊なのである。その漂泊の闇を運転するタクシー・ドライバーなのだ。アガンベンはときどきではなくて、いつもそういう「鍵と鍵穴」のあいだを見ている。たとえば、言葉は言葉以前の場所から育つもので、ポルノグラフィは神聖で犯せないものを犯すものであり、カリカチュアは付与と剥奪の両義性をもつということを指摘する。
そういう見方をするアガンベンが、言葉の鍵とイメージの鍵穴の間隙に介入した。それが『スタンツェ』だ。スタンツェとは、多様なイメージが通過する部屋のことだ。ベンヤミンのパサージュが意識と表象のあいだにまで及んだ場所のことである。この時代、スタンツェが足りなすぎる。
たいへん口はばったいからすぐあとで取り消すが、ジョルジョ・アガンベンを読んでいると、三十年前の自分を感じる。ぼくが一九七〇年代の後半に深みに落ちて夢想していた問題との接し方が次々と蘇ってくる。そのころは手ざわりはありながら自分の言説のつながりとしては適確に指摘できなかったいくつもの輪郭が、次々に暗示的に串刺しにされていくのだ。
アガンベンはいつも問題の輪郭とともにその凹んだ核心を、つまりは凸と凹や正と負を一緒に指摘するから、それがかつてのぼくの凹んだ手ざわりのエッジに次々に触れるので、よけいに奇妙な快感があるのだろう。こんなことをいえば、ぼくがアガンベンに似た問題意識を三十代前半でもっていたかのように映るかもしれないが、ちょっとはそうだとも、とうていアガンベンのように切り結びなんてできなかったとも言える。まあやっぱり、これは口はばったい。
アガンベンを読んで、「うんうん、わかった、わかった」なのではなくて、そういうふうに考えようとした自分がそこで言述されていくような感じなのである。だから「ふうん、わかった」とも「うん、そうに決まっている」というものでもない。「奥が疼いている」というものだ。準既視感とでもいうべき読中感が、アガンベンのやや衒学的な文章とともに本からぼくの記憶のクローゼットに引っ越してきて、点火された爆竹のように蘇るといえばいいだろうか。
なぜそうなるか、どうしてそうさせるのかということが、きっとアガンベンの思想の最も重要なところだから、それについては多少のことをあとでふれるけれど、ともかくもアガンベンによって、ぼくの三十代前半に疼いていた問題意識は初めて輪郭と核心をもてたのだ。
もうひとつ、あらかじめ言っておきたいことがある。それはアガンベンの問題意識やその表明には官能的なところがあるということ、エロスの根源を衝くようなところがあるということ、わかりやすくいえば助平が存在学的に疼いているところがあって、それがすばらしいのである。助平を政治哲学や社会学にするのはちょっとややこしくなるはずなのだが、アガンベンはそこを避けないで、漂わせる。そこがうまくて憎いのだ。
アガンベンを最初に読んだのは上村忠男が訳した『幼児期と歴史』(二〇〇七 岩波書店)だった。この本はインファンティア(幼児期)という概念と動向をめぐっているのだが、アガンベンはそれを「いまだ言語活動をもたない状態」というふうに捉えて、しかもそれを決して「言葉を語りはじめる以前の心的状態」とみなしはなかった。これがすばらしい見方だった。
インファンティアとは非言語的ではあるが、言語がそこを前提として成立していくような「埒」のことである。閾値の「閾」がインファンティアなのだ。そこは穿たれた「場所」で、言葉はその穿たれた非言語的なところから、なんらかの新たな衝動をえて言語的なものに向かって生じる。だから経験を語るのも、歴史を語るのも、美術表現にいたるのも、そもそもがインファンティアに発し、インファンティアに根づいていると考えられる。
そういうインファンティアを無視して言語や経験や歴史を論じるのはおかしいと、アガンベンは指摘した。
このような見方は、ぼくが三十代の前半に考えていた「意味は場所と表象のあいだにあるはずだ」という問題意識と微妙に共振ビブラートしていて、どきどきした。アジア古代の言語哲学者バルトリハリや空海なら、このインファンティア的なるものを「スポータ」とか「五大の風気」と言ったろう。
『幼児期と歴史』の構成には六本目に「ある雑誌のための綱領」という論文が収録されていた。これはアガンベンがイタロ・カルヴィーノとクラウディオ・ルガフィオーリと新たな雑誌をつくろうとしていたときの構想骨子のようなもので、これまたぼくにはぴったりだった。
一九七四年から二、三年のあいだ、アガンベンはカルヴィーノらと語らって新雑誌を計画する。残念ながら実現はしなかったようなのだが、そのコンセプトはかれらが「イタリアン・カテゴリー」と名付けた二項対比的な概念模様を、その雑誌で新たに再編集してしまおうというものだった。たとえばルガフィオーリは「建築/優美」の、カルヴィーノは「速度/軽妙」の、アガンベンは「権利/被造物」などの対概念の再編集にとりくんだという。
アガンベンは一九四二年のローマ生まれで、ローマ大学では政治思想にとりくんで、シモーヌ・ヴェイユを卒論にした。その後はヴァールブルク研究所の所員、パリ国際哲学学院をへて、ヴェネツィア建築大学の美学教授やヴェローナ大学の教授などをしている。ぼくの二つ年上になる。だからアガンベンらが新雑誌を構想しているときは、ぼくが「遊」の第Ⅱ期にとりかかり、「化学幻想/神道」「音界/生命束」「世界模型/亜時間」といった、一対の〝脱構築〟を好き勝手に編集していたころにあたる。そんなことも手伝って、ひどく近しいものを感じたのである。それにしても、その雑誌、ぜひ見てみたかった。

左より「遊」第2期 化学幻想・神道、音界・生命束、世界模型・亜時間
次に読んだのは不思議なタイトルの『中味のない人間』(二〇〇二 人文書院)だった。アガンベン二八歳のときの驚くべき処女作で、印象的なことをいえばベンヤミンがいっぱい、ポイエーシスとプラクシスの関係がいっぱい、芸術本質論がいっぱい、といった野心的著作である。
表題の「中味のない人間」とは芸術家、アーティストのことをいう。なぜアーティストに中味がないのかといえば、マルセル・デュシャンを引くまでもなく、芸術の本質は芸術自己を否定することだから、アーティストが自己弁明や自己延命的解釈をしているようでは、その本質的否定性すら失うことになり、それよりも中味なんぞをかなぐり捨てたほうがいいからだ。
このような見解は現代思想史的にはすぐにアドルノの「否定的弁証法」との近い関連を思わせるけれど、そして実際にもアガンベンはアドルノに多大な影響を与えたベンヤミンにこそ全面依拠するのだが、この本ではそのことを「ポイエーシス」(生-産)と「プラクシス」(行-為)のあいだの創発的間隙に向かう芸術の意志の問題というふうに扱っている。創発的間隙というところが、助平でいい。
ポイエーシスとプラクシスは、テオリアとともに編集工学とその実践のための基本の基本においてきた土台の考え方だ。むろんアリストテレスから借りてきた。アガンベンはそれをベンヤミン=アドルノふうに動かす気になったようだけれど、これに関してはぼくはまったく思いつかなかった。
ところで、この本には訳者の一人でもある岡田温司の長い巻末解説がのっていて、これが充実していた。岡田さんは千夜千冊ではすでに『マグダラのマリア』(中公新書)で登場している英明な美術史家だけれど、アガンベンを論ずるにも最もふさわしい視野と読解力と深さをもっているとも見受けられた。いや、『幼児期と歴史』の上村忠男の解説もよかったのだが、岡田温司はアガンベンに全面参入している。
ついでは『涜神』(二〇〇五 月曜社)を読んだ。ゲニウスとポルノグラフィについて書いていて、これもすこぶる明快だった。
ゲニウスというのは「ゲニウス・ロキ」の、あのゲニウス(genius)だが、そもそもは古代ローマで生誕とともに各人を支配する神のことで、ふつうなら守護神という意味になる。しかし、アガンベンが解いてみせるゲニウスは精神性との対比において語られるゲニウスなのである。
アガンベンによれば、精神性とは次のようなものをいう。「精神性とは、何よりもまずもっては、個人化された存在が完全には個人化されてはおらず、個人化されていない現実の力をいくらかまだ帯びているという事実についての、そして、この現実の力を保存するだけでなく、尊敬し、なんらかの仕方で自らの負債を引き受けるようにして引き受けるべきであるという事実についての、このような意識のことである」。
それに対して、ゲニウスはたんなる精神なのではない。「わたしたちのなかの非個人的なものすべてがゲニウス的なのである」。血液を送り、筋肉を緊張させる潜勢力のすべてがゲニウスなのだ。このようにゲニウスを捉えるのは、言語能力を欠いたインファンティアこそが言語の起源であるという見方とおおいに呼応する。すばらしい。
ポルノグラフィについては、一度、千夜千冊で何かの本を選んでゆっくり議論したいと思っているのだが(たとえばオーギュスト・ブランキとかマリオ・プラーツとか?)、アガンベンのここでの議論はたいへん端的なもので、ポルノグラフィとは「神聖を汚すことのできないもの」をどのように汚すのかという、その一点の「あいだ」に生じるものだというふうになっている。とくにアガンベン得意の「ホモ・サケル」を例に出しての快刀乱麻は、さすがに説得力がある。
ホモ・サケルというのは、ローマの古法に登場するもので、誰もが殺人罪に問われることなく殺害可能で、しかも神に犠牲として供するのは不可能な聖的な存在のことをいう。たとえば、ダニエル・デフォーが描いたモル・フランダーズ、アベ・プレヴォーが描いたマノン・レスコー、プロスペル・メリメが描いたカルメンである。いや、娼婦ばかりのことではない。ベンヤミンがいう「剥き出しの生」やカール・シュミットのいう「例外者」のすべてが含まれる。
この例外的な剥き出しの生に、ポルノグラフィの本質があるというのがアガンベンの見方なのである。これまた助平な存在学をゆさぶっていて、すばらしい。
こうして本書『スタンツェ』を読んだという順番だったのだが、アガンベンの著作順のほうは、さっきも書いたように『中味のない人間』(一九七〇)が二八歳のときの早熟の処女作で、ぼくが読んでいないものを含め、以降、『スタンツェ』(一九七七)、『幼児期と歴史』(一九七九)、『言葉と死』(一九八二)、『散文の理念』(一九八五)、『来たるべき共同体』(一九九〇)、『バーテルビー、創造の公式』(一九九三)、『ホモ・サケル』(一九九五)、『アウシュヴィッツの残りもの』(一九九八)、『涜神』(二〇〇五)というふうに続く。
こういうことなので、ぼくはアガンベンをでたらめな順でジグザグに読んできたわけで、これではアガンベンの思索にほとんど沿ってはいないということになるのだが、しかしそんなことより、何を読んでも、アガンベンはベンヤミンのパサージュを「生-哲学」のさまざまな場面や概念で費いきっているのが、なんとも官能的で心地よいばかりなのだ。それは『スタンツェ』でも一貫した。
スタンツェはイタリア語の「スタンツァ」(stanza)から派生した用語である。ラファエロの装飾で有名なバチカンの《スタンツァ・デラ・セナトゥラ(署名の間)》《スタンツァ・デリオドロ(ヘリオドロスの間)》《スタンツァ・デリンチェンディオ(火炎の間)》などの、あのスタンツァだ。ダンテが『俗語詩論』に説明しているところによると、「あらゆる技法を収容するに足る小部屋もしくは容器」のことをいう。ダンテは「カンツォーネ」があらゆる詩想のふところを意味するように、スタンツァはすべての技法のふところだと解した。
アガンベンもこれに倣って、イタリア語のスタンツァを「部屋」「すまい」であるとともに、「詩節」というふうにも、また技法のための「場=トポス」というふうにも解釈している。しかし、たんなる場所や容器なのではない。スタンツァはヨーロッパの多くの表象(ファンタスマ)と欲望と言葉とを収容するところで、そこを横切っていくことがスタンツェなのである。
本書のなかでぼくがとくに同調同期していた文脈は、軽くまとめると、次の三つにわたる。第一には、フェティッシュに関する文脈だ。
フロイトがフェティッシュの起源を、女性(母親)にペニスがないということを幼児が承認できないことから生じるとしたことは、その暴論のわりにはよく知られている。このフロイト説に従うと、フェティッシュはすべてペニスの代用品だということになる。しかしアガンベンはフロイトのフェティッシュ代用品説をほったらかしにして、美術や言葉におけるフェティッシュが、ミケランジェロからマラルメにいたるまで、もっぱらメタファー(暗喩)のふくらみのなかで、とりわけメトニミー(換喩)やシネクドキ(提喩)の技法をもっていることに注目し、そこには「否定的参照」とでもいうべき未完成な〝母のペニス〟があらわれていると見抜いた。ペニスの不在でも代用でもなく、そこには〝母のペニス〟が新たなフェティッシュとして生まれていたというのだ。
ついでアガンベンが目をとめるのは、リルケとマルクスとボードレールのフェティッシュである。
リルケは、かつての父の時代の家や噴水や外套や衣服が、それぞれ「なんでもしまいこめる懐かしい壼」のようなものだったのに、アメリカ文化がヨーロッパに押し寄せるようになって、すべてが均一で空虚で、うわべだけのものになっているということを嘆く。マルクスは『資本論』の第一章第四節で、労働の成果が「物品の外観」に転化して、そこに資本幻想が生じるようになるのは、商品が物神扱いされているせいだとみなした。ボードレールは一八五五年のパリ万博を思い出して、あのときすべての商品がシンボルを放って、それぞれをつなげようとしていたと綴った。
このリルケとマルクスとボードレールは、まったく同じことを言っている。同じスタンツェをしている。「商品の物神性が世界を犯した」ということを表明しているのである。アガンベンはそこに加えて、芸術もまた使用価値と交換価値を区分けして、デュシャンとポップアート以降、中味を空洞化することに気が付いたのだと見定めた。
ちなみにベンヤミンはとっくの昔に、このような現象を「アウラの失墜」というふうに指摘した。この点に関してはアガンベンよりもベンヤミンが圧倒的な先見性をもっていた。
第二に感心した文脈は、「像」(イメージ)をめぐるもので、アガンベンがいくつもの中世の画像や文芸を検討して、そもそも恋愛や愛情の発生は、目の前の実在(超越者や異性)の存在をめぐってのみ高まるものではなくて、描かれた像に出会ったり、憧れの像を描こうとしたりしてからの、はなはだメディア的で、媒介的なことではないかとみなしたことだ。
例題にもちだされたのはクレマン・マロの『薔薇物語』の挿絵などで、そのピュグマリオンの描き方から、アガンベンはファンタスマ(幻想的表象像)こそが恋愛と非恋愛のあいだの作用を担っているのだと喝破した。

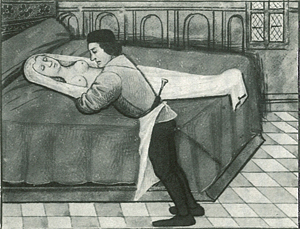
「ピュグマリオンの物語」パリ 国立図書館より(上)
「ピュグマリオンと彫像」オックスフォード ボードリアン図書館より(下)
アガンベンがヴァールブルク研究所にぞっこんであることを知れば、このような見方をたやすくできそうだという見当はつく。まして、このようなことは、マスメディア時代のスターやタレントの画像収集癖や〝追っかけ〟にあからさまに顕著になっていることで、とくに力説するほどのことでもないようにも思える。
けれどもアガンベンはそこにばかりとどまらない。ぼくが感心するのはここからで、アガンベンは、外形や姿形というものは、すなわちペルソナ=パーソナリティは、またすなわちフィギュア=プロフィールは、それが剥ぎ取られないことをもって成立しているのだから、逆にそれを剥ぎ取るという意図を観照者や相手や芸術家が内面にもったとき、まさにそのときに、恋愛や芸術が成立してくるはずであるというふうに切り返してもみせた。
これはさきほどのべたポルノグラフィ論にもつながるもので、すこぶるおもしろい。本書では、さらに「鏡の前のエロス」としてそのことを、ジャック・ラカンの鏡像理論にさえあてはまる理屈に仕立ててみせていた。
第三の感心はカリカチュアをめぐる。ぼくがカリカチュアに興味をもったのは、グランヴィルのイラストレーションを調べてからのことで、そのきっかけは杉浦康平さんと『ヴィジュアルコミュニケーション』(一九七六 講談社 「世界のグラフィックデザイン1」)にグランヴィルをとりあげたことにあった。
このとき直観的ではあったが、カリカチュアの本質が生物的分化の歴史を背景とするメタモルフォーズ(変容)にあると思った。それがどこかから人間の表現の歴史に吹き出してきたもの、それがカリカチュアなのである。だから、その変容は輪郭線にもシンボルの扱いにも意味の編集にもかかわっている。そう、感じたのだ。

グランヴィル
「フーリエの体系」
『もうひとつの世界』より
本書の用語でいえばカリカチュアの歴史は、アルタミラの洞窟このかた、縄文土器このかた、「シグニフィカツィオーネ」(形象的意味変容)のプロセス全部にかかわっているということだ。シグニフィカツィオーネは形象と意味がつながっている。 それを古風に「あらわれ」などと言ってもいいだろう。
今日の記号学では、「意味すること」と「表現すること」と「隠蔽すること」は必ずしもうまく扱われていない。大半がソシュール風に「シニフィアンの上にシニフィエという図式がのっている」(S/s)というふうに処理される。これでは秩序を二つも立てているようなもので、この二つの秩序のあいだの壁を通過するものがない。とくに寓意が動いていない。
しかしながら、そもそも寓意(アレゴリー)とはどの秩序にも限定して属さないものをあらわしていた。その寓意のシグニフィカツィオーネがイラストレイティブになったものがカリカチュアなのである。そうだとすると、われわれは何かの徴候を認めようとすれば、まずは寓意もしくはカリカチュアから入っていくということなのである。あとからカリカチュアがつくられたわけではないということなのだ。
十六世紀から十七世紀にかけて、ヨーロッパの社会文化はヘルダーの言うところの「エンブレムの時代」になっていた。何が何でもがフィギュアであってプロフィールでなければならなくなったのだ。
それはそれでよかったのだけれど、この時期はヨーロッパが合理科学を確立する時期にも当たっていたため、エンブレムのいくつかは科学のシンボルとなり、そこに入らなかったものたちはすべて怪しいエンブレムのほうに分割されることになった。こうして科学と錬金術が分かれ、芸術と民俗が分離され、有意性と曖昧性が分断された。
アガンベンはこれらを奪還しようとしている。ぼくが「遊」の第Ⅱ期でやろうとしたことも、この分断の撤回だった。ただし、その作業をカリカチュアに求めたあたり、足場にミシェル・フーコーの先駆的作業『言葉と物』や『知の考古学』などがあるとはいえ、やっぱりすばらしい。
以上が、この二~三年にアガンベンを読んだ感想の一端である。ずいぶん急いで書いたけれど、言いたい感想はあらかた述べた。
いま、日本ではアガンベンを「生-政治学」の覇者の一人として評価する傾向のほうが強く、またアントニオ・ネグリを批判できる唯一の論客と期待する向きも少なくないのだが、ぼくはぼくなりに、ポイエーシスとプラクシスの「あいだ」を語れる凄腕として読んできた。このこと、以上の感想の断片に如実に吐露されていると思う。
ネグリとアガンベンをむりやり区分しても仕方ない。存在を「ゾーエー」(すべての生命に共通する生きているという事実性)ではなく、「ビオス」(しかるべき個別知や共同知にいるという生き方)として掴まえるという思想なら、とっくにハンナ・アレントに提唱されていて、それがネグリにもアガンベンにも共通しているものなのだから、そこから政治を権力に結びつけるか、政治を美や趣向に結びつけるかというところが、二人の思想の方向のちがいなのである。
それよりネグリとアガンベンを串刺しにしたほうがいい。あるいは両睨みしたほうがいい。しかし、そういうことよりも、ぼくにとってアガンベンがおもしろいのはどんな問題の議論にも「場」や「あいだ」や「閾値」を見ているところなのだ。それは思想というより方法的編集力のおもしろさなのである。とくに「否定の方法」や「負の方法」に対するアガンベンの絶対的ともいうべき確信は、ぼくを何度もよろこばせる。
とりあえず今夜は、そのようなアガンベンの方法については、編集工学っぽく、そしてちょっと助平に「結合の奥義」(mysterium coniunctionis)の蘇生の仕方を知っている意味の外科医だというふうにしておきたい。