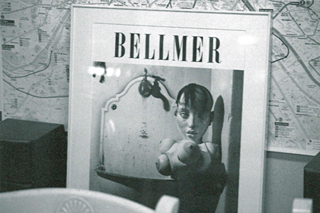土偶や埴輪は形代だった。
雛人形は「撫でもの」だった。
われわれは、いつも人形をそばに置きたがってきた。
ときにその人形に魂があるとさえ思ってきた。
それなら傀儡子は? 浄瑠璃人形は? セルロイド人形は?
ジュサブロー人形は? 四谷シモンの人形は?
フィギュアは? サイボットは? 球体関節人形は?
久々に読んで見させる人形記が本になった。
ひとときを、真夏の夜の夢に遊ばれたい。
雑誌の「なごみ」に連載されているときも見たり読んだりしていたが、あらためて間村俊一のデザインで一冊になってみると格別にいとおしいものになっていた。
青い目のセルロイドの人形、林駒夫の桐塑人形、伏見人形、四谷シモンの人形、流し雛、ジュサブロー人形、土偶、浄瑠璃人形、フィギュア、夢二人形、松本喜三郎の生人形、霊鑑寺の御所人形、ムットーニ人形、結城座のあやつり人形‥‥。都合18種18形の人形たち。
詩人の佐々木幹郎がこれらの人形たちに接する文章は丁寧で、その人形たちに接することのできない読者を導く先をよくよく心得てもいて、ぞんぶんに読ませる。衒いのない名文だ。「あとがき」には、この連載の仕事を通して「ひとがた」への旅が始まったことが静かに綴られている。ぼくもある意味では、ずっと日本の形代(かたしろ)を考えてきたようなところがあった。しかし日本の形代は、追いこんでいけばいくほど、日本の根元に蟠る「稜威」(いつ)にもつながってくるので、要注意なのである。
写真の大西成明君は、かつて「遊」をやっていた私をたずねて工作舎にやってきた青年で、当時は排水やどぶ川ばかり撮っていた。森永純の影響だった。その後、動物を接写するあたりから変貌して、かつては食らいつく目だけがギラギラしていたのだが、そこに、いつしか向こう側へさしかかるような奥行きが出てきた。その成果が『象の耳』で日本写真協会の新人賞に、『病院の時代』では講談社出版文化賞になった。
本書の人形の写真は、読者に作家の紹介も兼ねなければいけないので難しい撮影だったろうが、よく撮れている。ライティングもうまくなったものだ。
宇野千代(66夜)の『人形師天狗屋久吉』から始まっているのが、いい。昭和16年に、お千代さんが嶋中雄作の家で出会った阿波の浄瑠璃人形「阿波のお弓」に瞠目し、その作者である吉岡久吉に会いにいったのである。名人は天狗久とよばれていた。当時85歳になっていた。

鄙びた手織縞の着物を着た『阿波の鳴門』のお弓

宇野千代の書斎机
この小説はぼくも読んだが、天狗屋久吉の一人語りになっている。「人形をつくってます間が、神さまを拝うでおるような気持ちと言うのでござりましょうぞ。わが技の及ばんところが神さまでござります」という口調だ。
文楽の人形は動かしてナンボというものだ。名人の操りの手にかかれば、これほどものすごく妖しくなるものはない。しかも「かしら」は男の人形は眉も目も口元も動くようになっているが、女の人形は目だけが動く。そこを人形遣いが反らせたり、伏せさせたり。
いや、文楽人形には必ず浄瑠璃の言葉も加わっている。言葉のない人形は少なくとも文楽においては人形ではないのである。文楽人形を見るたび、ぼくにはいつも太夫の絞り出した声も聞こえる。お千代さんも、だからこそ天狗屋久吉の一人語りをもって浄瑠璃に代えたのであろう。
同じ「あやつり」でも、これを糸で操れば傀儡子(くぐつ)あるいはマリオネットである。大江匡房の『傀儡子記』では11世紀には街道筋を多くの傀儡師たちが首から下げた箱の上で小さな人形を操っていた。傀儡師の出自は西宮神社の神人(じにん)との縁が深かった。
いま、このような操り人形を代表しているのは結城座である。江戸時代から三百年以上も続いている一座で、8代目や9代目のあたりで「写し絵」と結びついた。当時、隅田川の屋形船に近づいて障子に蝋燭幻燈を映し出してみせる両川亭船遊(りょうせんてい・せんゆう)という男がいて、この「写し絵」が江戸の結城座の舞台にもとりいれられたのである。これを「風呂」とも言った。
以来、「操り」と「風呂」は結城座では一体になってきた。いまは12代目の結城孫三郎が率いているのだが、12代目は同時に両川亭船遊3代目にもあたる。

12代目結城孫三郎の「糸あやつり」と「写し絵」のドッキング

あやつり糸の僅かな動きが表情をつりだす
ぼくが人形というものに衝撃を受けたのは、ひとつはヴェリエ・ド・リラダン(953夜)の『未来のイヴ』の中の自動人形アダリーを知ったときで、もうひとつがハンス・ベルメールの関節人形とそのドローイングに出会ったときだった。とくにベルメールの人形は、ここに世の中の内なるエロスとタナトスが息を顰めて組み合わされているのではないかというほどの、おおげさなほどの“秘密の呼吸”を感じた。
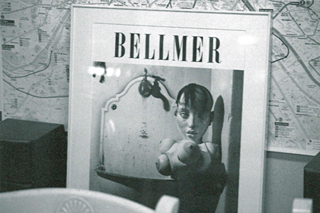
ハンス・ベルメールの間接人形のポスター
同じころかどうかはわからないが、やはりハンス・ベルメールに衝撃を受けていたのが四谷シモンだった。ぼくとは同い歳である。それまで少年期からぬいぐるみ人形作りをしてきたシモンは、ベルメールの人形写真のたった一枚を見て、転向した。「ベルメールの人形にはテーマがない。人形そのものになっている。それがぎくしゃく動く」。と、そのころ感じたそうだ。しかしベルメール人形を作ればいいのか迷っていた。唐十郎の状況劇場で一番の人気をとっていたシモンはしばらく“女形”をやってみせたのち、1971年秋にそこから風のように去ると、ベルメールに追随することなくシモンの人形を作ることに専念する。
1972年、10人の写真家たちがシモンを撮った『引力のまたたき』展が開かれた。その会場に等身大の人形が展示されていた。いま、高橋睦郎(344夜)さんのところに収まった『ドイツの少年』だ。ペニスが直立している。ベルメールの『道徳小論』にも少女の股間からペニスが突き出ているイメージが語られていたものだ。

四谷シモン「少年」

「少年」と「少女」の間に横たわる四谷シモン
その昔、澁澤龍彦に『人形愛序説』(第三文明社)という本があった。ベルメールの人形を、レオノール・フィニやジャック・エロルドなどともに「危険な黒いエロティシズム」と書いていた。しかしシモンの人形を見ていると、そういう澁澤哲学をすっかり乗りこえている。
それかあらぬか最近のシモンは「ひんやりとした人形」をめざしているのだという。定まった位置にいず、確固としたものもなく、何者でもないものであるような人形。それがシモン人形である。
ハンス・ベルメールと四谷シモンに衝撃を受けたあと、順番でいうなら辻村ジュサブローの人形に驚いたのだと憶う。肌が縮緬で作られていて、ともかく衣裳が凝っていた。その人形が出てくるだけで物語が動いた。
1973年から放映された連続テレビ人形劇『八犬伝』で一般には知られたが、その前から寺山修司(413夜)とも唐十郎とも組んで、“芝居ができる人形的衣裳”を作っていた。とくに蜷川幸雄と組んだ仕掛け意匠はものすごく、築地本願寺の境内をつかった『オイディプス王』(657夜)の夜は妖しい美しい悪夢のごとくに忘れがたいものだった(1986)。
ジュサブローさんとはときどきしかお目にかからない。『アート・ジャパネスク』で三浦屋の意匠を作ってもらい、『色っぽい人々』(淡交社)で対談をし、のちにはときどき人形町のジュサブロー館を覗かせてもらっている。「あたしは満州が原点です。あの国が滅んだときに、あたしが生まれたようなものです」が、ジュサブローさんの口癖である。もうひとつの口癖は「喋らない、息しない、聞こえない、目が見えない。すべてない世界で嘘をついているのが人形です」というもの。

嘘と幻の女
23歳のときに藤浪小道具に入って、歌舞伎の小道具作りを学んだ。このとき縮緬張りの手法を知った。しかしその縮緬だけが素肌なのではない。ジュサブロー人形では縮緬張りと衣裳との両方が素肌なのである。それはボキャブラリーでできているのだという。土方巽(976夜)が、踊りは体と衣と光のボキャブラリーでできていると言ったことに呼応する。
ぼくの少年時代の人形といえば、雛人形と五月人形とセルロイド人形である。セルロイド人形は、妹が人形派ではなかったので、家には小さなフランス人形一体と途中から欠けてしまったキューピー人形くらいしかなかったのだが、そのかわり野口雨情(700夜)の『青い目の人形』にはぞっこんだった。本居長与の作曲だ。
青い目をしたお人形は アメリカ生まれのセルロイド
日本の港についたとき いっぱい涙を浮かべてた
「わたしは言葉がわからない 迷い子になったらなんとしょう」
やさしい日本の嬢ちゃんよ なかよく遊んでやっとくれ
なかよく遊んでやっとくれ

青い目の人形(横浜市立西前小学校蔵)
ところが本書を読んで知ったのだが、「アメリカ生まれの青い目のセルロイド人形」というのは事実とはちがっているらしい。
大正末期、アメリカで日本人排斥運動が高まって排日移民法案が通った。これに心を痛めた親日家の宣教師シドニー・ギューリックが、日米親善のために270万人の寄付をもとに12739体の「青い目の人形」を日本に送った。ほとんどがアメリカ製のコンポジション・ドールというもので、セルロイドではなく木屑や混成品を化学糊でまぜてつくった人形だった。これを日本の少女たちが雛祭りを迎えたときの雛壇に飾ってもらおうという趣旨だ。ギューリックは20年ほど日本に住んでいた。
日本側でこれを受け入れたのは晩年の渋沢栄一である。渋沢はさっそく日本国際児童親善会というものを設立して、全国の幼稚園・小学校、および満州・台湾にこれを贈るように手配する一方、ギューリックに感謝して58体の市松人形をアメリカに贈った。これを「答礼人形」というらしい。

青い目の「マリーン」(左)と「ポリーン」(右)
だから、「青い目の人形」はセルロイド製ではなかったのである。雨情らしい勘ちがいだが、しかし雨情と本居は同じ年にさらに『赤い靴』もつくって、横浜の波止場から異人さんに連れられて船に乗った少女を歌った。その3番には「青い目になっちゃって、異人さんのお国にいるんだろう」とある。
大正昭和の日本では、「青い目」とはすべからく異人の国の、異人の言葉しか解さない人形のことなのである。
本書のなかで最も美しい写真は、林駒夫の桐塑人形「神ノ坐ス森」だ。佐々木幹郎もこの人形を見て電撃が走ったと書いている。

桐塑人形「神ノ坐ス森」
林は昭和11年に割烹「赤尾屋」の家に生まれた。19歳のときに人形師の面屋庄三に入門し、27歳で能面師の北沢如意に学んだ。やがて桐塑(とうそ)の技法を極め、平成14年には人間国宝ともなるのだが、それよりも作り出された人形が神さびている。
おととし、日本橋高島屋のギャラリーで「雅の刻」という林駒夫の展覧会が開かれていた。さっそく覗きに行ってみたが、観覧者たちが息を詰めて見ているのが怖いほどだった。なかに、お能の『斑女』をモチーフにした『松聲』があって、松を渡る風の音を聞いている。なんともいえない絶佳の風情。

桐塑人形「松聲」
林は「人形は情緒だ」と言い切っている。その情緒が「型」になるのだとも言う。それには京都になりきっていくことが大事だと思っている。「京都でなけりゃ、しょうがないんですよ。ぼくのすべてが京都で、ぼくの京都が人形を作る」。
たしかに京都は情緒である。その情緒は岡潔(947夜)ではないが、「春泥」(しゅんでい)のようなものだ。けれども京都に住んでいるからといって春泥にはなれない。たとえば最近の舞妓や有名割烹や繁華街には春泥がない。そこをあえて京都であろうとすれば、「奥」へ行くしかない。林駒夫はかなり以前にそこに気がついたのだろう。
そういう京都の「奥」は、よく見ればわかることだが、小さな「細工」と透かれた「好み」で成り立っている。本書には霊鑑寺の御所人形も掲載されているが、かつて御所には「お細工どころ」というものがあり、そこでは「お好み布」というものが織られていた。人形用の小さなものたちを作っていたわけである。

「万勢伊さん」(ひだり)と「おたけさん」
手前に小さな這い這い人形
この小さな細工の好みから、京都の「奥」はあらわれてくる。ちなみに霊鑑寺は後水尾院時代の尼門跡で、「谷の御所」と呼ばれてきたところ。ふつうの観光客は入れないが、ぼくはNHKの「おもかげの国・うつろいの国」の撮影に遣わせてもらった。ここには芥子粒ほども小さな人形もあったのである。
京都に生まれ育ってときどき奈良へ行くと、京都とはかなり異なる「遠い古代」や「閉じない中世」に包まれることをひしひしと感じる。その奈良をできれば「まほろば」とか「万葉の国」と言わないで語りたいと思ってきたが、なかなか難しかった。
今年、平城遷都1300年記念事業のひとつとして、荒井正吾知事から3冊シリーズの本を作ってほしいと言われ、そのシリーズタイトルをユーラシアならぬ「ナレーシア」(NARAIA)と名付け、1300年をひとまぎする高速編集構成に挑んでみた。ダブルページに大半のコンテンツを入れて、あえて『NARASIA(ならじあ)』(発行は丸善)とルビをふって、奈良っぽさを出そうともした。ブックデザインは美柑和俊君を起用した。本のほうはすばらしい出来になったと思うけれど、それであらためてわかったことは、奈良の中世・近世が日本人の歴史観のなかに入っていないということだった。

『NARASIA』発行丸善
佐々木幹郎は奈良の生まれである。子供時代は奈良人形で育ったらしい。この人形は、そもそもは興福寺の檜物座(ひものざ)に属する檜物師が春日大社や興福寺に指し物や曲げ物をつくっているうちに派生したもので、江戸時代に入って檜物屋平右衛門が初代の岡野松寿を名のるようになると、「春日有職」としての奈良人形が定着した。
以来、9代目保伯、10代目保久などの名工を生み、幕末明治になってついに森川杜園という名人を輩出した。本書にも『後高砂』という名品が載っている。杜園は根付(ねつけ)も多く、日本の工芸のなかで最も繊細で大胆なアートである根付独特の冴えも見せた。杜園は京都の和事ではなく、奈良の荒事とでもいうものをあらわしたのであったろう。

森川杜園作「後高砂」

森川杜園作『寿老人根付』
本書は最後になってフィギュアと土偶と埴輪が出てくる。フィギュアは大阪の海洋堂の宮脇修一がはやらせたもので、たちまちオタクのあいだに広まり、さらに「食玩」としてスーパーやコンビニのスナック菓子の棚を席巻していった。そうした矢先、村上隆は本書にも登場するボーメ(海洋堂の原型師)と組んで美少女フィギュア「プロジェクト・ココ」を作り、ヴェネチア・ビエンナーレの話題をさらった。
その美少女フィギュアは、いまでは「初音ミク」というボーカロイド(ボーカル・アンドロイド)として有名になった音楽ソフトにまで拡張されている。パソコンに自分で歌詞と音符を打ち込むと、初音ミクがその歌を唄ってくれる。きのう、ケータイ関連で名を挙げているチームラボの猪子寿之君が赤坂にやってきて、ぼくの前で経産省の猛者たちを相手に初音ミクのぶっちぎりのおもしろさを論じていたばかりだったのだが、今日、『人形記』の美少女フィギュアを綴ることになるとは思わなかった。

ボーメ作の美少女フィギュア
しかしボーメは、フィギュアはそのうち時代と社会のなかに埋没していくだろうと見ている。フィギュアは“リアルを壊して作ったリアル”なのだから、ユーザーがリアルになっていけば埋没していくしかないというのだ。
では、土偶や埴輪はどうだったのか。茅野の尖石(とがりいし)縄文考古館の「縄文のヴィーナス」や「仮面の女神」は死者のための驚くべき造形のフィギュアであったけれど、いまなおいっさいの彫塑的人形を凌駕しつづけているのだから、これは格別フィギュアということになるのか。それとも土偶や埴輪もまた、土中に埋まって1000年、2000年をへて今日に蘇っているのだから、ガンダムやエヴァンゲリオンのフィギュアも、これから幾多の星霜を食んで別格イコンとしていつか蘇えるのか。こういうことは、いまこそNARASIAをこめて考えるべきことである。

土偶『縄文のビーナス』(左)と『仮面の女神』(右)
かつて土師師というものがいた。埴輪などを専門に作る職人集団で、いまは近鉄大阪線の「土師(はじ)の里」という駅の近辺に出自した。最初の人形師といっていいだろう。
佐々木幹郎は少年期をすぎると奈良から大阪の河内に移って暮らしたようだ。それもあってか、埴輪をはじめとする土の人形には言い知れぬ畏怖のようなものをもっているとおぼしい。ぼくも似たような畏怖をもっている。人形というよりも、人形師たちその人たちに。
中学時代、ぼくにはいままで他人には説明しにくいので、まったく喋ってこなかった癖があった。寝床に入ると粘土細工をしたくなるという変な癖だ。こっそり油粘土やゴム粘土の束を布団の下に隠しておいて、寝付く前までを好きな動物や機械を作って遊ぶのだ。なぜか、決して机の上では作らなかった。出来上がったものを枕元に並べて、それで眠るためである。それらは寝ているあいだのぼくの守護神だったのである。
そのうちふと、ふつつかな女身を作るようになった。ところが作っていくうちに意外にリアルなものになっていく。さすがにこれを枕元に並べてはおけないので布団に入れて寝たのだが、ある夜にぐにゃりと歪んでしまった。それからこの奇癖が消えた。以来、ぼくはずっと不眠症なのである。人形というもの、みだりに一緒になるものではないのかもしれない。