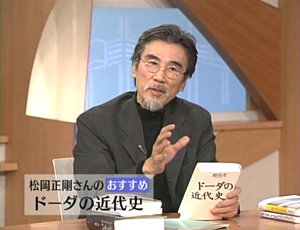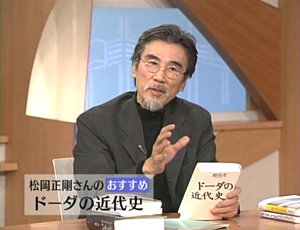これはドーダ? ドーダ、まいったか。
世の中、いろんなドーダが罷り通っている。
説明がつかないことこそ、
ドーダの理論になりやすい。
たとえば尊王攘夷のイデオロギー。
たとえば水戸学の爆発的流行。
たとえば西郷隆盛の不可解な行動。
幕末維新はドーダのオンパレードなのである。
それが中江兆民や頭山満にも及んでいた。
こんなドーダが、いまでもありそうだ。
いいのか日本、ドーダの日本。
先だって、NHKの「週刊ブックレビュー」に出て、この本を「イチオシ本」としてとりあげた。とても短いコメントしか言えない番組なので、たいしたことは言えなかったのだが(この番組に出るのは3回目か4回目なので、そういう事情はわかっていたのだが)、そこまで持ち上げた以上は、「千夜千冊」でも案内しておいたほうがいいだろうと思っての、今夜だ。そういう事情を含めて、つきあっていただきたい(ちなみにあとのイチオシ2冊は、ネグリ&ハートの『マルチチュード』と国立劇場で伝統音楽の再生を手掛けてきた木戸敏郎の『若い古代』。木戸のほうもいつか「千夜千冊」に入れたい本だ)。
で、『ドーダの近代史』であるが、実はぼくは鹿島茂については、あまりよい読者ではなかった。まあ、たいして熱心に読んでこなかったと言ったほうがいい。だいたいぼくは、早稲田のフランス文学科にうっかり入ったときに「これは、しまった!」と思って以来、フランスかぶれやフランス気取りが嫌いなのである。フランス料理も、ミシュランが3つ星をつけた銀座の「ロージェ」で福原義春さんの御馳走にあずかった以外、ほぼ15年ほど食べてはいない。
だから、たとえば澁澤龍彦ですら、長らく敬遠していたものだった。澁澤の文章と澁澤さん本人と親しくなったのは、前にも書いたことだけれど(968夜)、澁澤さんが日本回帰してしばらくしたのち、伊吹山をめぐって二人で想像を逞しうしてからのことだった。
そんなこんなで鹿島茂にもついつい敬遠気味だったのだが、それが、毎月送られてくる「一冊の本」という朝日新聞社の読書小冊子に連載されていた『ドーダの近代史』の第1回目をふと読んで(この「一冊の本」は他誌の版元小冊子にくらべてちょっとデキがいい)、突然に引きこまれた。急に別の幹線を走る列車のレールのほうに跳び移ったという感じだったのだ。

NHK BS2『週間ブックレビュー』に出演
(2007年12月9日 8:00~8:54)
連載は意外に長かった。2003年11月号から今年の2月号まで続いた。だからちゃんと読み続けていたかどうかは怪しいのだが、最初に扱っているテーマの「水戸学」が気になって、つい読んだ。が、やっぱりトビトビに読んでいたようで、今年の7月に単行本になってから、あらためて通読した。
中身は何かというに、「週刊ブックレビュー」でも5分だけ説明したように、幕末近代の日本を席巻した尊王攘夷から征韓論をへて西南の役にいたった「説明しにくい異常」をどのように解釈したらいいのかという、それ自体はまことに重大なテーマになっている。それを歴史学的に解こうというのではない。まるで次々に並ぶ料理に箸をつけながら、その出来具合をあれこれ話題にして座談をたのしむというふうに斬る。
その斬りぐあいを「ドーダ」の超論理で片付けていこうというものなのだが、そのドーダの超論理というのは、べつだん難しいものではない。学問でもないし、高遠なものでもない。「これはドーダ!」「ドーダ、まいったか」というふうに、いつのまにか自身をとりまく状況や思考に自己満足する論理にはまっていくこと、それを持ち出している連中にはドーダの超論理が使われているのじゃないかという、ただそれだけなのだ。
それを鹿島が「陽ドーダ」と「陰ドーダ」、「外ドーダ」と「内ドーダ」などとドーダを切り分けて、水戸学や西郷隆盛や中江兆民や頭山満が、幕末明治に自身の言動を反転させ、しだいに超然としていく様相にあてはめて、これまで説明しがたかった裏歴史をなんとか解読していこうというもの、けっこう読ませた。とくに前半・中盤まではかなりおもしろかった。
さすがに後半はシマリがなくなったけれど、これはドーダの超論理なんぞを持ち出したからには、仕方がない。ドーダが燃え尽きたのだ。
そんなことを言ってもわからないだろうから、幕末近代史の流れにそってかんたんに説明するが、鹿島は、幕末の水戸学や尊王攘夷の思想が政治的ドーダ(その実態は「見えっ張りドーダ」らしい)にはまっていたことを、まずあげる。
水戸学がどういうものかは、997夜の『水戸イデオロギー』のところで詳しく書いたので省略する。鹿島はその水戸学が「貧乏自慢」から発露されたということを、山川菊栄の『覚書 幕末の水戸藩』(岩波文庫)によって気がついた(この本は必読書)。水戸学がまるでオセロ・マジックのように、貧困という状況を逆手にとって日本改革の論理に次々に白黒反転していったのではないかというのだ。
実際にも、水戸藩は三代藩主のときに25万石から35万石への持高の加増を申請して幕府の承認を得るのだが、その見えっ張りがたちまち藩を逼迫させた。いったん窮乏した藩は回復が遅い。それこそ二宮尊徳型の農村改革か九州の藩のように貿易に転じれればいいが、それができないとなるとジリ貧だ。ところが、その貧乏であることをこそ「ドーダ!」と威張る手があったのである。それが水戸学だったのではないかというのが、鹿島の乱暴な推理になる。
かくして藤田幽谷・東湖や会沢正志斎が「貧乏ドーダ」を別のドーダにマジック変法することになるのだが、そのオセロ・ゲームの白黒反転をおこすためには、いったい何をもってくればよいか。
ここで持ち出されたのが尊王攘夷だった。なぜ、水戸藩が尊王攘夷を持ち出せるのか。これを推理するのは難問のはずだが、鹿島には容易な推理になった。さかのぼれば「水戸光圀のドーダ」があったというのだ。
光圀は徳川御三家のひとつとはいえ、中央からはあきらかに外されていた。そこで『大日本史』の編纂を計画して、日本史の基軸そのものを将軍家に代わるものにすることを考える。実際にはそこに日本乞師・朱舜水(460夜)の進言なども加わっていたのだが、本書はそのへんにはふれていない。
光圀はともかく、この自分の計画(これが水戸ドーダのオセロ・ゲーム的原型らしい)にぞっこん惚れて、天皇の歴史に戻した日本史を叙述させることにした。これはさしずめ「天皇ドーダ」の登場である。こういうプレ段階があったうえで、幽谷や東湖の尊王攘夷が水戸ドーダになったというのだ。
いやいや、こんな説明で何か歴史の本質を突いているのかどうか不安になってきたが、それがしかしドーダの理論というものなのである。
まあ、いいか。それで「水戸ドーダ」がどうなっていったかというと、攘夷だけでは外敵理論で終わってしまうので、ここに尊王を持ち出し、その尊王を持ち出すために、仏教をこてんぱんにやっつけることにした。藤田東湖の『回天詩史』には、こんなふうにある。現代語にしてある。
そもそも神皇の道と儒教とはとくに祖先の祭祀を重んじ、これを政教に対応せしめてきた。しかるに、仏教が祭祀権を奪ってからというもの、これが官民のあいだに採用され、政教の分野にも施行されるようにった。
このため神道はわずかに種々の神官に委ねられ、儒教は地位が下がって博士家たちの専業となるにいたった。皇道が衰え、大道が暗くなったのは、ひとえにこの理由による。
まことに勝手な見方だが、半分くらい事実ももりこんでいる。しかし、ここまではまだしも仏教批判によってシーソー的に尊王を持ち上げるという程度の効果だったはずである。
それが東湖から会沢正志斎に時期が移るにしたがって、日本人全体が贅沢に溺れ、外敵におののき、遊興に耽って、ろくな日々をおくっていないから、日本のシステムがおかしくなったのだというような、やたらに議論を広げる視点に変わっていったのである。まるでテレビのコメンテーターがどんな事件もなんでも全国に波及すると言わんばかりのコメントなのだが、しかし、これが水戸の海岸沖に英国船があらわれるという文政7年の事件とだぶってくると、一挙に「外ドーダ」と結びつき、尊王と攘夷はみごとにぴったり重なる表裏一体のカードとなった。
その逆転を高らかに宣言しているのが、正志斎の『新論』である。このように冒頭からドーダを連発した。「謹んで思うに、神国日本は太陽のさしのぼるところ、万物を生成する元気の始まるところであって、日神の御子孫たる天皇が世々皇位につきたもうて永久にかわることのない国柄である。本来おのずから世界の頭首の地位に当たっており、万国を統括する存在である。しかるにいま、西の果ての野蛮なるものどもが、世界の末端に位置する下等の輩でありながら、四方の海をかけめぐり、諸国を蹂躙し、身のほど知らずにも、あえて貴いわが神国を凌駕せんとしている。なんたる驕慢であろうぞ」。
こうなると、すべてはどんでん返しのロジックである。いっさいの正義は尊王につらなるものとなる。ふつうなら、攘夷のために尊王が持ち出されて、挙国一致となるだろうに、ここでは尊王ゆえに攘夷するというドーダの逆転がおこったのだ。
これで幕末の流れは決まった。ここではふれないが、山県有朋が、高杉晋作が、久坂玄瑞が、次から次へとドーダを振りかざすようになっていった。鹿島はこれらの“志士”たちを1ダースほど並べ、かれらに共通するのは「仲間からの人気がない連中」だったというふうに、まとめている。
次に、本書が持ち出すのは、西郷隆盛(1167夜)だった。これはいかに鹿島のドーダ理論でもきっと手にあまるだろうと思っていたのだが、かなり苦しまぎれではあったものの、西郷にもドーダ人間の看板をおしつけてしまった。
すでに「千夜千冊」ではいろいろのところに書いてきたので省略するが、鹿島が着目したのはお由良騒動を含む一連の薩摩藩の情勢変化のプロセスだった(364夜『南国太平記』参照)。島津斉彬がお由良騒動のあとに頭角をあらわし、島津久光によって暗殺まがいの死を迎えたそのプロセスで、西郷が久光に睨まれ、錦江湾に月照とともに投身自殺をはかったというあの事件、それが自分だけ助かって奄美大島に流され、それがふたたび戻されて幕末のリトマス試験紙の鍵を握るお役目になっていったというあの経緯、それにもかかわらずまたまた久光と激突して沖永良部島に流されたのち、今度は幕閣との交渉のために呼び戻されて勝海舟とわたりあい、ついに官軍の総大将になってしまったというあの逆転劇を、それぞれ「逆転ドーダ」で説明してしまうのだ。
そこを鹿島は、「陰ドーダ」的な西郷が、あにはからんや「陽ドーダ」に転じざるをえなかった不幸と矜持として扱っていく。いってみれば西郷をマキャベリストとして扱ったのだ。
わかりやすくいえば、幕府勢力がセリーグなのだ。すでに読売ジャイアンツの威光は衰えている。そこで一橋慶喜という、これまではアンチ巨人だった阪神の監督のような男を筆頭にして、なんとかパリーグ勢力にぶつかろうとする。
パリーグは薩長土肥だ。トップは天皇や公家のソフトバンクか西武あたりだが、実力は日ハムあたりになっている。その象徴が西郷である。
しかし、これではセリーグは必敗だ。そこでナベツネのような老獪な知恵袋が出てきて、ここから先は1リーグ制にしようじゃないかと言った。天皇をコミッショナーにすえて、全員総当たりで痛快な日本挙国一致ゲームをしようじゃないかというのである。
ところがここで孝明天皇が崩御した。岩倉具視あたりが毒殺したという説もあるけれど(1091夜『幕末の天皇』参照)、その真偽はべつとして、これでシナリオが狂ってきた。しかし、1リーグ制はそのままだ。そこで西郷がセパ両方の代表にさせられたというわけである。
しかし、これではナベツネの目論みのままになる。ここは衰えていたとはいえ、やっぱり憎っくき読売ジャイアンツをいったんは叩いておいてからでないと、1リーグ制には進めない。そこでいったんは戊辰戦争をおこして、幕府を叩くことにして、そのうえで明治天皇による1リーグ制に移行することにした。
まあ、乱暴にいえば、こういうことだった。こんな説明もとんでもないが、これには田中彰の『開国と倒幕』や安藤英男の『西郷隆盛』からのヒントもあったようで、ぼくには解せないところも多々あるのだが、まあ、いいだろう。なにしろ、誰かが「ドーダ、まいったか」と言って、すぐに答えられずにいると、「よし、まいったのだな」と誰かがいえば、これで事態は進むのだ。いまのマスコミのやりくちと似ていよう。いま、日本でドーダのカードはすべてマスコミが握っていると言っていいだろう。
問題はそれより、そのあとの征韓論と西南戦争である。そこにはどんなドーダがはたらいたのか。
幕末維新の急展開と逆転につぐ逆転のなかで、相楽総三や益満休之助のような早とちりの犠牲者が何人も裏切られていったことについても、本書はふれているのだが、このへんも長谷川伸の名著『相楽総三とその仲間』(864夜)などでかなり詳しく書いておいたことなので、省略しよう。
省略はするが、鹿島はこの相楽の赤報隊の悲劇をおこさせた責任を、ほとんど西郷になすりつけている。そして、このときから西郷がふたたび「陰ドーダ」になっていったと分析した。
どこが「陰ドーダ」かといえば、西郷は赤報隊事件を自分の誤謬だったと自戒してしまい、そこに陽から陰へのドーダ転換がおこったというのだ。毛沢東(188夜・869夜)なら、そんな反省などゼッタイにしなかったろうと鹿島は言う。ほっかむりしたはずだ。けれども西郷はそれができなかった。つまり西郷は革命家としては失格なのだ。
ぼくなど、だから西郷が好きなのだが、本書ではそうはいかない。征韓論での立ち回りも、西郷がつくりあげようとした日本の軍事組織構想の挫折として、またその一方での人治主義国家構想の挫折として、扱われる。西郷が本気で日本をつくろうとしていたことはまちがいがない。けれども西郷はいっさいの「利害を抜きにした構想」をたてていた。これではダメなのである。大久保利通・伊藤博文を筆頭に、近代日本は富国強兵・殖産興業の国家として、あらゆる利害を収益に変える大国家にならなければならなかったのだ。それを西郷は純粋な思想で構想をもった。最近著の『国家論』で佐藤優も書いていたが、政治は純粋派と知性派は必ず負けるのだ。
かくて西郷は引っ込まざるをえなくなる。ぼくはそこもまた西郷が好きなところになるのだが、実際にはそうした大西郷の心情が周囲にわからぬはずはなく、結局は私学兵の反乱ぶくみの動きとなって、ここに西南戦争勃発となったわけだった。「愚にかえりたい」という西郷隆盛の声だけがこだまする。
だいたい鹿島の手は読めてきただろう。だから、これ以上に本書を案内することもないと思うのだが、以上のことをかつては「ロマン主義の高揚と敗北」といった視点で綴るのがふつうだったのである。
それをくつがえすのに、ただ「ドーダの作用があった」というだけでは話にはならないと思われるだろうけれど、それは本書ではもっと克明に解説されているので、念のため。
ただし、次にとりあげられた中江兆民(405夜)と頭山満(896夜)になると、これまでの切れ味がかなりにぶってくる。でも一言だけ、案内しておこう。
中江兆民がなぜドーダ人間になっているかといえば、兆民は「日本のルソー」と言われながら、つまり「ルソーで、ドーダ!」と言ってのける民約的看板になりながら、ドーダ転換をしたというのだ。それが「シニフィアン・ドーダ」から「シニフィエ・ダーダ」に転換したというのだから、これは説得力がない。シニフィアン(文字や言葉の記号表現性)とシニフィエ(文字や言葉の記号内容性)のちがいなんて、よほどポストモダン思想に詳しくないとわからない。
それよりもフランスかぶれの「おたくドーダ」が仏日転移の「民間ドーダ」に変じたというほうがまだわかりやすい。もっとも鹿島は兆民には『民約論』(社会契約論)の読みちがえがあったという重要な指摘もしているのだが、それをもってドーダ理論に組み入れるのは、やはり大仰すぎた。
頭山満について鹿島が持ち出したのは「知り合いドーダ」と「目撃ドーダ」である。「あ、その人知ってる。この前もパーティで会った」、「ああ、彼はね、誰々のスポンサーなのよ」と言って、世の中をどんどんと知り合いドーダで埋め尽くしていくドーダだ。
ここは、いろいろケーレツに分かれるらしい。大人物系列、みんながちょっと知らない人物系列、実はつながっている系列、などなど。これらを総合してあてはめられるのが、頭山満の「玄洋社」だということになる。
が、これはおもしろくなかった。すでに「千夜千冊」では玄洋社を何度も注目してきたが、そのうち杉山茂丸をとりあげるので、このあたりはぼくが「千夜ドーダ」であらためて補充をしておきたい。
どう? ちょっとまいった? まいらなかった? それとも、自分でドーダを持ち出したい? どっちにしてもこの本は、まことにみごとな「詮索ドーダ」だった。「週刊ブックレビュー」のイチオシ本にあげただけのことはある。では、今年の「千夜ドーダ」は次の夜のビブリオテカールでおしまいです。