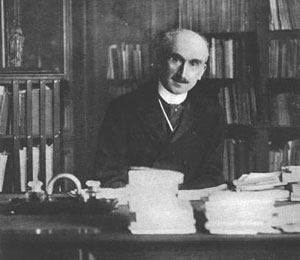物質は記憶か。時間は持続か。
自由は、エラン・ヴイタールか。
あえて形而上学に挑み続けたベルクソンを
いま、どう読むか。
ぼくをかつて揺動させたフランスの「生の哲人」は、
なお何を、語り告げようとしているのか。
それはまた、あの稲垣足穂の「機械学」の香りと、
どんなふうに交信していたのか。
パリ九区を友人二人と歩いていたら、一人が「ここはベルクソンが生まれたところでね、ここのリセ・フォンタネで古典や数学をやったんだ」と言いだした。リセ・フォンタネは今のリセ・コンドルセだ。
ソルボンヌを出て、その時は小さな版元をしていたそのフランス人の友人は、続いて「でも、最近のフランスではベルクソンは受けないんだ。どうしてだと思う?」と振ってきた。「うーん、それはベルクソンだけでなくサルトルもメルロ゠ポンティもガブリエル・マルセルも受けてないんだろ? みんなポストモダンにしてやられたんだよ」などと言ったような気がするが、すかさずもう一人から「それは責任転嫁だ。われわれの中にベルクソンを読み抜く力が衰えているんだ」と言われてしまった。あれから十七、八年がたった。
ベルクソンを読むということは、ヨーロッパ哲学がつくりあげた出来のよい二元論のあいだを堪能する気分になってみるということだろうと思う。二元論のあいだというのは、ベルクソンがデカルト以来の「心身問題」を、最高峰の矛盾と葛藤のなかで思索しつづけたということである。ベルクソンは最初から最後まで、精神と物質の二元論のなかで、この二つをつなごうとしつづけた。
二元論に与しないぼくがそんなふうに言うと、敵ながらあっぱれと言っているようで、不埒な感想のように聞こえるかもしれないが、いまのぼくには、まあそういうふうに言ってもいいところもあるはずだ。が、かつて最初にベルクソンを読んだときは、そんなことすら気付かないで、ちょいちょい没頭したものだ。小林秀雄の読み方が気にいらなかったせいもある(小林の哲学の七〇パーセントはベルクソンである)。
ふりかえってみると、最初に読んだベルクソンは林達夫が訳した『笑い』だった。ごく初期の執筆で一九〇〇年代にまとまった。ただし、これは感心できない。「笑いは生からの機械的こわばり」だとか「ぎこちなさ」を強調していて、つまらない。素材もモリエール論に終始していた。
次に学位論文『アリストテレスの場所論』を読んで、コーラやトポスについて言及しているのに興味をもった。場所が何かを占拠していること、だから場所がトピックを内蔵していること、その何かを占めた場所は動かせることなどに刺戟をうけた。ぼくの場所論の出発は、このときのベルクソンと、それに中村宏のタブロー《場所の兆》にあった(これが「遊」創刊号に『場所と屍体』の連載を始めるきっかけになった)。
このあとアリストテレスやロレンス・ダレルやルネ・デュボスの場所論の書林叢萱のほうに入っていったのだが、そこからベルクソンを眺めると、実は場所論が得意な哲人ではなかったということが見えてきた。
それでしばらくこの哲人から離れていたのだが、一九七三年の春、「遊」が第Ⅱ期に入るのを機会に二〇〇冊ほどの本を入手することにしたとき、白水社の「ベルクソン全集」の古本を購入した。これでベルクソン再突入がなんとなく始まった。手はじめに『物質と記憶』を(これはややコンを詰めて)、次には『創造的進化』を(これはかなり急ぎ足で)読んだ。これらの主張に納得ばかりしたわけではなかったけれど、かなり愉快な揺籃というものがあった。当時のぼくは「無」が存在に先行するのかどうかということを考えていたからだ。
ベルクソンは「無」が当初からあるという見方には反対だった哲人である。ヨーロッパに伝統的な「人はタブラ・ラサ(白紙)に何かを描くことで生き、何かを刺繍することで思考する」という強固な考え方を、なんとか覆そうとしていた。
端的にいえば、トマス・アクィナス以来の伝統に文句をつけようというのだが、ベルクソンはこの方針にはかなり頑固で、この点についてはカントにもヘーゲルの言い分にも屈服しなかった。ベルクソンよりちょっとあとのハイデガーですら、その哲学の全貌に「無」の一滴が必要だったのに。
しかし、「無」と「存在」の関係は、そう容易に片付くものじゃない。ハイデガーを承けたサルトルはそれこそその半生を、この「存在と無」の問題に終始したのだし(サルトルはベルクソン批判に正面からとりくんだ)、そもそもは知性卓抜のライプニッツにしてからが、「なにゆえに無ではなく、むしろなにものかが存在するのか」を考えこんで、モナドに窓をあけるかどうかという究極の決断に迫られたのだ。
だから、ベルクソンといえども「無」を打擲して、あたら「存在」のみに加担するわけにはいかなかったはずなのだが、『創造的進化』の最終章がそのことの論議にすべてあてられていたように、結局は生命の発生と進化を持ち出して、「無の先行」をまるきり否定してのけたのだ。つまりベルクソンはルイ・パスツールになったのだ(生命が無から発生しないと最初に言ったのがパスツールだった)。
けれども、それは哲学というものではなくて、生物学なのである。生命史観なのだ。ぼくは哲学と生物学がいくら一緒になってもかまわないという立場ではあったものの、二十世紀では評判の悪い生気論だとみなされた。では、どのようにしてベルクソンはこの評判から脱していったのか。
ごくごく端的にいうのなら、哲学というものは「真の実在」を知ろうとする作業のことをいう。三枝博音の千夜千冊のときにもふれたように、この「真の実在」は、仏教にいう「真如」でも、プラトンの「イデア」でも、プロティノスの「ヌース」でも、空海の「秘密曼荼羅十住心」でも、カントの「理性」でも、ハイデガーの「現存在」でも、かまわない。ようするに「真の実在」とか「知の真実」とでもいうような、そんなことがいったい世の中の何に役立つかというほどの、そういう他愛もない絶対知や普遍知に対しての探求に徹底することを、哲学という(なかで絶対知をもとめたのがヘーゲルである)。
それゆえ、「真の実在」が何々だと言明されるということについては、哲学者によってはその言明の核心が何であってもかまわないのだが、しかしその「知の真実」とおぼしいものを知るには(言明するためのプロセスの説明では)、どんな方法をとるかということが決定されなければならない。
こうしてここに、少なくとも二つの思索方法が浮上する。ひとつ(A)は外から眺める方法、もうひとつ(B)は内側からつかまえる方法だ。科学はもっぱらAを、哲学はおおむねBをつかう。どちらも、演繹でも帰納でもかまわない(パースが提案したアブダクションなら、もっといい)。
Aのばあいには、何をどこから眺めているかという立場が明確になる必要がある。むろん富士山をぐるぐる動きながら眺めたっていいけれど、それはそれで「ぐるぐる動いた」という立場(視点)が生じたのであって、その立場はいくらでも厳密に記述できる。これはニュートンが微分方程式によって対象世界(=システム)を設定してから「真の実在」に向かっていったという、あの古典力学以来の方法になる。
このAの方法は、いいなおせば「存在」を相対的に記述しているという特色をもつ。ニュートンの相手も、せんじつめれば太陽系という「存在」(つまりシステム)だった。その存在をあらわす相対的な分量はいくら多くてもいいし、いくら複雑でもいいけれど、それはやっぱり「存在の相対性」にアプローチしたということなのだ。
これに対してBの方法は、事態の内側にいて、真の実在を記述できるかどうかを試すという方法になる。内側にいたから成功するとはかぎらないし、また、その方法が誰にも検証できるともかぎらないので、これは厳密には科学とは言いがたい(フッサールの現象学はそこを「厳密な学」にしようとした)。
しかし、このBの試しにも、やはり立場がいる。この立場(視点)は内側に入るのだから、存在の動向と一緒くたになった立場にならざるをえない。したがってBの方法で得られる実在は、自分の立場と存在の本質とが一緒くたになっている可能性と、危険性を語らなければいけない。Bの方法はその危険な一緒くたにあえて介入することにした。それが哲学というものだ。だから、哲学の多くには、それはおまえの実感や推理にすぎなくて、「真の実在」なんてこれっぽっちも説明できていないじゃないかと言われかねないような、そんなゴタクもたくさんまじっているということになるのだが、それでもそれはBによる哲学なのである。
ただし、これではゴタクと真実とがあまりにごっちゃになりすぎる。ではどうするか。ひとつは、ゴタクの語りと真実の語りをまぜこぜにする語りに向かってみることだ。エマニュエル・レヴィナスなどはこの方向に進んでいった。もうひとつは、この「ごっちゃ」そのものを、いったん哲学的思考の方法主体としてつかまえておこうというものだ。当初の思考が「ごっちゃ」というレンズをもっていたとしてしまうのだ。
ベルクソンはこの後者でいくことにした。そして、この「ごっちゃ」の方法主体を「直観」とみなしたのだった。ちなみに、Aの方法、Bの方法とはべつに、もうひとつのCの方法もあって、それが「真の実在」さえカッコに入れようというフッサールの方法だった。
直観(intuition)とは何かというと、Bの方法が動いているときの、「方法の親玉」のようなものをいう。少なくともベルクソンはそのように見た。だから、これを内観といってもいいし、内見といってもいい。またごく一般的には、意識といってもいいだろう。ただしこの意識はだだっ広い意識のことではなく、真の実在に向かって動く焦点をもった、あるいは焦点をさがしているごちゃごちゃな方法的意識のことだ。
ところが、このようなごちゃごちゃの方法的意識をもつ直観は、いつも一定の様相をもっているとはいえない。焦点すら動くのだから、その動向を走査できない。そのかわり「ひらめいた!」とか「ユーレカ!」というように、直観は刻々変化しているなかでヴィジョンのように見えてくるものを獲得している可能性がある。
そういう「ひらめき」がはたして直観の正体かどうかはいまは措くとして、では、直観は直観だけが自立しているのかというと、そんなことはあるまい。そこにはおそらく「流れる時間」というものがある。直観は「流れる時間」に乗っていそうなのである。おそらく直観は時間とは分けられないかもしれない。しかも、直観が直観になるときは、そこは言ってみれば、「ずっと現在」なのである。
そこでベルクソンは、その「流れる時間」とともに直観が一緒くたに動いていると見て、直観が関与する「ずっと現在」の状態のことを、あらためて「持続」(durée)とよぶことにした。「直観的に考えるとは持続において考えることである」「直観の理論の前に持続の理論がある。前者は後者から出る」というのは、このあたりのことを示すための説明だ。また、そのような時速とともにある直観的意識には「強度がある」というふうに見た。
こうしてベルクソンは、直観と持続という内的な立場から、真の実在を哲学するという方向をもったのである。これが『物質と記憶』の基本的な枠組というものだった。一八九六年、ベルクソン三七歳のときの執筆だ。
いささか遠い街で見知らぬ少女と出会った思い出のようにはなっているのだが、『物質と記憶』はぼくに香ばしい想像力をかきたてた。ということは、当時のぼくが二元論とはまだ十分に訣別しきっていなかったことを証してしまうのではあるけれど、それはそれ、なるほどベルクソンはうまいカマエとハコビを考えたものだと感心した。
しかし、いくつかひっかかることもある。それは第一には「時間」と「持続」を持ち出したことで、たくみに「無」の君臨を消してしまったということだ。いつのまに「無」を消去してみせたのか、そこがわからない。
第二には、「流れた時間」と「流れる時間」をはっきり分けて、「流れた時間」を過去や経験とみなし、「流れる時間」だけを相手にしたということだ。そんなふうに便利に時間を分けられるものなのかどうか。そこがひっかかった。
第三には、どうも「物質」と「記憶」の関係がわからない。ベルクソンは物質というとき、ニュートン力学が提供したシステム(系)のなかで記述される物質を、いつのまにか取り払っていて、むしろ生命や人間を構成している有機的な「内側の物質」ばかりを相手に選んでいるような思考をしていたからである。いわば「意識を構成している物質」がベルクソンの物質なのである。
これは他方では、ぼくをして、いったい「意識が物質を帯びているのか」、それとも「物質が意識を帯びたのか」という、その後の何十年をも悩ませるチョー難問を喚起させたのであるが、それはそれ、そのチョー難問をベルクソンは必ずしも解いてはくれていなかったのだ(これについては最近、本になった茂木健一郎との文藝春秋の対談集『脳と日本人』にもふれてある)。
こうして、これらのひっかかりは、『物質と記憶』をいくら読んでも次の方向を暗示しているわけではなかったので、やっと、かの難解で鳴る『時間と自由』を読むことになったのである。たしか元麻布に引っ越したころだったから、一九八三年か、その次の年くらいのことだ。
最初に断っておくが、『時間と自由』というタイトルはベルクソンのものではない。英訳のときにこうなった。以来、このタイトルが思想ギョーカイでも通り相場になっているけれど、原題は『意識に直接与えられたものについての試論』という面倒なものである。いや、『時間と自由』のほうがかえって面倒なのかもしれないが、どちらが面倒かはともかくも、本書は「自由とは何か」を考察したくて書いたものになっている。出来は、まあ六五点といったところだ。
もうひとつ断っておくと、本書は『物質と記憶』よりも前に書かれている。ベルクソンが二九歳のときに文学博士になるために提出した乾坤一擲の博士論文なのだ。つまり最初のデビュー大論文なのだ。したがってベルクソンは、「時間」については「直観」や「持続」よりも前に考察し、その後、『物質と記憶』のなかでその時間論を哲学編集していったことになる。
そういうデビュー作だったこともあって、『時間と自由』はかなり生硬だ。若書きの文章が生硬だったり、粗削りだったり、勢いにまかせたものであることはめずらしくない(和辻哲郎を千夜千冊したときも、そのよしあしを書いておいた)。けれども『時間と自由』はそれが生硬だから問題だということではなくて、その内容がほとんどその後の『物質と記憶』や『創造的進化』に吸収されていったということで、あえて単著として扱うよりも、ベルクソン哲学の変容のなかで見たほうがいいということになる。
ということで、ここから先は『時間と自由』を含めての、つまりはベルクソンの著作のあらかたを含めての、ベルクソン哲学のぼくなりの全般的な評釈というものにしておこう。次のような順で評釈してみれば、なんとかベルクソン哲学の、むろん全容ではないにしてもだが、その核心にふれられるのではないかと思う。むろんそうしたところで、先にあげたいくつかの「ひっかかり」は氷解するとはかぎらない。
ベルクソンの最大の哲学上の課題は「自由」とは何かというところから始まる。自由を考えるには、その自由をほしがる人間というものがどういう本質をもっているのか、あるいはどういう本質的な方向をもちたいと思ってきたのかということを、片付けなければならない。
この「本質がまだわからない人間」のことを、哲学者たちは好んで「存在」と称んできた。プラトン以来のことだと思っていい。のちにサルトルは「実存」とも呼んだ。
存在とは何か。哲学上の定義からいって、存在とはその本質が不分明なものをいう。中身がよくわからないから、人間は「存在」という思考存在様式そのものなのである。けれども何もかもが不分明では、話は始まらない。
そこでベルクソンは直截に、存在とはひとまず「精神」であろうとみなした(これはヘーゲル以来の哲学の課題だった)。ただし「存在は精神だ」という程度では、ほとんど同義反復になることもわかっていた。そのため、ただちに「存在=精神」のかなりの大半を、「意識」が占めているだろうと考えた。存在は精神であって、その精神の大半は意識なのである。そう、仮定した。
ちょっと気になったのは、「存在=精神」の大半が意識だとしても、そのほかに「物質」がどのように関与しているかが、当時の生物学や生理学ではなかなかわからなかったことなのだが、とりあえず、さらに先に進むことにした。
しかしとはいえ、仮に「存在=精神」≒「意識」だとしても、その意識をどこから、どんなふうに捉えればいいのか。外から眺めているだけではさっぱりわからない。まさにBの方法で、内側に入ったまま哲学してみるしかない。運よく内側に入れたにせよ、この意識は「本質がまだわからない人間」がもっている意識なのだから、「ごっちゃ」の感覚をなんとか整理しておく必要がある。それには意識をまるごと扱わないで、ややはっきりしているところと、まだよくわからないところとを分けておく必要がありそうだ(フッサールはこれらをすべてカッコに入れた)。
こうして、まずは「記憶」が重大な分水嶺になっているのではないかということになってきた。
次にベルクソンがとりくんだのは、意識は、記憶の部分と、まだ記憶になっていない部分とに分けられるのではないかということだ。
ベルクソン自身はこの分け方がそうとうおおざっぱなものだということは、よく知っていた。だいたい記憶にはやたらに詳しい部分とやたらに曖昧な部分とがあるし、おまけにそれらは複雑にまじっている。夢に出てくるのも記憶の正体に関係しているだろうし、忘れてしまう記憶というものもある。だから記憶を議論するには、記憶の広さや大きさというより、記憶の「強度」といったものを重視する必要がある(この「強度」はベルクソン得意の概念だ)。
意識の中身が記憶やそのヴァージョンそのものかどうかは、わからない。けれども、もし記憶がなければ意識もないだろうということだけは前提になりそうだった。実際にもベルクソンは当時の脳科学の成果も調べて、記憶喪失者たちが意識をも喪失している例をいくつもとりだしている(ブローカの症例など)。それらの例によると、記憶が意識をコントロールしているらしいことは、どうやらまちがいがなさそうだった。
一方、意識には記憶になっていない部分もある。こちらのほうの意識は何なのか。その多くは知覚や行動と結びついているわけだろうが、記憶になっていないものは、現在や未来にかかわっているとみなせる。とくに現在だ。ということは、意識というのはおそらく「時間」にディペンド(依存)しているということなのである。とくに記憶は過去に結びついている。では、どこからが意識にとっての過去で、どこからが現在で、どこからが未来なのか。
記憶と過去をあまりにも堅く結びつけてしまうのはよくない。なぜなら、記憶は貯蔵庫(アルシーヴ=アーカイブ)に入っているときよりも、それが思い出されるとき(想起するとき)が問題であるからだ。想起は現在の意識でおこるのだから、記憶は現在にもかかわってくると言わざるをえまい。そうだとすれば、意識を考えるとは、実は意識が「現在」に何をおこそうとしているものなのかを考えることなのである。
そういう「注意のカーソル」をアタマの中で動かすことが、意識を考えるということなのだ。いいかえれば、意識にとっては「ずっと現在」とでもいう状態こそがあからさまなのだ。
そういうことを考えているうちに、ベルクソンは、ひょっとするとこの問題のありかたにこそ「自由」とは何かということがかかわっているのではないかと、そんなふうに方向づけるようになっていた。そして、「存在=精神」≒「意識」という問題の解き方には、実は「時間・記憶→自由」という未知の問題の立て方があるのではないかと思うようになった。この二つのシェーマの「≒→」がついている「あいだ」は、おそらくはどこかで、何かがつながっているにちがいない。
いったい「存在=精神」≒「意識」と「時間・記憶→自由」との「あいだ」をつなげているものとは何なのだろうか。これは当初は難問だった。しかし、ベルクソンはここで転換をする。かなりの大転換だ。「あいだ」に何かがあるのではなく、「あいだ」そのものこそが、かなり重要な何かなのではないか。そういうふうに考えを転換した。そして、この「あいだ」こそ「持続」というものだろうと結論づけたのである。「持続」という概念はベルクソンをそうとう気にいらせたようで、のちには「純粋持続」という抽象度の高い概念にまで引き上げている。
こうして存在と時間が、意識と記憶が、それなりの関係をもつようになってきた。そういう関係を支えているものが、「ずっと現在」を演じさせつづける「持続」という意識であろうということになってきた。
もっとも「持続」だけでは何も生まれない。純粋持続は純粋意識しかもたらさない。ベルクソンは、「存在が存在の本質にふと気がつく時」というものを想定して、ここに「直観」の関与があるというふうにした。かくして直観は持続を破るものであり、また、持続の奥底に眠っていたかもしれない本質的な意識をめざめさせるものともなったのである。
ぼくが惟うに、直観がどういうものかということは、ベルクソンの手に負える代物だったろう。へたすれば直観は「ごっちゃ」意識そのものなのだ。なぜなら、直観もまた時間の流れにディペンドしているのだし、そうだとすれば意識の流れとともにその前身があったはずなのだから、先に書いておいたように、直観といえども意識のゴタクとともに「一緒くたの現在」をもっていると言わざるをえないからだ。それでも、直観が持続を破り、持続が直観を支えているということ、そこには「あいだ」という領域があるだろうということは、ベルクソンを大いに弾ませたのである。
さて、ここからがいよいよベルクソンが「生の哲学」の創始者だと称ばれてきたゆえんともいえる独自の展開になっていく。ごく簡潔にまとめよう。
ベルクソンは以上の推論を前提に、生命が進化という大きな時間を次々に費やすにしたがって、意識をもつ人間存在というものになったという構図をもった。そしてその大いなる進化のなかで、一個ずつの生命がそれぞれの意識をもち(言葉も行動ももち)、それぞれの記憶を貯め、そこに過去と現在と未来の区分を感じ、さらにその先の自由に向かっていくというふうに考えるようになった。ベルクソンの時間は生命史的な進化と重なったのだ。
この構想はすこぶる生気に満ちたものではあるが、特段にめずらしいものではない。すでにダーウィンが生物の進化と人間の進化をつなげて、そこに共通の「時間の流れ」を組みこんでいたのだし、エルンスト・ヘッケルは十九世紀末に「個体発生は系統発生をくりかえす」と言って、大胆ではあるが、しかしたいそう暗示力に富んだ部分と全体を関係づけるテーゼを発表していた。
ただしそれらは哲学的にはまだシェーマにすぎず、そのシェーマを生命や意識が持続させている「あいだ」が説明されたわけではなかった。ベルクソンはその「あいだ」をこそ哲学し、そこについに「創造的進化」という、ダーウィンの進化論だけでは導き出せない構想をくっつけたのである。これが『創造的進化』という著作になった。
このことはベルクソン一人の独創というわけではない。ハーバート・スペンサーが「総合哲学体系」の名のもとに社会進化論を提唱していて、そこに「ハイパー・オーガニゼーション」(有機的社会意識)が形成されていることを縷々説いていた。十九世紀末のことである。ダーウィニズムは、すでに意識の進化にもあてはめられつつあったのだ(これがいわゆる「社会ダーウィニズム」のスタートにあたる)。
ベルクソンはこのスペンサーからも大きな影響を受けている。ベルクソンだけではなく、フェノロサ、岡倉天心、森有礼、西田幾多郎、パーソンズ、ルーマン……いずれもスペンサーの申し子であった。
が、ベルクソンはスペンサーそのものではなかった。意識が進化し、社会が進化するということだけを言いたかったのではなく(それが大前提にはなっているのだが)、そのなかで人間は(つまり存在は)、ある種の精神的飛躍をおこすということ、意識的飛躍をおこすということを強調したのである。ここにふたたび直観が関与した。
これが有名な「エラン・ヴィタール」(élan vital)という見方だ。「生の飛躍」というもので、ベルクソン哲学の核心にあたるものになっていく。
どういうものかというと、一方には、生命の悠久の進化の連続があるわけなのだ。これは大いなる持続ともいえるものだろう。そしてこの大いなる持続こそが人間を生み、意識を派生させ、精神を形成していった。ということは、他方では、これを精神や意識のほうから見ると、この大いなる持続を破って、精神や意識が人間を通して地上の生命圏や生態圏に出現したことになる。その破開をおこした意識の親分、あるいは方法の親分が直観である。
その直観が「脳」に所属しているのか、「心」に遍在していたのか、それとも「体」のどこかに蹲っていたのか、そのへんはわからないのだが、ともかくも持続の打破は、人間の内側に爆薬の破裂のごとく出現したことになる。これがエラン・ヴィタール(生の飛躍)である。
ベルクソンにとって、エラン・ヴィタールは生物史の異様な起爆とも、さらには宇宙史の最も果敢な創発とも感じられた。ここだけを強調するなら、まったき生命賛歌としてのエラン・ヴィタールである。こういうと、ベルクソンの「生の哲学」ってなんだかおめでたいほどの生命賛歌なのかと思われそうであるが、またやっぱり生気論じゃないかと思われるかもしれないが、そしてそういうところも多々あるのだが、おめでたい賛歌に酔ったわけでもない。ここはベルクソンのために哲学史上の説明を少々加えておかなければならない。
さかのぼってベルクソンは、若き学徒のころから一貫してカント哲学と対峙しつづけた哲学者だった。カント哲学というのは、一言でいえば「判断はどうあるべきか」ということを考えた哲学である。これはさかのぼればアリストテレスに発していた命題(判断命題という)を、カントが劇的に高めたものだった。
カントはそのために、判断のよってきたる作動因のようなものを考えた。そして、そこには因果律のようなものが支配的に関与していて、それが科学的法則になったりしていると見た。ただカントは、われわれはそのような科学的な因果律を自分の判断のどこかに投影しすぎていて、そのため純粋な判断がにぶっているのではないか。それならもっと純粋で、理性的な判断がどういうものかをちゃんとつきとめるべきだろうと考えた。わかりやすくいえば、人間の理性や悟性(意識)は、科学が発見するようなものとはべつのところにあるのではないか。だから哲学は(自然科学とはちがって)、人間の本性に属するとおぼしい「主体の意識の哲学」だけを考えたほうがいいのではないか。おおざっぱにいえば、そういう方針を立てたのだ。
そのためカントは、空間や時間は、われわれの意識や判断とはべつのところにアプリオリ(先験的)にあるものだとみなした。
これを、ベルクソンはなんとか崩そうとしてきた。時間も空間もわれわれの意識に関与しているのだし、そもそも人間が存在として宇宙的生命の歴史の只中に誕生して、このような意識をもったということは、そしてそれを物質の歴史とともに記憶の歴史としてもってきたということは、カントの言うように、純粋な判断とかかわりのない時空がどこかべつのところにあるのではなく、まさに意識を生み出す時空というものがあって、これからの哲学はそのことをこそ思索し、表現するべきなのではないか。そう、考えたのである。
そして、このようなカント哲学との対峙が、エラン・ヴィタールという「生の哲学」になったのだった。だからベルクソンの哲学は、生命の力を過信したものであるとともに、哲学史から時空を奪い返したものでもあったのである。
ざっとは、こんなふうにベルクソンを読んできたのだったが、付け加えなければならないことは、もちろんいっぱいある。
ひとつは、主観や客観には分けられない思考は「イマージュ」(image)として駆動しているとみなしたことが当時としては新しかった。これはイメージのエンジンのようなもので、言葉にも論理にもならないで、それらを反映呼吸しながら駆動するものである。ただそのイメージのエンジンは記憶体に従属しているようで、そこは物足りない。
もうひとつは、ベルクソンが「生の飛躍」を主唱したのち、意識の生命力は「物語」(作話力)に向かっていくということを強調していたということだ。これはあまり知られていないベルクソンの世界解釈論ともいうべきもので、のちにレヴィ゠ストロースが自分の文化人類学とはなはだしく類似すると共感したものでもあった。ベルクソンは「人物を創出し、その歴史を自分自身に物語る能力」こそが「存在=精神≒意識」にとって最もエラン・ヴィタールなことだと見たのだった。
ついでながら、ベルクソンは「朗読」の重要性も指摘した。これもさすがのことである。文脈にひそむリズムを意識して文章や詩歌を声を出して読むことは、これまたベルクソンにとってはエラン・ヴィタールだったのである。
世の中に出回っているベルクソン論についても、一言加えておく。ちゃんと目配りしたわけではないけれど、ジャック・シュヴァリエの『ベルクソンとの対話』(みすず書房)とウラジーミル・ジャンケレヴィッチの『アンリ・ベルクソン』(新評論)、ジル・ドゥルーズの『ベルクソンの哲学』(法政大学出版局)、マリー・カリウの『ベルクソンとバシュラール』(法政大学出版局)、市川浩の『ベルクソン』(講談社学術文庫)、篠原資明の『ベルクソン』(岩波新書)などが印象にのこった。
なかで篠原のものが分析の仕方や解説の仕方もいろいろ工夫してあって(とくにトマス・アクィナスとドゥルーズとベルクソンの比較、「あいだ」の議論、ホワイトヘッドや大森荘蔵の持ち出し方など)、なにより、ぼくとしては稲垣足穂がふんだんに登場しているのが香ばしかった。こんなベルクソン論、これまでまったくなかったのである。
で、このあと書きたいと思っている「ぼくの好きなベルクソン」も、この稲垣足穂に密かに連動するアンリ・ベルクソンなのである。
稲垣足穂がベルクソンにたいそう依拠していた時期があることは、タルホ・ファンならば先刻承知のことだろうと思う。タルホは、ベルクソンが「物質を意識の回顧や延長でとらえよう」としていたこと、記憶が物質を保存しているのではなくて、「物質の記憶がすでに世界に波及している」のだとみなしていたことなどをうんと拡大解釈して、そこにタルホ流の天界的転回のためのペパーミントなリキュール数滴を加えて、新たなタルホ・ベルクソンをつくりだしたのだった。
それは、これまでのベルクソン観とはかなり異なるものであるが、だからこそタルホが言っておきたかったことなのだ。「小林秀雄のベルクソンと稲垣足穂のベルクソンとの違いを知って貰いたい」というタルホ自身の言いっぷりからも、その自信のほどがうかがえる。ぼくが『人間人形時代』(工作舎)に入れた『カフェの開く途端に月が昇った』には、こんな文章がある。
自分が小学上級だった頃、ベルクソンはオイケンと並び騒がれ、中学四年の春にはタゴールが加わった。オイケンやタゴールには、関心もなかった。彼らが人生派を出ていなかったからだ。人生派とは、只行われているべきもので、彼此言う必要のないものである。ニイチェもキェルケゴールにも、自分は縁がなかったが、ベルクソンには、将来きっと好きになれるという予感があった。

『人間人形時代』より
予感は当たった。タルホは『物質と記憶』を読んで、イソギンチャクのマークのついた黒い想像力のマントをベルクソンに覆い、「六月の都会の夜のエグゾースト」を胸いっぱいに吸いこみ、その息をベルクソンにふっと吹きかけることに夢中になった。それでそこに何を読み取ったかといえば、こういうことだった。「何事であれ、重大なことは本当にあったかどうかなのではなくて、たったいま現在のことすらも、遥か遠方の物質の記憶として思い出されてよいということなのである」。
このことを、タルホが一言で「地上とは思い出ならずや」と名付けたこと、また「宇宙的郷愁」とも名付けたことは夙に知られていよう(ぼくはここから「遊星的郷愁」という言葉を編み出した)。
この見方ほど痛快なベルクソンはないのではあるまいか。この見方こそ、ベルクソンの切っ先が香ばしいことを伝えているのではないか。ぼくにはそう思えた。そこには、タルホがしきりに「機械学」という言葉を好み、また「ヰタ・マキニカリス」という言葉を造語してまで、自身の少年時代の一千一秒を綴っていたことがおおいに関係してくる。それはベルクソンが世界の記憶と表現を、大きく「機械系」と「神秘系」の二つに分けたことにヒントを得たものだったのである。
機械系と神秘系で織り成された世界はデュアル・ワールドである。それはタルホの認知からすれば、雲母のようにたいそう薄いもので、ある角度から見れば察知可能なものの、ふだんはよほど注意深くしていないと見えないようになっている。だからタルホはそれを「薄板界」とも称んだ。しかしながら、ひとたびその薄板界にふれたとたん、事態は世界がフィルムを逆回しさせるがごとくに意識の俎上に巻き上がってくるはずなのであって、それゆえタルホ・ベルクソンは、「カフェが開いた途端」と「ボール紙のような月が昇った」という互いに遠い二つの出来事を、神秘的機械学として、また機械的神秘学として〝同時了解〟してみせたのだった。
今夜はクリスマスも過ぎた年の瀬である。そんな夜にベルクソンについての印象喚起の一文を綴れたことを慎ましく悦びたい。「ジングル・ベルクソン!」。
ジングル・ベルクソン!
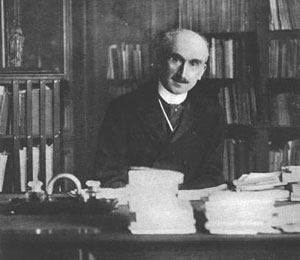
附記¶新宿抜弁天に近い富久町の横田アパートで、まりの・るうにいが毎日、ベルクソンを読んでいた。白水社の『ベルグソン全集』である。この全集では「ベルグソン」というふうに濁点になっている。たしか全集の1巻と4巻はぼくが買ったのだと思うが、あとはまりの・るうにいが入手しては、読んでいたのだ。
ということでベルクソンは白水社の全集が上々。ほかに、岩波文庫には『時間と自由』『笑い』『思想と動くもの』『道徳と宗教の二源泉』があり、中央公論社に「世界の名著64」の『ベルクソン』、中公クラシックスの『哲学的直観』『道徳と宗教の二つの源泉』(I・II)がある。
ベルクソン論としては、ウラジミール・ジャンケレヴィッチ『アンリ・ベルクソン』(新評論)、ジル・ドゥルーズ『ベルクソンの哲学』(法政大学出版局)、市川浩『ベルクソン』(講談社学術文庫)、ジャック・シュヴァリエ『ベルクソンとの対話』(みすず書房)、篠原資明『ベルクソン』(岩波新書)、同じく『漂流思考・ベルクソン哲学と現代芸術』(講談社学術文庫)、澤潟久敬『ベルクソンの科学論』(中公文庫)、金森修『ベルクソン』(NHK出版)、中田光雄『ベルクソン哲学』(東京大学出版会)、檜垣立也『ベルクソンの哲学・生成する実在の肯定』(勁草書房)、守永直幹『ベルクソン生命哲学・未知なるものへの生成』(春秋社)など。