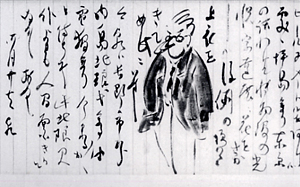光悦の再来とも、
乾山はだしとも言われるが、
半泥子の真骨頂は「遊」である。
轆轤に染まり、志野を生かし、
黒楽を光らせて、織部を躍らせた。
把和遊 How are you?
喊阿巌 Come again!
これで見えなきゃ、日本は闇よ。
かつてぼくは「一到半巡通信」(のちに「半巡通信」)というプライベート・ペーパーをつくっていた。勝手気儘なことを一人で綴った無料の月刊小冊子だったけれど(毎号一人ずつのゲスト執筆を入れた)、1994年9月に100部くらいから始めたものがいつしか噂が噂を生んだのか「送ってほしい」という要望が多く、ついに4000部を超えてからは紙や印刷はともかく郵送料が嵩(かさ)んでしまって、やむなく2002年11月に途切れさせた。
そのなかに「埒外案内」あるいは「絆然半碍記」という連載をしていて、そこに「キレイダ・キライダ」という欄をつくっていた。キレイダというのはぼくが気にいったものを、キライダは気にいらないものを独断であげる。のちに興に乗ってキレイダ・キライダのほか、キホンダ・キカイダ・キシンダなどのキ印をふやした。たとえば第1回にあげたのは、エヴァレット・ブラウンの写真、内藤こずえ(のちの日比野こずえ)の衣裳、アグネス・バルツァのカルメンはキレイダだが、吉村作治のエジプト論、子安宣邦の本居宣長論、ミスター・ビーンはキライダだというものだ。
懐かしいからもうちょっとあげておくと、いずれも当時の見聞にもとずくものになるけれど、オスカー・デラ・ホーヤのボクシング、橘芳慧の清元『深川女房』、ハーヴェイ・カイテルの声づかいはキレイダで、広島カープ江藤の巨人入り、相田みつをの詩書、クリントンのコソボ演説、セブンイレブンのおでんが、キライダなのである。
ちなみにキカイダは富田勉のユードラアート、椎名林檎の歌詞、小林健二の幻想鉱石ラジオ、クリストファー・ギブスのアンティーク・ショップなどで、キシンダの2000年3月版は石原都政、ヤマンバ女学生、愛知万博計画、吉川ひなのの「笑っていいとも」出演とある。よくぞ、こんな好き放題を書いていたものだ。

『半巡通信』(第70号~74号)
いま川喜田半泥子の随筆、作陶、あるいは半泥子その人を語るにあたって、こんな他愛もない自慢をしたのはほかでもない、三つほどの理由というか、ちょっとした暗合があった。
第1には、半泥子こそはキレイダ・キライダをはっきり言いつづけためずらしい風流断言人だったということだ。あとでも補充するが、たとえば志野・唐津・井戸茶碗はキレイダだが、仁清やノンコウや京焼はキライダなのである。竹の花生けは清浄な青竹を切っての掛流しはキレイダだが、鉋や木賊(とくさ)まで加えておまけに古びているものはキライダなのだ。こういうことを歯に衣着せないで言える男はいなかった。
第2には「半巡通信」に、20世紀のラスト・キレイダにその半泥子の茶碗をあげておいたことだ。よくぞそのことを書いておいたものだった。まさに半泥子こそ20世紀の忘れものなのである。このときぼくのアタマに光のように見えていたのは、粉引茶碗の「雪の曙」や刷毛目茶碗の「一声」あたりだったろうか。おもえば1984年のことだったが、生誕105年を記念して三重県立美術館で大掛かりにひらかれた「川喜田半泥子展」でこれらを見たとき、息がとまるかと感じたほどだった。いや、もっともっと傑作はある。
第3には、そもそもぼくも「半」が大好きで、だから「半巡通信」だとか「半碍記」といった命名をしてきたということだ。いまは民主党の参議院議員になった鈴木寛君に頼まれて、「半塾」という塾をしばらくやっていたこともあった。このころはいまは構想日本や東京財団の代表をしている加藤秀樹さんもよく顔を見せていた。そのほかなぜぼくが「半」という文字がやたらに好きだったかということは、第342夜にも書いておいたことなので、ここでは省略しておこう。
ちなみに、半泥子が号に「半」を入れたのはどうしてかというと、南禅寺の前管長で当時は無礙庵にいた大徹禅師から、「半ば泥(なず)みて、半ば泥(なず)まず」という意味を与えられたからだった。だから半泥子。それがやがて号になった。半泥子にとってこんなにぴったりした号はないだろう。その大徹のところにぜひとも参禅しなさいと勧めたのは、祖母の政子によるもので、半泥子は少年時代すでにして禅に打たれていたはずなのである。
では、最初にそういう半泥子の生きざまのことを話しておきたい。

『粉引茶碗 銘 雪の曙』

『刷毛目茶碗 銘 一声』
川喜田半泥子は明治11年に三重県の津の富豪の家に生まれている。本名をいかめしくも久太夫政令というのは、江戸時代から木綿問屋を営んできた生家の跡取り16代目だったからである。わずか1歳で家督を継いだ。
そんなに早々に継いだのは父親が半泥子をもうけてすぐに死去したからで、そのとき母親は18歳にすぎなかった。そこで、18歳の未亡人ではあまりにかわいそうだというので、母親は実家に戻された。そういう心配りをしたのは祖母の政子(まさ)である。ということは、半泥子は最初の最初から父母を失ってまるまる祖母の手で育てられたということになるのだが、そこが代々の素封家を守ってきた祖母のこと、決して半泥子を甘やかさなかった。少年になった半泥子はすぐに禅の修行をさせられた。恋しい母とも20歳まで再会することが許されてはいなかった。
このあまりに厳しい気丈婦の祖母は、伊勢の射和(いざわ)の名だたる豪商、竹川竹斎の妹であった。兄の竹斎は佐藤信淵や勝海舟と交流のあった憂国の才人で、『海防護国論』や『護国後論』を書いたかとおもえば、沼波弄山が創始して廃れたままになっていた萬古焼の復興に手を尽くした。そのこともあって、半泥子は本書『泥仏堂日録』のなかでもしばしば射和萬古のことに言い及んでいる。半泥子にはこの血が流れた。だいたい半泥子が焼きものにあれほど傾注できたのも、この竹斎が郷土の焼きものにこだわった由来を身に受けていたからだろう。
それにしても祖母の教えは凄かった。「おのれをほむる者は悪魔と思ふべし。我をそしめる者は善知識と思ふべし。只何事も我を忘れたるが第一なり」。これは祖母が書きのこした『政子遺訓』というもので、半泥子はこの言葉をずっと守り続けたようだ。一説には、大人になってからも、いつもその遺訓をメモしたものを内ポケットに入れておいたともいう。

川喜田家(中央左が祖母政子)
そんな半泥子が陶芸に遊びはじめたのは明治も暮れる34歳ころからである。早稲田に入って23歳で結婚、25歳で百五銀行の取締役となり、29歳には市議会議員や三重の県議会議員にも選ばれてつねに公人のコースを歩んでいた半泥子が、30代半ばになって大徹禅師に数息観や内観法をしこたま教えられ、さらには「半分は泥(なず)め」と言われたことがトリガーになった。そのうちなんとなく楽焼に手を染めたのが34歳ころである。光悦への憧れから手を染めた。
そのとき轆轤(ろくろ)も少しはまわすようになったのだが、ここまではまだ何も了解すらできていなかったろう。それが37歳で自宅近くの千歳山に邸宅を建て、大徳寺の川島昭隠和尚に参禅し、さらには大正5年に「集古会」の同人に連なるうちに、しだいに目が肥えてきた。それはそうだろう。坪井正二郎や山中共古らが発起人となった「集古会」といえば、内田魯庵・泉鏡花・鏑木清方・岡田三郎助・三田村鳶魚、三村竹清らの錚々たるメンバーが書画骨董を求めて交遊し、古今の文献に通じあうという切磋琢磨の高等巣窟のようなもの、半泥子の心眼が鍛えられないわけがない。
しかし、半泥子の経済界オーガナイザーとしての嘱望もますます高く、大正8年の41歳には百五銀行の頭取を、大正11年の44歳のときは相互商事の社長や三重合同電気(のちの中部電力)の社長などを引き受けざるをえなかった。途中に三谷有信に日本画を習ったりはしているものの、やはり公務は忙しい。やっと長江寿泉の指図に助けを借りて千歳山に窯をひらいたのは関東大震災のあとの大正14年の47歳のときだった。
この窯では長江寿江をはじめ、京都からは堀尾竹荘が、桑名からは加賀月華らが来て窯を焚き、何度も陶芸制作が試みられた。京都大丸で展示されていた小山富士男の全作品も買い上げて、研究も重ねた。ところが、どうも気にいるものが仕上がってはこない。
それでも半泥子は地域の産業振興にも役立つはずのこの集団制作体制の確立になんとか力を入れていたのだが、昭和7年6月4日、ついにこの方針をあきらめて自身で作陶に打ちこむことを決意した。本書においても、「何れも心に充たざるもの故、同年6月4日、此時から自己流で焚いて見る」と、その決意のほどがのべられている。54歳だった。
ふつう、半泥子の作陶というと、この54歳から始まったというふうに見る。まことに遅い。けれども早くも同年の暮、その腕試しが銀座資生堂での「土クレ会」で発表された。資生堂とともに、「天一」の矢吹勇雄が応援をした。

千歳山のロクロ場でロクロを引く半泥子(昭和10年)
ここからの半泥子はものすごい。余人には真似できない。妖刀を自身に突き刺している。益子の橋本清正をたずねて轆轤の技を学び、小さな石炭窯をつくってさまざまな土を練り、みずからは無茶法師と名のるようになった。
泥仏堂とは昭和8年に川喜田商店創立三百年を記念して、従業員一同が半泥子に贈った登窯のことをいう。小山富士男をわずらわせて設計してもらった二袋煙突式の窯だった。けれどもそういう窯だからといって、うまく焼けるとはかぎらない。半泥子は唐津を訪れて中里無庵の窯で試作をし、朝鮮に渡って登窯を見て歩き、加藤唐九郎にはみっちりその技法の一部始終を伝授してもらっては、その腕を上げていく。そのいきさつは『泥仏堂日録』の半分を占めている。
さて、その半泥子がどういう作陶をしたかというと、これが筆舌に尽しがたいほどにすばらしい。生涯に3万点を焼いたというからむろん駄作も多かったろうが、少なくともぼくが見たものの大半は唸りたい。
これは思うに、半泥子にキレイダ・キライダ・キカイダ・キシンダが一貫していたからである。ようするに好みを徹底して貫いた。ぼくはそう思っている。以下、その半泥子のキレイダ・キライダがどういうものであったかを少々あげておくが、詳しいことは本書を読まれたい。
半泥子は土の味で茶碗の出来を見た。轆轤をさわっているときの味と焼き上がったときの味が変わらないものが、最高の陶土なのである。そうでないものには「腰」がない。あるいは「金属的」になる。それらはキライダなのだ。ことに京都の五条坂あたりで「合わせた土で焼いた品物はけっこうでっせ」というものほど、ひどいものになっている。「単味で焼いた焼きものの味は灘の生一本の味。合わせ土の焼きものは安物のコクテル」なのである。
ひるがえって、書画も骨董も遊芸も、約束にとらわれているものの大半はキライダなのだ。「トトヤの目は七ツにかぎります」と得意になっている連中ほど、田舎者の代物ばかりを褒めている。「約束のお化け」ほどこわいものはない。つまり半泥子は、市場価値があるものや値が出そうなものを求める卑しい気持ちが大キライダだと断言しきってみせたのだ。また、玄人ぶっている訳知りがキシンダだったのだ。そこで誰かに「ものの見方」を聞かれると、「茶人と骨董屋の説明などに耳を傾けないこと」をお勧めするばかり。
そんなことより自分の目でじいっと、ただひたすら「もの」を見る。それだけがいいと言う。「イイ」か「イケナイ」か、「スキ」か「キライ」か、それをとことん自分で見ることだけが大事なんだと言い続けた。
それでもキレイダと思ったのは、骨董屋道具屋では、東京の大村正夫、京城の田中明、唐津の古館九一だった。そのほか半泥子はキレイダ・キライダを次のようなもの、次のようなことに示している。順不同にあげておく。
「キレイダ」(スキダ)=古志野、古唐津、古伊賀、瀬戸黒、李朝初期、古染付、井戸、長次郎、光悦、黒織部、乾山、朽木盆、吉野絵、織部百ケ条、桂離宮八ツ窓の中柱、土の味のする土、炭のいぶり、分相応のお茶、八八歳の石川宗寂、鏡花の小説、奥平武彦の陶磁研究、小山富士男の目、金重陶陽の仕事、日本橋の医者の野田先生、魯山人の書、赤羅宇の長キセルの一服、反古のたぐい、廃物に見えるもの、パステル画、清元、都々逸、「仏法僧幽かに峰の雨夜かな」(青々)‥‥。
「キライダ」(コマッタ)=青磁、高麗雲鶴、支那趣味、蘇州の風景、伊万里、京焼、仁清、ノンコウ、博多人形、古銭収集癖、魯山人の壷、絵付の写し、多くの油絵、麻雀、婦人のちりちりパーマ、婦人の毛皮、鼻につく茶人、茶の湯の作法、シャモット、底が悪重い茶碗、極彩色の絵、「何迷ふ彼岸の入り日人だかり」(鬼貫)‥‥。
こんなところだろうか。あえて魯山人もキレイダにもキライダにも入れておいたのは、そこも半泥子のお好みだ。
いちいち評釈がついてるものもあって、なかには傑作もある。婦人のちりちりパーマについては、こういうものはアスパラガスの缶詰にして西洋にまるごとお返ししたい、婦人が毛皮を帽子から着込んでいるのなんぞはまるでカンガルーにしか見えない、といった口調だった。
それでは何が何でも半泥子はすばらしいのかといえば、実は半泥子の文章はヘタクソである。お世辞にもうまいところなんぞ、ない。含蓄もないし、土の味もない。仁清や京焼でもないけれど、長次郎でも乾山でもない。言いたい放題がつらなっているだけで、半泥子の茶碗を想像して読んではがっかりするだけだろう。これは魯山人にも共通するもので、ようするに文人ではなく遊び人なのである。
けれども、このような口調(文体ではない)で書き損じていくところが、やはり半泥子だった。どちらかといえば第696夜に紹介した益田太郎冠者に近い「深すぎる愛嬌」というものだ。ぼくはこういう男が、かつての桃山の等伯であり、慶長の光悦であり、元禄の乾山だったかと想いたい。
さて、半泥子の茶碗について話したいのだが、なんだか言葉にするのがつまらないような気がしてきた。ここはひとつ、ウェブ「千夜千冊・遊蕩篇」の特権で、左右上下の作品写真を見てもらうだけにする。
写真だから伝わらないものはいくらもあるが、これで何も感じないなら、まあ、遊蕩はあきらめたほうがいいだろう。1991年に銀座松屋で開かれた「川喜田半泥子展」の図録から転用することにする。
(1)「初音」が最初期に千歳山で焼いたもの(1925)。(2)が井戸手茶碗の「萩の宿」(1941)、(3)は井戸茶碗の「渚」(1942)、(4)いくつかある伊羅保茶碗の「ほし柿」、(5)が最初にあげた刷毛目茶碗の傑作「一声」で広永窯のもの、(6)も広永窯の「月の影」、(7)も最初にあげた粉引茶碗の名作「雪の曙」、(8)は刷毛目茶碗「天の川」、(9)と(10)がぼくがこっそり好む粉引茶碗の「日本左エ門」と白掛茶碗の「ささがに」だ。
とりあえず10作をあげてみたが、このほか名作傑作、秀作逸品は数知れない。キリがない。たとえば、「赤不動」「大さび」「あつ氷」「松の内」「わすれな艸」「たつた川」「夏ふじ」「窯のさち」、そして黒楽の「伊吹山」「文福」「みそぎ」、瀬戸黒の「松ケ根」、黒織部の「暗香」「ヘイナイ」だ。

『茶碗 銘 初音』
1925

『志野茶碗 銘 不動』

『織部黒茶碗 銘 暗香』
半泥子の陶芸は轆轤づかいの妙技にあらわれている。半泥子自身もこのことについてはよく話していて、本書にもその口伝の一部が載っている。なかで最も半泥子らしいのが「轆轤のイケコロシ」というものだろう。
これは、一言でいえば「急所だけに力を入れて、そのほかは気を抜くように轆轤をつかうこと」をいう。それをすばやくくりかえす。たとえば、茶碗の高台をしっかり締めて、ここにどんな大きな茶碗であろと力を引き受けさせる。次は「腰」を張らせて力をもたせ、そこから力を柔らかく抜いていく。いよいよ飲み口に達したら、ここで一呼吸、キューッとひとつの力だけで仕上げてしまう。この呼吸が「イケコロシ」なのである。
これは「形を追う」というものではない。この呼吸からしか「形」は出てこない。そういうものだ。これが半泥子の轆轤づかいなのである。それでも茶碗の底のほうが「悪重い」ようなものは、すべてキライダなのだ。これは茶碗が厚いか薄いかとはまったく関係がない。
こういう口伝を読んでいると、もっと半泥子には文章なり口述記録なりがのこっていてほしかったと思うけれど、まあ、それもほとんどのこさなかったのが半泥子だった。そう思うしかないだろう。それが桃山の半泥子で、元禄の半泥子なのである。われわれもただただ、本物をじいっと見るのがいいのだろう。
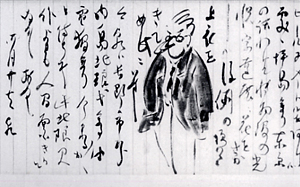
交遊深い知人宛の書簡(昭和26年)
附記¶川喜田半泥子の著書はめったに手に入らない。なかで編集ものに『唐子の友』『ちとせ』(私家版)、編述ものに『じゃわさらさ』(學藝書院)、『内観法』(私家版)、『大伝馬町』(學藝書院)があり、さらに『乾山異考』(學藝書院)、『乾山考』(千歳文庫)、『莫加野盧之記』(広永陶苑)があるのだが、ほとんどお目にかかれない。発売されている作品集は『定本川喜田半泥子作品集』(淡交社)が唯一で、ほかには80歳のときの『半泥子八十賀百鹽鑑』(刊行会)と、三重県立美術館の『川喜田半泥子展』の図録、松屋での『川喜田半泥子』展の図録があるばかり。いずれにも森本孝の熱意のこもる解説がついている。なお本書には解説と年譜を森孝一がわかりやすく書いている。