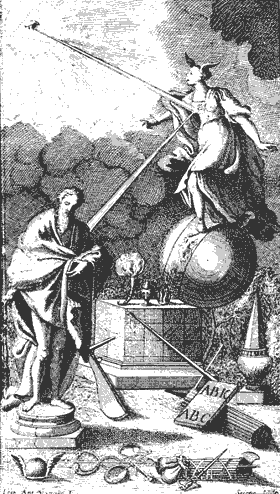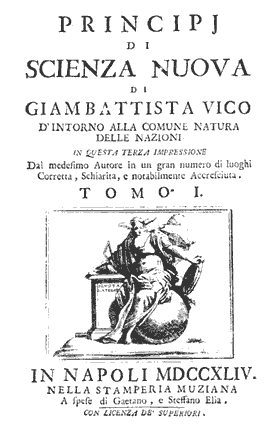バロック紀から近世にかけて、「インヴェスティガンティ」(investiganti)という言葉が新しい響きをもって囁かれていた。探究者という意味だ。
十七世紀半ば、このインヴェスティガンティとして新しい科学や学問をめざす動きが各地に生まれた。デカルトやガッサンディやライプニッツがそういう一人だった。ナポリにもそういう動きが入りこみ、小さなインヴェスティガンティ学会のようなものができていた。
ジャンバッティスタ・ヴィーコはこの動きの最後の舞台に登場してきた思索者もしくは構想者もしくは教育者である。それまでの動きを覆すようなインヴェスティガンティをめざしたヴィーコのその両手には、「クリティカ」(判断の術)と「トピカ」(発見の術)という二つの方法の剣が握られていた。
そのころナポリ王国には四〇軒の本屋があったという。ヴィーコはその本屋の一軒に生まれた。すでに王立ナポリ大学は創立されていて、一六九九年、三一歳でやっと大学に職を得て、修辞学の教授になる。
ここまで就職に時間がかかったのはヴィーコが早熟すぎて学校になじめず、長きにわたって自学自習に専念していたからだ。そうでもあろう。そうでなくてはヴィーコは生まれまい。十八歳からはドメニコ・ロッカ侯爵にひどく気にいられ、子息の家庭教師としてチレント地方のヴァトッラの居城に過ごしていた。これもよくわかる。こうでなくてはヴィーコではなかった。
これらのことは、その後にヴィーコ自身が書いたやや風変わりな『自叙伝』(平凡社ライブラリー・法政大学出版局・みすず書房)にとくとくと語られている。花田圭介がいみじくも〝オイディプス型の自伝〟と名付けた自叙伝だ。ぼくは西本晃二の訳によるみすず書房版を薦める。
インヴェスティガンティ(探究者)について、もう少し説明しておく。この呼称を漲らせたのはナポリ大学の解剖学教授のマルコ・セヴェリーノの二人の弟子、コルネリオとディ・カプアだった。
二人は示しあわせて一六四四年のローマやフィレンツェをまわった旅で、ガリレオ、ガッサンディ、デカルト、ベーコン、血液生理学のウィリアム・ハーヴィ、化学のロバート・ボイルなどの本をしこたま仕入れ、その宝物のような本を仲間を集めて学習するようにした。指針にはコルネリオが作成した「プロギュムナスマク・フュシカ」(自然学予備演習)を使い、アレーナの侯爵がパトロンとなった。これがインヴェスティガンティ(英語ならinvestigator)のうねりの始まりだ。
アカデミーもつくられたが、それよりも知的青年たちが自主的にサロンや集会や学習会を重ねたことが広がりをつくった。その盛り上がりのエースとして登場してきたのがヴィーコだったのである。ナポリ大学としても応援するに吝かではなかった。
ナポリは以前はカルロス二世のスペインの支配下にあって、王位継承にからんで新たに皇帝カールに率いられたハプスブルク家に占められつつあった。ナポリ大学としても皇帝カールに捧げる何かをしなければならない。
当時のヨーロッパの新学年度の開講は十月十八日だった。一七〇八年、その開講記念講演がヴィーコに託された。ヴィーコが選んだ講演テーマは「学問方法において、私たちのものと古代人のものは、どちらがより正しく、より良いものであるか」というものである。
このテーマはヴィーコの独創ではなく、そのころ芽生えつつあった「古代人・近代人優劣論争」を踏襲している。すでにピエール・ベールやシャルル・ペローがこの論争に十七世紀の後半から乗り出していた。しかしヴィーコは古代人と近代人(近代人とはここでは十八世紀人をさす)のどちらかに軍配をあげようというのではなく、古代から近代を貫くべき精神の歴史を構想し、あることを二つ提示したいと決意していた。そのあることというのがデカルトの哲学を批判することと、自分なりに学問の進歩の歴史を総編集し、そこから新たな「方法」を編み出したいということだった。
開講日、ヴィーコはインヴェスティガンティの烽火を上げるように「学の確立」に向かって新たなプログラムを提示することにした。講演の内容はいまは『学問の方法』として岩波文庫で読める。原題は「芸文を学ぶ青年に向けて、われらの時代の学問方法について」となっている。
このなかでヴィーコはデカルトの方法との対決姿勢を切り出した。デカルトの『方法序説』は「理性を正しく導き、諸科学において真理を求めるための方法」を提起した。この方法は修道院のアントワーヌ・アルノーとピエール・ニコルが共著した『論理学もしくは思考の術』、通称「ポール・ロワイヤルの論理学」として機関的に継承されていたもので(ここにデカルト派がこぞって集っていた)、真理と虚偽を最初から分けて学問に臨む方法だった。
しかしヴィーコはこれに正面から反抗し、むしろ真理は共通感覚から出所するべきものだと断言したのである。自然や世界には先験的に真理なるものなどはなく、「真理は作られたものに等しいはずだ」というのがヴィーコの思想だった。
ヴィーコはまた、デカルト的でライプニッツ的な代数解析的方法にも疑問をもち、あえて幾何学的な方法によって青年を教育すべきだとも考えていた。これはありていにいえば、デカルトやライプニッツの方法は「普遍の学」(マテーシス・ウニヴェルサリス)に名を借りたフィクションにすぎないとみなしたということだ。ヴィーコはむしろフランシス・ベーコンのような〝学問における森の森〟のような構想を実現したかったのだ。学問における森の森、それはまさにバロックの知の総合起爆を暗示した。
ヴィーコの『新しい学』には「諸国民に共通の自然本性」という副題がついている。これだけでもヴィーコが何を狙いたかったかは漠然とわかる。ぼくもこの副題があることをずいぶん前に知って、どきどきしながら、なんとかこれが日本語で読めるようにならないものかと思っていた。
日本で『新しい学』が読めるようになったのは中央公論社の「世界の名著」がこれをとりあげたからだった。清水幾太郎が解説をしていた。巻頭に掲げられた口絵に目を奪われた。一七四四年版に印刷されたこの口絵は友人の画家ヴァッカーロが描いたもので、ヴィーコ自身も「著作の理念」のなかで詳細に言及しているもので、こんな図柄になっている。
中央に祭壇があって、杖と水壺と燃える火が飾られている。祭壇の上の右側の端にあぶなっかしく天球儀に乗った女神がいる。天球儀では獅子座と乙女座だけの絵柄が目立つ。獅子座はヘラクレスを暗示し、「新しい学」がヘラクレスのごとく古い学を焼き払うことを象徴する。
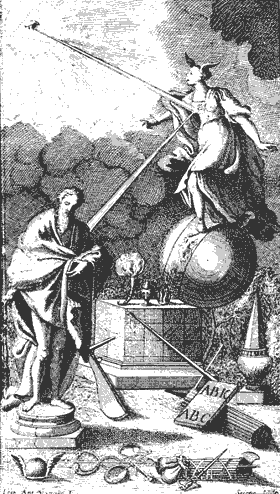
『新しい学』1744年版の口絵
女神は天空に輝く三角形の中の瞳が放つ視線の光を浴びている。ヴィーコはこの天球儀は自然を、女神は形而上学を、視線の光は摂理をあらわすと言っている。視線の光は女神の胸に飾られている凸面宝石で反射し、地上の台座に立つホメーロスの彫像に射しこむ。その台座はひび割れていて、ヴィーコによるとそれがホメーロスの再発見を意味するという。ホメーロスは言葉以前の世界を初めて言葉に変える術を知っていた者の名の象徴なのである。
祭壇のもとには象形文字が並んでいて、文明世界の各種素材をあらわしていた。背後には森があって、その前に骨壺がある。これは土地が分割所有されてきたという歴史のアレゴリーになっていて、そこに一本の鋤がのびているのは、氏族というものが家父長制に仕切られてきたことを意味していた。また祭壇の右側に船の舵がある。これは民衆の移動が航海術の恩恵をうけることを示す。
では、この舵と鋤とが隔たっているのはいったい何を意味するのかというと……というふうに、この銅版画はおびただしい「知の情報」を提供していた。「著作の理念」と銅版画を見くらべながら読むと、そのいちいちがヴィーコの「新しい学」の複合的なアレゴリーの集大成だったということが判然とする。清水幾太郎はどうしてこんな重大な絵図に一言もふれなかったのだろう。
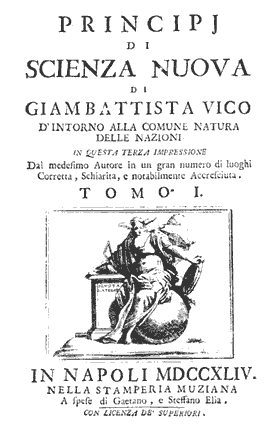
『新しい学』1744年版の扉頁
ぼくはそうとうに興奮してしまっていた。銅版画の解読に刺激され、最初のうちは『新しい学』を読みながら次々に白紙の上にダイヤグラムのようなスケッチを描いていたのだが、しだいに混乱した。ついで、大学ノートの表紙に〝Scienza Nuova〟と万年筆で書いて、メモをとりはじめた。たちまちノートの半分以上を占めたのだけれど、これ以上のノートをとるにはデカルトやベーコンのノートも作らないかぎりどうにも役に立たないと思い、途中放棄した。
ところが、このあたりで突然にアリストテレスやキケロの「トピカ」がこの絵に再生されていることを知るようになって、愕然とした。ヴィーコは、知識というものは、事物が作られていく場と過程と様式についての認識そのもののことであって、それゆえそういう認識をもつためには当の事物を作った場のアレゴリーにもとづいていけば、当事者と同様の作業をなんらかの方法で再生できるのではないか、逆にそうしないかぎりとうてい獲得できないはずだとみなしたのだった。また、それを伝達していくことが知の歴史というものであって、それこそが教育だと言っているのだった。トピカとはその方法そのものだった。
古代ギリシア・ローマ以来、トピカ(topica)というのは知識や思考を動かす技能のことをさしていた。トポス(topos)にもとづいてトピック(topic)を動かす。トポスは「場」のことで、そこには記憶や情報がまつわっていると考えられるので、思考が動くにはトポスに絡める技能が有効だとみなされたのである。
その技能がトピカだった。アリストテレス、キケロ、アグリコラ、ルルス、キルヒャー、ライプニッツらが注目してきたが、ここにきて新たにヴィーコが全面的にとりくんだわけである。冒頭にも書いておいたように、ヴィーコはクリティカは「判断の術」で、トピカが「発見の術」だとみなし、クリティカとトピカが追いつ追われつ動くような学を創発させたかったのだ。
ヴィーコのトピカ論は驚くほどにぼくの〝好み〟に合うものだった。どんな事物や現象についての知識も、それをトポス(分母の場)から切り離さずに、しかもそれを「あとから発見しやすいように知を組み立てておくという方法」が、まさに編集思想の根幹にかかわるものと見えたからである。
以上のような知識についてのヴィーコの掴まえ方には、とても悦ばしいものがある。いかにもインヴェスティガンティらしい。
西洋知の潮流では、知識は「原因によって知られるものだ」というアリストテレス以来の見方が定番になっていた。それをヴィーコは「真なるものと作られたものとは相互に置換しうる」というふうに掴まえて、知識には類似性や比喩性がかかわっているとみなした。これは知識には詩的記号が動いているという見方によるもので、相互に似通った言葉の種子のようなものが知のモデルないしは肖像に作用するのだという卓見だった。ヴィーコの研究者である上村忠男は、こうしたヴィーコの卓見はフッサールやガダマーの現象学や解釈学に届くものだと言っている。そうだろうと思う。
まとめていえば、ヴィーコの「新しい学」は、文明の知をその発生時のトポスとともに継承し、その継承のために駆使するトピカの方法を、そのまま新たな科学や学問とドッキングさせて、さらに新しい文明を用意しようというものである。ヴィーコの計画通りなら、ここには原則的には〝発生の連打”とでもいうべき「知の再生装置」が用意されることになる。
しかし、そんなことがありうるのだろうか。これは大きすぎる構想ではあるまいか。もしこの試みに問題があるとしたら、ひとつはそのような再生装置が「知の永久機関」のような世界観になってもいいのかということ、もうひとつはこれだけの計画をトピカとクリティカの組み合わせだけで支えきれるのかということである。
けれどもまた、こうした心配をさておきさえすれば、ヴィーコの方法こそが、時代がこれから立ち向かう編集的世界観の模索のためには有効なものであるとも見えた。一九七八年あたりのぼくの判断である。
その後、実のところはヴィーコを詳しく検討していないままにある。ということは、ぼくが「知の永久機関」のような計画に結局は疑問をもったということになるのだが、けれどもその一方で、ヴィーコがどんな「知」も「変化」しつづけていて、その「変化」を感知するには詩的言語やアレゴリーやメタファーによってしか、その間隙を埋めえないと考えていたことについては、なるほどその通りだと思っていた。その点では、いまだにぼくは徹底的なヴィーコ主義者でありつづけているのである。
日本にもヴィーコ・ブームが到来した。だいたいの議論に目を通してみたが、このようなぼくを、ちょっとだけ安心させてくれる事実が、少なくとも二つあった。ひとつは、ヴィーコは正真正銘のバロックだったということだ。これについては、いつかまたぼくのバロック論として説明したい。ともかくバロックとしてのヴィーコを解くこと、このことを思うとまことに気持ちが落ち着いてきて、かつ胸騒ぎがするのである。
もうひとつは、かのジュール・ミシュレが、生涯の終わりにこう言っていたことである。「私の唯一の先生は、そうです、ジャンバッティスタ・ヴィーコただ一人であったのです」。